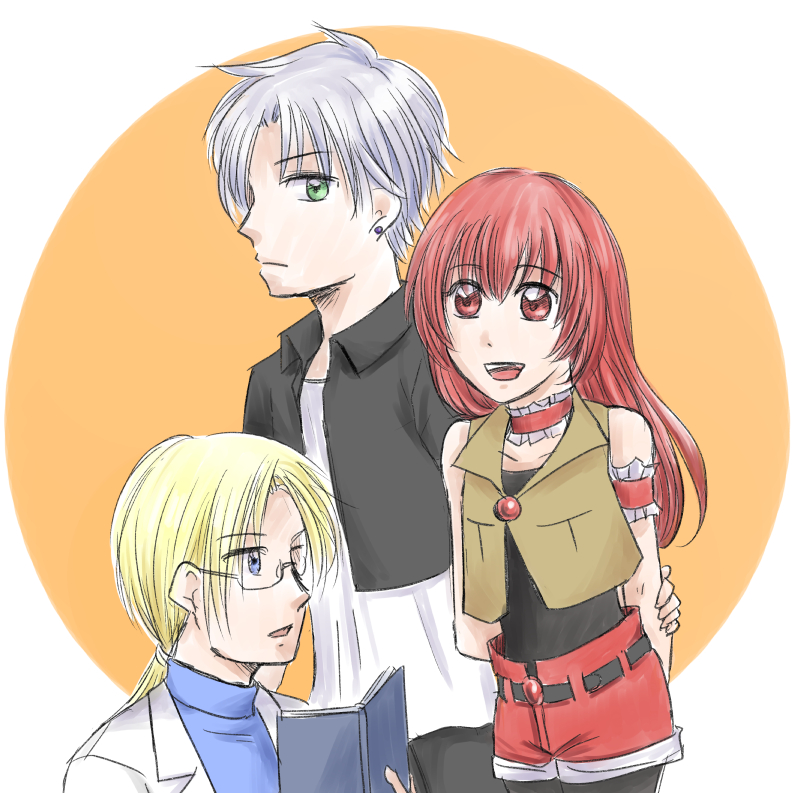やわらかな朝の日差しが、木々の間から差し込むのを感じて、ファーナは目が覚めた。
「んー…」
大木の幹に寄りかかり寝ていたせいか、身体が固くなっている。伸びをして、眠気を振り払おうとする。周囲を警戒しながらの睡眠なので、しっかりとは眠れていない。しかし、日々の緊張感が、その疲れを押さえ込んでいた。
カルディアを発ってから6日。途中、他の人間に遭遇することは無かった。ただひたすら、道無き道を歩き進むだけだった。魔獣に遭遇する率は次第に高く、そして凶暴になってくる。戦うにつれ、段々慣れてくる自分に、ファーナは時折ぞっとすることもある。廃屋に泊まることもあったが、基本は野宿だ。何時魔獣に襲われるか解らない。
「うーん…」
近くの川で顔を洗い、意識をはっきりさせる。川に映る自分の姿は、くたびれていた。服もドロドロで汚い。南に進むに連れ、段々と暑くなってくるのが解る。だから長袖は既に半袖にしてしまい、その切れ端でいつも顔や身体を拭いている。いい加減、城の生活が恋しくなってきた。
「…それもこれも、自分のせいだし…」
そう呟いて、はあ、と一息溜め息をついた。
「朝から辛気臭せぇ奴」
突然後ろから声をかけられ、ファーナは咄嗟に後ろを向いた。そこには、もう見慣れてしまった銀髪の青年が面白くなさそうに立っていた。
「カ…っ、貴方ねぇ」
ファーナはカティスをその名で呼べない。たった一度の過ちが、今こうして自分を苛んでいる。だが、この期に及んで名を呼ばないのは最早意地と言っても過言でない。
「ほら、採りすぎたからお前にやるよ」
そう言うと、カティスは乱暴に大きな果物を投げつけた。とっさにキャッチしたが、そのスピードで手が痺れた。
「…あ、ありがと…」
「じゃ、行くからな」
ファーナに構うことなく、カティスは歩き出した。それを見て慌ててファーナも後に続く。果物を歩きながら食べるのも、慣れてしまった。
この数日、ファーナはカティスとあまり口を利いていない。ファーナの場合は意地だったが、相手のカティスも進んで何かを話すタイプではないらしい。しかし、自分に対する振る舞いに、時折優しさを感じることに、ファーナは戸惑い始めていた。彼は本当に、この世界を壊そうとしている『堕天使』なのだろうか。
「――!」
物音が聞こえ、物思いに耽っていたファーナは突然現実に戻された。
「叫び声がする!向こうの方から!」
「大方魔獣に襲われてんだろ。ほっとけよ」
しれっとファーナの叫びをカティスは流した。
「助けに…」
「勝手にしろよ。…そのお節介が元で国に還されるかもな」
「そんなの関係ない!困ってる人を放っておくなんて、出来ないわ」
そう言い残して、ファーナは声が聞こえた方へ駆けていった。数百メートル離れた所で、木こり風の男性が二頭の大きな熊のような魔獣に襲われていた。男性も応戦しているが、手が回らない様子である。
「お手伝いしますっ」
ファーナが勢い良く茂みから飛び出す。一番近い魔獣めがけて、火を喚んだ拳を突き出す。
「グオオォオオ!」
ドスンと大きな音を立ててその一頭が倒れる。
「てぇいっ!」
間髪入れずに、そのままファーナは蹴りを入れる。それでその獣は息絶えた。
「大丈夫ですか?!」
ファーナが男性の方を見やる。同時に、もう一頭の方も倒されていたようだった。斧で戦ったらしく、筋肉質の身体には返り血が付いていた。
「おう、ありがとな、嬢ちゃん。…ところでこんな山中で一人かい?サルアから登山にでも来たのか?」
「え」
ファーナは内心驚いた。サルアとは、首都ハルザードから南西に五百キロ離れた所にある、山間の貿易都市だ。普段なら街道を使って迂回して行くので、馬車で6日はかかる。それなのに山中を徒歩で6日とは、驚異的なペースであったからだ。
「う、うん、そう。でも迷っちゃって…。ようやっと人に会えました」
咄嗟にファーナは嘘を付いた。しかし男性はそれを鵜呑みにしたようだった。
「はあ…それでそんなにボロボロの格好なのか。大変だったろう。…ん?後ろの男は連れか?」
ファーナはハッとして後ろを振り返る。そこには面倒臭そうに腕組みをして突っ立っているカティスがいた。何だかんだで付いて来てくれたことに、内心でほっとした。
「うん。この人はカ…」
このまま名前を言ってはダメだと咄嗟に気が付いた。しかしもう頭まで言ってしまっている。
「…カディ!私はファーナ。友達同士なんだ~っ」
ファーナの名前は比較的ありふれた名前だ。しかし自分も追われる立場であることをすっかり忘れてしまっていた。突然「カディ」と名付けられてしまったカティスは、後ろで苦々しい顔をしていた。
「兄さん、随分かわいらしい名前だなぁ」
「そう言われる度、名付け親を恨んでるぜ、全く」
遠回しにファーナにちくりと釘を差した。
「解った。二人とも俺ん家に来いよ。一泊させてやる。相当疲れてるだろ?」
その言葉にファーナの顔が明るくなる。本当だとしたら、実に一週間ぶりのベッドとシャワーだ。
「いいんですか?嬉しい…」
「けどよぉ…」
男性が言葉を濁す。
「今、俺の村がおかしな事になってるんだ。夜が暗くならなくってよ。だから、安眠出来なかったら悪いな」
ファーナとカティスは顔を見合わせて目をぱちくりさせた。言っている意味がよく分からない。
「何それ」
「さあ…聞いたこともねぇな」
カティスでもその言葉の真意が解らないようだった。難しい顔をして何かを探るように考えこんでしまった。
「まあ、歩きながら話そうや。あ、俺はレクターってんだ。よろしくな」
「よろしく、レクターさん。ほら、カディも」
咄嗟のことではあったが、ファーナは内心、しめたと思った。カティスを渾名で呼ぶことができるようになったからだ。
「…世話になる」
当のカティスも、それに異論を唱えようとはしなかった。
村までの道は多少整った小道となっていた。レクターを先頭にして、続いてファーナ、カティスと続く。歩きながら、レクターは先ほどの『おかしな事』について話し始めた。
「アレは確か半月くらい前かな。スレークに出稼ぎに行ってたヤツが土産に、光る石を大量に買って帰ってきたんだ。それ以来だ。夜中になっても昼間みてぇに明るくなっちまったのは」
スレークはカルディアの東の隣国である。機械産業、特に精霊魔法と機械の融合を計る研究が盛んだ。殆どの国が照明に天然の光や火の宝石――ジェムを使うほか、普通に火を起こして明りを採っている。しかし、スレークは照明としてより長持ち出来るジェムを独自開発、人工的に生産しているという。
「じゃあ、そのジェムが問題じゃないんですか?捨てれば…」
「捨てたんだけど、ダメだった。原因はアレしか無さそうなのに」
レクターが溜め息をつく。後ろに控えて歩いていたカティスが不意に口を開いた。
「…もう村の敷地か?」
「ん?ああそうだ。この辺りから、俺らの村の敷地。ほら、あの畑とか、隣の家のだし。暗くならないから、何か最近作物も調子悪いんだよな」
レクターは周囲を見渡しながら答えた。作物がどこかくたびれて萎れている。ファーナは後ろを振り返ってカティスの方を見やった。眉間に皺を寄せて、どこか不快そうな顔をしていた。
「全部そのジェムは捨てたのか?」
「あー…村長が一つだけ持ってるかも。あの爺さん、光り物に目が無くて、一番光ってたの持っていったし。でもあれ、捨てるときには出してなかったから」
「そうか…」
それきりカティスは黙りこくった。俯いて、一つ深呼吸をした。
「…だ、大丈夫?カディ。顔色悪いよ?」
ファーナはなるべく自然を装って『友人』の心配をする。
「…だろうな。なあレクター、その石見せてくれよ。何とかなるかもしれねぇ」
「ええっ!?」
二人同時に叫んだ。レクターも流石に振り返った。心底嬉しそうな顔をしている。
「マジ?」
「ああ。ただその石、ひょっとしたら使い物にならなくなるかもしれないけどな。村長がそれでいいなら、やってみるぜ」
カティスには何か解決する方法があるらしい。ファーナには思い当たる節がない。一体どんなことをすれば解決するというのだろう。
「っしゃあ!じゃあ着いたら早速村長に掛け合ってみるぜ。…っと、ほら、あそこの家が俺ん家。早く行こうぜ!」
浮き足立って、レクターは半分スキップしながら指さした方向へ向かう。二人は速さを変えず、その後をゆっくりと追う。
「…何企んでるの?」
ファーナは声を潜めて訝しんだ。
「何も。ただここは俺にとって居づらい場所だから、そのついでだ」
「…?」
そう言って、カティスはさっさと歩いていってしまう。ファーナはその言葉の意味を考えながら、後をゆっくりと付いていく。
――光。その対極の闇。カティスは、その闇を扱う。
(まさか、カティスは)
闇を扱うからこそ、その正反対の光を嫌う。だからこの場は居づらい。それを、闇をもって解決しようとしているのでは―。
「何よそれ、それって…」
カティスを止めようと声をかけようとしたファーナの脳裏に、小躍りするレクターの姿が横切った。あんなに嬉しそうにしていた。苦しみが解放されるなら、その手段は何を使ってもいいのだろうか。
「何か?イイコトしてやろうってんだ。文句はないだろ?」
にっと笑い、勝ち誇ったように彼はレクターの後に続いた。ファーナはそのまま黙りこくってしまった。
二人は木造の簡素な家屋に通された。家の中は小奇麗に整っている。
「カミさんと娘が二人揃ってハルザードまで旅行行っちまってよ。明後日まで俺一人なんだ。だから一部屋空いてんだ。使ってくれ」
その言葉に、ファーナは一瞬顔を引きつらせた。一足遅ければ、自分の正体に気付かれてしまっていたかもしれない。
「どうした?」
「い、いえ…何でも」
ファーナは笑顔を取り繕って首を横に振った。
二人が通された部屋には、ベッドが一つ置いてあり、そこに隣部屋から布団を一つ運んできてくれた。それだけで部屋はいっぱいになってしまった。
「狭くて悪いな」
「いいえ。泊めてもらえるだけでありがたいです」
ファーナが深々と頭を下げる。対して、カティスは面白くなさそうにファーナの後ろに立っていた。
「あ、それと、道具貸してやるから、着てる服洗えよ。そのまま町に降りたら皆驚いちまうぜ。サイズ合わねえかもしれないが、服も貸してやる」
「あ、ありがとう…ございます」
至れり尽くせりの対応振りに、ファーナは恐縮してしまった。
「何、いいってことよ。じゃあ、俺、村長に掛け合ってくるわ」
そう言い残して、レクターはさっさと家を出ていってしまった。それを見送って、一瞬沈黙が流れる。
「…じゃあ、着替えよっか。私部屋の中で着替えるから、絶対覗かないでよね」
ファーナはそう言って、貸してもらった寝室に入っていった。
「誰がんなことするかよ、バカか」
扉の外から、イラついた様子のカティスの声が聞こえた。
着替えた後、二人は洗濯をするために外の共同水路へと向かった。まだ日が落ちるには早い時間だった。服も着替えたせいか、うららかな陽気がファーナには気持ちが良かった。
「この天気なら、朝までには乾くかな」
水路に洗濯板と衣類を入れ、石鹸を付けてゴシゴシと洗濯を始める。
「へぇ…。箱入り娘の姫様かと思ったが、洗濯は出来るんだなぁ」
その様子を横から覗き、カティスは嫌味ったらしく感嘆の声を上げた。
「失礼ね。私、6年間はエルガードに留学してたし。あそこでは結構、自分で色々とやってたから」
パン、と勢いのある音を立てて服の形を整えながら、得意げにファーナは笑った。名を呼べるようになったからだろうか、今までよりも随分と会話が弾んでいる気がした。
「エルガードか。…あの金髪男、お前の知り合いなのか?」
不意に投げかけられた質問に、ファーナは一体何の事を言っているのか解りかねた。しかしすぐに思い当たる。
「…ラーク先生のこと?あの、カルディアで魔法仕掛けてきた人のことなら、知り合いっていうか、留学してた時に家庭教師してくれた人だけど…何で?」
ファーナは「何で」という言葉に、様々な疑問を乗せた。
「あの男、エルガードのクラーテ家の出身だろ?」
「そうだけど?…やっぱりカディとは敵同士なの?」
ファーナは暗に二人の関係を予測した。ラークは『光の貴公子』と噂されるほどの光の魔法の使い手だ。それに対して闇を使うカティス。その対立構造だけではない。ラークは以前に、『堕天使』について、恐ろしい口調でその悪行を非難していたことがあるのを、ファーナは覚えている。
「さあな。向こうが敵と思えば敵だ。あの様子じゃあ、今度会った時には思い切り掛かってきそうだな」
ファーナもその時の事を思い出す。ぽつりと、不安そうに呟いた。
「…先生も、私のこと、倒そうとするのかな…」
南国であるエルガードは、秋であるとは言え、まだカルディアの夏並みの暑さである。昼下がり、学院の入り口へと続く坂の前を、ノートでばさばさと風を送りながら歩く一人の青年がいた。短い薄茶色の髪が、わずかな風にそよぐ。北の街道から、相当な速さで近づく馬車を見つけると、彼は歩くのを止めてその馬車の到着を待った。
「ラークさんっ」
青年は馬車から降りてきた金髪の青年に声をかけた。
「ティオ。…丁度いい。カルディアからの早馬は何時来た?」
ティオと呼ばれた青年は、待ってましたと言わんばかりの勢いで話しかける。
「3日前です。布告が出てからっていうもの、学院の中はファーナの話題で持ちきりですよ!もう心配で心配で…。ラークさんなら何か知ってるんじゃないんですか?」
ティオにとってファーナは友人だ。ファーナにとっては一時それ以上の存在だったことを、ラークは知っていた。
「…はっきりと無事だ、と私も言いたいが、判らない。だが、ファーナのことだから、きっと無事だろうが」
歯切れの悪い答えを貰い、ティオはがっくりとした。
「ええ~…ラークさんでも判らないんですか…」
「分かるはずないだろう。魔法なんてものは、こういういざと言う時に限って役に立たん。ただ…そうだな、私が最後に見たファーナは…元気だった」
優しい嘘をラークはついた。脳裏には、溢れる涙を止められずにいたファーナの顔があった。きっと、自分が崩れていくような不安や恐怖を感じただろう。無事でいたとして、そこから彼女は立ち直れただろうか。全ては、自らが憎む男の手に掛かっている。
「…元気、でしたか…。なら、大丈夫かな」
根拠にもならない微かな情報で、ティオは何とか安心しようとした。
「あまり心配するな。…これから長老会に顔を出してくるから、積もる話はまた後でな」
そう言って、ラークはまた馬車へと乗り込んだ。
「は、はい!取り敢えず、アドネスのみんなに伝えておきます」
「そうだな、頼む」
馬車の窓から顔を出して、ラークはティオに告げた。そのまま馬車は、坂道を、先ほどより少しスピードを落として駆け上がっていった。
日が傾き始めていた。空は橙に色づき始めているというのに、地上から数十メートルの場所はまだ昼のような明るさだった。
「…確かに、変なの」
村の広場の中央で、周りを見渡してファーナがぽつりと言った。レクターは三十分ほどで村長を説き伏せて戻ってきた。しかし、村長が「なら自分の目の前でやってみせろ」と騒ぎ立てたせいで、村の広場には他の村人達が見物をしにやってきている。
「別に見せモンじゃねぇぞ。ったく何だよこの客の多さはよー」
「上手いことやってくれたら、お捻りやるよ、アンちゃん!」
ぼやくカティスを余所に、村人達はまるで大道芸を見に来ているかのような雰囲気だ。その時を、今か今かと待っている。
「もう少し待ってくれな。陽が落ちたら始める」
太陽が森の向こうへと落ちる。空は深い紺色に染まり、星々が瞬き始めた。しかし空からこの村の大地に視線をやるにつれ、段々と明るくなる。何かが特に発光しているわけではない。周りが明るいのだ。
「…村長、いいか?石借りても」
カティスが村長に話しかけた。大事そうに持っていた黒い袋から、明るく真白に輝く石を取り出した。昼のように明るい空間に、尚一層輝きが広がる。
「眩しい…。こんな石、初めて見た」
ファーナは眉をしかめ、驚きの声をあげて、カティスの手に渡された石をまじまじと見つめる。
「だろうな。俺もこんないびつな石は初めてだ。…始めるから離れていろ。危険だ」
カティスが周囲の人間に離れるよう促す。ファーナも含めて、皆カティスから五十メートルほど離れた位置まで下がる。カティスは石を右手に握り腕を伸ばす。そして、ゆっくりと魔法を唱え始めた。静かで、穏やか。以前に聞いた、闇の精霊術とはまた別の、知らない言語だ。
「…あれ…。何か、これどこかで…」
知らないはずなのに知っているような気がした。困惑しながらカティスを見ていると、ふと、目が合った。ばつが悪い気がして、さった視線を逸らす。その瞬間、石が弾けたように突然ぱぁっと光を放った。
「うわっ…」
「おおっ…」
村人が一斉に声を上げて顔を覆う。カティスの手元にあった石は、以前の輝きを失っていた。
その後、さらにカティスはまた二言三言詠唱する。すると、少々暗くはなったが、完全に夜にはなりきらない。
「…ちっ」
一つ舌打ちして、今度は違う言葉で詠唱を始める。
「あっ…これはっ!」
ファーナは小さく叫んだが、何もすることは出来なかった。闇の精霊術だ。言葉に聞き覚えがあった。やがてカティスの周りから、段々夜の闇が広がる。しばらくしないうちに、辺りは完全に夜になっていた。村人達がざわめく。
「おおっ…」
「凄いや、夜になった!」
お祭り騒ぎのような喧騒の中心に立っているカティスは、長い溜め息をついた。魔力を帯びた銀の髪が、月明かりのように光る。
「…よく解んねぇけど、アンタの連れ、すげぇな…」
呆然としているファーナに、レクターが話しかけた。ファーナを見ると驚いた顔をした。
「う、うん?」
「って、嬢ちゃん、…それにあの兄ちゃんも、天使さまだったのかい…どーりで」
ファーナの髪も、フワリと光を纏っている。普通の人間にはない魔力が元で、髪や身体全体がオーラのように光に包まれるのが『天使』―竜人の特徴だ。ファーナは内心「しまった」と叫んだ。
「…これで終いだ。村長、悪いな。残った光はこんなモンだ」
カティスが右手を開くと、そこには静かに光を放つ水晶があった。恐る恐る近づいた村長は、その細い両手で、カティスの手を包む。
「…これはお主がもっておいてくれ。ワシらに夜をくれたお礼じゃ。ほんに、ありがとう」
その言葉で、村人達は皆、堰を切ったように大歓声を上げた。
その後は宴会となってしまった。明朝すぐに経つと言って、何とか早めに切り上げさせてもらったが、それでも充分遅い時間だ。
「悪いなぁ。この辺りには天使さまは最大の客人としてもてなせっていう習慣があってよ」
借りた寝室で、レクターが寝る前の二人に暖かいミルクを出してくれた。
「いえ、私たちもそんなに血は濃くないんです。それこそ、何代も前のおじいちゃんが…」
というふうに、宴会の席からファーナは嘘を突き通した。
「いいって。今日こうして救ってくれたんだから。じゃあ、もう邪魔しちゃ悪いから、寝るわ。ゆっくりしてくれな」
そう言って、レクターは去っていった。それを見計らって、ファーナはベッドの上で寝っ転がっているカティスにこっそりと話しかける。
「…どんなことしたの?」
宴会の席では誰もその話題に触れなかった。「天使さまだから」と、その言葉一つで片付いてしまった。ファーナも敢えて触れるようなことはしなかった。
「あのジェムには、無理矢理大量の光の精が封じられていた。周りが明るかったのは、その光の精が周りに充満していたからだ。それを解放して、あとはそのせいで追いやられてた闇の精を呼び戻しただけだ」
さらりとカティスは手の内を明かした。きっと教えてくれないものだと思っていたファーナは少し面を食らった。
「…やっぱり、闇の魔法は使ったのね…」
「ふん、今日も責めるか?」
「…皆喜んでたけど、でも…悪いことは悪いことよ…」
ファーナは複雑だった。悪い手段を用いて、いいことをすることは、結局悪いことではないのか。ただ知らされていないだけで、事実は変わらない。なら、知らされていなければいいのか?
ファーナは心の葛藤と戦っている。何が良いことで、何が悪いことだろう。カティスは仰向けになって、クスクスと笑う。
「な、何がおかしいのよ!」
「光が何でも正しくて、闇は少しでもあったら邪なことだとでも思ってんのか?馬鹿馬鹿しい」
カティスは忌々しそうに吐き捨てた。
「えっ…そ、それは」
ファーナは答えに窮した。それに構わずカティスは続ける。
「光が溢れた結果がこの様だろうが。闇が無ければ、こんな静かな夜もこねぇんだ。何だって同じだ。火は温もりを与えるが、過ぎればたちまち全てを焼き尽くす。…だろ?」
その言葉に、ファーナは絶句した。胸の支えが取れたような気さえした。
「…ああ、そっか…。そう、だよね…。」
「じゃあな、俺はもう寝る」
ベッドの側に灯してあった火を、苛立ちを隠さないままカティスはふっと一息かけて消した。部屋は闇に包まれ、半月のわずかな月光だけが差し込んでくる。周りは静かだ。外から虫の鳴き声が聞こえてくる。
(これが、闇が与える静寂…)
ごく当たり前の夜だ。なのにその当たり前の夜を今までこんなに落ち着いた気持ちで過ごすことなどなかった。その静寂さが、今この時を、どこか厳かなもののような気分にさえさせる。
ファーナは視線をカティスに移した。寝息を立てて、もう寝ている。
(『本当に悪い人なんて、どこにもいない』…か。母様の言っていたこと、信じてみようかな…)
迷子になった大満月の夜、悪魔と言われる人物が、自分を助けてくれた。それだけで、「この世に本当に悪い人はいない」と言い切れる母は流石に短絡過ぎだとファーナは思っていた。けれど、この人物に限ってはそうなのかも知れない。
(…でも…。それはお兄ちゃん達に対する裏切りなのかな…)
ファーナは、先程とは違うことでまた心の葛藤と戦い始めた。
深夜。誰も通らない建物の中を、一人の青年が歩く。手に光を喚び、暗闇を照らして、目的の部屋へ静かに辿り着く。
ノックもせず、その扉を開く。素っ気ない事務机には、髪を剃り上げた初老の男性が頬杖をついて座っている。ランプが一つ、彼の周りだけを灯している。青年と同じ青い瞳が照らされて光る。
「…長老会では、取り計らい、ありがとうございました、ロストール様」
青年が静かに口を開く。
「…子細は、既にご存じなのですね」
「当たり前だ。光の精がかように怯えるのは初めてだ。皆口々に言うぞ。『闇が目覚めた』とな」
ランプの光が揺らぐ。青年はそのランプに視線を落とした。
「我らがすべき事はただ一つ。真実を…歴史を見極めて裁く事だけだ。『呪い子』として生まれたこと…それも今日のためだと思えば、お前も少しは救われよう」
「そう…そうなのかも、知れません」
青年は目を閉じ、長い溜め息をつく。胸の中にある様々な思いを整理しようと必死な様子だった。
「既に当主はお前に譲ってある。そのための教育もしたつもりだ。お前の好きなように行動せよ。…ただ、情には流されるな。いいな?」
その言葉に驚いて青年は顔を上げた。まさか、自分の好きにしろと言われるとは思っていなかった。
「…お爺様」
「行け。真の仕事に取りかかれ。古き時代より受け継がれた全てが、お前の代で終わること、祈っているぞ」
「はい。では…」
青年は踵を返す。部屋を出て、また元来た道を歩いて行く。部屋に一人残されたロストールは、旧い言葉で呟く。
『頼む。ラークの元へ。正しき道を歩めるよう、側で支えてやってくれ』
その言葉に呼応するかのように、ランプの光がふっと消えた。
日が昇る。まだ布団の中で温もりに甘えていたい気持ちを奮い立たせて、二人は再び旅路に出る。レクター以外に見送りに来るような村人は居なかった。明け方早い時間なので、まだ寝ているのだという。心の中でファーナはほっとした。
「よかったら、これ持っていってくれ」
村の入口で、レクターから剣を一振り、そして保存食を渡された。
「そんな、一晩泊めて頂いただけでもう充分です」
ファーナが遠慮するが、レクターはぐいっと押しつける。
「いいから、な。この村を救ってくれたお礼だ。ほれ、あの道行けば夕刻前にはサルアに着く。道中また魔獣に出くわすかもしれん。気を付けて行け」
「ありがとう…大切にします」
「いいって。じゃあな」
ファーナはぺこりと頭を下げる。カティスは「世話になった」と一言だけ告げてさっさと先へと進んでいた。ファーナは後ろを振り返って、見えなくなるまで手を振り続けた。
「…剣は俺が使う」
追いついたファーナに早速、カティスが要求する。
「そうね。私は使えないし。はい」
あっさりとファーナは剣を手渡した。カティスはそれに違和感を覚えたのか、怪訝な顔をする。
「お前…どうした?」
「?何が?」
何か吹っ切れたような元気さが、ファーナにはあった。腰のベルトに剣の鞘を付けながら、カティスは答える。
「…いや、何でもない…」
「あ、そう?ならいいけど」
ファーナは昨日の件で、少しカティスを見る目を変えた。すると少しだけ、心に余裕が出来た。見える景色も何か違うような気さえする。
(そうだ、真っ新な目で見てみればいいんだ。それで、悪いことをするなら止める。…きっとそれでいい。)
そういう答えにファーナは達した。それはすなわち、今までの自分の価値観も一度リセットするということでもある。辛いことだ。しかし、もう賽は投げられている。後に引けぬなら、せめて、一度白紙に戻すのだ。それなら、思い悩むことも少なくなる。
数時間後、眼下に街が広がってきた。空気を伝って、鐘の音が聞こえてくる。
「あーっ、サルアだ…!」
「あ、おい…」
久々の都会に胸躍らせ、ファーナは駆け足で山を下っていった。