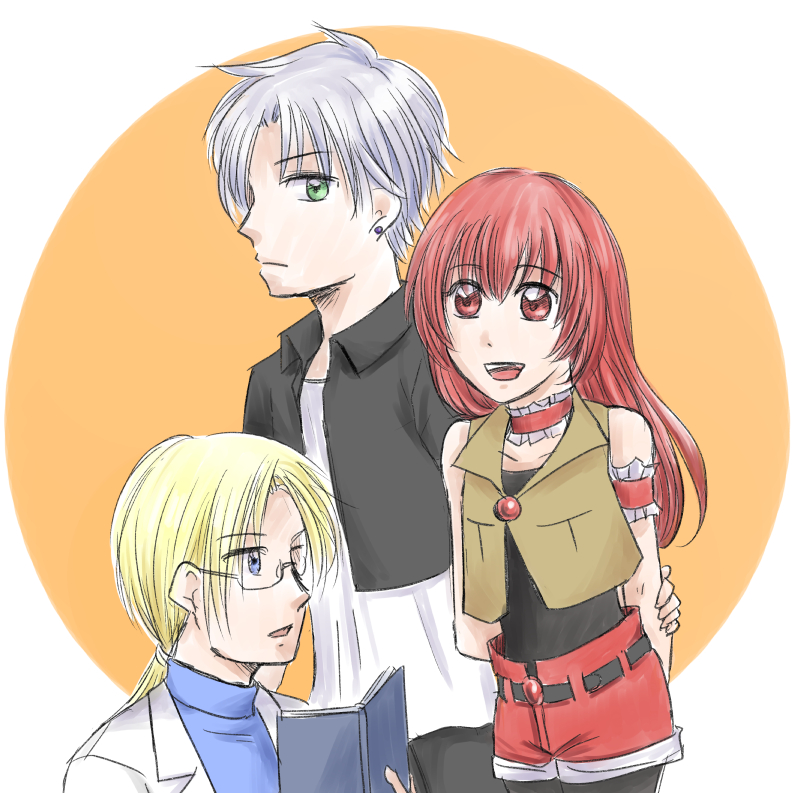朝日が昇り始める。
ようやっと眠りにつけたと思ったその時、ドアが激しくノックされる音でまた現実に引き戻された。
「王子、起きてくださいませ!」
眠い目をこすりながらドアを開ける。そこには、青ざめた顔のリンが立っていた。
「リン?どうした?こんな朝早く」
どうした、と聞いたところで、リンが来た理由はヘディンには解りきっていた。
「あの…ファーナ様はこちらですか?!」
「…いや…?どうかしたのか?」
「…いらっしゃらないんです」
か細い声だ。肩が震えている。
「…ファーナが?昨晩、別れ際に散歩して酔いを醒ましてから戻るって…」
「―いいえっ!戻られていないんです…!」
堰を切って泣き出したリンを、渋い顔でヘディンは見つめていた。
辺りは霧が立ちこめていた。
昨日からずっと、空は雲が少なく晴れ渡っている。季節は秋。朝晩は冷え込む時期となり、森林が放出した水蒸気が、辺り一帯を真っ白に覆っている。
あの大きな満月は何時しか空から消え、やがて太陽が昇ってきた。木々生い茂る中でも、その葉の間から差し込む光が、安らぎを与えてくれるような気がした。
ファーナは昨晩、そのままカティスに付いて行き、首都ハルザードから南百キロほどの所にあるダーナ山脈へ入った。山に入ってからは、ずっと登山道を歩いている。先頭をカティスが歩き、そこから数歩離れてファーナが付いていく。道中、言葉を交わすことは殆ど無かった。ファーナは昨晩自分のしたことを振り返っていた。
あの玉に触れて、誰かの記憶みたいなものが流れてきた。それはきっと最後に見た女性のものなんだろう。気が付いたら『堕天使』の目の前にいて、彼の――カティスの名を言ったと同時に、彼の封印は解けてしまった。それは禁忌だった。だから、お兄ちゃんも、先生も、私を殺そうとした――。
大体の状況の整理は付いた。そしてこれからどうなるのか。きっと私たちは追われる。私は捕まったら、直ちにではなくても殺される。無論、目の前にいるカティスもそうだ。死は厭わない。でも、このまま何も知らないまま、そして、何も償えないまま死ぬのは嫌だ。だから付いていく。
自分は何者なのか。どうして彼を目覚めさせてしまったのか。そして、彼は一体何をしようとしているのか。それを見極めて、何か悪いことをしでかすようなら、差し違えてでも止める。そう心に決めた。
歩き始めてからもう五時間ほどになる。一度も休憩を挟めずに歩き続けている二人だが、とうとうファーナが音を上げた。
「ねぇ…そろそろ休まない?お腹も空いてきてない?…ほら、何か向こうの方から水の音聞こえてくるし、せめて水だけでも」
「…ふん…まあいいだろう。そこの小川で一息つくか」
振り返らず、そして足を止めることなくカティスは言った。ファーナはホッとした。無視されるのではないかと思っていたから、口をきいて、尚かつ賛同してくれたことに安堵した。『堕天使』といえど、話の通じない相手ではない。
少し歩いた先に、確かに小川が流れていた。カティスはそのまま小川のほとりにある岩に腰掛けて川の流れを見つめていた。ファーナは周辺の食べられる木の実を採り、抱えてその隣に向かった。
「…食べる?」
薬草にも重宝されるベリーを恐る恐る差し出した。ああ、と一言だけ言って、カティスはそれを受け取り食べ始めた。
「隣、いい?…座って」
「構わねぇよ」
ファーナは遠慮がちに座って、自分の分のベリーを食べ始めた。しばしそのまま無言の時が流れる。
小川のせせらぎ、木々の葉の揺れる音、鳥や虫の鳴く声――。留学先のエルガードから帰って一年の間、こんなに自然に囲まれた所に来る機会が無かった。ファーナはベリーを食べると目を閉じ、その音に聞き入っていた。
『貴女は、私たちの望みを叶えてくれる?』
「えっ…」
ふと耳元でそう誰かに囁かれた気がした。急に風が起き、木々がざわめく。目を開けて隣のカティスを見やる。カティスは丁度自分の方向を見ていたのか、目が合ってしまった。
「えっ、あ、いやその、今、私に何か言った?」
何故か気まずい気分になったファーナは慌てた。カティスもそうだったのか、すぐにそっぽを向いてしまった。
「何も…。幻聴だろ」
またしばらく無言の時が流れる。ファーナはふと思った疑問を振ってみた。
「あ、あのっ…!何十年か前に、女の子に会わなかった?茶色の髪と目をした女の子…」
「…さあな。会ったとしても忘れたよ。俺はかれこれ五百年彷徨ってたんだ。俺の姿が見えたヤツは何人かいたし、一々覚えてねぇな」
視線を向こうに向けたまま、カティスはさらっと流した。
「…そう、そっか…」
母のあの言葉が真実なら、カティスが覚えていてくれてもおかしくないと思っていたが、当人がこれなら未だ真実は闇の中だ。だが、真実であろうが無かろうが、目の前にいるのは、母が話した『堕天使』その人そのものだ。
ファーナは勇気を出して、続けて話題を振ってみた。
「『肉体は封印されて、魂は未来永劫、この世界を彷徨い続ける』…って言うの、本当だったんだ」
「…天教の伝説か。そうだな。ほぼ真実だ。地獄以外の何者でもない…。お前には感謝してるんだ、これでもな。あの地獄から救ってくれたんだからな」
鼻で笑い、皮肉混じりにカティスは言う。
「それ、私にとっては褒め言葉でも何でもないわ。嬉しくも何ともない」
ファーナはむっすりとむくれた。カティスは徐ろに立ち上がり、表情一つ変えず歩き出した。
「…え、もう行くの?」
驚きの声をファーナは上げた。
「アンタは別に休んでていいんだぜ?アンタが勝手に付いてきてるんだからよ」
「い、行くわよ!絶対付いていってやるんだから!」
ファーナも勢いよく立ち上がり歩き出した。小川を飛び越えて、再び二人は山道へと入っていった。
「ファーナ様が居なくなったって、本当ですか!?」
ヘディンの自室にノックもせずにサリエルが飛び込んできた。着替えている最中のヘディンは思わず声を上げた。
「うわっ…!お、驚かせるな!」
「あ、す、すみません、あの、つい…」
しゅんとしたサリエルにヘディンは心を落ち着けてから、自分の机を指差した。
「あー…そこに座ってろ。説明するから」
「は、はい…」
ヘディンの説明はこうだった。王家の者しか入れない所でもう一つ儀式をやって、無事終わった後にファーナは一人で夜風に当たりたいと言ってそのまま別れた。そしてそのまま戻らなかった。それは朝、リンがファーナの自室に入ったときに、ファーナが居なかった事から発覚した。
「家出、あるいは誘拐…どちらにしても捜索はする。同盟国・中立国には触書を出して、見つけ次第領事館に保護してもらうよう依頼をする」
「兵は出さないんですか?」
サリエルが懇願するように問うた。
「生憎、城の守備兵を残してほぼ全軍がフィリア、そしてスレークの国境紛争に狩り出されている。宮廷騎士団から数名出す他は、各都市の守護団に任せることになる…俺もこれ以上は無理だ」
苦渋の表情を浮かべてヘディンは理解を求めた。その姿に、サリエルははっとした。王不在の間、残された軍の指揮はヘディンに一任されている。ファーナ一人ではない、多くの国民を護る使命を、ヘディンは背負っているのだ。その中で、少しでもファーナの捜索に人員を割いてくれることに感謝をすべきなのだろう。
「…僕は…何かお役に立てることは」
「お前は神官だ。…ファーナの無事を、祈っていてくれ。サリの祈りは、きっと天に通じるから」
すっかり着替え終わったヘディンが、机に座っているサリエルに近づいて頭にポンと手を置く。
「…は、はい!そうですよね、僕ができることをやらなきゃ…」
少しだけ元気を出したサリエルにヘディンはふっと笑った。
「…いいかな。俺はこれから各国の使者たちに説明をしなくてはならないから」
「は…はい、すみません、では、途中までご一緒します」
説明すると言っても、殆どはヴィオルが話すことになっていて、自分は後ろに控えているだけだ。使者たちが待っている部屋の前でサリエルと別れ、ヘディンは気を引き締めてその扉を開いた。
ヘディンがサリエルに話した通り一遍のことを、ヴィオルは祝賀に集まった使者や貴族に伝えた。カルディアの影の支配者と言われるヴィオルの手前、特に意見も不平不満もあがることは無かった。それどころか、クスクスと笑え声さえ漏れていたのだった。
ラークは末席で静かにその会話の内容を聞いていた。大体、ヴィオルがファーナのことを嫌っている。それは既にこの会場にいる者達に浸透しており、蔑みや嘲りの感情を生み出している。
「あの低俗姫だ。閣下もそれほど真剣に探せと言っているわけではない」
「確かに。形式上は捜索するとしても、結局は戻ってこない方が閣下にとっては都合がいいはず。我らもそれでいいだろう」
と、こんな調子である。
ファーナの母親は後妻だ。それも、後宮上がりの身分の低い女性だと言うから、母子共々誹謗中傷されていた。それに耐えきれなくなったのか、母の方はファーナが四歳になった年に突如居なくなってしまった。その時は、単に離婚して実家に帰ったということで収まった。残されたファーナ一人が、陰口を叩かれることになってしまった。
そんなファーナを庇い続けたのが、父ハサンと兄ヘディンだった。しかし、世間では「低俗なる姫、高貴なる王子」と揶揄され続けていた。
あらかたの説明が終わり、各々がその部屋から去ると、ヘディンはラークの元に近寄った。ヴィオルも既に退室している。
「…話にならん」
不機嫌な様子でラークは溜め息をついた。未だ椅子に座り、腕と足を組んで背もたれに体重を預けた。
「だがこれでいい。もし下手にヤツと一戦交えることにでもなったら、ヤツの存在が明るみに出る」
『堕天使』の存在はとにかく伏せていたい。それがヘディンとヴィオルの唯一の共通認識だった。民をいたずらに不安に晒すより、何も知らない方が幸せなこともある。それにこれは王家の機密事項なのだ。
「…果たして、どこまで隠し通せるものかな」
「しばらくは何とかなるだろ。立ち会ったのは俺たちだけなんだから。…もっとも、いずれは瓦解するだろうけど」
人の悪い笑みをヘディンは浮かべた。それを見て、ラークもまた似たような笑みを浮かべる。
「…でも、ファーナ、無事かな」
天井を見上げて、ぽつりと、へディンは呟く。
「ヤツが本当に伝説通り、『堕天使』と呼ばれる男なら、今頃ファーナは無事じゃない。…ま、上手く逃げられているかもしれないが」
「ファーナもそんなに弱くはない。…それよりも奴だ」
「そうだな…。正直、生粋の竜人なんて相手にできないよな…」
ヘディンは深い溜息をついた。しかし、ラークは不敵な笑みを浮かべている。
「ん?何か策でも?いくらお前でも…」
「任せてくれないか。…いや、これは私にしか出来ないことだ」
ラークは言葉を遮ってきっぱりと言い放った。ヘディンは深く溜息をついて、一瞬考え込んだが、納得したような表情で返答した。
「…解ったよ。止めたって、それがお前の本当の“仕事”だもんな」
日は南中した。山中を、今度は少し休憩を入れながら、ファーナとカティスは歩いていた。相変わらず言葉はあまり交わさない。上り下りが幾度も続く。一体今居る辺りがどこなのか、ファーナには見当が付かなくなっている。少なくとも、今太陽がある方角――南が進行方向であることは間違いなかった。
「…!」
目の前を歩くカティスが急に止まった。ガサガサと、何かが森の奥から近づいてくる音がする。ファーナも咄嗟に身構えた。
「まさか、魔獣?」
「そのまさかだ。姫さん、アンタ腕っ節の方は?」
小さい声で言葉を交わしあう。五百年前に駆逐されたはずの魔獣達は、生き残りの子孫達が、今も息を潜めて人里離れた山奥などに住み、時折人間を襲う。
「体術と、火の魔法…簡単のなら、他系統も」
「それだけあれば上等だ。来るぞ!」
草木を掻き分ける音が大きく、早くなる。その音の方向に、ファーナは身構える。
「グオオオオオッ!!」
咆哮と共に、犬のような魔獣が数頭飛び出してきた。足は六本、頭は二つ。その頭を振り乱し、口から唾液を垂らしながら襲いかかってくる。
『我が血と盟約結びし火の精よ、我が拳に纏え』
ファーナは拳に炎を作り出し、覆い被せられる前にその魔獣の腹に拳を繰り出した。更に襲いかかってくる魔獣を、身を翻して蹴り上げる。木々の奥まで弾き飛ばすが、入れ替わり新手が襲う。
「あーもう、ここが森じゃなかったら、魔法で一撃なのにっ」
拳を繰り出しながら、ファーナは喚く。
「燃やすなよ、火事になったら手ェ付けられねぇからな」
カティスは身近にあった木の棒を上手く使い、魔獣を殴り倒していた。
「…だが、これじゃホントに埒あかねぇなぁ…」
結局、四方を十数頭の魔獣に取り囲まれた。いつどこから襲いかかられてもおかしくない。目をギラギラさせて、グゥウウゥと唸っている。ファーナとカティスは背中合わせになって身構えた。
「くっ…貴方、世界を震え上がらせた『堕天使』なんでしょう?何とかならないの?!」
息が上がったファーナが後ろのカティスに文句を言う。その言葉を聞いて、カティスは溜め息をついた。しかし、口元には笑みが浮かんでいたことを、ファーナは知らない。
「…いいのか?後悔するなよ…。よく聴いておくんだな」
カティスは目を閉じ、すうっと息を吸う。そして静かに詠唱を始めた。それは、ファーナが一度も聴いたことのない言葉で紡がれる。冷たく、そして、胸の底に大きな不安が起こるような、不思議な言葉だった。
「!」
程なくして、周りの魔獣達がパタパタと倒れていった。中には苦しみもがくのもいる。詠唱が終わった頃には、もはや全てが絶命していた。
「な、何、これっ…」
ファーナは驚き、魔獣とカティスとを見比べた。カティスの耳に付いているピアスの紫色の石が、淡く発光している。
「…その石!ま、まさか、闇の精霊術…」
実際に聴いたことは無かったが、知識としては学んでいた。他者の命を左右する、いわゆる禁呪である。紫や黒の宝石―ジェムに、多く闇の精霊は宿ると言われる。
「そういう事だ。どうだ?初めて聴いた感想は」
満足そうな笑みをカティスは浮かべた。ファーナは恐ろしい物を見たかのような形相で、カティスを睨む。
「信じられない…!禁呪よ?!こんな…簡単に生き物の命を奪うなんて!」
対してカティスは、人を小馬鹿にするような笑みを浮かべていた。
「おいおい、さっきお前自身が言った言葉、忘れたのかよ?『堕天使』の俺に、何とかしろって言っただろ。望みどおりにしてやっただけだが?」
その言葉にファーナは絶句した。『堕天使』――この能力があったからこそ、彼はそう言われたに違いない。簡単に他者の命を奪って、そうしてこの世を支配せんとした――。そして何の躊躇いもなく、今もこの禁呪を使う。
「…貴方が、地獄だって言うほどの罰を受けても、貴方は五百年前から何も変わっていないってことなの?また世界を恐怖に陥れて、自分のものにしようと考えてるの?!」
既に前を向いて進み始めたカティスに、ファーナは悲鳴に近い叫び声を上げた。カティスは足を止め、ファーナの方を振り返る。
「変わることなんぞ無い。この世界を壊すこと…。それが俺の目的だ。他人の命なんざどうでもいい。俺の前に立つ者は、全て殺す」
まるで決意表明だ。きっぱりと、迷うことなく言い放った。初めて『堕天使』の本懐を彼は語ったのだ。その言葉に、ファーナは呆然とした。
「…」
「ククッ…言葉もないか?改めて責任感じてんだろ?…愚かな姫さんだ」
カティスはファーナに歩み寄り、右手でファーナの顎を引き上げた。緑の瞳が、ファーナの紅い瞳を射抜く。
「どうせならお前も堕ちろよ。俺の所まで来てみろよ。立つ場所が変わるだけで世界の真実は変わることはない。…なあ、お前がしたことは本当に過ちか?楽になるぜ?」
舐めるような口調でカティスは囁く。背筋が凍る。この男は、敵である自分を誘惑している。昨日も感じた、緑の双眸に吸い込まれるような感覚。生粋の『天使』が本来持つ、魅力そのものなのだろうか。ファーナは何とか目を閉じてかぶりを振った。
「ふざけないで。立場が変われば勿論世界の見え方だって違うのは解る…。でも、貴方の存在は、どんな立場に立っても邪悪であることに変わりはないわ!」
必死でファーナは自分を保とうとする。半分は自分に言い聞かせるように、語気を強めて言い放った。カティスは諦めたようにぱっと手を離し、また進行方向に向いて歩き出した。
「その天教の戒律を破ったのはどこのどいつだ?…まあいい。お前も直に解る日が来る。お前なら、きっと俺の所まで辿りつく」
笑いながら颯爽と進んでいくカティスを、ファーナは鋭く見める。敵だ。絶対に心を曲げてはいけない。そう思うことが、カルディアの王女としての残されたプライドだった。それすら捨ててしまえば、自分はどうなる?カルディアに帰ることは絶対に許されない。「もしかしたら」という一縷の望みさえ、断たれる気がした。
「お兄ちゃん…私…、頑張るから…。」
カティスに聞こえないように、ボソッと呟いた。自分を冷酷に突き放し、剣まで向けた兄を、ファーナは未だ心のどこかで信じていた。否、すぐにはその現実を受け入れられなかった。
考えれば考えるほど、深みに嵌っていく。それを振り切るかのように、ぶんぶんとかぶりを振り、ファーナもまた後に続いて歩き始めた。
日が傾き始め、カルディア城の南城門前にも、長い影が落ち始めていた。ラークは背に馬車を従え、ヘディンと向かいあっていた。ヘディンの後ろには、黒髪を一本で纏め、青い軍服を着た女性が立っている。
「エルガードの長老達によろしく頼む。それと…ファーナも。もし会うことがあれば、どうか護ってやってくれ。今の俺には、お前に託すことしかできない」
苦渋の表情を浮かべるヘディンに、ラークは少しだけ微笑んだ。自分とは正反対で、ヘディンは感情が表に出やすい。その人間臭さが羨ましいとさえ思っていた。
「会えればな。ファーナの命の保証はしよう。攫ったヤツは生死を問わないのだったな?なら遠慮無くやらせてもらう」
ラークの口調は落ち着いていたが、随分物騒な事を言っている。後ろの女性に聞かれてもいいような言葉を選んで話していた。
「そうだな…あとは神のお導きってやつに任せるか。武運を祈る」
「神がいればな。では、全てが済んだらまた会おう」
ラークは城門に背を向け、待たせていた馬車に乗り込んだ。しばらくして、馬車が動き出す。南の方向へ、止まることなく走り去った。
それを見届けていたヘディンに、後ろに控えていた女性が近づく。
「…王子、仰せの通り、騎士達に捜索を命じます。半数がハルザード待機で本当によろしいのですか?」
「ああ。混乱に乗じて、ハルザードで不測の事態が起こるやもしれん。地方については、主に各国や領事達に任せるとするさ。宮廷騎士は遊撃部隊。その領事達では手薄になるところを潰していって貰うのが役割だ」
「…姫を本気になって捜してくれる貴族も国も、無さそうですけれど…」
女性は主筋に対してある種暴言を吐いた。しかしヘディンは気にかけなかった。
「お前達宮廷騎士なら捜してくれるだろう?ライラ。つまり、お前達が一番大きな役割を担ってるんだ」
ライラははっとした。王子であるヘディンが、絶大な信頼を置くのが、王家直属の宮廷騎士団だ。人数は十二人と少数だが、それぞれが個性を発揮して、王族の手足となって働く。ファーナも無論護るべき人物であるが、その役目以上に、ファーナの人柄を好いている騎士もいる。噂や対面を気にして何もしない貴族達よりも、この件に関しては、そんな宮廷騎士団を頼っているのだと、ライラは自覚した。
「はっ…。必ずや、我らが見つけだしましょう」
「頼む。ただ、無理だけはするなと伝えてくれ。もしも誘拐ということであれば、背後に何が絡んでいるか解らないからな」
ヘディンは真実を知りながら、平気で知らない振りをする。本音を言えば、深追いなどしないで欲しいのだ。ファーナの事は抜きにして、このままヤツを野放しにしてはいけないと思いつつ、野放しにしてみたいという黒い欲望が、徐々にヘディンの胸中に広がりつつある。
「心得ております。…ですが、例えば…家出、だったとしたら…我らは引きずってでも連れてくるべきでしょうか?」
ヘディンはそのライラの半ば無邪気な問いに「うーん」と唸った。しばらくして、口を開く。
「…俺を捨てて行ったと思うか?」
「例えば、ですよ?」
コホンとライラは咳払いをする。
「…放っておけ。アイツの意志を、勝手に俺達がねじ曲げる訳にもいかんだろう…。息災かどうか確認して、後は逐一連絡寄こせとでも言っておいてくれ」
はぁ…と深く溜め息をついて、ヘディンはがっくりうなだれた。その背中をライラが軽く押して、城の方へと導く。
「…無事ですよ。そして私たちが必ず見つけだします。ですから…」
「いや、うん、それは…。ただ、家出だったらショックだなぁと思って」
クスクスとライラは笑う。ヘディンはその横顔を、複雑な表情で見つめていた。二人はそのまま、城の中に入っていった。
カルディアの西の空に、陽が落ちていった。
秋晴れの北の空に、一つの人影が浮かんでいた。
青い軍服に身を包み、長い緑の髪を北風に棚引かせている。年の頃は20代半ばの女性だ。
固く目を閉じて、眉間に皺を寄せている。何かを聞き取ろうと傍耳を立てているようにも見える。ややしばらくそうしていたが。
「あー!もう、駄目だあーっ」
苛立った声を上げ、女性は緑の目を見開いた。癖のある長い瞳と同じ緑色の髪を、無造作に掻きむしる。
「…向こうに私以上の『風読み』がいるってこと?そうでなきゃ、こんなジャミング、できっこないよ…」
建物よりもずっと高い空中で、彼女は愚痴る。地上に戻るか否か、考えていたその時。
「…え?」
南から来た『風』が語る。
『世界が変わるよ。闇が目覚める』
「え?何、どういう意味?!」
『風』からの答えは無い。その代わり、同じ方角から、鳩が飛んできた。見覚えがある小さな管を足に付けている。
「…王子の!」
鳩を捕まえて胸に抱く。足に付けられた管の表面には、『ハサン王宛』と書かれていた。日付は、二日前。
「…いつもなら、使者の便を使うのに、一体どうして…」
嫌な予感がする。鳩を抱いたまま、陣地へと戻った。
幕舎が無数に並んでいる一角に彼女は降り立ち、入口にあるゲージに鳩を仕舞い込んで中へと入った。そこには、大きな机に広げられた地図をじっと見つめる一人の青年の姿があった。
「カリーナ、ただ今戻りました…って、なんだ、シオンだけ?」
「いや、奥にハサン様はいらっしゃる。それで?『風』は読めたか?」
シオンと呼ばれた青年は無表情のままカリーナにきつい視線を送る。彼もカリーナと同年代の若者で、同じ青い軍服に身を包んでいる。
「駄目ね…。私より上手の『風読み』がいるみたい。向こうの陣営に関することは、全然聞き取れない。でも…」
「でも?」
「変な声を聞いた。世界が変わる、闇が目覚めるって。南から来た子がそう言うの」
「…闇だと?」
陣の奥から、低い声と共に足音が聞こえてきた。
「あ、ハサン様」
奥から姿を現したのは、白髪交じりの赤毛の壮年だった。紛れもなくカルディア神聖王国の王であるのだが、普段はどこか軽い印象がある。しかし今日はいつもより真剣味が増しているように、カリーナには感じられた。
「は、はい。南から、『闇が目覚める』って。あ、それと、王子から」
カリーナが、鳩の足に括り付けてあった手紙を差し出す。その手紙を、ハサンは一読して、顔を歪めた。
「…そうか…」
目を閉じ、じっと考え込んでしまった。ハサンが握り締めた手紙に、シオンが目線をずっと向けている。
「ハサン様、王子は何と?」
「…ファーナが、行方知れずになったという連絡だ」
その言葉に、カリーナとシオンは表情を固くした。
「えっ…」
「…どういうことです?」
「解らん。ただ、それだけしか書いていないからな。詳細は戻られてから、とな」
ハサンが手紙をシオンに渡す。そこには、いつもと同じ、力強いヘディンの筆跡で、今言ったようなことが書いてあった。
「…不思議な手紙だ。重要なことなら、仔細に書いてくる筈なのに。しかも、これは王子からの撤退要請ではありませんか」
それとも、この文面で伝えるべきことは足りているのか?とシオンは勘繰った。
「ああ。…もうじき冬も来る。最低限の守備隊だけ残し、我らは撤退の準備にかかるぞ。…シオン、休戦の使者を出しておけ」
「はっ…。仰せのままに」
シオンは風を切るように、颯爽と部屋を出て行った。それを見送って、カリーナがおずおずと、気になることを聞いてみた。
「ハサン様、…姫がいなくなったのと、『風』たちの噂は、何か関係が…」
御伽噺に聞いたことがある。カルディアの王家は、闇の封印を監視していると。その封印がよもや解かれたのでは。それに姫も巻き込まれているのでは――?
「さあな。この手紙からは何も読み取れん。とにかく、帰ったら詳しく聞くことにしよう。必要な対策はヘディンが取っているだろう。…ああそれと、その『風』の件は、他言無用にしろ。いたずらに周囲の不安を掻きたてる必要はない」
「は、はい…。解りました」
一礼して、カリーナも幕舎から出る。空は雲もなく、変わらず晴れ渡っている。
「何も起こらなければいいんだけど…」
虚空に、カリーナの呟きが消える。いつもと変わらない空のはずなのに、感じる『風』は、ゆっくりと、漠然とした不安を奏で始めていた。