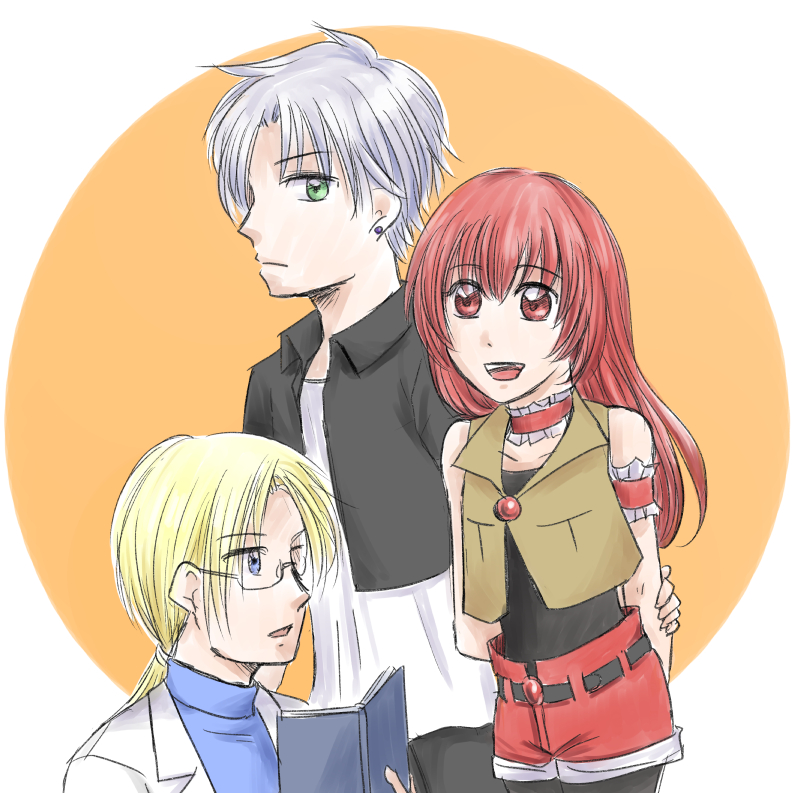スコールが降りしきる中、ラズリの船は目的地へと向かって進んでいた。海へ打ち付けられた雨の雫で水分が跳ね上がり、周囲は霧に包まれていた。
「参っちゃいますねぇ、この天気…」
操舵室で舵を取るシジェがぼやく。
「天気はどうしようもないからな。方向さえ見失わなければ…」
ラズリがそう言いながらコンパスを見る。すると、急にぐるぐると針が回りだしてしまった。
「なっ…!」
「どうしたんすか、お頭…?」
「シジェ、引き返せ!コンパスの磁界がおかしくなっている!これは…」
「ま、まさか、『神隠し』?でも、お頭は…」
「それとこれとは関係ないのかも知れない…今はそれよりも舵をっ…うわっ」
ラズリが言葉を言い切る前に船体がゴゴッっと大きな音を立てて何かにぶつかり大きく揺れる。そのはずみでラズリは尻もちをついてしまった。
「何があったんだ?!」
異常事態に気づき、ラークとファーナ、他のクルー達が操舵室に駆けて入ってきた。座り込んでいるラズリにファーナが手を伸ばし、立たせる。窓の外は真っ白で、周囲に何があるか分からなかった。
「『神隠し』にあったようだ…」
「『神隠し』?」
ファーナがラズリに聞き返す。
「船乗りの間の伝説っす。水神さまが気まぐれに航海中の船を遭難させてしまうって。でも、お頭には水神さまが付いているからそんなこと無縁なんだとばかり…」
「…『神隠し』は水神さまとは関係ねえな、多分」
遅れて操舵室に姿を見せたカティスがぽつりとつぶやく。どこか険しい表情を浮かべていることに気が付き、ファーナは不安になる。
「…何か心当たりが?」
「…この感じ…異界に彷徨いこんだんじゃねえか」
「い、異界?!」
操舵室の中がざわめく。
「どうやって元に戻れば…」
「…入口もあれば出口もあるはずだろ。…それよりも、さっき何かにぶつかったみたいだがそっちはいいのか?元に戻れたとしても、船が壊れて浸水して来たら堪ったもんじゃねえ」
「確かにそれは一理ある。…皆、船体のチェックを!」
ラズリの掛け声にウス!という威勢のいい返事が聞こえ、皆それぞれの持ち場へと捌けていった。
「ダタ殿にも船体のチェックと修理を頼みたい。貴方の技術は助けになるはずだから」
「それもそうですな、姫様、それでは行ってまいります」
「ダタ、気を付けてね」
「ええ」
会釈して、ダタもクルー達の後に続いて操舵室を後にする。その姿を見送ってから、ラークが口を開いた。
「我々は一度外に出てみよう。このような視界では周囲がどうなっているかも分からないが、不意にこの船が何者かに襲われる可能性も無くはない」
ファーナがこくりと頷いた。
「うん、そうだね…。ちょっと怖いけど…。元のところに帰れるまでどれだけかかるかわからないし」
甲板に出ると、ひんやりとした空気が辺り一帯を覆っていた。周囲は深い霧でほとんど何も見えず、三人は甲板からロープを伝ってゆっくりと地面に着地した。
「この霧が厄介だな…。ファーナ、少し気温を魔法で上げられるか?この霧を飛ばしたい」
ラークがファーナに提案をする。
「あ、なるほど、そうか。やってみる」
うーん、としばらく悩んでからファーナは詠唱をした。霧が次第に晴れて、視界が開けてくる。周囲は岩場で、先ほどまで航行していた海は見渡す限り見えない。植物もほとんど生えていない不毛の大地――そんな印象を受けた。
「完全に違う場所だね…。それに何もないし…。あっ」
ファーナの視界に、岩とは別のものが入った。遠くに木製の構造物がある。それを指さしてラークとカティスに向き直った。
「あそこ、何かあるよ!行ってみよう?」
飛び跳ねるように走っていったファーナの後姿を、カティスとラークは顔を見合わせて互いに渋い顔をした。
「…行くか」
「しゃーねえな…。何か嫌な予感がするんだが…」
二人もゆっくりとファーナの後に付いて歩く。先を走っていったファーナは途中で足をぴたりと止めて、何かを窺うように慎重な足取りになった。
「…?」
「どうした、ファーナ」
ラークは心配になって小走りでファーナの元に駆け寄った。
「先生、これ…」
ぞっとした顔を浮かべて、ファーナはその先を指さした。そこには朽ちかけた木造船が幾重にも折り重なっており、まるで塔のようにそびえたっていた。
「これは…まるで船の墓場だな…」
ラークもごくりと生唾を飲んだ。
「この船って、私たちと同じようにここに迷い込んだ人たちの末路ってことだよね…?私たちもここから出られなかったら、こんな風に…」
「出られなかったら、な。我々は出る方法を探す。それより…」
ラークが渋い顔をして振り返る。後ろからゆっくりと歩いて来ていたはずのカティスが、胸を押さえて立ち尽くしていた。息が荒くなっているのが見て取れる。
「カディ…?どうしたの?具合が悪いの?」
そう言って駆け寄ろうとしたファーナの肩を、ラークが掴んで止める。
「私が行く。それより一つ頼みがある」
「え?頼みって…」
「この船と、乗っていたはずの人々の『魂送りの儀』をしてほしいんだ」
「『魂送りの儀』…?私、ちゃんとやったことないけど…?それに、この人たちは天教徒じゃないかもしれないよ…?」
ラークの言葉にファーナは戸惑う。『魂送りの儀』は、カルディア王家の者が、死した天教徒の魂を天に返すという葬送の儀礼の一つだが、ファーナは周囲の踊り子として踊ったことはあるものの、実際に葬送を執り行ったことはなかった。
「お前のやり方でいい。ただ…天にも地にも還ることのできない魂が、ここに滞留しているのが問題なんだ。彼らに道筋を付けてやってくれ、頼んだ」
ポン、と肩を叩いて、ラークはカティスの元へと歩いていく。その後姿を見送って、ファーナは船の残骸に対峙した。思い出す。兄が、父が、祖父が、どのようにしてその儀礼を行ってきたか。記憶の中のその姿を、弔いの詠唱を、一つ一つ、なぞるように。
『天を統べる神イーレムよ、我が言葉を、祈りを奉ず。
我が聖火によりて彼の御魂を天へと葬送す。我は希う、彼の者達の生命の、魂の、地界での一切の労苦と悲しみを癒し、彼らに永久の安寧が与えられんことを――』
そこまで言葉を紡いだファーナの耳に、ギィン、と剣戟の音が入ってきた。はっとして振り返ると、カティスとラークが剣を合わせていた。状況が飲み込めずファーナは動揺した。
「…!ちょっと!先生これってどういう…!?」
「いいから、お前は儀式を続けろ!」
「で、でも」
ふと、カティスと目があった。目を爛々とさせて、興奮しているような、我を失っているような――。その獣のような眼光に、ファーナの背筋は凍った。
「っ…!」
どう考えても普通じゃない。よく分からないが、ラークの言う通りに儀式を続けることが、今自分ができる最善なのだと言い聞かせる。
ファーナは再び船へと向き直る。両手を天に掲げ、巨大な火の玉を発現させた。
『聖火よ、彼の者の魂を白煙に乗せイーレムへ導き給え!』
火の玉が船の残骸へと飛んでいく。船体の一部に火が付くが、全体には行き渡らない。その状況にファーナは内心焦る。
「くっ…!もっと…!『我が炎よ、大地を焦がせ!空に、天に轟かせ!』」
一段と大きい炎を作り出し、上段へぶつける。それでもなかなか燃え広がらない。魔力の消耗で身体が疲弊して、ファーナは肩で息をしていた。
「うう~~!こうなったらやれるだけ…!」
(ファーナ、早く…!)
カティスから繰り出される滅茶苦茶な剣筋を、ラークはなんとか受け流すことで精一杯だった。この異界に来てから予想はしていた。かつて航海中に同じようにここに紛れ込んでしまった船は、乗組員はどうなっただろうか。抜け出すことができずに朽ちてしまったのなら――。
その予感は的中したし、それによって引き起こされる事態も的中してしまったのだ。
「くっ…!これが…『堕天使』と呼ばれた所以…!」
バイタルでぽつりと言っていた。闇の精霊は生死を司る。数多の
『死』に直面したら、この目の前の男はどうなるか。本能的に、より多くの『死』を欲してしまう。
「命を寄越せ…!」
「やれるものか!」
一瞬の隙をついて、ラークは思い切りカティスの腹を蹴飛ばした。カティスの身体が数歩後退する。わずかに作られたその瞬間に、ラークは賭けた。
『光よ、彼の者を捕らえよ!』
勢いよく振りかざされた腕に呼応するかのように、カティスの周りに光の檻が出来上がった。
「ぐっ…」
カティスはその場でよろめき、膝をついて頭を抱える。
「これで、闇の精霊の暴走を少しは抑えられるか…?」
息を整えながら、ラークはカティスに近づいて、見下ろす。頭を抱えたまま苦しみの声を上げている。
「…お前のその内にある闇の精霊を取り払えば、お前はどうなる…?」
ぽつり、とラークは呟いた。
「…んなこと…お前に…できるのかよ…」
息も絶え絶えのカティスの声が聞こえた。正気を取り戻しつつあるようだった。
「それが我が一族に与えられた使命だからな。やってみなければわからない。ただ…もしできるとしたら、お前はそれを望むか…?」
しばらく沈黙が流れる。カティスの荒い息遣いだけがラークの耳に入ってくる。
「誰かの命を奪うこと…それをお前は、望んでいないんじゃないのか?こんなことが起きるならいっそ、とは願わないのか…?」
語気を強めてラークが言う。バイタルで見せたあの表情こそが、彼の本音ではないのか。
「…解った風な口を…」
重い沈黙を破り、カティスが言葉を続けようとしたその時、眼前から瓦礫が崩れるような轟音が聴こえた。船の墓場が火で包まれ、崩れ去っていく。煙は曇天の空へと立ち昇り、雲と同化していく。その様子を、地面にへたり込んでファーナは眺めていた。
その様子を見たラークの表情が少し緩む。
「…ファーナ、上出来だ」
ラークの言葉に、力ない笑顔を浮かべてファーナは振り返った。
「えへへ…頑張ったでしょ…。これならきっと、イーレム様の所に迷わないでみんな行けると思う」
そう言って、ファーナは再び煙を見上げた。ラークも、カティスも、同じように空を見上げる。やがて船体が炭と化し、内部で火がくすぶるようになった頃合いで、カティスが口を開いた。
「おいセンセ、もういいからこの檻どうにかしてくれよ」
「…ああ、忘れていたな、すまない」
パチン、と指を鳴らすと、光の檻は消えてなくなり、カティスはゆっくりと立ち上がった。
「忘れてた、じゃねえよ!あーくそ…具合わりぃ…」
「何だ、悪態をつく威勢は残っているじゃないか。それだけ元気なら、ファーナに手を貸してやれ」
そう言って、ラークはカティスの肩をポンと叩き、ラズリの船の方へと歩き出した。
「お前がやればいいだろうが…っ」
鳴りたくなるところを抑えながらカティスは悪態を吐いたが、一つ大きな息を吐いてからファーナに近寄った。
「カディ…?」
差し出された手と少し照れたようなカティスの顔を、ファーナは信じられないといった顔で見上げた。
「早くしろ。…一応、礼だ、これは」
「へっ?」
何のことか思い当たらず、ファーナは素っ頓狂な声を出した。
「お前自分がどうしてあの船焼いたのか分かんないでやってたのか?」
呆れたような声をカティスは出した。
「え、だって先生が燃やせって」
「あれは言わば死体の山だったんだよ。何年モノかは知らねえけど、とにかく闇の精霊が好む環境だ。だから俺は…それに中てられたってわけだ、不甲斐もないが」
「…私がバイタルでなっちゃったのとおんなじ感じ?」
「ああ。もっと死が、命が欲しくてたまらなくなる。それが抑えられなくなっちまうんだよ。…知ってるか、『死の大地』って場所を」
ほら、とカティスが促す。ファーナは手を伸ばして、カティスに引き上げられる形で立ち上がった。ふらり、と身体がぐらついたところで、カティスがファーナの腕を引っ張った。ファーナの身体がカティスに預けられるような格好になる。その身体の温かさに、ファーナは一瞬どきりとした。
「あっ…ゴメン…」
とっさにファーナがカティスから身体を離す。そのまま微妙な距離を保ったまま、ゆっくりとラズリの船の方へと向かう。
「『死の大地』、勿論知ってるよ。『天使』が『堕天使』に大量虐殺されたっていう、カルディアの東にある高地…。定期的に王家の誰かが弔いに行くもの…。あっ、もしかしてそれって」
カティスはゆっくりと頷いた。
「何一つとして覚えてないが、旨くて、心地よくて、もっと欲しいと本能的に駆り立てられたことだけは、感覚が残ってる…」
右手の手のひらをじっと見て、カティスは回顧する。
「その時に、ハーレイ様が追い払ったって…」
「ああ。アイツがいなければ俺はどうなってたか分からねえな。…今回もその子孫に助けられるとは、全く何の因果なんだか。だから、礼だと言った」
そっぽを向きながらカティスは言い捨てた。
「…私はできるだけのことをしただけだし、先生がいなかったら私だけじゃ多分カディを止められなかったと思うよ」
そこまで言って、ファーナは一瞬口をつぐんだ。「カティスが何か悪いことをしたら自分が止める」と意気込んで付いて来ているはずなのに、自分一人だけではこの男を止められることはできないと、身に染みて理解したのだ。彼の本意がどこにあるのか分からない今、いざまた「その時」が来たとしたら、自分は一体何ができるのだろうか。
「…だから、先生にもお礼言ってね」
多分、礼を言わなければいけないのは自分ではないか、と思う。自分の不手際を、ラークがカバーしてくれているのではないか。
「アイツに言うのは何か癪だな…」
「もう、素直じゃないんだから…」
クスっと笑みがこぼれる。
「それよりも、どうしよう。ここから元の海に戻れるのかな」
「ああ?出来るに決まってるだろ。『門』を開けばいい。俺を誰だと思ってるんだ」
にいっ、と口の端を上げてカティスが笑みを作った。
「あ、お帰り皆。外はどうだった?だいぶ時間かかってたようだけど」
ラズリが三人を出迎える。
「同じようにここに迷い込んだ船が向こうにいっぱいあったの。それを供養してきました」
疲れた笑みをファーナは浮かべた。
「…そりゃ大変だったな。船体については致命的な傷はなかった。クルーたちももう全員乗船しているから、いつ海に戻っても大丈夫だ」
「それじゃあ…」
カティスが詠唱をしようとしたその時だった。船がふわりと宙に浮き、丸いシャボン玉のような膜に覆われた。船の目の前の景色がぐにゃりと曲がったかと思うと、一面真っ白な空間になった。
「な、何ここ…?」
ファーナは身体が粟立つ感覚に襲われた。懐かしいような、居たくないような、そんな不思議な感覚。
「誰だ!?」
カティスが叫ぶ。その言葉に、今の現象にカティスが一切関わっていないことをその場にいた全員が悟った。しかし言葉は返ってくることなく、目の前にぐにゃりと曲がった大海原が現れた。
ゆっくりと着水したところで、シャボン玉のような膜ははじけ飛んだ。転移する前に降っていた大雨は止んでいて、既に日が傾き始めている。
「…何が起こったんだ…?現在位置を確認してくる」
ラズリが慌てて操舵室へと駆けて行く。カティスは周りをつぶさに見渡すが、特に変わった様子は見受けられなかった。
「ねえカディ、さっきの白い空間…なんだったの…?」
ファーナが不安そうな表情を浮かべてカティスに聞く。
「…あそこは『闇世』…。総てが帰り総てが生まれいずる場所。そして…数多の時空を繋ぐ場所だ」
「『闇世』…。死した後に魂が行くと、天界で言われていた世界のことか…。宗教上の概念の話ではないのか」
ラークが驚いた様子でカティスに尋ねる。
「天界のほとんどの奴らはそう思ってたはずだ。異世界に渡る時に必ず通るから、この世界に来た『竜人』は全員知っているはずだが、それが『闇世』だと認知していた奴らは多分いない」
「さっき、カディは何もしてなかったんだよね?たまたま開いたってこと?」
ファーナの問いに、カティスは渋い顔をして頷いた。
「…そうかもしれねえけど、それにしてはタイミングが良すぎる。まるで誰かが俺達の行動を見ていたかのようだ…」
そんなことを話している最中に、ラズリが甲板に戻ってきた。
「どうだった?」
「元居た座標と変わらない。戻ってこれたみたいだ…」
「よかった~。細かいことはとりあえず置いといて、元通り先に進めばいいってことよね!」
ファーナがパン、と手を叩いて喜ぶ。
「それもそうだな。元通りの航海を続けよう。…総員配置に就け!」
ラズリが声を張り上げてまた操舵室へ戻っていく。
「私たちも、船室に戻ろうか」
ファーナが声をかけて、ラークと共に船内へ入っていく。カティスはその場に残ったまま、じっと周りを見渡していた。
「一体、誰が…」
そのつぶやきは、海風にかき消されてしまった。
天空を突き抜けるほどに巨大な樹の葉の間から、橙色の陽光があちこちに差している。その中を疲れたようにとぼとぼと肩を落としながら長い銀髪の青年が歩いてくる。年の頃は見た目若く、小麦色に焼けた肌と長い耳が特徴的だ。
巨大な木の幹の前にいるフードを被った女性に会釈をして、青年は幹に向かって姿勢を正した。
「…ギアナ」
青年は巨大樹の幹に向かって話しかける。すると、幽霊のような出で立ちで、土色の髪の女性の姿が浮かび上がった。青年の姿を確認すると女性は少し驚いたような表情を見せた。
『ジュライ。しばらく見なかったけれど貴方今までどこに…』
「ミイラ取りがミイラになっちゃって…。洋上の『門』を閉じに行くはずが逆に向こうに飛ばされて、帰るに帰れず…やっと戻って来ることができたんだよ…」
はあ…と疲れ切った溜息をジュライは吐いた。
『そう…それは災難だったわね。でも、私を呼び出したのはその報告以外にも理由があるのでしょう?』
「それが、帰りの船に居合わせたんだよ、『天の守人』。ただ…人が多くて姿を現して挨拶するわけにいかなくて。こっちの世界に戻ってすぐここに『飛んで』きたから」
その言葉を聞いて、幹の傍に居た女性がはっと顔を上げた。
『…どの地点かしら』
「ロートの港まで船で正味3日ってところかな。混乱を避けるためにも使いを出した方がいいと思って。今なら間に合うし」
『それがいいわね。…サイを呼んできて貰えるかしら、セディナ』
幹の傍に居た女性はそう呼びかけられると、叩首してその場を立ち去った。それを見計らって、ジュライが口を開く。
「それじゃ、奏上者が来る前に僕はお暇するかな。『剣』の手入れもしなくちゃね」
『ええ、念入りにお願いするわ』
「分かってるよ」
そう言って、青年は忽然とその場から姿を消した。それと入れ替わるかのように、先ほどのフードの女性と、筋肉隆々の青年が姿を見せた。
青年は膝をつき、うやうやしくギアナの前で礼をした。
「ギアナ様、お呼びですか」
『ええ。サイ。貴方のお友達が私の客人と一緒にここへ向かっているの。ロートまで迎えに行って貰えるかしら。到着までの猶予はおそらく3日。彼らは『竜人』だから、道中トラブルを起こさないようにね』
「私の友人?『竜人』の…?」
サイは呆気にとられた顔をした。そんなの、エルガードに留学していた時以外に作ったことがない。
「あっ」
サイは心当たりを数人頭の中に思い浮かべた。
『必要な書類はセディナから受け取って。官吏もそれさえあれば何かトラブルがあっても通してくれるでしょう』
「かしこまりました」
『頼みましたよ』
そこまで言って、ギアナは姿を消した。セディナと呼ばれた女性が、手元に何も書かれていない書状を持って掲げると、魔法のように文字が浮かんできた。
「これを」
手際よく書状を丸めて、筒の中に収めてセディナはサイに手渡した。
「ありがとう、セディナさん…。あの、俺の友人の『竜人』はあまりいないんだ。でも、その心当たりの中には…」
「…きっとそれが宿命だったのよ。私も心の準備をしておくわ」
サイが言わんとしていることを、セディナは汲み取って言葉を引き取った。
「もしそうだとしたら…怪我無く連れてくるから」
「私からもお願いするわね」
サイはセディナに一礼してから、足早に元来た方向へと走っていった。その場に残されたセディナは、幹を見上げた。被っていたフードが頭から落ち、左の目元にある泣きぼくろがはらりと現れた。
「ファーナ…私は…」
その呟きは、静寂な森の中に静かに消えていった。