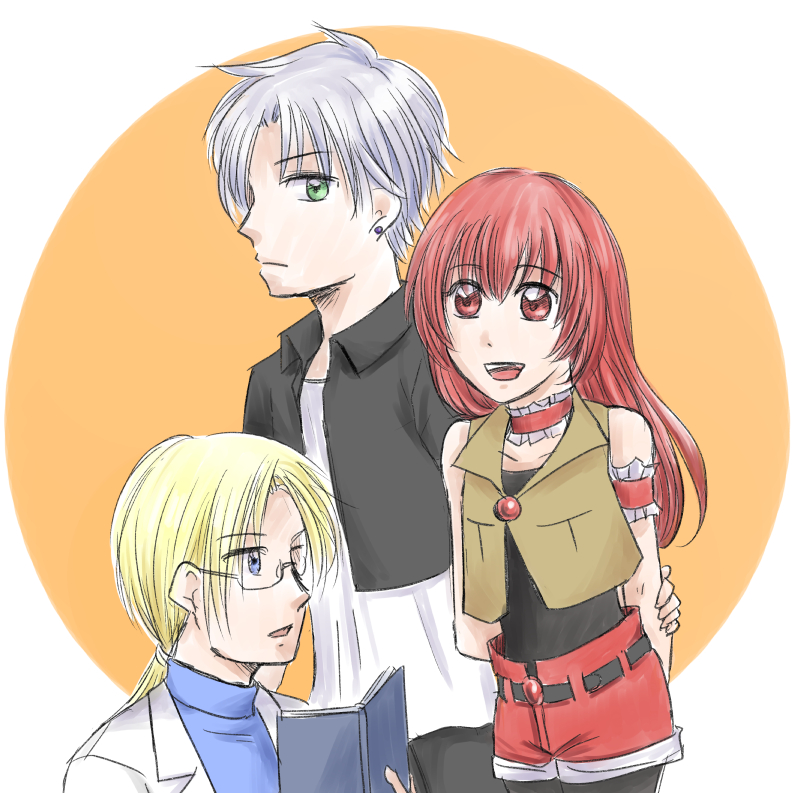白い、白い世界。
もう幾度この世界に呼ばれただろう。声も次第にはっきりと聞こえるようになってきた。
「…白天使さま…いずこにあらせられますか」
霧に包まれた世界では視界が利かない。だから、こうして声を発して探さなければならない。
『…リエル、我が…を聞く…よ』
不意に、空間に声が響いた。
「白天使さま!いずこへ…!お姿を顕してください!」
『彼の里の……の階下に、…が…。さすれば道は…』
その声を残して、ザァーっと視界が元に戻っていく。
「白天使さま!…」
手を伸ばしたが、白い世界は目の前から消え失せ、満天の星空が広がる森の風景が戻ってきた。周りには野営のテントが張り巡らされ、ところどころにくべられた照明用の松明が、パチリ、パチリと高い音を立てながら、辺りをぼんやりと照らしている。
「…里の…何の階下だろう…。そこに何が…」
ぶるっと、身震いをする。もう初冬と言ってもいい時期だ。フード付きの外套を着こんではいるが、盆地の夜は冷える。吐く息は白く、耳は痛くなるほど冷たい。
サリエルの目指す里は、ここからさらに4、5日はかかる。今はまだシャルが所属する魔獣討伐隊に同行させてもらっているが、人目に付かない山奥のさらに奥にある故郷には、途中から一人で歩いて行かなければいけない。一人になって、果たして目的地まで辿り着けるのか。サリエルの胸には時々そんな不安がよぎっていた。
「こんな夜に何してる?」
不意に、後ろから声が掛かった。振り返り見ると、猫っ毛が特徴的な青年がランプを手に持ちながら立っていた。見回り中なのだろうか、厚手のコートを着込み、腰には剣を下げていた。
「シャルさん…。ちょっと、眠れなくて。故郷が近いから…でしょうか」
困ったような笑みを浮かべたサリエルに、シャルははぁー、と深い溜息を吐いてみせた。白い息が派手に空気中へと漂う。
「いくら見張りがいるからといっても、夜は魔獣が襲ってくる可能性が高くなるんだから、特に用がないならテントの中で大人しくしていてほしいんだけど?」
ふてぶてしい態度ではあったが、シャルはサリエルを気遣うように言った。
「あ、そうですよね、ごめんなさい…」
「無事に目的地までたどり着いてもらわないと、王子が悲しむってことぐらいは、覚えておいてよ」
「あ…はい」
渋りながらも送り出してくれた王子の顔をふと思い浮かべる。初めて会ったのも、そういえばここからしばらく東に行った町だった。今回はその町の近くでこの一行と別れることになっている。
「解ったなら、早くテントに…ん?」
遠くから何か物音が聞こえた。シャルもサリエルも、その方向に視線を向ける。
「ほら、言ってるそばから魔獣だよ!サリ、お前は下がってろ!」
「あ、は、はい…」
シャルは走って物音のした方向へ駆け出す。サリエルはその場に佇んだまま、目を閉じ、ぽつりと呟いた。
『…我らに仇なす者を、闇世へと誘え』
すると、グオォォ、と大きな断末魔が聞こえ、何かが倒れた音がした。その物音に気が付いて、寝ていた兵士が何があったのかと疑問に思いぞろぞろテントの外へ出てくる。
「…今のって、魔獣の咆哮だったよな?」
「でも、それっきり何も無いな…どうしたんだ?誰かが仕留めたってことなのか?」
不思議そうに、兵士たちは顔を見合わせる。ややしばらくして、やはり首を傾げて不可解だというような表情を浮かべたシャルが、幕舎へと戻ってきた。
「シャル!お前が仕留めてきたのか?!」
兵士たちが戻ってきたシャルに詰め寄る。しかしシャルは困惑した表情を浮かべて首を横に振った。
「い、いや…行ったらもう事切れてた…。また、突然死ってやつかな…?」
シャルの表情を見て、周りの兵士たちもシャルがとても嘘をついているとは思えないと考え、互いに顔を見合わせた。
「…ま、まあ。何もなかったんだしいいじゃないか。戻るぞ」
「でも、これで3回目くらいか?魔獣が突然死してたのって」
「とても偶然とは思えないけどなあ…」
そんなことを口々にぼやきながら、兵士たちは自らの寝床へ戻っていった。
「シャルさん、無事で良かったですね。僕も戻ります」
他の兵士があらかた戻っていったのを見計らってから、サリエルは口を開いた。
「あ、ああ…。って言うか、戻ってろって言っただろ!」
「シャルさんが心配だったので」
にっこりと、サリエルが微笑む。それを見て、シャルは逆に眉を顰めた。
「まさか、お前じゃないだろうな」
「?何がです?」
「魔獣の突然死のことだよ。こんなこと、この遠征が初めてなんだ。それって、お前がこの旅に同行するようになってから…」
シャルの言葉が終わる前に、サリエルは首を横に振った。
「一介の神官に、そんな力があるわけありません。あるとしたら、神の御加護、かもしれませんね」
ぺこりと頭を下げて、サリエルは自分のテントへと戻っていく。それを、シャルは憮然とした表情で眺めていた。
(王子は一体何を考えて、こいつを旅に出したんだ…?何か、嫌な予感がする…)
カルディアの首都・ハルザードの目抜き通りを、一台の馬車が駆け抜けていく。白く塗り上げられた客車を金の装飾品を身につけた白馬が牽いて走る姿は太陽に照らされているせいか豪華絢爛としていて、それを街行く人々が物珍しそうに目で追っていた。
「どこかの国の王族がいらしたのかしら?」
「随分と煌びやかだな…」
口々に囁かれる下々の喧騒は、馬車の中までは聞こえてこなかった。
「どうなさいますか。そのまま邸宅に戻られますか?それとも…」
御者から声がかかると、客車の中の人物は長い赤い髪を右手で弄りながら言葉を返した。
「王宮に先に行ってくれたまえ」
「承知いたしました」
バシン、と馬を叩く音が大きく鳴り、馬車は速度を上げて湖に掛かる橋へと向かって行った。
「一年半もの間、留守にしてしまい申し訳ありませんでした、ヴィオル様」
「よい。それで首尾はどうだった、カナン」
膝を曲げて恭しく頭を垂れていた赤毛の青年が顔を上げる。ヴィオルと目が合うや否や、口をへの字に曲げて今にも泣きだしそうな顔をした。
「…語らずともよいわ」
ヴィオルは冷たく吐き捨てた。
「もっ…申し訳ございません!最後に邪魔が、邪魔が入らなければ…!」
「邪魔だと?」
ヴィオルが怪訝な顔をする。
「そっ、それが…、地元の海賊が反乱を起こして…封じ込めていた水の精どもを蘇らせてシャクーリアの王宮を制圧してしまいました…」
カナンはそこまで言って、再び頭を垂れる。
「ふむ…反乱側に水神の巫女か何かがいたということか…。仕方ない。お前の力で及ばなかったのだ、シャクーリアへの布教はあきらめるしかあるまい。ご苦労だったな、下がってよい」
「は……?」
カナンは呆然とした表情を浮かべて、ヴィオルを見た。もっと恐ろしい叱責が飛んでくるのかと思っていたのに、随分と反応が薄い。まるで興味が無いかのようだった。
「下がってよいと言っている。下がらんか」
「は…はっ!」
慌ててカナンは立ち上がり、足早にヴィオルの私室を後にした。
(何だ…?何かがおかしい)
そのまま城内の様子を見ながら歩く。兵はいつものこの時期よりも随分と多い。フィリアへの遠征が早く終わったのだろう。しかし、戦支度を続けているのだ。マイペースのカナンでさえも、流石に妙だと感づく。
(こういう時は、アイツに聞いてみるのが手っ取り早い)
踵を返し、カナンは目的の部屋へと真っ直ぐに向かった。
ヘディンの部屋では、ライラとレオンと共にフィリアへの遠征の打ち合わせが行われていた。正直、日々やることが少ない。天教関係の国事行為を済ませてしまえば、日中でさえ暇なものなのだ。
そんな中、扉が叩かれる。三人が一様にハッとして扉の方を向いたその瞬間――。
「やあやあ、久しぶりだね、義兄上」
声も高らかにカナンが突然入ってきた。
「か、カナン?!」
ヘディンの声が驚きで裏返る。
「あにうえ…って、この方は」
ライラがヘディンに尋ねる。
「ふふん、レディには私から説明を。私はカナン。王家の分家・キオ派の跡取りで、ファーナの許嫁だ」
「ふぁ、ファーナ様の許嫁…?」
貴族風の礼をして得意げに自己紹介をしたカナンにライラは目を白黒させる。
「まあ、私は『布教』で国に居ないことが多いし、彼女も一年前までエルガードに留学してたから、全然会ったことないんだけどね。私もここに戻ってきたのは一年半ぶりだよ」
「は、はあ…」
カナンは呆気にとられるライラから、レオンに視線を移した。
「それにしても、レオンまでいるとはね。この王宮に嫌気がさして出ていったんじゃなかったのかな?」
「まあ、気まぐれって奴ですな。それより、『布教』の旅から戻られて、王子にお会いに来たのはどういう理由で?」
レオンの問いかけに、カナンはポンと手を叩いた。
「そうそう、それだ。ヴィオル閣下にシャクーリアでの布教失敗の話をしてもどうでも良さそうだったし、兵たちはまだ戦の支度をしているから、何があったのだろうと思ってね。ヘディン、君なら知ってると思って訪ねたのだよ」
「ああ…。最近頓に魔獣の出現情報が増えていて、フィリアからの遠征部隊を早めに引き揚げさせて、その対応に追われているんだ。俺もその内現場へ赴く」
「…え?王子の君が自ら…?」
まさか、といった声をカナンは上げた。
「まあ、色々といきさつがあってな」
ヘディンの言葉に、解せないといった風な表情をカナンは浮かべた。
「私もここに戻ってくる道中、幾度か出くわしたが…。君が行かねばならないほどのことなのか」
「ああ。このままじゃジリ貧だからな。戦力はあればあった方がいいだろ」
サバサバと言ってのけるヘディンに、カナンはどこか違和感を覚える。
「ふーん、まあ、いいや。でもヴィオル閣下が熱心にその指揮を執ってるとは思えないし、他に閣下の気がそぞろになるような事があったのか?」
カナンの問いに、三人が一度目配せをする。仕方ない、といった表情を浮かべて、ヘディンが口を開いた。
「…『白天使』のことかな」
「『白天使』…?伝説の?それがどうしたんだい?」
「『白天使』のお告げを聴いたという少年が現れたんです。五百年前のように、魔獣が現れる事態となった今、『白天使』が再び降臨するのではないかと…それで気をもんでいるのだと思います」
ライラがヘディンをフォローする。
「『白天使』の再臨…。それが本当なら、私の『布教』なんて確かに些末なことだね」
そうカナンはぽつりと呟き、口元に手をやり考え込むような仕草をした。
「カナン?」
「ああごめん。それが本当にいいことなのか、少し疑問になってね」
「え?」
ヘディンは怪訝そうな声を出した。
「変かい?」
「いや、カナンはそれこそ天教を大事にしてきただろう?『白天使』が現れると聞いたら喜ぶのかと思って」
「だからさ。『赤天使』を最高位としたこのカルディアの支配体制と信仰がほぼ一致しているからこそ恐れているんだ。『白天使』は伝説上の…信仰対象だったからこそ今まで成り立っていた治政がだ。本人が登場したら我々はどうなる?ヴィオル閣下はそこまでお考えの上で執心されているのか?」
ヘディンはその問いに、ライラと目配せをしてから口を開いた。
「…そうだと俺は思ってるし、俺はそんなの許す気がない」
はは、とカナンは乾いた笑い声を出した。
「相変わらず君は自分のお祖父さんが嫌いだなあ。でも、あの態度を考えればそうかもしれないと私も思う。そして、『白天使』が再臨するという公算が高いということも…あっ」
カナンはそこで言葉を切って、何かを思い出すように頭を上げた。
「あっ…あ…あー…もしかして!」
「ど、どうした?」
ヘディンが恐る恐るカナンに声をかける。
「どうしてそんな確信を持って『白天使』が再臨するなどと言えるのか不思議だったんだ!あいつ!アイツだ!シャクーリアで対峙したあの男!どっかで観たことあるって思ったら!」
血相を変えて捲し立て始めたカナンに慌ててヘディンが待ったをかける。
「あー!待て、待て、カナンちょっと落ち着け!それには訳が」
「ヘディン、お前何か知ってるのか?!この城の塔のあの『堕天使』は!?」
「いいから落ち着け。落ち着かないと俺も何も教えてやれない」
カナンの両肩にヘディンは手を置く。カナンは目を泳がせて、ヘディンの周りに居る人物の様子をうかがう。レオンも、ポニーテールの女性騎士も、どちらかと言えばヘディンの言葉ではなく自分の態度に少し動揺している様子だ。
「…なるほど。君たちも、事情を知っているということか」
明らかな嫌悪感を、カナンは示した。はあ、と溜息をついて軽く両手を挙げる。
「分かったよ。それを他に誰が知っている?」
「この城に残る者であればお爺さまと父上…くらいか」
「あと、俺からシオンの小僧には伝えてますぜ」
急に入ってきたしゃがれ声に、ヘディンがふっと顔を向けた。
「は?レオンいつの間に」
「食い下がってきたから仕方なく」
「…そういうことは早く言ってくれ。機密事項なんだから」
「はいはい」
ヘディンはカナンの肩から手を離し、ごほん、と咳払いをして佇まいを直した。
「…私だって『成人の儀』を通過したんだ。あの日のことを忘れたことはないぞ」
カナンがヘディンを睨み付けながら問い詰める。
「ああ」
「『堕天使』と波長の合った者はあの棺の前に召喚されて、その前で『禁句』を言えば…その封印が解かれると」
「ああ…」
「そんなことをしたのは誰なんだ…?!」
「ファーナだよ」
冷たくヘディンは言い放つ。その言葉に、カナンは憤りの行き場を失ったかのように表情を凍り付かせた。
「ファーナが…?待て、ファーナはどこに?」
「ファーナが『堕天使』の封印を解き、彼と一緒に行動している。だからカナン、シャクーリアでの一件は『運が悪かった』な」
「な…お前…そのことも知った上で…!」
ヘディンに食ってかかろうとするカナンをライラが間に入って止めた。
「お前…!下がらないか!」
「申し訳ありませんが、ヘディン様への危害は誰であろうと許しません」
そのままライラに力負けしてカナンは拳を降ろした。
「くっ…」
「誰よりも苦しんでいるのはヘディン様です。近くに居たのに守ってやれなかった。最愛の妹を殺すように命じられたお気持ちが分かりますか?」
「ライラ…」
ヘディンがなだめるような声を出す。一方で、カナンは自分の感情を収めようと俯きながらかぶりを振って、一つ大きな溜息をついた。
「なるほどね…よく分かったよ。感情は追いつかないけど、状況だけは、よく分かったよ…」
「カナン…その、悪かった」
「いい。確かにシャクーリアでは運が悪かったと思うしかない。そして考えるべきは、『堕天使』の動きと、それを阻もうとする『白天使』の動向、そしてファーナの身の安全…そういうことだろう」
「ああ…そうだな」
カナンは背筋を正してヘディンに向き直った。
「私が信じてこれまで行ってきたこと、そしてこれから起こること。…少し考えて整理する時間が必要そうだ。しばらくは旅に出ずハルザードにとどまることにするよ。時々こうして君の部屋を訪ねさせてくれないか」
「ああ。出立前ならいつでも歓迎する。ただしこのことは他言無用にな」
「分かっているさ。こんな…国民を不安にすることなんて、誰にも言えやしないよ」
来た時にあった勢いは完全に削がれ、静かにカナンは部屋を退室していった。
「…あの、大丈夫なんですか。カナン様はどちらかと言うとヴィオル閣下の…」
カナンの足音が聞こえなくなってから、ライラが不安そうに口を開く。
「カナンは確かに熱心な天教信者だが、同時に物凄い自信家でね。自分の中で筋が通らない事は何よりも嫌いなんだ。だから今の話で何か引っかかりを覚えたんだろう。正直俺も驚いてる。それに…俺が居なくなったら、この国を継ぐのはきっとアイツだから、ちゃんと言ってやらないと」
「王子…」
どこか遠くを見つめながらそう言ったヘディンを、複雑な表情でライラは見つめた。
太陽はとっくに南中し、窓からはギラギラとした日差しが入ってくる。昼食を済ませたファーナは、その向かいの席に座って紅茶を飲んでいるラークにふと目線をやった。
「…ねえ、遅くない?」
「ああ…カティスがか?そういえば朝も起きてこなかったな」
めいめいの部屋に閉じこもっている事が多い船旅だが、食事の時間は台所仕事をしてくれるクルーに配慮して大体一緒に取っている。それが今日は朝も昼も見かけないのだ。
「まさか死んで…」
「そんなわけないだろう。大方、朝方まで起きていたんじゃないのか」
「うーん、心配だしちょっと声だけかけてこようかな」
そう言ってファーナは席を立った。
「寝ているようなら無理に起こすなよ」
「はーい」
ラークに生返事を返して、ファーナは自分の船室のはす向かいに向かう。
「カディー?お昼終わるけど、持ってくるー?」
扉を叩きながらファーナは部屋の主に声をかける。しかし返事がない。
「カディ…?」
流石に了承を得ないで開けるのは躊躇われる。どうしようかなと逡巡していたその時だった。
「…要らない。あと…今日は、俺に話しかけんな…」
途切れ途切れに、どこか苦しそうな声が返ってきた。
「カディ?具合悪いの?」
「いいから話しかけんな!」
ビリビリとするような怒気が含んだ声が今度は返ってきた。
「え、わ…分かった…」
取りあえず生きてたしまあいっか、とファーナは心の中で独り言ちておずおずとその場を立ち去った。共有スペースに戻ってきたファーナを、ラークは不思議そうに見た。
「どうかしたか?」
「え?」
「顔がこわばってる」
「あ…いや、なんか、話しかけるなって怒鳴られて」
元いた席にファーナはストンと座った。
「虫の居所が悪かったんだろう。あまり気にするな」
そう言って、ラズリが紅茶を差し出した。
「ありがとう、ラズリさん」
カップを持って、ふうふうと冷ましながら口に運ぶ。一口飲み下すと、少しだけ気持ちがほっとした。
「ほんと、どうしたんだろう…」
ファーナは不安そうな顔で船室の方を見やった。
「…八つ当たりとか、俺もヤキが回ったな…」
ベッドに横たわったまま、カティスは肩で大きく息をしていた。
「今朝方見た悪夢が原因で誰かの命を奪いそうだ、なんてダサイこと言えるかよ…ぐっ…」
身体中がざわつく。カティスは自分の腕で自分の身体をきつく抱きしめた。
思い出す。あの時の死の匂い、手の感覚、血の美味さ――。
数日前にそうラークに言った、あの時の記憶を。
「守人は…闇に飲まれるべきじゃない…例えその力があったとしても…そうだろう…?」
仰向けになって右手の甲を額に当てる。ひどく冷たい。その冷たさに意識を集中して、心を落ち着かせる。
(返す返す、失格だな、俺は)
閉じられた瞼から水が一筋こぼれ落ちるのを、カティスは拭くことなくそのまま放っておいた。
乾いた冷たい風が、大地を吹き抜けていく。空にはどんよりとした雲が立ち込めていた。
昨晩一泊した森を抜けると、次第に木々がまばらになり、短い枯草が広がる広大な平地になった。冷たい風を直接顔に受けると痛いため、旅の一団は顔にスカーフを巻いたり、兜を被り行軍をしていた。
「この辺で休憩にするぞ」
昨晩雨でも降ったのだろうか、小さな水溜りができている場所で一行は馬を止める。馬に水を飲ませながら、サリエルは遠くに広がる山並みをぼうっと眺めていた。
「…サリ、ほら、少し腹ごしらえしておけよ」
その隣にシャルが並んで小さなパンを差し出す。ありがとうございます、と礼を言って、サリエルはそのパンを口に運んだ。
「しかし、何もない所だよなあ。流石『死の大地』って言われてるだけある」
「死の大地?」
サリが興味深げに尋ねる。
「ああ。知らないか?ここはかつて『天使戦争』の激戦地で、『堕天使』が多くの『天使』を殺戮したっていう土地なんだよ。その呪いで不毛の大地になったとかいう伝説があるくらいだ」
「…多くの『天使』を…殺した」
その言葉にサリエルはどういう訳かぞくりとした。
「それを止めたのが、我らカルディア神聖王国が開祖、ハーレイ様だったって話さ。女性ながらに勇猛果敢な将軍で、優雅な立ち回りで『堕天使』を追い払ったって話さ。ファーナ様みたいな、素敵な方だったんだろうなあ~」
話しながら悦に浸るシャルを見て、サリエルはくすりと笑った。
「シャルさんも、ファーナ様の事がお好きなんですね」
「そりゃ勿論。影口叩く連中もいるけど、あの太陽みたいなお人柄は正しくカルディアの姫って感じで…ボクはさしずめ、それを追う向日葵みたいなものかな」
へへっ、とシャルは鼻の下を人差し指でこすって照れ笑いをする。
「…ん?『も』ってことは、お前もか?!」
シャルの言葉にサリエルは笑みを返す。
「…初めて会ったとき、なんて綺麗な人なんだろうって思いました。ヘディン様もそうですけど、僕を照らして温めてくれるあったかい人だなって…。だから…また会いたいです」
だから取り戻したい。この大地を血で赤く染めたような人物が傍にいるのだとしても。目の前にいるシャルは、そんなサリエルの気持ちを知る由もない。
「うーん…。どうなんだろうなあ。ボクもまた会いたいけど、あの男と一緒になるとか言ってたの、本当だったら…もしかしたら今頃、温かい家庭を築いていたりして…人妻のファーナ様…うう、羨ましい…」
「シャルさん、あの男って?」
シャルがブツブツと妄想を繰り広げはじめそうになったところで、サリエルが現実に引き戻す。シャルはハッとして、「あっ」と声を上げた。
「そうそう、ボク、お城からいなくなった後のファーナ様に会ったんだよ。その時…そう、サリと同じような感じの銀髪で、怖いくらい透き通った緑の瞳の男と一緒でさ、ずっとファーナ様を見てきたボクですら知らない奴で…ああ~くそ…アイツ何だったんだよホントに…」
シャルの後半の嘆きは、サリエルの頭に入ってこなかった。
(…銀髪の…緑の目の男…。そいつが『堕天使』…)
いつか対峙するはずの相手の情報をインプットする。
「なあ、サリ聞いてるか?」
「聞いてますよ。銀髪の緑の瞳の男ですよね」
「そうそう。イケメンだった。めっちゃ悔しいけどイケメンだった」
「イケメン…ファーナ様って面食いなんですか…?」
別の事を考えていることを気取られないように、サリエルはシャルに会話を合わせることにした。
「そ、そんなことは無いと…ああ、でも、留学時代に好きだったとかいう奴は結構顔整ってた…ああ~くそ~ボクももっとイケメンに生まれたかった…」
「そんな…シャルさんだって十分イケメンじゃないですか」
「そ、そうか…?」
「そうですよ!だから自信持ってください!」
「お、おう…ありがとうな!なんか自信ついた…」
そんな不毛な会話がひとしきり続いた頃合いで、遠くから声がかかる。
「おい、2人とも、そろそろ出立するぞ。準備出来てるか?」
「は、はい…!今すぐ!」
2人は急いで馬に跨がり、『死の大地』を駆け抜ける。
(ファーナ様…絶対に僕が助けに行きますから…!)
サリエルは決意をより固くし、厳しい向かい風の向こうをただひたすら見つめ続けた。