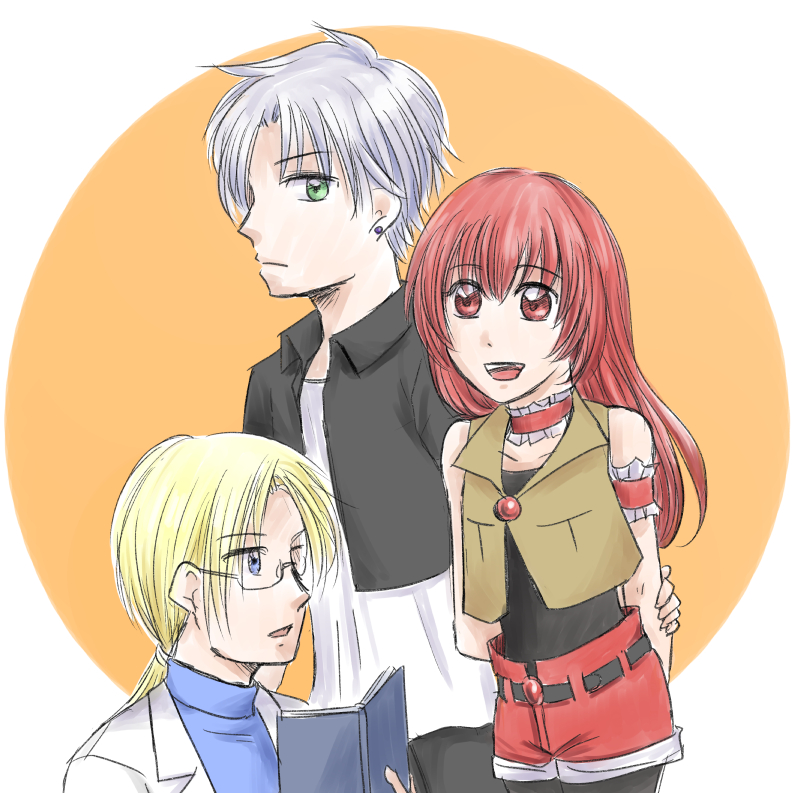カルディアの上空は、見事な秋晴れだった。
城下町の喧騒をはるか下に見ながら、カリーナは風に身を任せてふわふわと浮いていた。
2日前のことだった。城下町の『風』を探ってきてほしい、というシオンの依頼を受けて、カリーナは街中を探索した後、『風読み』を行っていた。
市井の『風』は、『天』を望んでいる――
カリーナはそんな感想を持った。根拠のない上昇気流を感じる。『天』を望めばすべてが解決するのでは、という漠然とした期待感。そしてその『風』は、あの『怖い風』に吸い込まれている。
(皆が求めているのは…あの『怖い風』の先にあるものなのかも)
カリーナは天教徒ではないが、根拠のない上昇気流は信仰心によるものであることは何となく理解できた。しかし、どうしてそれが『怖い風』に繋がっていってしまうのかがいまいちよく解らない。
(『怖い風』と思っていたけど…神への畏れ、なのかしら、これ)
一度戻って、シオンに報告しよう。そう思って城へと向いたその時だった。
「――!」
自分以外の『風の力』を不意に感じた。はっとして振り向くと、鳥の形をした木のおもちゃが南から滑るように飛んできた。そしてそのおもちゃは、吸い込まれるように、城のとある部屋へと消えて行った。
(あの場所って、王子の部屋よね…。それに、この『風』は…アイツの…。え?でも何で南から来るの?)
頭に浮かんだ疑問符をそのままにして、カリーナもゆっくりと城へと向かった。
「…着いたか。…日付は…3日前。流石早いな」
ヘディンは自分の手にするりと滑り落ちた木製の鳥から、ジェムと手紙を取り出した。いつもよりも多い枚数に疑問を持ち、ふと紙を裏返す。そこには、見慣れた妹の文字があった。
「…ファーナ…」
どきりとした。この城からいなくなってから一度も連絡を直接もらっていない。タイミングを考えると、前回自分が送った手紙は読んでいないだろう。その手紙は後に取って置き、まずはいつも通り、ラークからの手紙に目を通す。そこには、シャクーリアの政変の一部始終と、カナンの所業について書かれてあった。
『大丈夫だと思うが、カナン殿が『彼』に気が付いていたら少々厄介だ。ヴィオル殿のネタにされてしまう可能性がある』
(…確かに、カナンもあの『成人の儀』はこなしている。だが、ラークが心配するほど覚えているものかな。…でも、これはお爺様に泣きつくために帰ってくるな)
あまり歳の違わない遠戚の顔をふと思い浮かべる。いつでも自信家で、天教を心から信奉している。うるさいのが帰ってくるなと、一つ溜息を吐いた。
(さて…)
ごくりと唾を飲み、もう一つの手紙を開く。
『お兄ちゃん、元気?私は元気だよ。今海の上にいるの。
先生からあの時の話を聞いて、私、すごくほっとした。全部私を想ってやってくれたことだったんだって解って、本当に感謝してる。
いつ帰れるのか、また会えるのかは解らない。それに、『彼』がどうするのか、どうなるのかも解らない。けど、私は『彼』に付いて行く。『彼』が何か悪い事をするなら、責任もって戦わないとね。
でもね、『彼』は、口は悪いけど根はいい人なの。悪い事するようには見えないんだ。だから、私の旅路は心配しなくてもいいよ。先生も、ダタもいるし。
だから、心配しないで。いつかきっと、また会える日まで、お兄ちゃんもどうか息災で。父様にも、もし帰られていたら、元気だよって伝えてね」
手紙の持つ手がふるふると震える。ヘディンは頭を項垂れて、湧き上がる感情を抑えようとした。嬉しい。何より無事で、何より、嫌われてなくて。
「…良かったー…」
やっと吐き出せた言葉には、万感の思いが詰まっていた。
「…何が良かったって?」
と、不意にかかった言葉にびっくりして顔を上げる。そこには、仏頂面をしたシオンと、何故かおろおろしているカリーナの姿があった。
「なっ…ノックもせずに!」
「しましたよ。一向に返事が無いからノブを捻ったら開いたんです。で、何が良かったって?」
シオンの顔がますます怖い。ヘディンはシオンの後ろではらはらしながら様子を見ているカリーナを見やったが。
「あ、えっと、その…」
カリーナは困ったように笑みを浮かべていただけだった。
「その手紙。誰からのなんだ?カリーナが、ノエルの『風』を感じたと言っていたが、まさか…敵側と内通してるとでも?」
その言葉に、シオンが怒って室内に入ってきた理由を悟る。カリーナのことだ、感じたことを素直にシオンにぽろっと言ったのだろう。『風読み』は本当に敵に回したくない。そう思いながら、ヘディンは嫌々ながら最後の一文だけが見えるように手紙を折りたたみ、ぐいっと前に差し出した。
「これがノエルの字に見えるのか、シオン」
シオンは差し出された手紙の一部を一瞥した。綺麗な、女性らしい文字。シオンも何度か見た覚えがある。
「…姫の手紙…!」
「え!嘘、見せて見せて!」
興味深そうにカリーナも後ろから覗く。じっと見ていて、「あっ」と小さく声を出した。
「…どうした?」
「うん、いい旅してるんですね。いい風を感じたの。爽やかで、何もとらわれない風。文って、書かされてる可能性もあるでしょ?でも、ほのかについてた風は、そんなことないって言ってた」
「成程、これは確かに僥倖ですね。…で、もう一つの質問だ。ノエルとはまだ付き合いがあるのか?」
「ああ、あるよ。ラークと3人な。アイツがフィリアにいるのも知ってるが、あくまで友人以上のやり取りはしていない。国益を損ねることはないさ」
あっけらかんとしたヘディンの言葉に、ふーんとシオンは唸ってからぽつりと言った。
「…だが、ある意味いい駒だな」
「…おい…いい駒って…」
顔を顰めてヘディンがたしなめる。
「…いや、こういう繋がりもあった方がいい。何が起きても…それこそ、総てがひっくり返っても生き延びられるように」
「…どういう意味だ」
ヘディンが訝しげに尋ねる。
「カリーナが城下で感じ取った民の『風』…。上空に流れ込んでいる『怖い風』に吸い込まれているそうだぞ」
「何…?カリーナ、どういうことだ」
ヘディンがカリーナに視線をやる。
「あ、あの…。シオンが言った通りなんですけど、民は『天』を望んでいて、その想いが『怖い風』に吸い込まれているんです。その先に、望んでいるものがあるかのように…」
感じたことを上手く言葉に言い表せず、カリーナは戸惑う。しかし、ヘディンにはおおよその事が伝わったのか、渋い顔をした。
「民が望んでいるものは…つまり、『神』や『白天使』と言うことか」
魔獣が跋扈し始めたこの世の中に恐怖を覚え、元の平和な世界に戻せる存在。どちらにしても『怖い風』とは、天界への『門』なのかもしれない。しかし、それを開く手段など、ヘディンには思いつかなかった。
「そういうことだろうな。ヴィオル閣下の思い通りに事が運んでいるということだ」
シオンがさらりとヘディンに現実を突きつけた。
「…この流れなら致し方ない」
諦めたかのような声音でヘディンは返した。
「しかし、国を治める側としては、それでも充分いいのでは?お前は一体、ヴィオル閣下の狙いの何が嫌なんだ」
シオンが素直な疑問をぶつける。
「…いざ、『白天使』がこのカルディアに現れたらどうなると思う?」
ヘディンがシオンに逆質問をする。
「…現れると踏んでいるのか?」
そんな馬鹿な話があるか、と顔に書いてシオンは尋ねる。しかしヘディンは一向に気にしなかった。
「もしも、の話だ」
シオンはすぐに思い当たった。天教の――『天使』の本来の権力構造は、『白天使』が最も上だ。
「『白天使』に、この国が支配される…か…」
シオンの言葉にヘディンがゆっくりと頷いた。カリーナはシオンの隣で、ぎょっとした顔をした。
「俺は、『白天使』がどんな存在かなんて、伝説の上でしか知らない。だが、そいつは本当に信頼に足る人物なのか?信頼に足らない奴に、ただ強いから、信奉しているからと言って、総てを明け渡すわけにはいかない。飼い馴らすなど出来るはずもないしな」
『白天使』は『堕天使』と同等か、それよりも強い存在に違いないのだ。対峙したからこそ分かる。あの男は一筋縄ではいかないが、ラークの報せ通りなら、自分が賭けてみる価値のある男だと。
「それをヴィオル閣下は認めるというのか?」
信じられない、という思いをシオンは言葉に含めて言った。
「認めるだろうし、権力を明け渡すだろうな。それだけ信心深いんだから」
ヘディンの言葉にシオンは眉間に皺を寄せて下を向いた。
(どうして、こうも両極端なのに結果は同じなんだ…)
ヘディンは『堕天使』と組んで国を亡ぼすかもしれないし、ヴィオルは国を『白天使』に明け渡すかもしれない。どちらにしても『今の状態』を維持するためには、『白天使』が現れないことを祈りながら『堕天使』を討って、魔獣を何とか全滅に追い込まないといけない。無理にも程がある。
「し、シオン、大丈夫?」
カリーナが心配して、立ちっぱなしで考え事を巡らすシオンに話しかける。
「…大丈夫だ、ああ、頭が痛いな」
「え?風邪?大丈夫?」
「…そういう意味じゃない」
はあ、とシオンは溜息を吐いた。どうこれから差配するか、悩んだその時だった。
「シオン、お前は…もしも『白天使』が現れたとしたら、そいつに自分の力を貸せるか?」
ヘディンがシオンに言葉を投げかける。
「それは目の前に現れてみないと…正直、そんな夢みたいな話がそうそう起こるはずがない。現実的な手を打つしかない」
「そう、現実的な手だ。そこを皆が認めてくれないのがな…」
ヘディンが苦笑する。
「しかし、兵の士気が落ちるような案は認められないな」
「はは、その通りだ」
シオンの窘めにヘディンは力なく笑って、改めてシオンに向き直った。
「…シオン。この国の軍事はお前に掛かってる。俺が言うべきことじゃないかもしれないが…頼りにしているからな」
そう言ってヘディンは右手を差し出した。シオンは一つ咳払いをして、口を開いた。
「…私は握手をしませんよ、王子。貴方には『乗れない』。ヴィオル閣下にも『乗れない』ですが」
ヘディンは頭を振った。
「そうじゃない。俺に手を貸して欲しいってわけじゃない。父上を支えてほしいんだ。俺は多分支えることができなくなるから」
その言葉に、シオンは愕然とした。ヘディンはもう、この国を捨てるつもりなのか。いや、この国に居られないと思っているのか。
「…どういう意味です」
「俺は近く、このハルザードから離れるつもりだ。…先日の会議で言っていただろう、あの後詰の部隊に志願しようと思っている」
「お、王子自ら?!」
叫んだのはシオンではなくカリーナだった。
「ああ。禊はそれでするつもりだ。こうなった以上、先兵として働かないと、誰もついてこないからな」
晴れ晴れとした表情でそうカリーナに告げたヘディンを見て、はー…と、長い溜息をシオンは吐いた。禊のつもりとヘディンは言うが、多分それは『表向き』の話であって、きっと真の狙いは――。まさか、それを狙っていた訳ではないだろうが、時々この後輩は底が知れない。
しかし今自分が何を言っても、ヘディンは聞く耳を持たないだろう。
「そういうことならば。…ご武運を。留守は私が預かります」
シオンはヘディンの右手を、がっしりと掴んだ。
船室の前で、ファーナは周りをきょろきょろと見渡し、誰もいないことを確認してから目の前の扉を静かに叩いた。ややあってから、船室の主が扉を開けた。
「…何だ、随分元気になったんじゃねえか。もう二、三日は寝込んでると思ってたが」
出てきた銀髪の青年にファーナはにっこりと微笑んだ。
「先生の術がよく効いたみたい。…ね、あの続き、お願い」
そう言われたカティスも、一度周りを見渡してから小声で「さっさと入れ」と促した。
この船旅の最中、日中は全員が思い思いに時間を過ごしている。ファーナは、他の仲間の目を盗んではこっそりカティスの部屋に通い、『時空術』の教えを乞うていた。いつぞや用意した小さなノートは、いつのまにか半分ほどまで埋まっていた。
「…まあ、この辺りまでが基本文法だ。あとは上級の単語覚えて、応用利かせれば低位の魔法ぐらいは使えるだろう」
今日の授業開始から1時間程度が経過した頃、カティスはコンと指で軽く机を叩いて、椅子の背もたれに体重を預けた。
「え…これだけ?もっと難しいのとかないの?」
ファーナが不満を口にする。これまで教わったものは、例えるならば、異国で何とかたどたどしく旅行ができるかどうかの水準だった。
「…『憶えても意味が無い』んだよ。これ以上は、『守人』になった奴だけが、『奴ら』から勝手に教わるからな」
「『奴ら』?時空の精のこと?」
「ああ。『奴ら』は自分達を使役し得る人物でなければ真の力を貸さない。…他の精霊術も同じだろ?魔法の成否は魔力以外にも、『親和性』が重要になってくる。…『時空術』は、それの最たるモンだ」
「あれ?じゃあ私、勉強しても意味なかった?」
「…試してみろよ。『親和性』が多少でもあるんなら少しは発動するはずだ」
その言葉にファーナはどきっとした。初めて何かをやる時の緊張感。それ以上に、本当にやってもいいのだろうかという不安も付きまとう。
「…でも、『守人の術』は余人に知られてはならないって」
「今更かよ。それにこの部屋には俺しかいない」
「え、じゃ、じゃあ…」
ファーナが目を瞑り、呼吸を整える。カティスも心なしか緊張した面持ちになる。
「ど、どうしようかな…」
「適当に、その辺の椅子でも浮かべてみたらどうだ」
「そ、そうする…。えーっと、『時と空を統べしうつろいたるもの達よ、我が眼前の椅子を浮かび上がらせたまえ…』…でいいかな?」
多少たどたどしいが、何とか詠唱は形になった。
「…っ!わっ…」
カティスが声を上げる。ファーナが目を開けると、カティスが座っていた椅子が宙に浮き、カティスはそれに捕まっていた。
「あー出来た出来たー」
ファーナはそれを見て無邪気に手を叩いた。
「馬鹿か!喜んでないでさっさと元に戻せ!頭ぶつけるっ!」
「え、わ、分かった!えーと、『元に戻りたまえ』…でいいかな?」
すると、重力に逆らうことなく勢いよく椅子が床に叩きつけられた。
「ってぇ…」
その衝撃で、椅子を掴んでいたカティスの手が痺れた。
「ご、ゴメン…大丈夫?」
「あ、ああ…」
手をぶらぶらさせながら、カティスは呻いた。
「ど、どうだった?」
恐る恐るファーナはカティスを覗き込む。
「…初めての割には上出来だ」
「そ、そっか…。私、意外と魔術士の才能あるのかな?先生みたく」
「…かもな。お前の魔力、そんなに低い方じゃないし。ま、センセの方が遥かに上だけどな」
そう言ってゆっくりとカティスが立ち上がったところで、扉がノックされた。
「おい、凄い音だったが大丈夫か?」
ラークの声だった。椅子が落ちた音を聞いて心配したようだった。
「大丈夫だよー」
そんなラークの問いかけにのんきにファーナが答える。
「…ファーナ?」
カティスの部屋にいることを怪訝に思って、ラークは部屋の扉を開けた。椅子が転がっている以外は、特に問題はなさそうだった。
「何してるんだ?」
「いや…話してて、椅子に体重かけてたらコケただけだ。別に何もねえよ」
カティスが腰に手を当てて、顔を顰めて言った。
「…ふーん…。まあ、船は壊すなよ」
そう言って、ラークは扉を閉めて去って行った。足音が去って行ったのを見計らって、ファーナが口を開く。
「…危なかったね」
「お前もう少し気ぃ使えよな…」
「そ、そう言ったって、初めてだったんだから、仕方ないじゃない」
ファーナの抗議に、カティスは、はーっと長い溜息を吐きながら椅子を起こしあげて座り直した。
「…まあいいけどよ…。ああ、人前では使うなよ。またスレークの連中みたいなのが出てきたら面倒だからな」
その言葉に、ファーナは表情を曇らせた。
「……ねえ、カディ」
「何だよ」
「こないだヴォルスが言ってたでしょ、私なら…『竜人を竜人ならざるものに変えられる』かもって」
カティスの顔が不機嫌にゆがむ。
「…ああ」
「それって、どうやったらできるかな」
「やるつもりなのか?」
真剣な目でファーナはこくりと頷いた。
「お兄ちゃんの受け売りなんだけど、『力ある者は、正しいことにちゃんと力を使わないと皆に怒られる』って。もし私がそれを出来るのなら、私がやらないといけないことだから」
カティスは眉間に皺を寄せた。
「真面目な奴…」
「私はこれでも一国の王女なのよ。真面目じゃないと務まらないわよ」
そう言ってファーナは腰に手を当てて、ふん、と一つ息を吐く。
「…別に全世界の王女サマでもないだろうに。やり方なんて俺も知らねえよ。あの時にも言ったが、神様にでもなれればいいんじゃねえの」
「そういう荒唐無稽な話じゃなくて…」
そこでファーナは言葉を噤んだ。カティスの表情が真剣そのものだったからだ。
「…ほ、本気で言ってるの?神様になれって?」
「なれるわけねえだろ。神様の力をうまく使ってやりゃあ、いけるんじゃねえかって話だ。俺はそんな危険な事はまっぴらごめんだがな」
「神様の力って…イーレム様?ってこと?それともギアナ様…?」
カティスが何のことを指しているか分からず、ファーナが尋ねる。そういえば、彼が言う『神様』とは一体何者なのだろう。
「宗教がいくらあってもな、世界に横たわる真実は一つしかねえんだ。それが神様ってやつだ。普通の生き物はそれを認知出来ないから、想像して、作り上げて、讃えて、崇める」
「…カディはそれが何なのか、知ってるんだ?」
どこか遠くを見つめながらそう話したカティスに、ファーナは確信を持って尋ねる。カティスはその問いに机を見つめたまましばらく黙っていたが、軽くふっと一息ついてからファーナに向き直って口を開いた。
「…俺は『天の守人』だからな、知ってて当然だ」
「カディ…」
カティスに浮かんでいた深い憂い顔に、ファーナはこれ以上の言葉を紡ぐことが出来なかった。
夜。ハルザードの王宮周辺は静まり返り、ホウホウと夜行性の鳥の鳴き声が聴こえてくる。
あらかじめ約束していた時刻に、ヘディンはハサンの自室を訪れた。互いに後は寝るだけ、といった風なゆったりとした服装だ。既に人払いのしてある部屋は、落ち着いた雰囲気を漂わせていた。
「さて、こんな夜分に何の用だ?」
ハサンがにっと口の端を上げて、訪れたヘディンを応接用のソファに座るように促す。ヘディンは促されたままに座り、口火を開いた。
「先日の、少数精鋭の派兵についてですが、私とライラをフィリア方面へ行かせていただきたいのです。…禊として」
ハサンはその言葉に一度驚いたように目を見開いたが、目を閉じ、納得したかのようにゆっくりと頷いた。
「…なるほどな。二人でか?」
「今ライラの所にいるレオンも含めて、三人でですが、正式な人数としては二人で構いません」
「それより人員を増やす必要は…ないな」
鋭い眼光でハサンが尋ねる。
「ええ。大丈夫です」
きっぱりと、ヘディンは言い切る。
「…解った、その話は預かろう。出立は半月程度先になるだろうが、引継ぎを含めしっかりと準備しておくように」
「はい、ありがとうございます」
ヘディンは深々と頭を下げた。
「…それと、父上」
ヘディンは頭を上げて、懐から一枚の折りたたまれた紙を取り出した。
「これを」
ハサンはその紙きれに手を伸ばし、中身を見開く。
「――そうか、…そうか」
忘れもしない、娘の文字。ハサンの顔に優しい笑みが浮かぶ。その文字を、じっと眺めて、しばらく視線を外さなかった。しばらく経ってから、ハサンはようやく口を開いた。
「ありがとう、ヘディン」
そう言って、ハサンはヘディンに紙を返した。
「いいのですか?父上がお持ちになっても…」
「いい。お前が御守代わりに持っていけ」
少しためらいがちに、ヘディンは紙を受け取り、再び懐にしまう。
「…出立したら、お前ともいつ会えるか分からなくなるな」
寂しそうにハサンはぽつりと言った。その言葉に、ヘディンは胸が締め付けられるような気持ちになった。
「父上…わがままを言って、申し訳ありません」
「謝ることはない。それがお前の道なら、ここに残るしかない俺は背中を押すことしかできないからな…。だが、絶対に、生きて帰ってこい。例え俺とお前が相対することとなったとしても、俺はお前やファーナが生きていれば、それでいい」
ハサンは優しい笑みをヘディンに向ける。ヘディンは胸にこみ上げてきた感情を抑えられず、目に涙を浮かべた。
「っ……!父上も…ご健勝で…っ」
静かな広い部屋に、ヘディンのすすり泣く声だけがしばらく響き渡っていた。