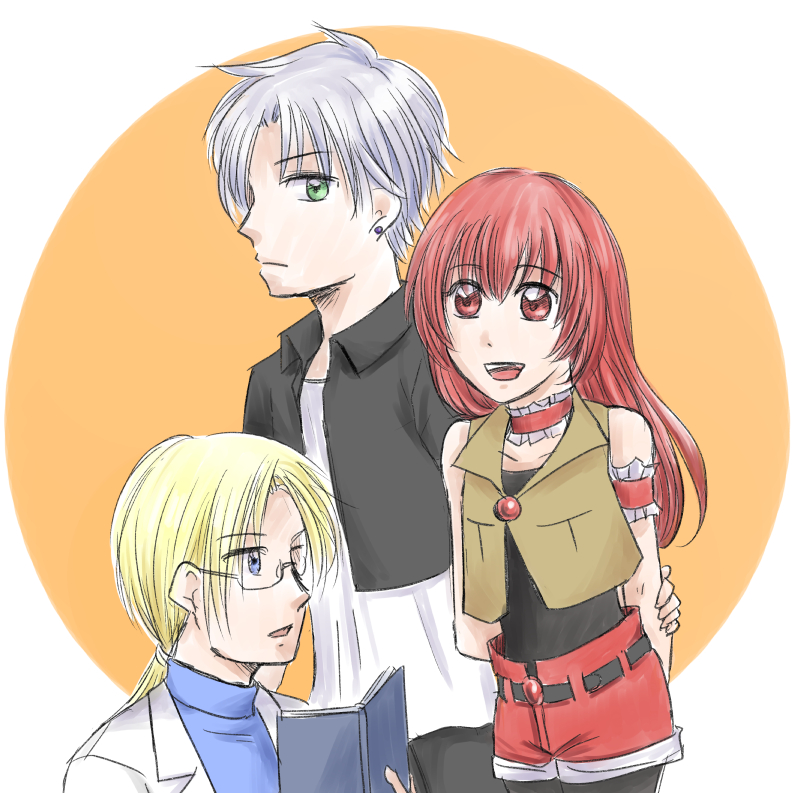「う…ううーん……」
深い闇の底から這いあがるように、ファーナはゆっくりと瞼を開けた。身体は重たく、全身が筋肉痛に見舞われている気がする。ゆらゆらと船体が揺れている。きっと既にバイタルを出立して、フォーレスへ向けて航行しているのだろう。
「目が覚めたか、ファーナ」
聞き慣れたテノールとともに、視界にラークの金の髪が映りこんだ。ファーナはそちらの方に顔だけ向けた。
「先生…私、どのくらい寝てたの?」
「一晩だ。回復魔法は適宜かけているが、しばらく安静にしていた方がいい。…ああ、消化にいい食べ物でも貰ってくるか。少し待っていろ」
「うん…ありがとう」
ラークが部屋から退出し、遠ざかっていく足音をファーナはぼうっとして聴いていた。昨日言われたことを思い返す。自分が『精霊の民』の血を引いていること、このままでは世界が滅んでしまうこと、それを止めるために『竜人が竜人ならざるものになる方法』を探さなくてはいけないこと、それに――
(カディは、何かを知ってるのかな)
『気付いていない訳がない』とはどういう意味なのだろう。節々の痛みを感じながらゴロンと寝返りを打ち、ファーナは一つ溜息を吐いた。昨日は色々なことがありすぎて頭の整理が追い付かない。
やがてラークがカットフルーツを持って戻ってきた。一口、口に入れると、十分に熟れた甘さに身体が癒されていく心地がした。それを一切れずつゆっくり食べながら、ファーナはラークに口を開いた。
「…先生、昨日のことってカディから何か聞いた?」
紅茶をカップに注ぎながら、ラークが返事をする。
「昨日のこと?いや…。お前を連れ戻して来てから『疲れた』と言って船室に戻ってそのままだ」
「そっか…」
どこからどう話そうか、ファーナはうーんとうなって悩む。
「あのね…びっくりしないで聞いてね」
「ああ」
「私、『精霊の民』の血を引いてるんだって」
「ああ。やはりそうなんだろうな」
冷静なトーンで返ってきた返事に、逆にファーナが驚く。
「…え?知ってたの?」
「お前がエルガードに来てすぐの頃、精霊術の適性検査をしたのを覚えているか?あれで相性の高い属性が地だったからな」
ラークは淡々と答えながらカップをファーナに差し出した。
「ま、また先生そういう大事なこと黙ってたの…!」
「『有り得ない』ことだと思ったからな。竜人の血の方が人間の血に劣るはずがない。だから私も、一応ハサン様にだけはお伝えした程度にしか捉えていなかった。…まあ飲め。この前ラズリが勧めてくれた茶だ」
ファーナはむくれた表情を浮かべながらも、淹れたての紅茶を口に含む。ほんのりと甘くておいしい。表情が少し緩んだのを見て、ラークが言葉を続けた。
「…先日渡したヘディンからの手紙はな、ハサン様からその話を聞いてわざわざお前に宛てたものなんだ。知ればきっと落ち込むからと」
「お兄ちゃんが…」
紅茶の温かみと、兄の心遣いとで、ファーナの胸はじんわりと温かくなった。
「でも、どうして…」
「疑わしいのは母親だな。私もヘディンの話や噂程度にしか聞いたことがないが、平民出身で後宮上がりだと聞いた」
「私もそれくらいしか…あっ」
「何か思い当たることでも?」
ファーナは一瞬逡巡してから、口を開く。
「あのね…これ、誰にも言ったことなかったんだけど…。…母様がいなくなった前の日の夜に、語ってくれたことがあったの。小さい頃、大満月の日に『堕天使』に会って、迷子だった自分を村まで送り届けてくれた。故郷では『悪魔』と呼ばれていたけれど、その人はすごく優しかった…って。別れ際に名前を教えてくれて驚いたけど、それで『この世の中に悪い人なんていないんじゃないか』って思うようになったって」
「お前がカティスの名を知っていたのはそのせいか…」
「うん…よく夢に見たから…。でも今大切なのはそこじゃない。カディを『悪魔』と呼んでいたってところ」
「…!地教国家か!」
ファーナはこくりと頷いた。
「だから、もしかしたら…母様は『精霊の民』に連なる人なのかもしれない…でも、だとしても」
ファーナはカップの紅茶に目を落とす。
「どうしてそんな人が、カルディアの…憎んでるはずの竜人の国のお妃になったのか…全然わからない…」
あの日、忽然と消えた母。よくよく思えば、どうして父と結婚したのか、そして去ったのか、まるで分らない。宮中ではタブーのように扱われ、父もそんな話をすることはなかったのだ。
「…フォーレスに行けば、もしかしたら会えるかもしれないな」
ラークが優しい口調で言葉をかけた。ハッとしてファーナは顔を上げた。
「『精霊の民』は、ギアナに仕える巫女の家系…『神官家』とも言う。ギアナに会うということは、もしかしたら」
「…そう、だね…。でも…知ったところで、何にもならないよ」
「カティスの封印を解いたのが、『精霊の民』の血を引いていたから、という仮説もなくはない。…無価値ではないさ」
「でも、カディは『俺と同質の者』って前に言ってたし…それに…」
「それに?」
「何か…知ってそうだった…私のこと」
不安げな表情を浮かべてファーナはラークを見つめた。
「何かを知っている?」
「うん…あのね」
ファーナは、昨日のヴォルスとのやり取りをラークに語って聞かせた。ラークは眉間に皺を寄せて、考え込む。
「…竜人が竜人ならざる者にならなければやがて世界が滅ぶ?…?それを、お前がどうにかできると?」
「さっぱり分からないよね。そもそも、500年前に来た時ならまだいいけど、こんなに混血が進んでたら、誰がどうだかもわからないでしょ?世界中の一人一人に会ってどうこうするとか、そんなのできっこないし」
ファーナは肩をすくめた。
「分からないことばかりで頭痛くなってきた」
「……」
「先生?」
いまだ考え込むラークに、ファーナが声をかける。
「…いや、もしかしたら、お前がアイツと旅をしているのは、私やヘディンの思惑に乗ったからではなくて、最初からお前に何か用があって連れているのかもしれない、と思ってな」
「最初から私に用があって…?」
「あくまで可能性だ。封印を解ける者はアイツと『同質の者』、そして、それがアイツに必要だったとしたら…」
その言葉に、ファーナの胸がざわつく。
「…今はアイツの船に乗るしかない。その先に…きっとフォーレスにすべての答えがある」
すくっとラークは立ち上がって、すっかり空になった皿とカップをまとめて手に持った。
「先生」
ファーナは不安げな表情を浮かべてラークを見上げた。
「不安かもしれないが、あまり深くは考えるな。なるようにしかならない」
それじゃあ、と一言だけ残して、ラークは部屋を出て行ってしまった。
「うう…考えるなって言われても…」
一人残されたファーナは、はー、と深い溜息を吐いた。
「ふわあ~~…おはようございま…」
あくびをしながら宮廷騎士の詰所に入ったカリーナは、室内にいた面子を見て内心驚いた。戻ってきてから毎日見ていたヘディンとライラの姿がなく、逆にいつもは別の場所にいてこの部屋にあまりいないようなエルンストやオードが詰所にいる。
「あれ?なんか今日むさ苦しくない?ライラ副長は?」
素直にペロッと思ったことを口にしたカリーナに、ウルスがぎろりと睨む。その眼光にカリーナは生唾を飲んだ。
「全くお前は…。ちょっと表出ろ」
シオンがウルスに「申し訳ありません」と会釈をして、入ってきたカリーナを部屋から押し出す。
「ちょ、ちょっとシオン、痛いってば。どういうこと?」
「いいから、少し離れたところで話をする」
シオンはカリーナを前方に振り向かせてそのまま真っ直ぐ背中を押して歩かせる。廊下の角を曲がったところでピタリと止まり、小声で告げた。
「お前はいなかったから分からないだろうが、昨日の会議で王子が少しやらかして、ライラも巻き添えで降格だ。副長にはオード殿がなる」
「え?何それ。横暴過ぎない?」
カリーナはぎょっとしてシオンを見る。
「…あのサリエルって神官のお告げの一件から、急にヴィオル閣下の求心力が上がってな。ヴィオル閣下の派閥の人間が王子を降ろし始めた。…正直アイツのやらかしは口実みたいなものだが、そもそも革新的過ぎて人が付いて行けないと思われたみたいだ。簡単に言えば、『風向きが変わった』んだ」
「…ああ、なるほどね」
そう言って、カリーナは辺りを見渡す。
「…そこで一つ頼みがある、カリーナ」
「何?」
「この街の『風』を探ってほしい。多少時間は掛けてもいい。人々の機微を捉えて策を打つのも重要な仕事だ」
うーん、とカリーナがうなる。
「それって、街の人はヴィオル閣下派かどうかってこと?」
「端的に言えばそうだが、そこまで具体的じゃなくていい」
シオンの言葉に、納得してカリーナは頷いた。
「分かった、やってみる。…ところで、こういう局面になって、シオンは誰かにお味方するの?」
カリーナが無邪気に問う。
「…私は軍師としてここにいる。国に奉公する立場であって、誰か一個人のために働くつもりはない。まあ、個人的には、ヘディンのことが気にかかるが」
先日レオンから聞いた話が、シオンの脳裏をよぎる。ヘディンにとっては都合の悪い方向に話が転がって行っている。しかし、国の軍事を預かる身としては、ヘディンの理想論には同調できないともシオンは思っていた。
「…そうよね…。変なこと聞いてゴメンね」
「…いや。そういうお前はどうなんだ」
カリーナは、「うーん」と唸ってから口を開いた。
「私は派遣されて来ている身だし、そこまでこの国に対しては思い入れがないのよね。風の赴くまま。できれば、新しい風が吹く方に」
カリーナは悪気のない笑顔をみせた。その言葉に裏は無い。何だかんだと一緒に行動する機会が長いせいか、シオンはカリーナの言わんとしていることを何となく悟った。
「…なるほど、覚えておこう。それでは、詰め所に戻るか。くれぐれも粗相のないようにな」
「はーい、気を付けます」
二人は足並みを揃えて、元来た道を戻っていく。分かっていることはただ一つ、扉を開けたその空間は、昨日とは別物だということだ。
フルーツを食べ終え、ベッドに横になってウトウトとしていたファーナの耳に、扉を叩く音が入ってきた。
「はい、入っていいです」
ファーナはゆっくりと起き上がって返事をした。「入るぞ」と声がかかってドアが開けられると、何やら麻の袋を持ったラズリがひっそりと入ってきた。
「ラズリさん」
「少しは元気出たか?」
「おかげさまで。まだ本調子じゃないけど。ところでどうしたんですか?」
「ああ、元々着ていた服、連中に着替えられてしまっただろう?これ」
そう言って、ラズリは袋から服を取り出してファーナに手渡した。ファーナはそれを広げて、わあ、と感嘆の声を上げた。さらっとした手触りの、生成りの生地に大柄の模様が入ったロングベストだった。
「この南国の暑さに耐えられる、通気性のいい繊維で編み上げたものだそうだ。姫さんに合うと思ってな。サイズはフリーだから大丈夫だと思うが…」
「ありがとう、ラズリさん!でもこれ、元々ラズリさんが着るために買ったものじゃないの?」
「いや、おれの買い物のついでだよ」
そこではたとファーナは気づく。男性物にしては可愛らしいし、センスも凄くいい。
「…ラズリさん」
ロングベストを両手で広げたまま、ファーナはラズリに声をかけた。
「何だ?」
「ラズリさんって、実は女性物の服も結構持ってるんですか?」
ファーナの疑問に、ラズリはかあっと顔を赤らめた。
「あっ、いや…それは…ち、違っ…」
「あ、その反応…やっぱりそうなんですね!今度見てみたいです!ていうか、いつ着てるんですか?普段はずっと男性物ですよね?」
「う、じ、自室で……」
キラキラした目でぐいぐい食い込むファーナに、ラズリがたじろぐ。
「じゃあ今度、一緒に着替えっこして遊びませんか?絶対楽しいですよ!」
想像するだけでワクワクして、満面の笑顔でファーナが迫る。
「~~~~っ!」
ラズリは言葉を詰まらせて、うつむいてしまった。ファーナはまずかったかな?と内心で思い、恐る恐るのぞき込む。
「ラズリさん…?あの、もし、嫌なら…ごめんなさい…」
「…ひ…」
ぼそっと、ラズリが呟く。
「え?」
「是非…やりたい…かな」
恥ずかしさでしどろもどろになりながらやっと出てきたラズリの言葉に、ファーナの顔が明るくなる。
「やったー!嬉しい!」
服を持ったまま、ファーナはラズリに抱き着いた。ラズリも一瞬躊躇したものの、ファーナの背中に手を回した。
(…いいもんだな、こういうのも)
そんなことを考えながら、ラズリはポンポンとファーナの背を撫でるように叩いた。
「…じゃあ、まずは元気になることだ。おれも楽しみにしてるから」
「はい!私も楽しみにしてます!」
それじゃあ、と挨拶をし、ラズリは服を置いて退室していく。色々と考えすぎて鬱屈していたファーナにとって、とてもいい気分転換になった。
「いいなあ、こういうの」
ファーナは上機嫌なままで再びベッドに横たわると、妙な安心感から、すっと眠りに落ちていった。
ファーナが安らいで昼寝に就いたその頃、そのはす向かいの部屋では、凍り付くかのような張り詰めた空気が流れていた。
「…そろそろお聞かせ願いたいものだな、お前の真の目的を」
ラークはベッドに腰かけているカティスに厳しい視線を送る。先ほどのファーナとの話を黙って聞き流すわけにはいかなかった。彼女は親友の妹であるし、ラーク自身にとっても6年間という歳月を共に過ごした家族のようなものだ。
「ファーナを一体どうするつもりなんだ。お前はわざとアイツを連れ回して…何をする気だ」
「連れ回して?アイツが向こうから付いて来てるだけだぜ?」
「とぼけるな。ファーナから聞いた。お前はアイツの何かを知っている…と」
カティスは、はあ、と大袈裟に溜息を吐いた。
「それを見届けてどうにかするのがセンセの仕事なんじゃないのか?」
「…つまり、お前がファーナに用があるということは、認めるんだな?」
言葉で逃げようとするカティスに、ラークは食いついて離さない。カティスは腰を掛けていたベッドから立ち上がり、ラークに近づいて睨む。
「そうだと言ったらセンセはどうするんだ?俺を殺すなりなんなりするつもりか?」
「ぐっ…」
カティスの問いにラークは言葉を詰まらせる。
「どうにもしねえんなら聞いても聞かなくても同じだろ?黙って見てればいいんだよ」
そう言って、カティスはラークの肩をポンと叩いた。そのまま、ラークは横目でカティスを睨み返した。
「例えばだ、ファーナの命が危険に晒されるようなことがあれば…私は躊躇なくお前を殺す」
「はっ、結構な覚悟じゃねえか。やれるかどうかは分かんねえけど」
カティスはラークの肩から手を放してその場から離れた。船室についている丸窓から、外を眺める。
「ま、別に姫さんの命を危険に晒すつもりはねえよ、それだけは安心しろよ」
それは言葉通りなのだろうと、ラークは思う。昨日だって、あんなに必死になってファーナを探して、そして連れ戻してきたのだから。しかし問題は別のところにある。
「その点についてはまあいい。ならば質問を変えよう。ヴォルスが言っていたという、ファーナが『この世界の『鍵』たりえる』とはどういう意味だ。お前の封印を解いたこと、竜人と精霊の民との混血であること、何か関係があるのか?」
これはファーナ自身も知りたがっている謎だ。それを、この男は最初からそのことについて何かを知っていて黙っているのではないか。そしてそれこそが、ファーナを連れている理由なのではないか。ラークはそんな仮説を心の中で立てていた。
「…残念だが、俺も詳しくは知らねえんだよ。俺の封印を解けるのは『俺と同質の者』ってギアナのババアが言ってただけだからな」
「なっ…」
カティスの言いざまに、ラークは呆気に取られてしまった。
「俺が姫さんに用があるってのは、強いて言えばその言葉を残したギアナの目の前に連れって行って、どういうことなんだと問い詰めてやるぐらいだ」
カティスの言葉にぐらつく気持ちを何とか立て直して、ラークが問い直す。
「…ちょっと待て、そもそもお前は誰によって封印されたんだ?解く仕掛けを作った者は一体誰だ。そもそもそんな仕掛けがあるということは…いずれ解ける封印だったということだろう?どうしてそんな封印にしたんだ」
「何度も言うが俺も詳しく分からねえ。俺は…『アイツ』に刺されてから封印されるまでの記憶がごっそり抜け落ちてるからな。あのババアに適当に説明されたことしか知らねえんだ」
「…なん…だと…?」
ラークが生唾を飲む。目の前にいる男は、闇に葬られた歴史の生き証人だとばかり思っていたのに、肝心な点は何も知らないとは。どこかがっかりした気持ちになり、はあ、と溜息を吐く。
「それを知るために、お前はギアナに会いにフォーレスへ行くというわけか…」
「まあ、そういうわけだ。残念だったか?」
ご愁傷様、という言葉を顔に書いたかのような表情で、カティスは言う。
「ああ、残念だな…」
邪魔をした、と言って、ラークは肩を落として退室していく。その姿を見送って、カティスは一人ぽつりと呟く。
「悪いな…お前に教えてやれるようなことは、一つもねえんだよ。今んところはな」
無意識のうちに右手がシャツの胸元をぐしゃりと握る。翡翠色の透き通った瞳は、窓の外を一点を見つめ、そこから微動だにしなかった。