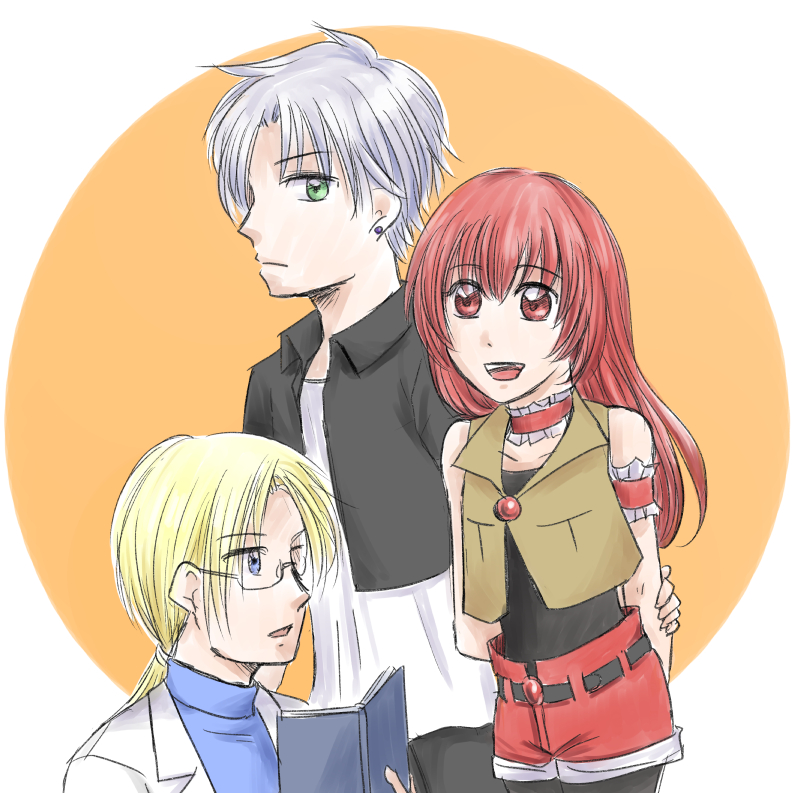ぬるい風が窓の外から入ってくる。
官公庁は既に執務の時間を終了しており、外は星が瞬き始めている。目的の人物がまだ行政官長室に残っていたことは都合がよかった。神殿からわざわざ走ってきた甲斐があったということだ。汗をかいた体には心地よい風だった。
「こんな時間に奏上とは…よほど急ぎの用のようだな」
質の良い生地の民族衣装で身を包む壮年の男が、手渡された書状を受け取り開く。男の眉間に皺が寄っていく。
「…サイ。これはどういう意味だ」
行政官長がしかめっ面をして尋ねる。
「読んで字のごとく、としか言いようがありません」
サイは息を整えながら、行政官長に答える。
「『私宛てに遠方から竜人の来客があるから、退去させることも、捕らえることも無いように神殿へ連れてくること』と書いてあるが…。これを受け入れろと?」
「はい。それがギアナ様のご意思です」
行政官長が頭を抱える。
「…ギアナ様のご意思は時々分からん…。竜人を領地に入れるなど…民の安寧が守られぬではないか」
「ギアナ様のご客人であれば、悪さはしないと思います」
「それを民にどう分からせるというのだ…。まあいい、分かった。現地の自警団には急ぎ報せを出す」
「俺も急いで現地に向かいます。行き違いがあっては大変ですから」
「…なるべく穏便に済ませてくれ。頼む」
「はい。官長もどうか、よろしくお願いいたします」
一礼をして、サイは執務室を出て走る。今から馬に飛び乗って休みなしで走って間に合うだろうか。その客人は、きっと自分のよく知る人物なのだ。危険な目には合わせたくない。
(ファーナ、ラーク、待ってろよ…!)
逸る気持ちを抑えながら、サイは星空の元へ駆け出して行った。
ハルザードは、星の見えない夜だった。
窓の外側には雨雫がたらたらと流れている。風も強いのか、時おりガタガタと音を鳴らしていた。
その音を聴きながら、小さな灯りだけを灯して、北方地域の状況が記された報告書を眺めていたヘディンは、コン、コン、コンと窓を叩く音に気が付いて、ふっと顔を上げた。木製の『鳥』が、中に入りたそうに窓をつついていた。
「早いな、こないだ来たばかりなのに。何かあったか?」
窓を開けて、すっかり雨にぬれた『鳥』を室内に迎え入れる。腹に仕込まれた手紙を器用に取り出して、机に座り直し中に書いてある内容に目を通す。そこには、バイタル島で起こったという一連の事件の顛末がラークの字で仔細に書かれていた。
「……『竜人が竜人ならざる者にならなければ、やがて世界が滅ぶ。それをファーナがどうにかできる可能性を持っているらしい』……だと?」
終わり間際に書かれてあった一文に、ヘディンは眉根をひそめた。そんな大層な運命を、大切な妹が背負っている。それなのに、自分はこの狭いカルディアの国で留まっている。その事実が、焦燥感に似た感情をヘディンの胸に抱かせた。
「こうなったら早く、動き出さなくてはな……」
ヘディンは再び、報告書を見つめる。自分の身を多少なりとも自由にするきっかけは、この中にあると信じて――。
昨晩の雨は上がり、未だ朝靄がかかる時間に、シオンは1人、ハルザードの城にほど近い豪奢な建物のそばを歩いていた。吐く息は白く、時折両手に吐息を吹きかけては暖めている。
(昨日の今日で、こんな時間に呼び出すなんて…)
シオンの手元には手紙があった。昨日の昼にこっそりと届けられたもので、『人目を避けるため、明朝早くに会いたい』と、場所と時間が書いてある。悪戯ならそのまま無視するところだが、差出人の名前はこの国の『もう1人の王子』と言っても過言ではない人物だ。
(一体どんな奴なんだ)
名前だけは聞いたことがあった。何でも地教国家を飛び回っては天教を『布教』しているのだとか。『布教』と言っても、信仰にとどまらず、経済援助などをすることで、実質的な支配下に置くという行為。シオンの故郷も、その昔そういった『布教』を受けてカルディアの支配下に置かれた国だった。
門の前の衛兵に招待状を見せると、快く中に通された。広々とした中庭は、綺麗にガーデニングがされており、東屋も設置されている。花の時期はもう終わりかけだというのに、うまく植えるタイミングを分散させているのか、色とりどりの花があちこちに咲いている。
丁寧に施された景色に感心しながら屋敷の玄関前まで歩くと、戸を叩く前に扉がギィ、と開かれ、扉の向こうから、長い赤髪をゆるく結んだ、軽装の男性が顔を覗かせた。
「カナン様」
使用人が出てくるかと思いきや、招待状の差出人本人が出てきたことに、シオンは驚きの声を上げた。
「こんな朝早くに申し訳無かったね、シオン・レックサーク殿。さ、上がってくれたまえ」
穏やかな笑顔を浮かべて、カナンはシオンを手招きした。
カナンの邸宅は3世帯くらいが住んでも十分な面積があった。大広間を抜け、階段を上がり、カナンの自室に通されたシオンは、まず目の前に広がった古今東西の品物に目を瞬かせた。
「こっちだ。雑然としていてすまないね」
応接に通されたものの、普段は高価なティーセットが並ぶはずのテーブルには、書物の類いが堆く積まれており、およそ高貴な身分の人物の部屋とは思えなかった。
「この資料は」
ソファに腰を掛けたシオンは驚きを隠すことなく尋ねた。
「歴代の日記やら歴史書やら、天教の解説本やら…まあ色々だ。私が発する言葉には、裏付けが必要。それを信条としているからね」
カナンは奥に置いてある水差しからグラスに水を移し、テーブルの上に静かに置いて、シオンと向かい合う形で腰を下ろした。
「それで、私にどのようなご用件で」
「君の…部外者の君の意見を聞きたくてね」
「部外者?」
シオンは眉間に皺を寄せた。
「ああすまない、言葉の綾だ。君は王家の人間じゃないけど、今王家に起こっている『事情』を知っていると聞いたから」
「……その話ですか」
シオンはその言葉に心当たりを思い浮かべ、溜息交じりに声を出した。
「君が一番客観的に物事を見ているんじゃないかなって、思ってね。ここにある歴史書は、天教の目線で書かれた物ばかりで当てにならないし、今大事なのは、これからどう身を振るか、だからね」
シオンはうーん、と唸ってから言葉を紡ぐ。
「正直、何かが起こらない限りはどうしようもないと私は思います。何が起きても結局は何を大事にするか、ではないでしょうか」
ひねり出した言葉に対して、我ながら論理的ではないな、とシオンは心の中で付け足した。
「何を大事にするか、か…。君は、何を大事にしようとしてるんだい?」
優しい視線を向けられて、シオンは困惑した表情を浮かべた。正直、自分でも悩んでいるのだ。これから起こるかもしれない、歴史を大きく動かすかもしれない『何か』に対してどう対処すべきかを。
「正直、わかりません。ただ…」
「ただ?」
「私はこの国の軍事の手助けをして欲しいと請われて雇われている身。この国の為になることは何かを、その一瞬一瞬考えるのでしょうね」
「成程、そうか…私は何を大事にするんだろうな……」
カナンは左手を口に当てて、右手で目の前の紙をペラペラとめくる。
「あの、何か…」
「実はね、私は『彼』に逢ったことがあるんだよ。ファーナが目覚めさせたって言う『堕天使』にね」
「えっ……」
シオンの驚きの声を聞き流して、カナンは言葉を続けた。
「先日ヘディンに会った時にそうだった、と知ったんだけど、シャクーリアの反乱分子……いや、元の地教を信奉する勢力に味方をしていてね、こっぴどくやられたんだ。今思えば、私は直接会ってはいないが、きっとファーナもどこかにいたんだろうなと」
「姫も……天教ではなく、地教側に付いていたと」
「きっとね。そしてその事実を……恐らくヘディンも知っていた」
そこまで言って、手癖のように資料をめくっていた手をカナンは止めた。
「私がこれまで正しいと思ってやってきたことを、間接的であれ、ファーナに止められた、と思ったんだ。小さい時分に ほんの少ししか会ったことのない許嫁だけど、それでもその事実が胸に刺さって抜けない」
「立場が違えば、そうなるものです。あまりお気になさらない方が…」
「そうは言っても気になるんだ。この部屋にある物を見ればわかるだろう。色んな国を見て回って『布教』をしてきたのに、大事な人にそれは違うと否定されたんだ。彼女は一体何を見て経験して、彼らの側に立ったのか……」
「成り行きということもあります。そうせざるを得なかったのかも知れません。否定されたというのは憶測の範囲を出ませんよ」
シオンはうなだれたままのカナンを励まそうと精一杯の声を掛ける。そのシオンに食ってかかるようにカナンは顔を上げた。
「じゃあヘディンは何なんだ。その事実を知ってもアイツは容認してる……」
そこまで言ってカナンは閉口した。シオンは黙ったまま、カナンの目をじっと見ていた。
「……そうですよ。容認してるんです、アイツは」
あえて「アイツ」と吐き捨てたシオンの顔には、険しい表情が浮かんでいた。
「どうして」
「どうしてかは、本人に訊かれるのが一番ではありませんか。今の秩序を破壊してまでやりたいことなんて、どうせろくなものではないとしか言いようがないですけどね」
少し苛立ち気味に言い放ったシオンに対して、カナンは釈然としない表情を浮かべた。
「それもそうだな。でもきっと、君の言葉を返すと、ヘディンもそれが大事だと思って行動してるんだろうな。君からみたらろくでもなくても」
「え……」
カナンは困惑した表情を浮かべた。
「よし、じゃあヘディンの『大事なこと』を聞きに行くか。ありがとう。なんかスッキリしたよ。君と話せてよかった。朝からすまなかったね」
カナンはすっと立ち上がった。シオンはカナンの言葉に当惑したまま、それに追随するように立ち上がる。
(あんな荒唐無稽な夢物語が大事なことだと……?)
レオンにいつぞや聞いた話を思い出す。あれはレオンがヘディンから感じ取ったことを聞いただけで、その実、ヘディンから真意は聞けていないのだ。
「……あの、カナン様!」
胸に湧いた衝動を、シオンは抑えることが出来なかった。
「うん?」
「その席……私も同席させてはいただけませんか」
カナンは目をぱちくりさせてから、ニッコリと笑う。
「ああ、勿論。ヘディンがいいと言えばだけどね」
――白い、白い空間が目の前に広がっている。
(ここ……昨日カディが言ってた、『闇世』…?)
夢にしてはやけにはっきりしている。いつの間にか、昨日のような異世界に飛ばされたのだろうか。
「『渡り』の影響が出たか、やっぱり」
不意に声が空間に響いた。聞き慣れた声だった。
「カディ?!」
ファーナは周りをキョロキョロと見渡した。
「こっちだよ」
上からすっとカティスがファーナの目の前に降りてきた。よく見ると、カティス本人のはずなのに、格好が違う。髪も長く、後ろで一本で縛っている。
「え…と?」
「ああ、ここじゃこの格好の方が落ち着くからな。あと、こんなところに長居するもんじゃない。とっとと現世に帰れ」
「いや、帰れって言われてもどう帰れば……」
「願えばいい。自分の身体のあるところに帰りたいと。…今どういう状況か分かってねえだろうから言うけど、半分死んでるようなもんだぞ」
「へっ…?!」
ファーナは声を裏返して驚いた。
「言っただろう、ここは闇世。あまねく世界を繋ぐ、総てが還り生まれ出ずる場所だと。今お前はそこに魂だけ来ちまってるんだって言ってるんだ」
「ま、まずいじゃないのそれ…!」
「分かったならさっさと帰れ」
「帰るけど、起きたらちゃんと教えてね!あっ、カディもちゃんと帰ってね!よく分かんないけど!」
「はいはい…ったく…」
「私の身体に帰れますように…」
ファーナはきつく目を閉じる。きっと洋上にあるラズリの船の中にある自分の部屋。そこを強く思い浮かべる。その時、とん、とおでこを手のひらで押された。
『あるべき場所へ帰れ』
冷たいカティスの声が耳に残った。
「わあああああっ!」
自分の叫び声で、ファーナは目を覚ました。心臓の鼓動が収まらない。窓の外からは柔らかい光が差していた。まだ朝も早い時間のようだった。
「何あれ、夢……?」
はーーー、とファーナは溜息をついた。起きた瞬間は何があったか鮮明に覚えていたが、落ち着きを取り戻すとともに内容が薄らぼんやりとしてきた。
(夢……か)
ゆっくりとベッドから降り、寝間着から普段の服装に着替える。鏡を見て雑に髪をブラッシングしてから、部屋の外に出る。甲板に出ると、まだ日が昇ったばかりの爽やかな風が吹き抜けていく。先端の方に人影を見つけると、ファーナはその方向に歩いて行った。
「ラズリさん、おはようございます!」
「姫さん、おはよう。今日は早いな」
ファーナはラズリの隣に立って、船が向かう先を見やる。
「何か変な夢を見て目が覚めちゃって。あとどのくらいでフォーレスなんですか?」
「正味二日、かな」
「そっか……そしたら、ラズリさん達ともお別れですよね、寂しいです」
そう言って、ファーナはラズリを見上げた。
「ああ、そのことだけど、少し考えていることがあって」
「え?」
「しばらく船はフォーレスのロート港に停泊させて、積荷を降ろしたり、交易品を買ったりしようかと思ってるんだ。数日は時間ができるから、折角だしおれは首都のシュルカまで姫さん達を馬車で送ろうかなと」
「えっ!いいんですか!?」
ファーナが喜びと驚きの声を上げる。
「シュルカまでは陸路で二日かかるんだ。その間、竜人の姫さん達が何事もなく無事に目的地まで辿り着ける保証がないなと思ってね。おれは何度か行った所だから、道案内くらいはできる」
「何事もなく…無事に…?」
ファーナの声のトーンは急速に落ちていく。
「竜人はフォーレスじゃ基本的に魔獣扱いだ。バレたらタダじゃ済まない」
ファーナは生唾を飲みこんだ。
「それは…その、かえってご迷惑に…」
「ははは、大丈夫だから、最低でも国外追放くらいだから。でもそうはなりたくないだろ?」
「――ああ、それは勘弁だな」
ラズリの言葉に対する返事が、2人の後ろから飛んできて振り返る。そこには、まだ眠たそうな顔をしているカティスが気怠げに立っていた。
「カディ!朝早いね、珍しい」
ファーナが心底驚いたような声を上げた。暢気そうな様子のファーナを見て、カティスは小さく舌打ちをして呟く。
「誰のせいだと……」
「え?」
「何でもねえよ。覚えてないんならそれで構わない」
うなじの辺りを掻きながら、カティスはまた船室の方へ戻って行った。
「……何だったんだ?」
「さあ?」
ラズリとファーナは2人で顔を見合わせながら、小さくなっていくカティスの姿を眺めていた。
朝方にかかっていた靄はすっかりと晴れて、風は冷たいながらも雲は少なく、青空が広がっている。
カナンの邸宅から戻った後、緊急の軍議があるとウルスに呼び出されたシオンは、入室して前方左斜めに立っていた人物の姿を見て内心で驚きの声を上げた。
「ヘディン王子も、ご参加されるのですか」
シオンはウルスの隣の自分の定位置まで進み、淡々と言葉を発した。室内の顔ぶれを見れば、どちらかと言うとヴィオルの息のかかった者が多い。その中で妙に存在が浮いているのだ。
「今回は王子に直接関わることだからな。来ていただいている」
隣のウルスが代わりに答えた。
「派兵の話ですか」
「話が早くて助かる。全員揃ったし始めるぞ。諜報部隊からの情報が今朝方来て、特に北方・東方で魔獣の発現が想定より多くなっており、早急に追加の派兵を送られたいとの要請があった」
赤軍服の面々からざわつきの声が上がった。
「北方はフィリアとの国境における争いで、恨みを持つ者も多かろう。そこで、ヘディン王子が手勢のみで北方へ向かうとの申し出があり、了承したいと思うがいかがか」
シオンはその言葉に表情を凍らせ、はっと顔を上げて向かいに立つヘディンの顔を見た。少し緊張しているような表情を浮かべている。その表情を見て、シオンは固唾を呑んで口を開いた。
「ウルス団長、私から具申しても」
「なんだ、シオン」
「先日の軍議で、王子は周辺国との連携を発案され、却下されています。王子が手勢のみで向かったら、却下されたその案を実行してしまうのでは」
シオンの言葉に室内がざわつく。
「赤軍服の方々がその場にいないからやってもいいという話ではありません。決まったことは決まったこと。そうしない保証ができない限り、私はその案に反対します」
士気を保つのも軍全体を司る軍師の役目とシオンは自覚していた。それを挫くようなことは絶対にしてはならない。
「王子。その点の弁明を」
真剣なまなざしをヘディンに向けてシオンは問うた。
「確かに、それを保証する術はないな。ならば目付役としてお前が着いてきたらどうだ」
不敵な笑みを浮かべてヘディンが言う。その言葉にシオンは呆気にとられてしまった。
「は……?それは不可能でしょう」
「冗談だ。ただ、そんなに信用出来ないなら誰か見張りでよこせばいい。お前じゃなくとも」
ヘディンの言葉に、シオンとウルスがどうする、と顔を合わせる。
「それならば、立候補してもよろしいでしょうか」
末席からすっと手が上がる。赤い軍服に身を包んだ、ヘディンと同じ歳くらいの精悍な青年だった。
「立って発言してよい」
はい、と一つ返事をして立ち上がった青年は、きっとヘディンを睨んでから正面に向き直った。
「第十二騎兵隊長のエラトと申します。私は……先のフィリアとの衝突で友を失いました。先日の軍議で王子が発言されたことについては、許せないという気持ちしかありません。シオン殿がおっしゃるような事態があれば、どんなことをしてでも王子を止める所存です」
ちらっとウルスはシオンの方を見やる。シオンは小声でウルスにささやく。
「一応、言っていることに嘘はありません。彼の部下で友人だったコーダ隊員はフィリアとの小競り合いの際に消息を絶っています」
「消息を絶った、か……成程」
ウルスはふん、と頷いてからエラトに向いた。
「エラト隊長、その友人を探しに行きたいなどという私欲があるのでは?」
「め、滅相もありません!切り立った崖の近くでの乱戦でした。崖から落ちていれば恐らく即死……。探しに行こうにも、あの山岳地帯では徒労に終わります。だから、アイツは、コーダは死んだんです。私の指示が間違っていたかもしれない。しかし、あそこで奴らに襲われなければこんな事にはなっていないのですから!」
かみつくようにエラトは言った。
「……分かった、信用しよう。ヘディン王子、彼を随行させるがよろしいか」
「構わない。エラト、よろしく頼む」
ヘディンの言葉に、怒りの表情をにじませながらエラトは軽く礼をした。
「急ぎ準備して、我々の出発は明日朝としよう。では、これで我々は失礼する」
ヘディンはすっと立ち上がって退室する。それに続くような形でエラトも部屋から出て行った。その後ろ姿を、シオンは眉根をひそめて見つめていた。
「では続いて東方への派兵についてだが……」
ウルスの言葉に、シオンははっと現実に戻された。考えるべき事は、ヘディンのことだけではない。全体をどう差配するかだ。そう自身に語りかけて、地図に改めて目を落とした。
「明日、ですか。突然ですね」
「しかも我々だけじゃなくて、お目付が付いちまった、と」
ヘディンの自室に集められたライラとレオンがヘディンから事の次第を聞き取ったのは、緊急軍議の一時間後だった。
「これくらいは仕方無いだろう。信用されてないんだから」
椅子に深く腰掛けて、腕組みをしながらヘディンはぼやくように言った。机を挟んでヘディンを見下ろすような形で立っていた2人は互いに困惑した表情を浮かべて顔を見合わせた。
「で、どんな奴なんですか、そのお目付って」
「エラトという、赤軍服の一隊長だ。槍の腕はかなりのものだった記憶がある。先の遠征で友人を失ったとかでフィリアと融和するようなことは許さない、と」
「それで、目付を進んでやると言ったのですね」
ライラの言葉に、ヘディンがこくりと頷いた。
「まあ、なるようにしかならないしな。そういう訳だから、食糧品の調達だけは頼めるか。先行部隊への補給もあるから、馬に乗せられる限界まで頼む。こっちに持ってくるのは出立前で構わない」
「かしこまりました」
2人は一礼して、扉の方へ向かう。ライラが扉を開けると同時に、守衛の姿が目の前に現れた。
「うわ……驚きました」
「これは…!失礼しました。ヘディン様、カナン様とシオン様が目通りを申し出ているのですが、お通ししてもよろしいでしょうか」
ライラはヘディンの方を向いた。
「丁度いいところに来てくれたな。通して構わない」
「私も同席いたしましょうか」
「いや。明日の準備の方が先だ。よろしく頼む」
ライラはもう一度礼をして、レオンと共に階段を下っていく。一服置いて、それと入れ替わりにシオンとカナンが入室してきた。
「お忙しいところ、失礼致します」
「悪いね、急に」
シオンは硬い表情を崩さず、カナンはいつものとおりの調子だった。
「いや、構わない。丁度2人にだけは話しておきたいと思っていたことがあったから。先に俺から話させて貰っていいか?」
ヘディンは自分の席を立ち、2人に応接に座るよう促し、自らも腰掛ける。
「まずはこれを見て貰いたい」
ヘディンは胸元から、昨晩届いたラークの手紙を2人の前に差し出した。
「シオンには前にも少し言ったが、ラークとは手紙のやりとりをして、向こうの状況を知らせて貰っている。これは昨日の夜届いたものだ」
読み進めて行く度に、シオンとカナンの表情が険しくなっていく。
「……待て……。理解が追いつかない」
「ざっくりまとめると、このままだと世界は世界自身に粛清されるけど、それを止められるのは『精霊の民』と『天使』の混血のファーナで、しかもその方法が、『天使』であることをやめること、ってことかな?存在を否定されているようで少し腹が立つけど」
腹が立つ、といいながら、カナンの声音は明るかった。
「話が壮大すぎる……。つまりお前はこれを我々に見せて何が言いたい」
シオンが頭を抑えながらヘディンに訊く。
「これが本当なら、俺はこれに乗りたい」
「いや待てヘディン、自分の存在を、『赤天使』の血が、この王家の座が否定されるんだぞ?」
カナンが困惑した表情で即座に反応した。
「構わない。俺は、昔からこうしたかったんだ。『竜人』であることをやめること、それができるなら、自分の総てを投げ打ってもいい」
「今の秩序が、破壊されてもいいということか」
シオンの問いに、ヘディンはしっかりと頷いた。
「その後、新しい別の秩序を作ればいい。でも、その秩序を作り上げるまで、2人にはこの国を支えてもらいたい。何年先になるか分からないからな。それが俺の伝えたかったこと」
シオンとカナンは言葉を失った。しばらく無言の時が流れる。シオンは苦虫をかみ潰したような表情で頭を抱えていた。
「なあ……どうして……そんなことをしたいと思ったんだ」
やっと、シオンは震える声でヘディンに尋ねた。
「俺は世界の有り様が間違っているとずっと思っていた。『竜人』であるが故に『呪い子』となり親の命を奪う可能性があること、純粋な人間との断絶が起こること、扱いに差別が生まれること……。
例えば…例えばだ。俺が愛したいと思った女性が普通の人間だったら?俺はその人を殺してしまうかもしれない。そんな小さな幸せすら守れない世界は、絶対間違っているんだ」
シオンはその言葉に目を見開いた。
「そんな、小さなことで」
「小さくなんかない。その集まりが社会や国、世界なんだから。それを当たり前と受容しながら生きるような事はしたくないんだ。だから俺は『竜人』が『竜人』でなくなる世界を、作れるのなら作りたい」
「お前……」
シオンは大きく溜息を吐いてから、聞こえないほどの小さな声で「やっぱりか」と呟いて目を閉じた。その様子を少し心配そうに見やってから、カナンは口を開いた。
「つまり、君がやりたいことは、ご先祖様が築いてきた世界を壊して、この国の五百年の歴史を終わらせたいってことだね」
「それが許せないと言うなら、それでいい。でも……俺に武力でカルディアを滅ぼすなんて気は毛頭無い。明日の朝起きたら、竜人じゃなくなってた、くらいの道を探りたいんだ」
「綺麗事だなあ。時間を遡ってこの世界に『天使』が来ないようにするくらいのことでもしない限り、そんなことは実現出来ないだろう?」
「そうかもな。でも、可能性はゼロじゃないってことが分かったんだ。分が悪くても賭ける価値はある」
迷いの無い表情で、ヘディンは言い切る。その自信ありげな言葉に、シオンが不意にふふっ、と笑って顔を上げた。
「ああ、本当に、お前は馬鹿だ。そんな夢見がちな事ばかりで。そんな現実味の無い話、誰も信じる事はないだろう。でも、その手紙が真実なら……その夢は逆に現実にしなくてはいけないものということだ」
「ああ、そういう事になる」
「それが――ファーナ様が抱えた運命を手助けして、自分の途方もない夢も叶えるということが、お前のやりたいこと、『大事なこと』なんだな」
呆れたような笑みをシオンは浮かべた。カナンはシオンの様子を見て、安心したように笑みを浮かべて口を開いた。
「未来がどうなるかなんて誰にも分からない。君の望み通りに行かないかもしれない。いや、そんな途方もないこと、叶わない可能性の方が高いんだ。それなら、私は君の望み通りにいかない方に賭けようじゃないか」
「カナン……」
ヘディンはカナンの言葉に身を少し固くした。
「君のやりたいことを邪魔するつもりはないよ。逆の立場にいる者も世の中必要だ。それを私が買ってやろうというだけさ。それに、私はやはり、今まで私を培ってきてくれたご先祖や歴史に、足を向けて寝られない」
いつもの緩い調子ではなく、至極真面目にカナンはヘディンに心の内をぶつけた。
「そうだな……きっとそれが本来あるべき姿なんだろう。だから俺はお前を信頼できる。野放図な俺なんかより、ずっとお前はこの国に対して真摯に向き合っているから。だから、この国のことは頼んだ」
ヘディンはそう言って、カナンに頭を下げた。
「よろしい、頼まれようじゃないか。このカナン様に万事任せなさい!」
ばん、と音を立ててカナンは自らの胸を自信満々に叩いた。
「はは……。カナンらしい。それとシオン、目付の件だが」
「何だ。この話をしたら外して貰えるとでも思っていたのか?それはそれ、これはこれだ。頑張ってエラト隊長を説得してみせるんだな」
「うーん、相変わらず手厳しいな……」
「体裁が保てないことはしない。そのくらい分かっているだろうが。……さて、これ以上話が無ければこの辺で失礼しよう」
「そうだな」
そう言って、シオンとカナンはすっと立ち上がった。
「2人とも、俺に話があって来たんじゃなかったのか?」
遅れて立ち上がったヘディンに、シオンは晴れやかな表情で返す。
「もう、充分に聞いたからいい。……命だけは落とすなよ」
「ああ、2人とも達者で」
シオンとカナンは会釈して、退室していく。振り返ることの無かった背中を、少し寂しいような気持ちを抱きながらヘディンは見送った。
珍しく人通りのない廊下を、シオンとカナンは並んで歩く。窓からは暖かな日差しが差し込んでいた。
「ヘディンの『大事なこと』、聞けてよかったな!シオン」
「ええ……ですが……」
シオンは声をひそめて続けた。
「あの手紙が真実なら、『白天使』がもし本当に降臨した場合、それは世界にどう影響を与えるのか……」
カナンは表情を固くした。そこでシオンは自分の配慮の至らなさにはっとした。
「申し訳ありません。この国や王族の皆様の存在を否定したいわけではないのです。ただ、純粋な疑問として」
「分かっているさ、そのくらいは」
シオンの言葉を遮るようにカナンが言葉を被せた。
「は……?」
「ほら、さっきも言っただろう。未来がどうなるかなんて分からないんだ。そうなったらその時考えよう。君とならうまくやれそうな気がするしな」
カナンはニッコリと笑って、シオンの目の前に右手を差し出した。シオンは一瞬躊躇ったものの、その手を握り返した。
「このことは2人の秘密だ。よろしく頼むな」
第29話へ 第31話へ