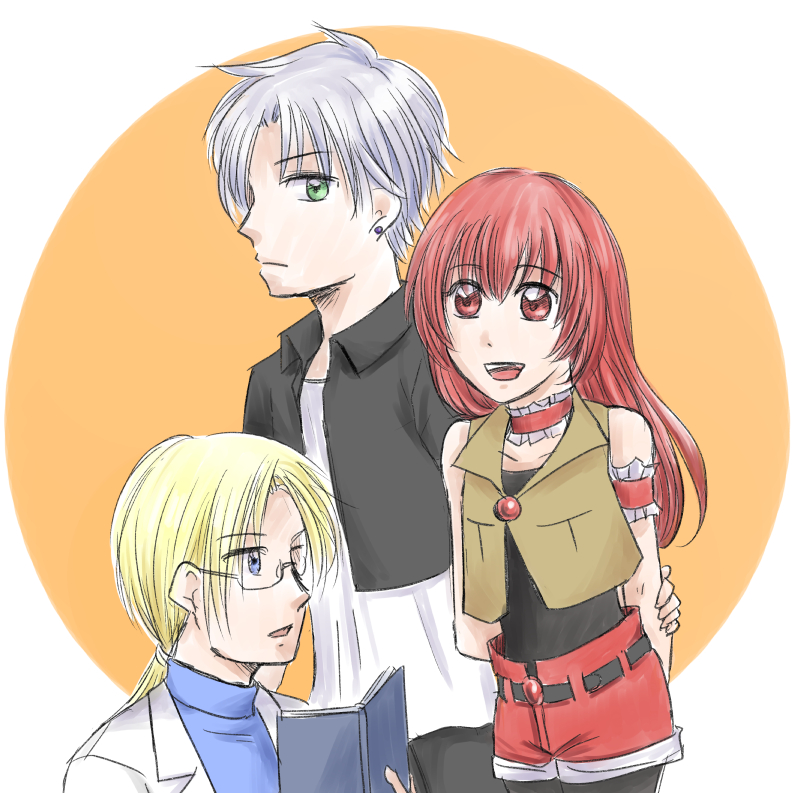朝方、湖に囲まれた城は霧が立ち込めていた。
その霧の中、城門の前に赤い鎧兜を纏った旅装の兵士が整列していた。騎兵500。つい最近まで、フィリアへ遠征していた軍隊の一部だった。
「誇り高き『炎の騎士団』の諸君!我々が最も大切とすべきは、人命だ!その人命が、魔獣の手により奪われている!諸君らは、人々の盾となり矛となり、人々を守り通すこと!これが今回の任務である!」
カルディア神聖王国・国王ハサンが騎士の前で激を飛ばす。それを、騎兵に交じり馬に跨ってサリエルは聞いていた。サリエルもまた、赤い鎧兜を纏っており、外からは誰かとは気づかれない。
「…しかし、王子も人使い荒いなあ…。よりによってサリの護衛って」
サリエルの隣で同じように馬に跨っている青年がぼやく。特徴的な猫っ毛が、赤い兜の隙間からはみ出している。
「…静かにしてください、シャルさん。怒られちゃいます」
年下なのに生意気な口を利かれて、シャルはむっとする。姫のことは昔から見てきたのに、姫はこの、一年くらい前に知り合ったどこの馬の骨とも解らない少年と、何故か仲が良かった。簡単に言ってしまえば、サリエルに対してシャルは嫉妬していた。
そんな気持ちにさらに追い打ちをかけられたのは、昨日の昼の出来事だった。
「…シャル、悪いんだが、一つ頼まれてくれないか」
申し訳なさそうに、王子であるヘディンがそんな頼みごとをしに来たのだ。騎馬能力に長けていることを理由に、最も遠方のスレーク国境付近への派遣が決まっていたシャルに、もう一つ使命が与えられた。
「サリを、お前の部隊に入れて行って欲しいんだ。彼の故郷はスレークの国境地帯にあって、まさに魔獣に襲われているかもしれないという状態なんだ。途中まででいいから」
(王子は、僕たちを便利屋扱いしてないか?)
そんな疑問をシャルは抱く。もちろん冗談なのだが、以前のレオンの言葉がどうにも引っかかる。しかし、その辺の探りは自分には向かないのでシオンに任せることにした。
(アイツ、超無愛想だけどその点はボクより賢いし)
そう思って、見送り側にいるシオンに目線をやった。フィリアに遠征していたシオンとカリーナは今回の遠征から外されていた。そもそも今回は大軍団での任ではなく、最終的には10人一組で小規模編隊を組むことになる。軍師と『風読み』が行ったところで大したことはできないだろう。
「皆、無事に戻ってくるように。…進軍開始だ!」
ハサンの掛け声で、軍隊は一斉に動き出す。城門の前、国王ハサンの隣に銀の鎧を身に纏って正装した王子・ヘディンも見送りに立っていた。サリエルは兜の下から、ちらりと視線を向けた。ヘディンは気が付いていないらしく、ずっと真っ直ぐ前だけを見つめていた。
(王子…。僕が必ず、何とかしてみせますから)
サリエルは目線を前に戻し、前を行く部隊の背中をじっと見つめた。
出陣式を終えたヘディンは、着替えのために自室へと足早に向かっていた。今回は緊急性の高い遠方への遠征部隊を早急に出立させただけで、近郊地域の対策はこの後の会議で決められる。なるべく迅速に、手を打たなければ人命が危うい――そんな焦りがヘディンの中にあった。
「王子!王子!こちらでしたか!」
ゼイゼイと息を切らして神官服をまとった老人が走ってくる。片手には何か紙切れを持っていた。
「ホルムス司教、どうかされましたか」
ヘディンも小走りでホルムス司教に近寄る。
「こ、これが、サリエルのベッドの上に……」
そう言って、ホルムスは紙切れをヘディンに手渡した。そこには、『故郷へ帰ります。心配しないでください。サリエル』と簡単に書かれてあった。
「彼の故郷の話は聞いたことがありませんでしたが…王子ならご存じかもしれないと思いまして」
ゆっくりと息を整えて、ホルムス司教が尋ねる。ヘディンは「ああ…」と声を漏らして、続けた。
「昨日挨拶に来ました。さっき出立した騎士達に同行させてもらっているから大丈夫ですよ」
あくまで途中までだけど、とヘディンは心の中で続けた。
「そ、そうだったのですか…。ご存じでしたら、よかった」
ふー、とホルムス司教は長い息を吐いた。
「しかし…彼が『白天使』の声を聴いたという話が城下で持ち切りなのに…そんな時に姿を見せなくなったというのは、民は不安にならないでしょうか…」
「そんなことになっているのですか?」
ヘディンが怪訝な顔をする。
「ええ。一目見たいと宮廷教会にもやってくる者がいるほどですよ」
参ったな、とヘディンは心の中でつぶやいた。ある大きな脅威に対して、人心が一つに団結するのはある意味統制がしやすい。しかしそれが『白天使』の名の下にされることは、ヘディンにとって本意ではない。サリエルをここから出奔させたとしても、一足遅かったのだ。しかし、いたずらに民に不安を抱かせるのも為政者としては避けたいところだった。胸に苦々しい思いを抱きながら、ヘディンは口を開いた。
「…実は彼は、『白天使』の手がかりを更に得るための旅に出たのです。もし何か聞かれたら、そう答えてはくれませんか」
これは紛れもない事実だ。事実だが、このことをひけらかすのは苦肉の策でもあった。敵に塩を送るとはこういうことを言うのだろうか。ホルムス司教は得心したのか、目を見開いて深く頷いた。
「そう、だったのですか…。それであれば、誰も悲しみはしませんね」
「司教。どうか、サリエルの旅路にイーレム神の加護があることを祈ってやってください。きっと、活路が見いだせると」
「そうですな。早速、今朝のお勤めからそうさせていただきます」
深々と礼をして、ホルムス司教は足早に立ち去っていく。その姿を、ヘディンは渋い顔で見送った。
南海に浮かぶ絶海の孤島、バイタル。
年中常夏のこの島は、フォーレスの隣国(と言っても、航路で一週間程度かかるが)で、特に地教国家の中でリゾート地として広く知られている。火山が島の中心にそびえ立っており、時折噴火することはあるが、青く澄み渡った海と白い砂浜は、来る者全てを魅了する『楽園』と言われている。
「うわあ…綺麗…」
島が見えてくると、ファーナは目を輝かせてその景色に目を見張った。
「…まあ、この辺までくるとこんな感じだな」
反面、さして面白くもなさそうにカティスがぽつりと呟く。
「フォーレスもこんな感じ?」
「ああ…あそこにはこんなにでかい火山はないけどな。けど…『楽園』って言われる場所は…やっぱ不思議とこういう景色、なんだよな」
どこか遠くを見つめてカティスが答える。
「そっか…ちょっと楽しみかも」
にっこりとファーナがカティスに微笑みかける。そんな二人を、後ろからじっと見つめる人物がいた。
「ダタさん?どうしたんです?こんなところで」
シジェが物陰から二人を覗くダタに気がついて声を掛ける。
「っ!…何だ、シジェか…」
シジェはダタが見ていた方向を見て、ダタが何をしていたかを察した。
「ああ…お姫さまとカディさんですか。お目付け役は大変っすね」
「お、お目付け…」
確かに当たってはいるのだが、今はそんなつもりで見ていたわけではなかった。あの青年――カディと皆が言う青年は何者なのだろうか。
「シジェ、お前は俺よりも先にこの一行に加わったんだったな」
「え?そうっすけど」
「あの…カディ殿とは一体何者なんだ?」
「え?…いや、お姫さまの恋人?じゃなくて?」
「誰が恋人などと!」
「うわあ!冗談ですってば!」
思わず声を荒げたダタに、シジェが驚く。ダタはハッとして、ゴホン、と一つ咳払いをして声を潜めた。
「…すまん、その…妙な御仁とは思わないか?」
シジェはその言葉に腕を組んで、うーん、と唸った。
「…まあ、確かに。妙に強いっすよね。初めて会ったのがクーラントでしたけど、魔獣の群れに先陣切ったりしてたしなあ。僕も正直それ以上は…」
「…そうか」
思いのほか深刻そうな面持ちのダタに、シジェはにかっと笑って見せる。
「ま、そんなに悩まなくてもいいんじゃないっすか?お姫さまのこと、ちゃんと護ってますし。じゃあ、僕はこれから接岸準備するんで、これで」
そう言って、シジェは持ち場へと向かっていった。その後ろ姿を、ダタはぼうっと眺めていた。
いくばくかしてから、港の船着き場の一番街から外れたところに、ラズリの船は停泊した。
「うわあー!砂浜が白いー!」
キラキラ目を輝かせて、ファーナは駆け足で船から降りる。久々の地面の感覚。それが妙に心落ち着いた。
「ガキかお前は。はしゃぐなよな」
その後ろからカティスが降りる。心底迷惑だと顔に書いてある。
「いいじゃない。初めてなんだもん」
むっとしつつ、まるでおのぼりさんのように周りをキョロキョロとしながら歩く。白い砂浜と宝石のような青い海、青い海と同化するかのような青い空に浮かぶ白い雲、大きな葉を付けた熱帯の木々。リゾート地かつ貿易の中継地点でもあるためか、建物は背が高く、綺麗で美しいものばかりだった。エルガードやリクレア、シャクーリアとも違う南国の景色に、ファーナは心奪われた。
「…相変わらずですなあ、姫は」
「まあ、らしくていいではないですか」
二人の後ろから、ダタとラークが会話をしながら降りてくる。無邪気にはしゃぐファーナの姿は、エルガードへ留学していたころをラークに思い出させた。懐かしく思って眺めていると、ファーナがくるりとラークの方を向いた。
「先生!じゃあここからは自由行動ってことでいいのね?」
「ああ。夕方には帰ってくること」
「わーい、やったー!カディ、どこ行く?」
隣のカティスに無邪気に声を掛けたが。
「…たまには一人きりにさせてくれねえか…」
完全に気が滅入っているようだった。
「えー、つまんないなー…。じゃあ、私一人で行くねー」
そう言って、ファーナは軽やかな足取りで一人先を進む。その姿を見ながら、ダタが自分よりも上背のあるラークを見上げた。
「…ラーク殿はどうされるのです?」
「私はラズリ達を待って紅茶の店を案内してもらおうかと。ダタ殿は?折角ですし、羽を伸ばされたら?」
ダタが「うーん」と唸って考え込む。目線の先には、町の中へ消えていくファーナと、ファーナとは違う方向に向かうカティスの背中があった。
「私は…調べものがありますので、これにて」
そう言って、ダタもカティスが向かった方向へと向かっていった。一人残されたラークは、渋い顔をしながらその様子を眺める。
(…あまり勘繰られても困るのだが…まあ、どうこうしようもないが)
そんなことを考えながら、ラークは船の方を振り向いた。準備が整ったのか、ラズリとシジェが降りてきた。
「うん?皆は?」
船から降りてきたラズリが周りを見て、不思議そうに尋ねる。
「もう行ってしまったよ」
「そうか。用事が済んだら町を案内でもしようかと思っていたんだが」
ラークの返答に、ラズリは肩をすくめる。
「用事が済むまでお付き合いさせるのも時間が勿体ないっすからね。いいんじゃないっすか?」
のんびりとシジェがラズリに言う。
「…まあ、そうだな。ラーク殿はどうする?」
「それなら、私は君たちと同行させて貰うとしよう。買い出しもあるのなら、人出もいるだろう?」
「そう言っていただけると有難い。それじゃあ、行くとしようか」
…困った。
一人で街中を探検しようとしたものの、周囲の看板に書かれている言語が、カルディアで使用されている共通語ではないことにファーナは気づいた。かろうじて、フォーレスからの留学生に教えてもらったフォーレスの言語だけは、基本的な単語程度なら読める程度だ。
ファーナが歩いているところは、繁華街のようだった。赤い髪という出で立ちは珍しいらしく、周囲の目を引く。町の人々は皆、こんがりと焼けた浅黒い肌と黒い髪をしており、日差しと熱を避けるため、刺繍をあしらった薄手のローブを纏っている。
(…シャクーリアでラズリさんから貰ったあの地味な服、着てくれば良かったなあ…)
少し気まずさを感じながらも、ファーナは官公庁や学校がある山側へと進む。その近辺には、ジェムの発掘所もあるといい、以前レオンから貰ったジェムの故郷を見てみたいと思ったからだ。
やがて人通りも少なくなってきた。見慣れない言語が書かれた看板とにらめっこしながら歩くこと数十分、やがて目的地が見えてきた。
「あー…ここかあ…」
ジェムを持ち運ぶための台車や、ツルハシなどの道具を持った人々が行き交っている。まだ加工されていない岩の影から、赤い宝石が覗いてキラキラと光っている。その煌びやかさに、ファーナは目を奪われた。
(綺麗…)
首から提げているペンダントを手に取り、見比べる。この石もああやって、原石として採掘され、加工されて手元にあるのだと考えると、感慨深いものがあった。
(中には…さすがに入れないかな…)
そう思って、洞窟の中を背伸びして覗こうとしたその時。
「――!」
後ろからいきなりすさまじい力で腹を抱えられ引き寄せられ、布のようなもので口をふさがれた。拘束を解こうとしても解けない。前にも、似たような目に逢ったことをファーナは思い出した。そう、あれはルバタで――
「そんなに暴れないで、お姫様」
背中から声が聞こえた。間違いない。聞き覚えのある声だった。
「迎えに来たんだよ。だから落ち着いて…」
その声がだんだん小さくなり、目の前の景色も閉じていく。
(…嘘、これって…睡眠薬…っ…)
そう思ったのも束の間、ファーナの意識は途切れてしまった。
「…おい、いつまでそうしてるつもりなんだよ」
繁華街を抜け、自然史博物館のある方向へ歩いていたカティスが、不意に立ち止まり、口を開いた。周囲にはあまり人はいない。独り言のようだが、カティスは確実に、その人物の存在を認めていた。しかし、その相手から返事は帰ってこない。
「…まあいいけどよ。俺なんかより、大切な姫さんの方に行ってやらなくていいのか?お守りさんよ」
そう言って、カティスはまた歩き出す。しかしその人物の気配が消えることはなかった。
「…これは俺の独り言だけどよ、ここの島は地教だぜ?右も左も解らねえお姫様が迷子になってもいいのか?」
その言葉を聞いて不安になったのか、カティスの目の前に、背の小さな男が音もなく現れた。
「…そうお考えならば、貴方もついて行くべきでは?」
「俺は別にあいつの保護者じゃねえし。それ言うならセンセに言えよ。俺だってたまには一人になりてえんだよ」
じゃあな、と言って手を振りカティスはまた歩き出す。
「…ならば。姫様がいない今お聞きしましょう。…貴方は、一体何者なのです?姫様をどう思われているのです?」
ダタの質問に、カティスは歩みを止めることなく答える。
「…そんなこと聞いて何になる?あるがままを見てあんたが勝手に判断しろよ。俺は…何も言う気はねえよ」
半分呆れたような声音だった。カティスはそのまま、博物館の中へと消えていく。ダタはその姿をしばし眺めていたが、やがてその後を追っていった。
繁華街を、大きな手提げ袋を両手に抱えてラークとシジェが歩いていた。中には、この先の航海のための食料品が詰まっている。
「じゃあ、一旦これ積んできてもらっていいか?おれはその間服屋に行ってくるから」
ほんの数分前。ラズリのその依頼に、一瞬ラークはむっとした表情を浮かべた。そこに、シジェが隣でこっそりとささやく。
「女物の服見に行くんすよ。ここは快諾してください」
その言葉にラークも成程と思い、一つ返事するしかなかった。こうして、船までシジェと荷物運びをするはめになったのだった。
「フォーレスまでは、どのくらいなんだ?」
「うーんと、ここからだと一週間くらいっすかね。いいところっすよ」
にっこりとシジェが笑う。
「行ったことがあるのか」
「ええ。一回だけ。大陸の人から…っていうか、天教の国からどう思われてるかは解らないっすけど、そんなに閉鎖的って訳でもないっすよ」
「それは、まあ…。知り合いにフォーレス出身の者も幾人かいるから解る。ただ、やはり最初は当たりが辛いな」
そう言ってラークは苦笑した。エルガードは世界各国から多くの者が集まる。自分はともかく、特に天教国家出身の者に対しては魔獣を見るような目で見る者もいた。
「まあ、そうなんでしょうね。侵略者とか、魔獣の一種だとか、そう教え込まれてる人も中にはいるみたいっすから」
「…それは、ある意味正しい。否定のしようはないな」
そう言って、二人は口を閉ざした。周りは賑やかなのに、二人が纏う空気はひどく重い。
「…ラークさん」
「うん?」
「そういうのって、どうにかならないんすかね?」
軽い調子で言ったシジェの言葉に、ラークは黙り込む。
「…難しい問題、だな」
きっと無くなることはないだろう、とラークは心の中で続けた。認識を変える変えないの問題ではない。事実として、そこに明確な差があるのだから。その差を無いものとして目を瞑ることは至難の業だ。
「それこそ、いるかどうかも怪しい神様とやらに頼むしかない」
「…そうっすよねぇ…」
はあ、とシジェは溜息を吐いたが、顔を上げて笑顔を見せた。
「ま、辛気臭くなっても仕方ないっすから。さっさと荷物積んで、買い物楽しみましょうか」
「う…」
熱さを感じてファーナは目を覚ました。仰向けに横たえられているらしく、天井には岩が見えた。手足は大の字に縛られており、身動きが取れない。空気が熱いせいか、意識がぼーっとする。
「ここは…」
見渡そうにも、首が固定されていて動かせない。どうやら捕らえられているようだった。
「目が覚めた?お姫様」
さっき聞いた声が聞こえた。目だけを右側に向けると、得意満面な笑みを浮かべた少女が見下ろすようにして立っていた。間違いなく、ルバタで接触した少女だった。
「ルナリアっ…!何をする気なの!」
どうせろくなことではないことは重々承知だった。だが、聞かずにはいられない。
「何って…。面白い実験だよ」
そう言って、ルナリアは得意気にガラスの密閉容器を見せた。中には赤い液体が入っている。
「コレ、何かわかるかな?」
「!まさか…血…?私の…」
意識が朦朧としているのも無理は無かった。大量の血を抜かれて貧血状態に陥ってしまっているのだ。
「…それで何をするつもり…」
「『竜人』はその身に強大な魔力と…精霊を宿してる。それを解明して、兵器に転用するんだよ。…君の血が君の国を滅ぼす。最高じゃない?」
そう言って、クスクスと笑う。
「非道なことを…」
ファーナの声が怒りに震える。
「何を言ってるの?『呪い子』を生み出している貴女達『竜人』の方が非道だよ。ボクたちはそんな『竜人』から世界を人間の手に取り戻すために戦ってる。…どんな手段を使ってもね」
「っ…!でも、それはっ…」
それは紛れもない事実だ。ファーナには返す言葉が見つからなかった。
「…ほら、言い返せないでしょ。そんなお姫様に、罪滅ぼしの機会を与えてあげるよ」
そう言って、ルナリアは軽々とファーナが横たえられている台に乗り、手のひら大ほどある茶色い宝石を懐から取り出した。陽炎が立ち上っているような、ゆらゆらとした光を放っている。ファーナはそれを一瞥すると、心臓がドクンと高鳴った。
「えっ…何…それ…」
何かよく解らないが、胸がざわざわする。何故か、触れたいと思う反面、とても恐ろしいと感じた。
「これはね…ボク達の神様の力が濃く宿っている石だよ。この大地の奥底におられる、この世界の創造主のね…。ふふ、やっぱり貴女にも解るんだね、この石の力」
「そ、そんなの知らない…!やっぱりって、どういうこと!?」
顔をひきつらせてファーナは必死にもがく。とにかく、近づいたら何かとんでもないことが起きそうな気がした。それに対して、ルナリアは心底面白そうに言う。
「何だ?知らないの?自分の事なのに。でもまあ、知らない方が面白いかも」
そう言って、ルナリアはファーナの眼前に石を見せた。
「うっ…」
頭が混乱する。ふつふつと今まで抱いていなかった感情が湧き上がってくる。――やり場のない、怒りや憎しみ、哀しみが、ファーナの心を支配していく。
「嫌っ…!私、はっ…!」
涙が湧き出てくる。どんなに頭を振って払おうとしても、その感情が払えない。
「無駄だよ。もうあきらめてその身を全てヴォルス様に捧げるんだ」
ルナリアは石を、ファーナの胸の上に置いた。そこから、灼けるような熱が全身を駆け巡る。それと同時に、身体の内から今まで経験したことのないような力が解放される。
「ああああああっ!嫌ああああ!」
『異なる者達よ、滅べ、朽ちよ…!』
『我が血に灼かれ無へと還れ…!』
耳の奥底で、怒りがこもった男性の低い声が聞こえた。いつか同じようなことを体験したのをファーナは思い出す。――そう、カルディアで、あの石に触れた時と同じ――。
(…カディ…助けて…!)
ふと、あの銀の髪の青年の姿が脳裏をよぎる。その姿を頼みに意識を保とうとしたが、ファーナは巨大な力と意志の前に力尽きてしまった。
カルディアの首都・ハルザードの王宮の大広間に、赤い軍服を着た人々が入室する。カルディア神聖王国が誇る『炎の騎士団』の定例軍備会議が始まろうとしていた。
赤い軍服が入口側に着席し、空間を隔てた向かい側に、青い軍服――宮廷騎士団の面々と、留守居の軍事を任されていたヘディン、そして、王ハサンとヴィオルが座る。
「ウルス団長、全員揃いました」
ライラが全員を見渡して、顔面の左に切り傷の跡の残る屈強そうな壮年の男性に声をかけた。
「まずは皆、フィリアの遠征ご苦労だった。戻ってからしばしの休息を経て、本日のこの会議を迎えているわけだが、本日再び各地へ派兵された者もいる。その背景について、留守居として各地の情報を整理していたヘディン王子から、現状を報告いただく」
ヘディンがこくりと頷いて椅子から立ち上がり、口を開く。
「皆も知っていると思うが、ここ1~2カ月の間、急激に魔獣の出現報告が上がってきている。この地図を見てほしい。発生時期毎に色分けして落としたものだ。ここ首都ハルザードよりも遠方の地域から、こちらに近づくようにして発生している。やがてここハルザードの近くにも発生する可能性がある」
地図上に指で円を描いて、ヘディンは続ける。
「今回はこの辺りまでの遠征だったが、次回は中間帯への派遣、それと同時に、ハルザードの警備強化も図りたい」
ふむ、とウルスは声を上げる。
「概ねよろしいのではないですかな。しかし、今回の遠征の後詰はどうされる」
「…これは反対意見を持つものもいると思うが、周辺国との連携も必要だと私は考えている」
会議の場がざわめく。
「周辺国…?王子、それはスレークやフィリアと手を結ぶということですか?」
赤い軍服の側からヘディンに非難にも似た質問が飛ぶ。
「ああ。各方面に行っている諜報部隊から、カルディアよりも魔獣の発生が深刻だという報告が上がっている。それならば、国境付近の魔獣については、隣国と協力して対処した方が効率的だと私は考える」
冷静な調子でヘディンは答えを返した。
「敵国がこれに乗じて攻め入る可能性もあるのでは…」
「対魔獣については、国の利害など関係ないだろう。民の安寧を図るためには必要なことだ」
難色を示すような声が卓上のあちこちから上がる。
「…私は反対です。そんなことをするくらいなら後詰せず、その場で立ちとどまり地元の自警団と共に戦います」
一人が声を上げ、それに続くように「そうだ、そうだ」の連呼となった。
ヘディンはその様子を見て、目を閉じ一つ溜息を吐いた。その様子を横目でちらりと見たウルスが口を開く。
「…それであれば、遠方への後詰はごく少数の精鋭を派遣することにしてはいかがか。そうすれば、中間帯への影響も微少に抑えられる」
ウルスの提案に、各所から拍手が起きる。ヘディンはその様子を見渡してから、ウルスの方を見やり、不満そうな顔で頷いてストンと椅子に座った。
「それでは、現遠征部隊の後詰についてはウルス団長の意見を採用ということで異論はありませんか」
異議なし、という声が続々と上がる。
「…では、人選は後程ということでよろしいでしょうか、団長」
少し心配そうな表情を浮かべながら、ライラが尋ねる。
「それで構わん。次は、次回の遠征部隊の班割についてだが…」
ウルスが次の議題について話をし始める。ヘディンの胸に苦々しい気持ちが込み上げてくる。そんな息子の様子を、隣に座るハサンだけが、何とも言えない表情で見つめていた。
昼が過ぎ、繁華街よりも海岸沿いに人出が多い時間になった。人通りが少なくなった街中を、ラークとラズリ、シジェが歩いていた。三人とも、あらかた買い物を済ませ、買い物袋を思い思いに持っていた。
「…ラークさん、いくらなんでもそれ買いすぎじゃないっすか?」
ラークが右手に持っている布袋には、溢れんばかりに紅茶の茶葉が入った袋が詰められている。
「知らない茶葉を見つけるとつい試してしまう性分でな…」
そう言いつつ、当の本人も思わず苦笑いを浮かべる。
「しかし、その量を持って歩くのは大変そうだな。もし他に見て回るところがあるなら、おれはもう船に戻るから持っていくけど」
「あ、僕ももう戻るっす。お頭は結構大きな荷物持ってますから、僕が持っていきますよ」
ラズリの左肩にかかっている大きな袋を一瞥してからシジェが言った。
「そうか。なら申し訳ないが頼む。折角だから博物館を巡っておきたいから」
そう言って、ラークはシジェに袋を預けた。
「いえいえ。お安いご用ですよ。ラークさん、楽しんできてくださいねー」
ぶんぶんと手を振るシジェとラズリを背に、ラークは博物館のある方向へと向かって歩き出した。すると、目の前に見慣れた人影が見えてきた。日差しを避けるためにフードを被っている地元民の中で、彼の銀髪は一際目立つ。
「…何だ、一人なのか」
少し大きな声で、ラークはその人物に声を掛けた。向こうも気が付いたようで、真っ直ぐラークの方へ歩いてくる。どこか不機嫌そうだった。
「…一人じゃねえよ。あの小さいオッサンに付けられてて気持ちわりい」
そう言って、カティスは横にある大木の枝を横目で睨む。ラークは内心で、まだ付けているのか、と苦笑した。
「で?センセも一人かよ」
「ああ。博物館に行くつもりだ」
「ふーん…」
そこで一瞬沈黙が流れた。それがおかしく、ラークはくすりと笑ってしまった。
「…何だよ」
カティスが訝しげに聞く。
「いや、ファーナがいないと、少しばかり調子が狂うなと思ってな」
何だかんだ、あの明るい少女は場を和ませているのだなとラークは実感した。
「…そういや、別れてから見かけてねーな。センセは?」
「私もだ。まあ、どこかで遊んでるんだろう」
再び沈黙が流れる。互いに顔を見合わせて神妙な面持ちになる。
「…いや、まさかな…」
「まあ、夕方になっても戻らなかったら探しに行きゃいいだろ。ガキじゃあるいまいし」
「それもそうだ。それではな」
歩いてしばらくして、後ろの方から声がかかる。
「ああ、なかなか楽しかったぜ、博物館」
「そうか。楽しみにしておく」
振り返らず、手だけ上げてラークはその声に応え、再び一人になって博物館へと向かう。しかし、心の中にできた不安のもやは、晴れることはなかった。
火山洞窟の最奥。マグマが流れ、空気は異様に熱い。そんな環境の中に、簡素な実験機器が置かれている。金属製のものは触れば熱いだろうに、眼鏡をかけた男はいとも簡単にそれらを取り扱っている。
「コークス、どんな感じ?」
ルナリアが、眼鏡をかけたオールバックの男に後ろから声を掛ける。
「同調段階90%…。もうすぐだ」
そう言って、コークスは目線をマグマの方へと向けた。そこには、赤茶色の宝石が随所にあしらわれた鎧を着こんだ少女が、台に固定され立っていた。少女は気を失っており、目を閉じぐったりと下を向いている。
「ふふ。楽しみだね。で、もう一つは?実用化できそう?」
「ああ。やはり竜人の姫となると、格別だったよ。試験体に使用して余った分については、持ち帰って量産化を図りたい」
コークスは、洞窟のさらに奥の暗がりに目をやる。そこから、地鳴りのようなグルグルとした音が響いてくる。
「そうだね。…なら、コークスはお姫様が仕上がったら、先に帰ってよ。後はボクが済ませておくから」
そう言って、ルナリアはコークスの目線の先の暗がりへと向かう。それを見て、コークスはルナリアの背中に言葉を投げかける。
「…一人で対処できるのか?」
「いや。正確には『二人と一体』だよ。それなら行けるでしょ?」
振り返って、ルナリアは不敵な笑みを浮かべた。
「…成程な。解った。奴らもそろそろ姫の不在に気づく頃だ。なるべく急ぐことにしよう」
ルナリアの姿が暗がりに消える。それを見届けて、コークスは再び機器に向かう。顔には狂気じみた笑みが浮かんでいた。
(この娘は、世界を変える『鍵』足りえる…。そう、この俺が、この娘を使って、世界の革命者となるのだ…!)
「では、本日の会議はこれまでとします。王族の方々から先に退席いたします。皆一礼を」
ライラの一声で、ハサン、ヴィオル、ヘディンが立ち上がり、赤騎士たちの礼を受けながら大広間から退室した。
昼前から始まった会議は、夕刻に差し掛かった頃に終わりを迎えた。廊下にはオレンジ色の陽が差し込んでいた。
「…ヘディン、あれはある意味正論かもしれんが、兵の気持ちを考えていなかったな。彼らは国境地域で小競り合いではあるが、隣国と戦っている身。協力体制を築く、というのは難しい」
前を歩くハサンの言葉がヘディンの胸に突き刺さる。
「はい…。面目次第もございません」
ヘディンが反省の弁を述べる。
「…お前には軍を纏めるには少し早かったか。ハサンやウルスも帰ってきたことだ、元締めの任から降りてまた一から学び直すとよい」
ヴィオルはヘディンにそう告げると、颯爽とその場を去ってしまった。ヘディンの胸に悔しさが込み上げる。残ったハサンがヘディンに向き直り、ポンと肩を叩いた。
「あまり気落ちはするな。親父の前では大きな声では言えないが、俺もお前の意見は一理あると思ってる」
「父上、それなら…!」
「前にも言っただろう。お前は違う世界観に身を置いているからそういう発想になる。だが、お前以外は昔ながらの世界観で生きているんだ。そこの違いだ」
「うっ…」
水を浴びせるような言葉に、ヘディンは言葉を詰まらせた。
「それはな…同志がいなければ孤独な戦いだ。そんなお前を俺は尊敬するよ。…後の事は俺が何とか舵取りをするから、お前は、お前しかできない、お前がやるべきことをやれ。いいな」
父の温かい言葉に、ヘディンは少し救われたような心地になった。
「父上…どうか、よろしくお願いします…」
ヘディンはその場を立ち去るハサンの後姿に、深々と頭を下げた。
火山の端に陽が落ち始める。博物館から出てきたラークは、その様子を横目で見ながら、足早に街の中心部へと向かった。過保護と言われるかも知れないが、どうしてもファーナのことが気にかかった。
「ん?あれは…」
背丈の小さい人物が、街の中心にある広場にいた。まだ遠目でしか確認できない距離だが、その人物もラークに気が付いて走って向かってきた。
「ラーク殿」
「ダタ殿。もしかしてファーナは…」
ダタは首を横に振った。
「先ほどから市街地を中心に探しておりますが、姿をお見かけしません」
不安が的中した。事故か…もしかすると事件か。ともあれ、一人で行動させたことをラークは心の中で悔やむ。そこに、カティスが海側から走って向かってきた。
「…あっちも、姿は見えなかった…。ラズリにも聞いたが、戻ってないってよ」
珍しく息を切らしているカティスの姿を見て、ラークは心の中で驚く。本気で探してくれている。彼にとって、ファーナはそれだけの存在になっているということだ。
「あとは、山側か…。暗くなる前に行かねえと」
そう言って、カティスは火山を見上げる。市街地から見て火山は南西側にあるため、余計に日が暮れる時間が早い。
「そういえば昨日、ジェムが里帰りとか言ってたな。採掘所あたりが怪しいか…」
何故かファーナとラズリ二人に笑われたことをラークは思い出し、苦い顔をする。
「ああ、そうだったな。行ってみる価値はある」
三人は、夕暮れの中、採掘所の方面まで走る。採掘所まで辿り着くと、筋肉隆々の作業員の他に、茶色の制服を着た警官らしき人物が何人か立っていた。
「…何かあったのか?言葉がよく解らないが…」
「俺が聞いてくる。ちょっと待っててくれ」
ラークにそう言い残し、カティスは困り顔で立ち話をしている警官と作業員に近づいて話しかける。
「悪い、何かあったのか?」
「ん?君も旅行者か。いや、このあたりで見慣れない格好の少女が、これまた見慣れない少女に連れ去られたって、ここの作業員が言っていたから探していたんだが…」
警官の言葉に、カティスははっとした。
「それ、連れ去られた少女って、赤毛で髪が長くなかったか?」
「ああ、そうだよ。…もしかして君の連れかい?」
作業員の言葉にカティスはしかめ面をする。ファーナを連れ去って益のある連中。すぐに心当たりが浮かんできた。
「じゃあ、連れ去ったって女は、髪が短くて、そいつよりも背が小さくなかったか?」
「…ん?何でそこまで解るんだい?君は二人の居場所を知っているのかい?!」
ごつい作業員に鬼気迫る形相でカティスは睨まれた。しかしカティスはしれっと返す。
「知らねえよ。俺は攫われた方の連れ。その連れ去った奴に一度攫われかけたことがあったんだよ。なかなか戻らねえって思って探してたんだ。情報ありがとな。後は俺らが何とかするから、アンタ達はもういいよ」
警官と作業員は顔を互いに見合わせた。
「そういうなら…。だけど、力になれることがあったら言ってくれ」
「ああ、気持ちだけ受け取っておく」
軽く礼をして、カティスは二人のところに戻る。
「どうだった?」
「当たりだよ。ファーナはこの辺で連れ去られたらしい。…スレークの連中に」
ラークとダタはその言葉に顔をひきつらせた。
「ったく、付けられてるなんて思いもよらなかったけど、気を付けておくべきだったな。ここは火山の国だ。奴らが信奉してるのはヴォルスって火山の神なんだ。…奴らにはうってつけの土地柄だ」
「で、では、我らはまんまと敵の懐に飛び込んでいたと…?」
顔面蒼白でダタが言う。
「まあ、そこは仕方ないでしょう。今はスレークの連中がどこにファーナを連れ去ったのかを考え、奪還することが肝要です。日も暮れてしまえば、それはますます難しくなる」
冷静にラークがダタに返した。
「では、その者達が居そうなところは…」
「火山…、だな」
カティスがきっぱりと断言する。
「まあ、そうだろうな。…ダタ殿。取り敢えず貴方はラズリ達に顛末を話しに戻ってもらえませんか。私達は先に山へ向かいます」
ダタは苦々しい表情を浮かべた。
「私も一緒に向かいます!姫様が攫われたのは、私の責任ですから…」
些末なことにこだわって、大事なものを失ってしまっては元も子もない。主であるヘディンにも申し訳が立たない。ダタはそんな気持ちでいっぱいになっていた。
「ダタ殿。ラズリ達にも、有事の際には動いてもらわないとなりません。そのための大事な仕事なんです。…これは、想像以上の事件かもしれませんから」
深刻な面持ちでラークが言う。その表情を見て、ダタは眉をひそめた。
「…解りました。姫様のこと、よろしく頼みます」
ダタは深々と頭を下げ、港の方角へと走っていく。それを確認して、カティスとラークは互いに顔を合わせて頷き、森へと走っていった。