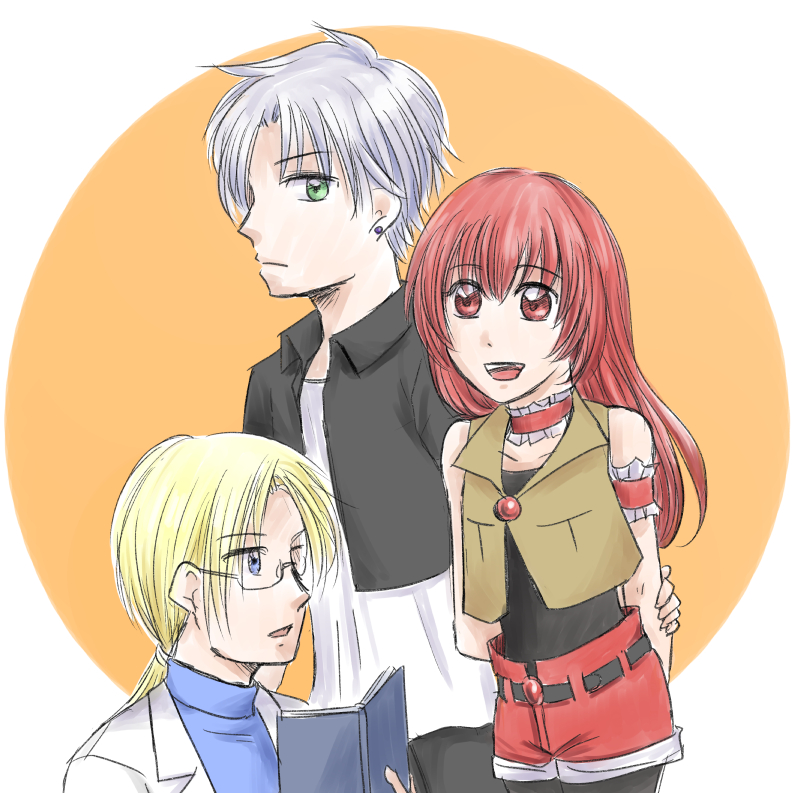手元に光を喚び、暗い森の中をラークとカティスはひた走っていた。出発してからかれこれ数十分は経過しただろう。カティスがふと口を開いた。
「センセ、想像以上の事件かもしれねえって、さっき言ったよな」
「ああ」
「何か思い当る節でもあるのか?」
カティスの問いに、ラークは少し逡巡してから口を開いた。
「昔…ファーナがエルガードに来た頃の話だが、精霊術の適正検査をして…妙な結果が出てな…。地の精霊術の方が、火の精霊術よりも親和性が高かったんだ」
「…は?そんなことがあるわけ…」
カティスが間の抜けた声を出す。しかし、それで合点が行った。
「…いや待て、センセと合流する前、地の精霊術を発動させてたことがあったな…。勿論、その後は倒れてたが」
本人は心当たりがないと言っていたことをふと思い出し、カティスは続けた。
「そのことは…伝えてないのか、アイツには」
「伝えていない。知ればショックを受けると思ってな」
「何でそうなのかは、アンタは原因知ってるのか?」
カティスの言葉に、ラークは一瞬返答に迷った。ヘディンからの手紙――しかしあれは憶測でしかないのだ。
「いや…確信的なことは何も」
「そうかよ。…けど、それでアンタの懸念は解った。…暴走、だな」
カティスが渋い顔をして吐き捨てた。
「最悪の場合は、だがな…。向こうがファーナの特異性に気がつけば…きっと利用する」
またしばらく無言になる。鳥の鳴き声が少しする以外は、辺りは静まり返っている。
「…なあ、センセ」
「何だ」
ポツリと、カティスが切り出した。
「アンタは…自分の中の精霊を暴走させたことがあるか?」
「いや…」
戸惑い気味にラークは答える。ややあってから、カティスが口を開いた。
「あれはな…気持ちいいんだ。我を忘れて、身体に溜まってた何かを全て吐き出した感じがしてな…。けど、俺が正気に戻った時には…大量の死体が転がってた」
「…!」
ラークが言葉に詰まる。
「その間の事は全く覚えてねえけど…あの心地良さだけは忘れられない。死の臭い、手に残る感覚、血の美味さ…」
心地良かった、と言いつつも、カティスの表情は暗かった。
(…成程、それが『堕天使』だの『悪魔』だのと言われるようになった所以か)
表情を見る限り、それが本心ではなかったのだろう、とラークは推測する。旅を共にしてきていても、それほど悪い人物ではない。ファーナが自分を止めるのに必死になったのも頷ける。
(だが、そうなると天教で伝えられている彼の姿は…虚飾に彩られているにも程がある…)
真実はどこにあるのだろう。この先に待ち受けているのだろうか。しかしその前に、成さなければならないことがある。
「…ファーナに、そんなことをさせるわけにはいかないな」
カティスと全く同じことがその身に起こるとは限らない。しかし彼女はきっと大きなショックを受けるだろう。
「…全くだな」
表情を変えることなく、カティスはさらりとラークの言葉に応える。内心、ラークは驚いたが、不思議とすぐに心にストンと落ちた。ふっと口に笑みを浮かべて、ラークは前を向く。
「急ごう。何かがあってからではまずい」
そう言って、二人は走る速度を上げて森の奥へと消えて行った。
「あ、ダタさん、お帰りっす!…って、どしたんすか、息切らして」
ラズリの船に辿り着いたダタは、肩を上下させながら甲板の上にいたシジェに近づいた。
「…ラ、ラズリ殿は…」
「?お頭なら下に…」
「そうか」
それだけ聞いて、ダタは船室へと向かおうとした。
「ちょ、ちょっと待ってくださいっす!何かあったんすか?」
後ろからシジェも追いかけてくる。
「…知りたければついて来ればいい。二度も話す時間はない」
振り向くことなく、ダタは足早に船室へと降りる。ラズリはミーティングルームで地図をじっと眺めていた。外から聞こえる大きな足音に気が付いて顔を上げると、表情に全く余裕のないダタと、心配そうな表情を浮かべたシジェが目の前にいた。
「ダタ殿。…何かあったのか?」
何も言わなくても、何か問題があったというくらいはラズリもすぐに察しがついた。ダタはラズリの言葉にコクリと頷き、口を開いた。
「姫様が…攫われました」
「えっ…」
ダタの後ろにいたシジェが声を漏らす。ラズリは表情を険しくしただけだった。
「今、カディ殿とラーク殿が、姫様を探しに行っています。私は状況をラズリ殿にお知らせに来たのです」
「…攫った連中の目途は付いてるのか?」
男性のような低い声で、ラズリが訊く。
「スレークの連中だと、推測しています」
「…スレーク…」
ラズリは腕組みをしながら、溜息交じりに呟いた。
「姫様が行方不明と言う布告が出た後、奴らは姫様を攫おうと画策していました。…まさかこんな、海を隔てた場所でこんなことになるとは…」
正直、ダタには油断があった。見ず知らずの土地で、誰が彼女をカルディアの王女と知って攫う者がいようか。だからこそ、自分はあの銀髪の青年の正体を探ることに腐心してしまった。悔やんでも悔やみきれない。ダタの拳は固く握られ、わなないていた。
「ダタ殿。あまり自分を責めてはいけない。まだ攫われただけで、この島のどこかにはいる。そして…あの二人が向かっているんだろう?なら大丈夫だ」
「何故、大丈夫だと言えるのです?」
「それは…そうだな。言わない約束だから、ご自身の目で見て来られるといい。おれ達は、ここで…みんなが帰るべき場所で帰りを待っている。何か起こればおれ達も微力ながら力を尽くそう」
ふっと、ラズリが笑みを浮かべた。
「…解りました。では、私は二人を追いますので」
そう言って、ダタは再び船の外へ行ってしまった。
日はどっぷりと落ちてしまい、ラークの魔法が無ければ、辺り一面が闇に閉ざされそうな時間になってしまっていた。
二人は大木に寄りかかり、小休止を取っていた。息が落ち着いたら出発する。それをもう幾度となく繰り返していた。
「…これでは、いざと言う時の体力が残らん…」
時間が経てば経つほど、焦りは強くなっていく。ラークは下を向いて、大きく溜息を吐いた。
「けど、近づいてはいるはずだ。この先から、怒りに満ちたヴォルスの気配を感じるんだ。…それと、歪んだ力も感じる。…スレークの連中の事だ、また濃縮ジェムでも使ってるんじゃねえかな」
「…確かに。異様なまでのプレッシャーは先程から感じてはいるが…」
今までにない大きな何かに飛び込んでいく気分をラークは覚えていた。もし最悪の事態が起きていたとして、自分達で対処ができるようなものなのだろうか。
「曲がりなりにも『神』とか呼ばれてる連中が相手だしな。…怖気づいたか?」
「そんなことある訳がないだろう!」
カティスの挑発的な言葉にラークはすくっと立ち上がり、ずんずんと先を進む。
「神相手だろうがなんだろうが、ファーナは救う。それだけだ」
「その意気だ。急ごう」
そう言って二人が再び走ろうとしたその時だった。
「…いい気概だね。けど…ここからは通さないよ」
進行方向から声が掛かる。暗闇から、うっすらと亜麻色の髪の少女の姿が見えてきた。
「貴様…!」
「君は…」
カティスとラークが二人同時に言葉を発する。二人は顔を見合わせて互いに首を傾げた。
「は?センセ、何でこいつのこと知って…」
「シャクーリア行きの船で出くわした少女だったんだが…」
ハッとして、ラークはルナリアの方を見る。
「発信機付きのぬいぐるみ、大切に持っていてくれてありがとう!おかげで見失わずに追うことができたよ」
満面の笑顔をルナリアはラークに向けた。それを見たラークは顔をひきつらせた。
「コイツだよ、ルバタで襲ってきたスレークのヤツって」
呆れた様子でカティスがラークに言う。
「し、仕方ないだろう!くそっ、やられた…」
「…ま、確かに今となっちゃ仕方ねえな。おい、ファーナはどこだ」
「さあね?知ってても教えないけど」
「なら我々の前に何故立ちはだかる」
「この先は神聖な場所だからだよ。ヨソモノ…しかも、竜人が入るべき場所じゃない。異物は排除する…それが、ヴォルス様のご意志だ!」
そう言うと、地鳴りと共にルナリアの目の前に巨大な岩壁が迫り立った。森の木々よりも高く、横幅も随分遠くまで続いている。
「これならこっちには来られないよねー!」
壁の向こう側からルナリアの声が聞こえてくる。
「…どうする」
壁の前で二人は立ち尽くしていた。
「飛ぶか、壊すか…。飛ぶにしても、センセ連れてくにはなあ…。抱っこするか?」
真顔でカティスはラークに訊く。
「…それは御免こうむる」
一つ溜息を吐き、少し後退してラークが壁に向かって右手を伸ばした。
「俺も勘弁だな。じゃあ…壊すか」
ラークに合わせて、カティスも右手を前に突き出した。
「魔力をぶつけるだけでいい。こんなことに精霊の手を煩わせることはない」
「そうだな。いくぞ…」
一点に力を集中させる。魔力はやがてエネルギーの塊となった。
「放て!」
同時にエネルギーの塊を壁に向けて放つ。壁にぶつかるとそのエネルギーの塊は、バシュっという音を立てて掻き消えてしまった。
「なっ!」
「あ、魔法使ってもムダだよー。魔力では壊せない仕様になってるからねー」
壁の向こうから、親切にもルナリアの声が掛かる。
「剣で切りかかっても壊せねえだろうしな…やっぱ…」
そうカティスがぼやいた時だった。
「…ならば、魔法以外で壊せばいいんですね?」
後ろから声が掛かる。カティスとラークが振り返ると、息を切らしたダタがゆっくりと歩いてきた。
「ダタ殿」
ラークが目を丸くして声を掛けた。
「お待たせ、しました…。ラズリ殿にはしっかりと、お伝えしましたので」
「おっさん、何か手があるのか?」
「…ええ。爆薬を使うんです」
そう言って、ダタは携行袋から黒い球体を取り出した。
「下がっててくださいね…!」
足元に転がっている石を持ち上げ、力一杯こする。バチっと火花が散ったのを確認して、ダタはその球体を壁に向かって転がした。
――ドン!
爆発した球体の周辺の壁に人一人が通れるほどの穴が開く。穴の向こうには、慌てふためくルナリアの姿が確認できた。
「な、な、な!」
「残念だったな、ルナリア!入らせてもらうぜ!」
三人が一気に駆ける。
「さ、させないんだから!」
ルナリアが勢いよく腕を上げる。小石がふわふわと宙に浮く。
「いっけえ!」
そのまま腕を振り下ろす。小石が向かってくる三人に向かって弾丸のように襲い掛かる。
「くっ!」
ガツガツと音を立てて3人の身体に当たる。しかし、誰もが怯むことなく走り抜ける。
「どいてもらうぞ!」
一閃。カティスが剣を抜き切りかかった。ルナリアは後ろに退いて攻撃をかわしたが、スレスレのところで胴回りの衣服が横に切り裂かれてしまった。
「…!」
切り裂かれた衣類の隙間から、赤茶色の何かがきらりと煌めいた。それを見て、三人は固まった。
「…それは…ジェムなのか…?」
目を見開いてラークがぽつりと呟く。カティスがその隣で渋い顔をしながら苦々しく続ける。
「やっぱりな。最初会った時から感じちゃいたが…。大方、その歪んだジェムを身体に埋めて、力を増幅させてんだろう?」
「な…!それではまるで、生物兵器ではありませんか!」
ダタが顔をひきつらせた。しかし当のルナリアは、クスクスと笑っていた。
「何?ボクの事が可哀想って?ボクは望んでこの力を手に入れたんだよ。何も同情することはないよ。むしろ嬉しいんだよ…。貴方達竜人とも対等に渡り合える力を手に入れることができてね…!」
狂気にも似た笑みをルナリアは浮かべ、周囲の岩を宙に浮かせる。
「走れ!ここは俺が引き受ける!」
カティスが大声で二人に告げる。
「行きましょう、ダタ殿」
「しかし…」
「大丈夫です。アイツは…アイツにしかできない技で、ここを切り抜けてきます。我々は一刻も早くファーナを取り戻しましょう」
「…わ、分かりました」
考えている暇は無い。ダタとラークはまだ背よりも高い位置にある岩をすり抜けながら走って行く。
「抜けさせない!」
ルナリアが腕を振り下ろす。宙に浮いた岩はこちらめがけて動き出したが。
「させっかよ!」
ほぼ同時に、カティスが右手を前に突き出した。すると、こちらに向かってくるはずだった岩の動きがその場でぴたりと止まった。
「てめえもだ!ルナリア!」
そうカティスが言った瞬間、ルナリアの身体もその場から自由が利かなくなった。
「なっ…!」
カティスに対して後ろ向きに、ラークとダタの背中が小さくなっていくのをルナリアは悔しさを噛みしめながら見つめる。
『汝らがあるべき場所へと移ろえ』
カティスの詠唱に合わせて、岩がドスドスと音を立てて元の場所に戻っていく。そして最後に、ルナリアの戒めを解いた。
「うわっ…ととっ」
勢いが余ってルナリアはその場で転びそうになった。何とか体制を立て直して、渋々カティスに向き直る。
「…報告にあった幻の時空術を操る男ってアンタのことだったんだね。白銀の竜人…まさか、『最初に来た悪魔』?」
そんなことはないだろうと口元に笑みを浮かべながら、ルナリアは構えてつぶやいた。
「そういうことだ。大人しくそこをどいて貰おうか」
カティスの言葉に、ルナリアは一瞬固まったが、すぐに表情を引き締めて啖呵を切った。
「嫌だね。アンタだって…いや、アンタこそが、この大地を穢した張本人じゃないか!アンタが来たから竜人が来た!そうでしょ!」
カティスははあ、と一つ溜息を吐いた。
「まあ、間違っちゃいねえけど…」
「なら、大人しくボクに倒されてよね!」
「残念だが、それは認められねえ。どかねえなら力づくで排除するまでだ…!」
カティスの左耳の紫色のジェムが光る。
「そんな図体になってまで神に尽くすなんざ、いい根性してるからな。苦しまずに死なせてやるよ」
そう言って、詠唱を行おうとした時だった。
大地がズン、と音を立てて揺れた。木々に止まっていた鳥たちが一斉に空へと舞い、辺りが騒然とし始めた。
「…これは…!」
カティスは周囲を見渡した。
「ふふ…アハハ!間に合ったみたいだね…!」
「何…?」
怪訝な顔をして向き直ったカティスに、にやりとルナリアは笑みを浮かべた。
「ボクらの勝ちだよ!もう君達には手出しなんかできない…。ヴォルス様が今、この大地から粛清を始めるんだ!アハハハ!」
パチン、とルナリアは指を鳴らした。すると木陰から、赤い色をした全長三メートルほどはある、翼の生えた蜥蜴のような生き物が現れた。
「…竜だと…!それに、この色…」
ルナリアは軽々と飛んで、その生き物の背に飛び乗った。
「察しがいいね。そう、仕上げはお姫様の血を使ったんだよ。凄く良かったよ…。『精霊の民』との混血のくせにね」
「!」
カティスは目を見開いた。
「…まさか…」
そうは言いつつも、カティスは心のどこかで納得をしていた。シャナの村で地の精霊術を発動させたこと、そして、竜人らしからぬ言動をしていること――。
「ふうん、その様子だと誰も気が付いてなかったのかな?それはそれで面白いね。…じゃあね、『彼女』と一緒にヴォルス様のところで待ってるよ。アハハハ!」
高らかに笑うルナリアを乗せた竜は、そのまま火山の頂上へと飛んで行く。その姿をじっと見つめていると――
「あれは…」
小さくて解りづらいが、人影が山頂付近に見える。周囲には陽炎のようなオーラがゆらゆらと揺れている。
「…くそっ、最悪の事態かよ…!」
カティスも大地を蹴り、白銀の翼を現して空へと飛び立った。
「うわっ…何だ、この揺れは」
森を抜け、洞窟の入り口の前に辿り着いたラークとダタに、地鳴りと地震が襲い掛かる。
「もしこの先にファーナがいたとしても、これでは逆に生き埋めになりかねないな…。どうしたら…」
そうラークが呟いて、周囲をぐるりと見渡す。視界の隅に銀の光がきらりと光ったことに気が付いて、その方角に目を向ける。遠目であるが、カティスだということが解る。さらに視線をカティスの進行方向に向けると、そこには赤い大きな空飛ぶ生き物がいた。
(…何だ、あれは)
顔を顰めつつ、更にその先を見やると、そこには人影がぽつりと宙に浮いていた。既に暗くなった空に、ほんのりと赤いオーラを漂わせているそれは、ラークにも正体を気付かせるに余りあった。
「…ファーナ…!」
別方向を見渡していたダタが、ラークの言葉にはっとして振り向いた。
「ひ、姫が…?」
「…あの人影です。解りますか?」
ラークは山の頂上付近を指さした。ダタもそれを視認して、あっ、と小さく声を上げた。
「あんなところに…!どうやって行けば…」
「それは…こうなってしまえばもうアイツに任せるしかないでしょう」
「えっ?」
ダタが疑問の声を上げた。しかしラークはそれに応えず、洞窟の奥を睨みつけた。
「ラーク殿…?」
「それよりも…誰かが来ます」
カツン、カツン、という足早な靴の音が、洞窟に反響して聞こえてくる。ラークは手をかざして、その方角を光で照らした。光に照らされたその人物は、荷物を抱えていない左手を額にかざして、眼鏡の奥からこちらを睨みつけてきた。
「…これはこれは。道にお迷いですか?」
眼鏡を掛けた、茶髪のオールバックの男性が姿を現した。背はラークと同じくらいだろうか。この島には珍しく白衣を着ており、研究者であることがうかがえた。
「…貴方は?」
「私はコークスと申します。この火山の研究をしているのですが、先ほどの地震でいよいよ危ないかと思いまして奥の研究室から出てきたんですよ」
そこでまた一揺れ。
「…これは火山性の地震です。ここにいては噴火に巻き込まれる可能性があります。早く市街地へ逃げた方が賢明です。道案内は私がしますから」
確かに言っている通りだろう、とラークは心の中で考えていた。しかし、このコークスという男がどことなく信用ならない。
「…どうしますか?」
ダタの問いに、しばらくラークは逡巡してから口を開いた。
「確かに、このままこの場にいたとしても、噴火に巻き込まれる可能性がある…。貴方の意見はもっともですが…」
ラークはそこで言葉を一度切った。
「その荷物の中身を、見せていただいてもよろしいですか?」
ラークの提案に、コークスと名乗った男は表情を硬くした。
「何故です?」
「本当に『この火山の研究』をされていたのかどうかを確かめたいのです。問題が無いなら見せていただくことも可能でしょう?」
「それは…」
コークスが一瞬、言葉を詰まらせた。
「…機密事項ですから、お見せできません。研究者ならば、公表するまで伏せておかねばならないことがあることは貴方も承知でしょう?」
それを聞いたラークは、ダタに一瞬目配せをした。すると、ダタが短剣をコークスの右腕めがけて投げつけた。とっさのことにコークスはうまくかわせず、右腕部分の服を裂かれてしまった。
「と、突然何をするんです…!」
「一言多かったんですよ。私が『研究者である』ことなど、一言も言ってはいない。つまり、私が何者かを事前に貴方は知っていたということだ。…そうだろう、スレークの者よ」
コークスが顔を顰める。
「その荷物の中身も、碌なことに使おうとしないでしょう。命だけは見逃しますが、その荷物は置いて行った方がいいですよ」
ダタがそう言って、再び短剣を取り出した。コークスは観念したように、ふっと口の端に笑みを浮かべた。
「流石…というべきかな、『光の貴公子』殿。そうだ、私はスレークのサンドラ研究院の者…。貴方の名はスレークにも広く知れ渡っておりますよ」
「そんなことはどうでもいい、ファーナに何をした」
「何って…?あの娘の特性を生かしてあげただけですよ。驚きましたよ、まさか『精霊の民』の血が入っているなんて…!天教教主国の一大スキャンダルを手に入れることができて嬉しい限りですよ!」
「何ですって!」
「…やはりか…」
素っ頓狂な声を上げたダタに対して、ラークは至極冷静だった。
「え?ラーク殿…?」
「私は付き合いが長いですから、薄々は感づいていたんです。それよりも、…彼には命もここに置いて行って貰った方がいいかもしれませんね」
「そうですね。世間に知られれば、カルディア王家の信頼が失墜してしまいます…!」
ダタが短剣を持つ手に力を入れる。
「本当に火山が噴火されては困ります。さっさとケリを付けましょう」
そう言って、ダタが真っ先に走っていく。見たところ、コークスは武器らしき武器を持っていない。すぐに片付く。そうダタは踏んだ。
「覚悟…!」
スピードに任せて切りかかる。しかし、左腕で易々と塞がれてしまう。
「な…!硬い!」
ダタは一度間合いを取るため後退した。コークスは不敵な笑みを浮かべてこちらを見ていた。
「私が何も対策をしていないとでも思いましたか?私のこの身体には、ヴォルス様の力が込められたジェムが埋められている…。生半可な力では倒すことなどできませんよ…!」
そう言って、コークスは手を振りかざした。拳の周りに陽炎が浮かぶ。
「我々の…いや、私の悲願のために、消えてもらいます!」
火の玉が飛んでくる。ラークがとっさにダタの前に出て、氷の結界を張る。
「ラーク殿!」
「…ダタ殿。奴はああ言ってますが、全身ジェムに覆われているわけではありません。覆われていないところを狙いましょう。このままこの氷の結界を拡大させます。それに合わせてもう一度…」
「…解りました」
ダタがこくりとうなずく。ラークは魔力を強め、結界をじりじりと拡大させていく。
「なっ…!ヴォルス様の加護が、貴様のような混血の進んだ竜人などに…!」
「ふっ、舐めてもらっては困るな。私は『呪い子』…。人造の竜人もどきに負けるはずなどない!」
一気に氷の空間が広がり、コークスの術がかき消される。
「な、なんだと…!」
「もらう!」
動揺したコークスに向かって、再度ダタが仕掛ける。ジェムが入っていない部分、それは――
「ぐ、あああああ!」
喉笛を深く掻き切る。傷口からシャワーのように血が噴き出て、ダタの髪にかかる。
「その荷物も、いただきますよ!」
痛みのせいで手を離した荷物を、ダタは素早く回収し、ラークの元に戻る。袋から、赤い液体が入った瓶を数本取り出して、透かすように二人は眺め見た。
「…血、ですか。おそらくファーナのでしょう。割ってしまいましょう」
「そうですね」
二人は袋から次々とガラス瓶を取り出し、勢いよく岩に叩きつけるように捨てた。その光景を、もはや血の気のない顔でコークスは眺めていた。
「では、避難しましょう。彼は…もうあれなら口も利けないでしょうし」
「ええ。しかし姫は…」
そう言って、ダタはふと、山頂付近を再び見やった。相変わらず、赤いぼんやりした何かが見える程度だった。すると、視界の隅に、鳥よりもはるかに大きな正体不明の飛行物体と、その幾分か後ろに、銀色に輝く飛行物体が映った。
「…ん?あれは何だ…?んん…?」
ダタが顔に疑問符を浮かべながら二つの飛行物体に視線を移した。
「…ダタ殿、そろそろ行きますよ」
「しかし…」
「言いましたよ。アイツに任せるしかないと。物理的に我々ではファーナを救いに行けない。でも…アイツならできるんです」
そう言って、ラークもまた銀色の飛行物体をちらりと見上げた。
「…え?ま、まさか…」
ラークの言わんとしていることが解って、ダタは総毛立った。ダタも一応は天教信者だ。それは、起きてはならない事象のはずだ。
「だから、我々は非常時に際して備えるんです。まずは街まで退きましょう。火山が噴火して、街まで被害が及ぶようなことがあったら、人々を避難させる人手が必要です。…アイツとファーナを問い詰めるのは、その後でも遅くはないでしょう?」
ラークはふっと笑ってダタを説得する。
「…わ、分かりました…。ですが、街まで走っている間、貴方も私の質問に答えてくださいね!」
「はは…。覚悟の上です。行きましょう」
ラークは乾いた笑いを浮かべて、元来た道に光を照らす。そうして二人は街へと駆け出して行った。