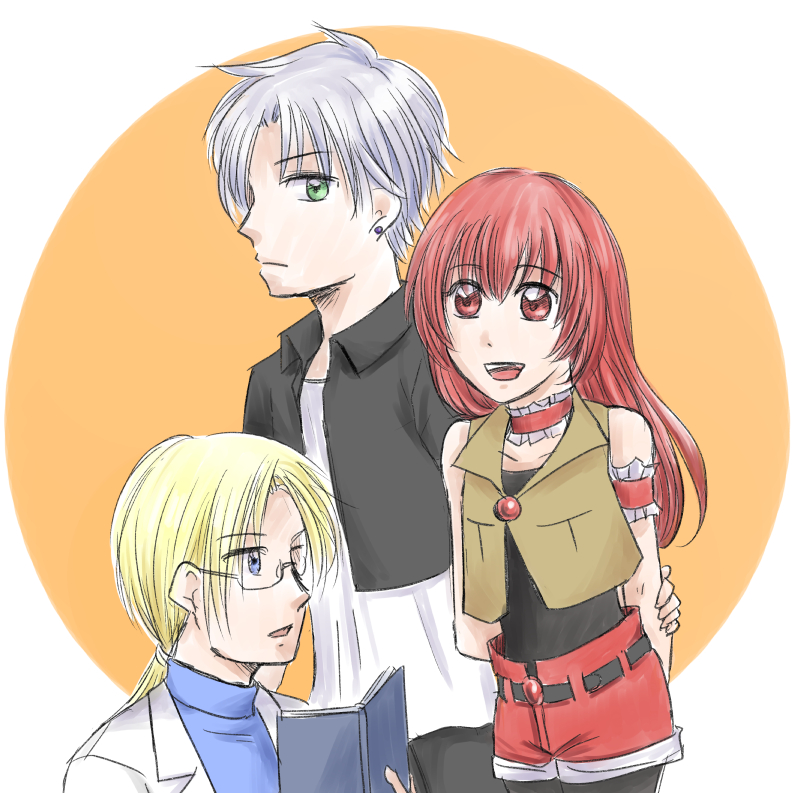早朝の日差しが、柔らかく室内を照らす。
ヘディンは窓から城下を一人呆然と眺めていた。昨日の父の言葉が頭から離れない。かと言って、自分に何かが出来るわけでもない。
(ファーナはこのまま、自分の預かり知らぬところへ行ってしまうのだろうか…)
そう思うと寂しくなる。妹離れはする、とラークに告げたのが、遠い昔のような気がする。あの日はまだ、目の前に彼女はいたのだ。
(…ま、いい機会かもしれないな)
皮肉めいた笑みを浮かべ、窓際から離れようとした。が、視界の端に、こちらへ向かって飛んでくる鳩の姿を認めて向き直った。窓を開けて、左手をかざして留まらせる。足に括り付けてある紙を開いて、中身を確認する。ダタの字がそこにはあった。
(…フォーレス…か)
鳩を鳥籠に入れ、餌を与えながら、ヘディンはまた物思いに耽る。そこに、不意に扉が叩かれた。
「…?」
ダタからの手紙を机の引き出しに仕舞い、ドアの外に声を掛ける。
「誰だ」
「シオンです。お時間いただけますでしょうか」
「構わない」
そうは言ったものの、こんな朝早くから一体何の用なのか。へディンは怪訝な顔をした。音を立てないように静かに扉を開け閉めしたシオンが、涼しい表情でヘディンに一礼をした。
「申し訳ありません。朝早くから」
丁寧に礼をしたシオンを、ヘディンは室内のテーブルに案内する。
「それで、何の用だ?」
「ご報告したいことがありまして」
水を入れたコップを二つ用意し、ヘディンもテーブルに着く。
「ああ、昨日言っていたことか」
「昨日帰城した後、カリーナがこの付近の風を気にしておりました。…何でも、『怖い風』がどこからともなく流れ込んできている、放置すれば良くないことが起きると」
そこでシオンは一度言葉を切り、ヘディンの様子を窺う。ヘディンは眉間に皺を寄せて、首を傾げる。
「良くないこととは?」
「特別な力を持たない私には皆目見当がつきませんので。…王子ならばご存知かと」
うーん、とヘディンは唸って一拍置いてから口を開いた。
「不穏な動きということであれば、各地で魔獣が異常発生していることかな。この地も例外ではない、という事かもしれないな」
「魔獣の発生…。『怖い風』が呼び水となって、このカルディアでも発生しうる、ということですか。確かに、カリーナもフィリアでずっとその風を感じていたとは言ってはいたが…」
最後の言葉は独り言のようだった。ふむ、とシオンはそのまま考え込んでしまった。一方のヘディンも、腕を組み考える。
(どこからとも無く流れ込む『怖い風』か…。『堕天使』と繋がるのか?)
もしかしたら何か手がかりになるかもしれない。そう思ったヘディンはシオンに尋ねる。
「ちなみに、この付近のどの辺りから感じたと言っていた?」
「…?あの中央の塔の…ずっと上で」
「ふーん…」
また旧い文献を当たらねばならない。『あの塔』に『堕天使』が封じられていたということは、何か意義があることなのかもしれない。
「一つ、伺っても?」
シオンが口を開く。
「あの塔は、確か『邪を封じた塔』だったと天教学の講義の際に聞いた覚えがあります。まさかその封印が解けているということでは?」
鋭い洞察にヘディンは内心ドキリとした。
「まさか…何も無いだろう。それに、あちこちでその妙な風は吹いているんだろう?ここだけの話じゃない」
「まあ…確かに…。外部要因を考えるべきか…」
再び考え始めたシオンを見て、ヘディンは内心胸を撫で下ろす。しかしシオンは、もう一つの疑問をすぐさまヘディンにぶつけてきた。
「そう言えば、ファーナ様の失踪は家出、しかも駆け落ちと聞きましたが…本当ですか?」
「本当か、と言われても、本当としか答えようがないな…。本人もそう言っていたそうだし」
当惑したヘディンを見て、シオンは溜息をついた。
「では質問を変えますが、何故連れ戻さないのですか?仮にも一国の王女ではありませんか。彼女のお転婆は度が過ぎていますが、家出放任まで許せるものでしょうか」
「帰りたくないのを無理強いするわけには行かないだろう。…それにファーナはこの王宮じゃどちらかと言えば嫌われ者だ。外に行っていたほうが本人の幸せだ。帰りたくなったら帰ってくるさ」
この言葉はヘディンの本心だった。外で幸せに生きていて欲しい。そこが例え自分の預かり知らない所でも。
「…変わったな…。あんなに妹バカだったお前が」
急にシオンは口調を変えた。
「好きでアイツを手放したわけじゃないですよ。俺だって本当は…」
そこまで自然に話してはっとヘディンは顔を上げた。
「…俺だって本当は?何?『先輩』に話してみろよ」
にっと人の悪い笑みをシオンは浮かべる。やってしまった。ヘディンにとってシオンはかつてエルガード留学の際に兵法学の教室が一緒だった『先輩』に当たる。当時の話し方をそのままされてしまうと、つい本音を言ってしまいそうになる。
「ず、ずるい…」
「聞き出したいことがある時は、油断を誘うのが一番だ。で、本当はどうしたいんだ?」
はあー、と、長い溜息をつきながら、ヘディンは言葉を出した。
「…一緒に家出したかった…」
正直、これも本心だった。出奔したい。ファーナを守るのは自分だと、小さい頃から心に決めている。だが今は、互いに離れるのが彼女を守る唯一の手段でもある。
「…はあ…そうか…。やっぱり変わらないな、お前…」
少々気抜けした声を出して、シオンはがっくりとうなだれた。
早朝の日差しはまた、城内教会にも優しく降り注いでいた。
その荘厳な雰囲気の室内に、剃髪の青年が一歩足を踏み入れる。目線の先に人影を発見して、目を見開く。祭壇の前に、うつぶせになって倒れている銀髪の少年がいた。
「…君は…!」
青年が慌てて駆け寄る。肩を揺すってみるが、ぐっすり寝ており起きる気配が無い。
「…良かった、ただ寝ているだけのようで…」
ふー、と長い溜息を青年は吐いた。そこに、祭壇の左奥からまた別の人物が現れた。
「おや、エルンスト殿、おはようございます」
白い髭を豊かに蓄えた老人で、青い神官服を身に纏っている。剃髪の青年―エルンストは、膝を床に着けたままの姿勢で、会釈する。
「おはようございます、ホルムス司教」
老人―ホルムス司教はゆっくりとエルンストに近づく。すっかり眠りこけている少年の顔を覗きこみ、髪を優しく撫でた。
「あの…、確かこの子はヘディン様の…」
「ええ。今はこの教会の見習いですがね。姫様が行方知れずになってからというもの、毎日ここで祈っておるのですよ」
それを聞いて、エルンストは内心複雑な気持ちになった。姫の無事は宮廷騎士限りの情報とされている。家出などという理由は格好がつかない、というのだが、こんな状態になってまで真剣に姫を心配する彼には告げてしまってもいいのではないかと思ってしまう。しかし、それを判断するのは自分ではなく、王子の役目だ。
「それは…大変なことですね」
エルンストが言えるのはその一言だけだった。
「時に、エルンスト殿…魔術士兼天教学者のお主に聞いてみたいことがあるのですがね」
「はい、なんでしょう?」
「『白天使』…は存在する、と言われたら信じるかね?」
「『白天使』…が、ですか。それは今この世に、ということですか?」
ホルムス司教は一瞬何かを躊躇し、再び口を開いた。
「他でもないこの子が…サリエルが最近口にするのですよ。『白天使』様が何かを自分に訴えかけている、と」
「えっ…。そんなことが…?」
エルンストは眉間に皺を寄せる。
「疲労による幻想だと、私は思っているのですがね、頑なにそう言うのです」
エルンストは考え込む。もしそれが本当なら、何を示唆しているのだろう。
「…もしそれが本当だとするならば、また、この世界に、『天使戦争』のような何らかの危機が訪れることを警告している…のでは?最近の魔獣の大量発生なども考えると、合点の行く話です」
「お主は信じる、ということですかな」
「…信じるとすれば、そうことかなと思います。正直、本当か嘘かまでは判別できませんよ」
そう言って、エルンストはサリエルの顔に目線を落とす。本当に疲れているのか、起きる気配は全く無い。エルンストはサリエルの背を抱きかかえて立ち上がり、教会の出口へと足を向けた。
「エルンスト殿、どちらへ?そちらはサリエルの寝室では…」
「…こういう時は、保護者の方にお渡ししたほうがいいと思いましてね」
エルンストがにっこりと笑う。それを見てホルムス司教もほっとした顔をした。
「王子に、よろしくお伝えください」
「ええ」
「…え、えーっと?」
ノックされた扉を開け、ヘディンは固まった。
「教会で倒れていまして。保護者の方に引き取ってもらおうと思って連れてきました」
剃髪の眼鏡の青年がにっこりと笑う。今日は朝から慌しい、とヘディンは内心溜息をついた。
「そ、そうか…。エル、済まないな…。でもどうして?」
「姫様の無事を、毎日夜遅くまで祈っているそうで…。祈っている間に寝落ちしてしまったのでしょうね。…ベッドをお借りしても?」
「あ、ああ…」
たじろぐヘディンを尻目に、エルンストは部屋に入る。そこにあった人物の姿を見て、またエルンストは驚いた。
「シオン殿…。朝早くから遠征の報告ですか?お疲れ様です」
「ええまあ…。エルンスト殿こそ、朝のお勤め、お疲れ様です」
シオンに会釈し、サリエルをヘディンのベッドに横たえると、エルンストはヘディンに向き合った。
「どうかしたか?」
「…彼には、姫が無事だと告げても良いのでは?これほどまでに尽くしてくれているのに、知らないままではむごたらしいです。…とうとう、『白天使』様の幻まで見るようになったそうですよ」
ヘディンはその言葉にドキリとした。
「は、『白天使』の幻…?わ、解った。考えておく」
声まで裏返ってしまった。正直、そんな言葉が出てくるとは『想定外』だった。
「お願いします。とてもじゃないですが、可哀想ですから」
エルンストはそれだけ言って、一礼して部屋を去った。ふう、と一息ついたヘディンだったが、鋭い視線に気が付いて再び緊張する。
「…『白天使』の幻…か…。随分な驚きようだな?」
鋭すぎる質問に、ヘディンは内心汗をかく。
「…サリの事、放置しすぎたかなって…。そこまで思いつめているとは思わなかった。…保護者失格だな」
シオンはその答えに満足したのか、席を立った。
「全く…。拾ったのはお前なんだから、最後までちゃんと世話しろ。…では、詰所に戻ります。御用があれば、何なりと」
「あ、ああ…」
口調を元に戻して、シオンは部屋を後にした。はあ、と大きく溜息を吐いて、今度はベッドに横たえられたサリエルに目をやる。顔面蒼白で、本当にぐっすりと寝ているが、ふと、眉間に皺が寄ったのをヘディンは見逃さなかった。
「うっ…ううっ」
うなされている。拾ってきた当時はいつものことだった。何があったのかは語ることは無かったが、おおよその察しは付いていた。手をそっと握り、サリエルの身体が温まるように少しだけ魔法で熱を出す。そうすると決まって落ち着き、そして―
「…あ、あれ…ヘディン様?何で僕…」
サリエルが目を覚ます。ゆっくりと身体を起こして、きょろきょろと辺りを見渡した。
「教会で寝ていたところをエルが運んで来てくれたんだ。ちゃんと面倒見ろってな」
それを聞いて、サリエルはばつの悪い顔をした。
「す、すみません…。ご迷惑をかけるつもりは無かったのですが」
「いい。…それだけ、アイツを心配してくれてるんだな、ありがとう。…それに…」
そこまで口に出して、ヘディンは少し黙りこくった。確かに、エルンストの言うとおり、ここまで想いを募らせているサリエルに対してだけは、言ってもバチは当たらないだろう。
「?ヘディン様?」
「いや…最近顔を合わせていなかったから言う機会が無かったんだけど、ファーナ、見つかったんだよ」
サリエルが目をぱちくりさせる。
「え…ええっ?」
「…家出、と言うことらしくてな。今はこっそりダタを付けさせているから、逐一情報は入ると思う。…だから」
その言葉を聞いて、サリエルは力なく俯いてしまった。
「家出…それほどまでに、このお城が嫌だったのでしょうか…。いつも言っていました。鳥のように、どこまでも飛んで行きたいって」
「成人の儀で、思うところがあったのかもしれないな。明るく振舞っていたが、内心は…。まあ、無事だった、ということで、安心してもらっていい」
ヘディンはぽんとサリエルの頭に手を置いた。サリエルはそのまま頭をこくりと上下させた。
「はい…。で、でも…」
「そんな顔色になるまで、無理はするんじゃない。…いつも通りの生活に戻るんだ。…あと、このことは他言無用にな。他国に知られれば、ファーナは狙われるかもしれない」
「は、はい…それは、解りました。…でも…」
サリエルがぎゅっと毛布を握る。何かを言おうか言うまいか、悩んでいるようだった。
「どうした?」
意を決したように、サリエルは顔を上げた。
「…あの、笑わないで聞いてください。僕…『白天使』様の声が聞こえたんです」
やはり、その話か、とヘディンは身構える。
「…どういうことだ?」
「すみません、それが、あまりよくは聞き取れないんです…。ただ、とても不穏な…良くないことが起きてる、みたいな、そんな感じで。ファーナ様もそこに巻き込まれてるみたいな…」
ヘディンはドキリとした。それは紛れもない事実だ。しかし、『堕天使』の話は一切出来ない。ましてやこれだけ信心深いサリエルには。
「…お前の不安な気持ちや疲労から、そんな幻を見ているのではなく?」
「…違う…と思います。上手く言えないですけど…」
ふーっと、ヘディンは溜息を吐いた。もし本当のことだとしたら?『白天使』は一体どこからどういうふうにサリエルに接触しているのだろう。…そして、自分は『白天使』の到来を、本当に心の底から祈っているのだろうか。もし彼が現れたなら、ファーナはどうなるのだろう。
どうあれ、サリエルの体験が真実かどうかを確かめるのが先だ。
「…さっきも言ったが、まずは、いつも通りの生活に戻るんだ。それでも『白天使』の幻を見るというのなら…それは幻じゃなくて本物だと思う。…それはその時考えよう」
念を押すかのように、ヘディンはサリエルの頭をぽんぽんと叩く。サリエルは不安げな表情を浮かべつつも、こくりと頷いた。
「はい…そうですね。そうします。済みません、何だか突然…」
「いい。俺はお前の保護者だからな。いつでも相談に来い。遠慮しないで」
「…はい」
今度は力なく、だがふんわりとサリエルは笑った。その笑顔に、ヘディンはかすかな不安を抱いた。
汽笛の音が、甲高く鳴り響く。日が西に傾き始めた頃、リクレアからの連絡船はシャクーリアの港に着いた。
「ここが…シャクーリアか」
下船したラークは、周囲一帯をぐるりと見渡した。生ぬるい風が吹き抜けていく。船着場の回りは、商船以外にも漁船が数多く停泊しているが、時間帯のせいか活気がない。港を抜けるとすぐに大通りがあり、その先の丘には小さな城がそびえていた。
(あれが、目的地…)
その姿を確認してから、ラークは街中を散策しはじめた。夕飯支度にはまだ早い時間のはずなのに、人通りは少なく、そして、次々に視界に入る教会の形に眉を顰めた。
「…天教の教会、か」
魂は天へと還る。だから祭壇のある建物奥の背が高いのが天教の教会の特徴だ。他にも、どこかしこで見たことのある風合いの建物がいくつか点在していた。
「…カルディアかぶれ、と言うべきか…」
嫌な気分になった。親友がこの場にいたら何と言うだろう。
取り敢えず、宿に入る前にこの国の事情を直に聞こうと思い、近場にあった市場に入る。市場も閑散としており、活気が無い。
(まるで閉まっているかのようだな…)
少し薄暗いテントの中に入ると、手前の店主がまじまじとラークを見つめてきた。その視線に気付いたラークはその店先へと足を向けた。
「…お前さん、旅の方かい?」
「ええ。諸国を巡っています」
そう言うと、ふと、店の品揃えに目が行った。鮮魚店のようだが、品数が少なくどれも高値だ。もしやと思いラークは尋ねる。
「…不漁が続いているのですか?」
「ああ。昔はこんなこと無かったんだがね。最近は日照りが続いてるせいかどうにも良くねえ。向かいのリクレアはそんなことねぇって言うからな…。大きな声じゃ言えねえが、バチが当たってるとしか思えねえ」
「バチが…」
それ以上聞く気にはなれなかった。日持ちのしそうな干物を買って、ラークは市場を後にしようとした。
「お前さん、観光なら、早めに引き上げたほうがいい」
立ち去ろうとした時に、そう店主に声を掛けられた。
「何故です?」
ラークの問いに店主は小声になった。
「ここいらは数日以内に戦争になるかもしれねえって噂だ。何でも、今の王政に不満を持つ輩が蜂起するってよ。危険が及ぶ前に出国した方がいい」
明らかにラズリ一味のことだ。民衆に噂が広まっているのでは、宮廷にも耳に入っている可能性がある。しかし、既に動き出している作戦だ。結果上手くいかなかったとしても、やらなければならないことに変わりは無い。
「ご忠告、ありがとうございます」
軽く会釈をして、ラークは市場を去り、宿へと向かった。
同じ頃。街からは幾分か離れた海岸に、ラズリの船は停泊した。やはり潮の流れが速い箇所で、普通の船ではうかつに近づくことができない。
船からは、二十人程度が一緒に降りた。早めに出たダタを含む部隊と合わせると四十人程度が作戦に参加することになる。
「うわあ…面白そう!」
植生が大陸南方のそれとはまた違うことに、ファーナは感心した。目の前に広がる鬱蒼とした森を見て、わくわくした気持ちになる。
「姫、残念だけどそっちじゃない。こっちの洞窟を通っていく」
「えー…」
ラズリの言葉にファーナは不満の声を上げる。
「ははっ、好奇心の強い姫様だ」
「こっちは色々と迷惑してる。何度どうでもいいことに首を突っ込んだか…」
イラつきながらカティスが毒づく。
「今回もか?」
「今回はフォーレス行きが懸かってるからな」
むすっとしたままカティスはラズリに答えた。洞窟に声が響く。外の光が届かなくなる前に手持ちのランプに火を灯して、しばらく歩いた。
「あれ、行き止まり?」
通路が途切れ、目の前には壁がある。
「いや、こうするんだ」
ラズリはその壁を、トン、トトトン、と、特定のリズムで叩いた。すると、壁がゆっくりとスライドして開いた。
「うわー…隠し扉だー」
ファーナは目を輝かせる。扉の向こうには、筋肉隆々の壮年が姿を現した。その姿を認めて、ラズリはふっと笑いかけた。
「デリス殿、息災で何よりだ」
「ラズリ殿こそ」
ラズリが挨拶を交わして扉の向こうへ行く。ファーナ達もその後に続く。扉の先は住宅だった。ソファとローテーブルが置いてあり、応接間らしいことが窺い知れる。
「ここがその…協力者の」
「ああ。デリス殿の邸宅だ。彼は前の近衛兵長でね、変わり行く王室の現状を嘆いている一人なんだ」
「引退した身だがね」
デリスが畏まった挨拶をする。ファーナも思わず貴族風の挨拶を返してしまった。あっ、と罰の悪い顔をする。
「話は先発隊から聞いております。偶然とはいえ、遠路はるばる、よくぞこのシャクーリアまでお越しくださった」
低音のよく響く太い声だ。何とか全員が部屋に入りきると、カモフラージュの本棚を元に戻した。
「元とは言え近衛兵長って…そんなご身分の人間までもが裏切っているなんてな」
当然の疑問をカティスは口にした。
「私は水神さまの加護の下に生きる人間だ。そして、この国は水神さまによってのみしか護られぬ。異国の神を受け入れることは即ち国の崩壊に繋がると思っておる」
「…成程な。じゃあ、その天教を広めてるお妃さんを殺すのが目的なのか?」
カティスの物騒な問いにデリスは首を横に振った。
「最悪、そうなるだろうが、できれば穏便に説得して済ませたい。これほどまでに民衆が不満を持っている、ということ示すことができれば…」
それを聞いてカティスは大仰に溜息を吐いた。
「…甘いな。そういうモンは根から絶やさなけりゃ意味ねーよ。いつしか勝手にまた天教が広まって、同じことを繰り返すに違いねえ」
「そうかしら?そうはならないと思うわ」
後ろで控えていたミランダがきっぱりとした口調でカティスに反論した。
「はっ、随分と自信があるみたいだな。何か確証でもあんのか?」
「一つは、リーテルが勝手に推し進めているだけのことだから。天教に宗旨替えした人は大体、弾圧を恐れてそうしたのであって、心の中までは変わっていないわ。もう一つ、歴史上、何度も水神さまのご加護でこの国は救われてきた。それはこの国の人間なら知らないわけが無いもの。水神さまは、形は見えなくとも、きっといらっしゃるからよ」
周りの海賊達も全員、うんうんと首を縦に振る。その光景を見て、カティスは安堵したかのような溜息を吐いた。
シャクーリアの夜は、日中の気温が下がらないまま、じっとりとした空気が漂っている。まだそれほど遅い時間ではないが、人通りはまばらで、少々寂れた感がする。
デリスの邸宅の屋根裏で、数人の男が次の日に使う爆薬や武器などを仕分けしていた。デリス邸は地下1階、地上2階建てという造りで建床面積は広く、それほど手狭ではないはずなのだが、今日この日だけは違っていた。
「ただいま…うわ、むさっくるしい」
シジェが屋根裏に昇るなり、眉間に皺を寄せた。十人弱がその作業に当たっており、その中にはダタもいた。シジェはダタの隣に座って、荷物の袋詰めを始める。
「ラーク殿には会えたのか?」
「ええ。びっくりしてました。何てったってフィリア語の手紙っすからね。思いついたお姫様も凄いけど、書いたダタさんも凄いっす。一体どこで習ったんすか?」
シジェは明日の行程を、宿に宿泊しているラークに渡して戻って来たところだった。万が一の事を考え、この国にいる者が殆ど読めない字を選択した方がいいと、フィリア語での記述をファーナが提案し、ダタが一筆したためたのだった。
「こういう仕事をする以上、使えるツールはいくらあってもいい。そう思えばいくらでも身につけることはできる。言語だけではない。魔法も、体術もな」
ほー…と、シジェは感心したような声を上げる。
「僕はまだまだっすね。ほんの一年位前まで、シャクーリアの外については何も知らなかったっすから。兵隊やってましたけど、武術なんかは我流だし」
「そう思えるのなら、上達は早い。要はやる気とそれを実行できる力だ。結果はその後についてくる」
手を動かしながらダタはシジェに説く。シジェは思わず作業の手を止めてしまった。
「…凄いっすね、やっぱり…」
「凄くも何ともない。ほら、終わったか?」
「あっ…も、もうちょっとっす!」
ダタに急かされ、シジェは残りの荷物を纏め上げた。
「後は闇夜に紛れて目的地点にあらかじめ配備しておけば、今日の仕事は終了…か。全く、こんなことが王子に知れたら何と思われるか…」
不安げな表情を浮かべて、ダタはぼりぼりと頭を掻く。
「お姫様のお兄さん?」
「ああ。俺の雇い主だ」
ダタは腰に両手を当てて、ぼーっと荷物を眺める。座って見上げている格好になっているからか、シジェには、小さい彼の身体が幾分か大きく見えた。
「…きっと、大丈夫っす。あの天真爛漫なお姫様見てたら、そう思います。ああ、きっとおおらかな人なんだろうなって」
シジェはにっこりとダタに笑いかける。
「そうだな…。確かにそうだ」
正義感が強く、真っ直ぐで、そして優しい主。自分が、姫がこれからすることもきっと、許してくれるだろう。ダタはそう改めて思い直した。