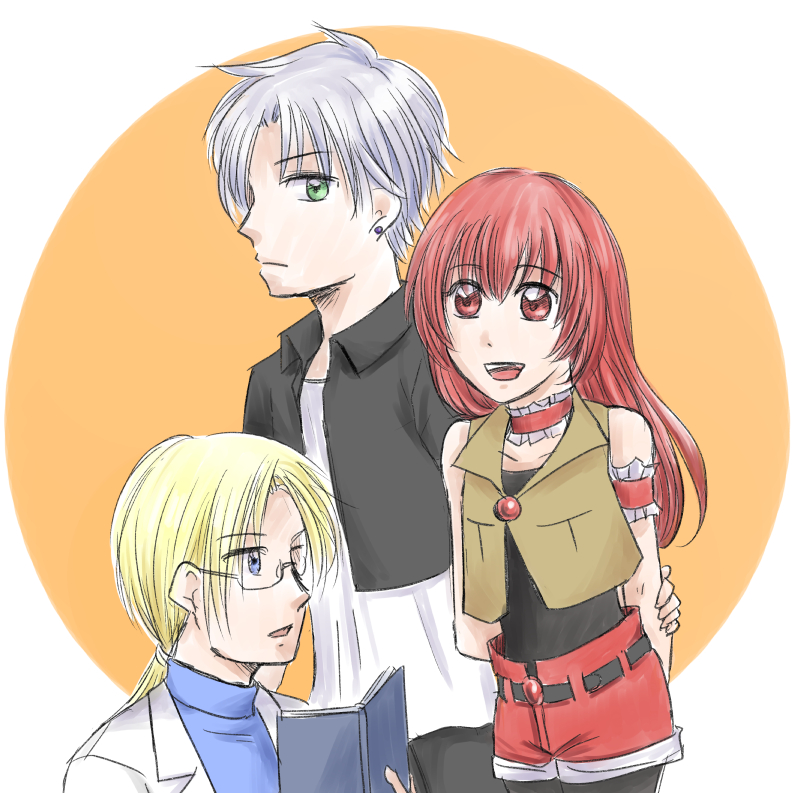――息が、出来ない。
暗い海の底、意識が遠のいていく。
海の水に身を委ねたその瞬間、何かに身体を掴まれて――。
「――っ!」
汗だくになって目が覚める。息が上がる。しばらく息を整え、落ち着いてから、額に右手をやった。
(…夢…。また…。もうすぐ念願が叶うというのに…どうしてこんな夢を…)
南国の朝の厳しい日差しが、容赦なく照りつける。秋と言っても、シャクーリアの気候はカルディアの夏と変わらない。見渡す限り広がる海に、気分が高揚する。
「凄いね…。どれだけ行っても陸が見えないもの」
ファーナが感嘆の声を上げる。商船に偽装した海賊船の甲板で、手摺りに掴まって海を見渡す。
「一昨日も乗っただろ」
隣にいるカティスが飽き飽きした様子でファーナに言う。カティスは海に背を向け、手摺りに体重を預けながら甲板の船員を眺めていた。
「だって、騙された時はすぐに船の中入っちゃったし、シジェに助けて貰った時は夜だったもの。お昼にこんな風に船に乗るのは初めてよ」
「…海賊船だけどな」
「私もあっちが良かったなぁ…」
怪しまれないようにと、正規のルートでシャクーリアに向かったラークをファーナは羨ましがる。
「お前は身辺調査入られると厄介だからな」
「うん…」
少しだけ涼しい風が、頬を撫でていく。どこまでも広がる海。そして底が見えない海。海を見つめ続けていると、ふと不安に駆られる。落ちてしまったら?陸が見えなかったら?
「よう。どうした?姫様、具合悪いのか?」
船内からラズリが出てきてカティスとファーナに声を掛ける。それに気がついて、ファーナは向き直った。
「あ、いや…。何か海って凄いなぁって、眺めていて思ってたところです」
「へえ?どんな?」
「広くて、深くて…。海に比べたら私達はすごくちっぽけで、それがとても怖いかもって」
ラズリはこくりと頷いた。
「確かに。おれも時々途方も無く、不安になるな。いつ海に投げ飛ばされて、死ぬかも解らない。けど、おれには他の仲間がいてくれる。それに…」
「それに?」
ラズリは前に出て、カティスの隣で手摺りを掴み海を見渡す。
「…おれには水神さまが付いてるからな」
にっとラズリは不敵な笑みを浮かべた。
「水神さまが付いてる…?」
「そう。おれは航海中に嵐だとかに遭ったことが殆ど無いんだ。こんなに海に出てるのにも関わらず、な。これも日頃の行いが良いからさ」
「海賊が威張ってもなぁ…」
誇らしげに語るラズリに、カティスがぼそりとつっこみを入れる。
「だーかーら、おれは義賊だって!」
「…どうだか。相手がなんであれ、襲われれば単純に『被害を被った』ワケなんだから。そいつらにもそいつらの生活があるだろうが」
ラズリはムッとする。
「それは罪の無い人々が追われた結果だ!罪の上に築かれた富など、悪以外の何者でもない!何もすることもせず、ただ見てるだけなんて、おれには出来ない!」
ファーナはラズリの気迫に圧倒された。しかしカティスは表情を変えず、冷ややかな目でラズリを見る。
「…そんなの偽善だ。アンタはただ、助けを求める奴等を助けた気でいて気分がいいだけだ。自分の欲に忠実に生きてるだけだろ」
「カディ…?」
声音が暗い。それが気になったファーナがカティスに声を掛ける。カティスはファーナを一瞥して、体重を預けていた手摺りから身を起こした。
「カ…」
ラズリの返事を聞かず、カティスはその場を去ってしまった。残されたファーナとラズリは、互いに顔を見合わせた。
「…ごめんなさい。彼、ひねくれてて…」
「いいんだ。…そう思われても仕方ないし、確かにおれがやってることは、相手からしてみりゃ略奪だ。欲っていうのは、ちょっと違うけど…、ま、助けるっていうのが気分良いのは本当のことだしな」
ラズリは肩をすくめ、ファーナに向き直った。
「…姫はどう思う?おれ達がどう映る?」
蒼の瞳が優しくファーナを見つめる。その眼差しにファーナはドキリとした。
「…ラズリさんはいい人だと思う…。でも、例えば自分の国で、海賊が暴れてたら、困るな…」
「まあ、それが普通の感覚だな。でも、今のシャクーリアは、こうでもしないと皆が生きていけない。ごく一部の、上にいる人間のためだけに国はあるんじゃないって、おれは思うんだ。綺麗事だってのは重々承知だけどさ」
ラズリはにっと笑って見せた。ファーナはそれを見て、ふわりと笑う。
「さ、戻ろうか。髪の毛潮っぽくなっちまう」
少し色づき始めた葉が、街の景色に鮮やかさを添えている。その風景をぼんやりと眺めながら、ヘディンは城門の前である人物を待っていた。その身には珍しく銀の鎧を纏い、数十人もの兵の列の先頭でその時を待つ。
にわかに、遠く、街の大通りの方から歓声が上がった。それを聞いて、ヘディンは姿勢を正す。やがて砂埃と共に、騎馬隊が日の光をちらちらと反射させて近づいてきた。大橋に先頭の騎馬の足が掛かると、一斉に手持ちの剣を顔の前に垂直に立てて敬礼する。騎馬が通り過ぎるのを、ヘディンはちらりと上目で見た。丁度、白髪交じりの赤毛の壮年と目が合う。数秒、互いに目配せした後、そのまま城門の中に消えていった。
(…後で来い、か。まあ解り切っていたことだが)
隊列が全て去った後、兵の列も整然と城門の中へと戻っていった。部下に解散の指示を出した後、ヘディンは早々に自室へ戻ろうと、人通りの少ない外周部の裏口へと向かった。
「カリーナ、シオン、帰りました~!」
帰城の報告のために真っ直ぐ宮廷騎士の詰め所に向かったカリーナとシオンは、室内の閑散さに互いに顔を見合わせた。副長のライラと、見知らぬ中年の男性しかいない。
「…あれ?皆は?」
「殆ど領内視察に行ってるわ。今城に残っているのは私の他にはシャルとオード、エルンストだけね。団長は?」
「ハサン様に随行しています。そのうちこちらにも顔を出すでしょう。…ところで、その後ろの御仁は。見たところ宮廷騎士の新入り…には見えませんが」
シオンが淡々と尋ねる。
「私の父、レオンよ。姫様の失踪…いえ、家出絡みでここまで報告に来てくれてそのまま居ついてしまって」
困惑した表情でライラは答える。それとは対照的に、にっと人の悪い笑みをレオンは浮かべた。
「?家出…なんですか?行方知れずって話は…」
カリーナが眉間に皺を寄せる。フィリアで姫が無事と言っていたノエルは、このことを知っていたのだろうか。
「シャルとエレンが突き止めて、そう姫様から答えを貰ったと。その場に居合わせたのが父だったの」
ふーん、とシオンは唸る。
「何が原因で『家出』などされたのか、レオン殿はご存知なのですか?」
その言葉にレオンは頭を掻く。
「簡単に言うと、かけおち、だな」
「は…?」
シオンもカリーナも呆気に取られた顔をした。
「ま、ままま待ってください!姫にそんなヒトがいたんですか?!」
驚きのあまり思わず大きな声でカリーナはレオンに尋ねる。
「いやあ、そうとしか言わないし、そうとしか見えなかったしなあ。相手は何か身分の低そうな男だったぜ?」
「えー…」
カリーナは半笑いになった。シオンは口元に手をやって、しばらく考える。
「では、今でも表向き『失踪』としているのは、どこの馬の骨ともわからん男と駆け落ちしたという事実が、対外的な印象として好ましくないから、ということですか」
「そういうこと。恥ずかしいもの。だからこの話は他言無用にお願いね」
「では、宮廷騎士達が不在にしているのは…」
「魔獣の発生状況の確認のためよ。…フィリアの方も被害が出ているそうね」
「は、はい…。私、遭遇しました」
ライラの問いかけに、カリーナが反応する。
「カルディア国内も、辺境ほど多く発生しているとの報告があるの。人手が少ないから、宮廷騎士からも幾人か派遣したのよ」
「成程…」
シオンは納得したような言葉を出す。
「じゃあ、私たちもどこかに派遣ということに?」
「それは団長や王子と相談して決めるわ。貴方達はそれまでの間遠征の疲れを癒しておいて」
「はい」
「了解した」
一礼して、二人は部屋を退室した。少し歩いてから、カリーナが口を開く。
「…何か引っかかる…」
「?何がだ?」
シオンが不思議そうにカリーナを見やる。
「姫の駆け落ちの話。そんな人がいる感じじゃなかったもの。それに、あの二人が纏っていた空気も…『風』達と同じ大きな不安を纏ってた」
「何かをあの二人は知っていて隠している、ということか」
「多分…。ライラさんを疑いたくないけど、姫の家出って、そんなに簡単なことじゃないと思うのよ」
「ふむ…」
溜息混じりにシオンは口元に手をやり考える。カリーナの『風読み』の力は一級品だ。人の目では捉えられない事象を確実に読み取る。ふと、シオンは思いついたことを口にした。
「…カリーナ。ここはどうなんだ?以前と…俺達が旅立つ前と変わらないか?」
「?ハルザードが?…そうねぇ…。ちょっと待ってて」
カリーナが辺りを見渡す。丁度空いていた窓から外に出て宙に浮く。そのまま目を閉じ、全神経を研ぎ澄ませる。
「…?」
目を開けて上空を見上げる。城の中央にそびえ立つ塔。その上の方から、妙な風を感じ取る。今まで感じたことの無い、酷く冷たく、暗い風。
「…カリーナ?」
シオンが窓からカリーナを見上げる。カリーナはそのまま上空へと向かう。塔の最上階には窓があるが、こちらからは内部を見渡せない加工がしてあったことを思い出す。
妙な風に緊張しながら上へと辿り着くと、そこには、以前と変わらず内側の見えない窓がはめ込まれていた。妙な風は、この塔の更に上の方から感じられた。
(い、行けるところまで…)
更に上へと向かう。その風はだんだんと気配を増していく。しかし、発生源がどこか解らない。
(…何だろう、この風、怖い…)
しばらく辺りを見渡してからカリーナは引き返した。窓から覗くシオンの顔を見て、カリーナはほっとした。
「どうだった?随分上まで行ったな」
窓から城内に戻ったカリーナに、シオンは話しかける。
「…この城の上空から…どこからか解らないけど、妙な風が少しずつ流れ込んでる。暗くて、冷たくて…。一言で言ったら怖い風」
「怖い風…?」
「…まるで、人気の無い、不気味な森に迷い込んだような感じ。少し…なんだけどね。前はこんなの感じたことなかった」
「…その風は、放置するとどうなるんだ?」
「解らない。でも『風』達が怯えてる原因って多分コレだわ。きっと…良くないことが起きる」
どうしたらいいのだろう、と顔にそのまま書いてあるかのような表情でカリーナはシオンを見やる。
「そうだな…。ん?」
向こう側から、赤い髪の青年が歩いてくるのが見える。彼に向かって背を向けた格好になっているカリーナの肩をポンポンと叩き、逆側を向かせた。その人物の姿を認めて、カリーナははっとした。
「あ、王子っ」
「カリーナ、シオン。遠征ご苦労だったな」
相変わらず暖かい空気を纏った人だ、とカリーナは感じた。しかしやはり元気が無い様子だった。
「いえっ…その、王子は…姫様が」
家出にしても何にしても、最愛の妹がいなくなったことには変わりない。その心中は察するに余りある。
「ああ…。俺なら大丈夫だ。アイツがいないのは…慣れてるからな」
口では殊勝なことをいうものの、浮かべた笑みはやはり寂しそうだった。
「王子…」
「じゃあ、積もる話は後でな。今は父上に挨拶してこなければならないから」
そう言って、へディンは早々にその場を立ち去ろうとしたが、カリーナの後ろのシオンの視線に気が付いた。シオンは値踏みをするようにじっとヘディンを見つめている。
「…どうかしたか?シオン」
「いえ。後ほど、ご報告申し上げます」
軽くシオンは頭を下げた。解った、と一言だけ告げて、ヘディンはその場を去って言った。
「…シオン、どういう事?」
「先ほどの話を、王子にしようと思う」
「…さっきの『風』の話?」
「ああ。留守居組の元締めは王子だ。…ライラ達が隠していることを知らないはずがない」
「確かに。でもはぐらかされるかもしれないよ?…実際、王子から感じる風は…あまり変わらないし」
「それが逆におかしいんだ。何も知らないなら不安になる。全てを知っているから普段と変わらない。…確実に、何かを知っているはずだ」
確信を持って、シオンは先ほどまでヘディンの背中があった廊下の先を見つめていた。
窓から、ギラギラとした日差しが入ってくる。その日差しを避けて、ラークは本を読みふけっていた。出航前にバイエルの古本屋で買い求めた、シャクーリアの歴史書だった。
ファーナの成人の儀の時のように、エルガード長老会の名代、使者として、近隣国の統治者や上層部の人間に目通りすることが最近は少なくない。粗相の無いようにと、会う前に一度、改めてその国の歴史を頭に入れておくようにしている。歴史研究家の端くれである以上、求められる最低限のたしなみだと、ラークは常日頃から考えている。
しかし、今回は少しその趣が異なっていた。純粋に、海賊のアジトで読んだあの絵本が気になっていた。
(水神さまは人々に豊穣と嵐をもたらし、この地の者達を海によって外敵から護る…か)
シャクーリアの歴史の中においては、他国からの侵略を受けては、奇跡的に退けていることが幾度かある。これがもし本当に「神の仕業」だとしたら?昔話や伝説の類は、全くのデタラメではなく、作られ伝承されてきただけの理由があると、ラークは常日頃から考えていた。
(…今度の「敵」は内にある。どうなるか…見物だな)
栞を挟んで本を閉じる。小一時間ほど読んでいただろうか。気分転換に船室を出てデッキへと出る。暑い中にも少しだけ、さわやかな風が感じられた。
「―あれ、お兄さん…」
ふと声を掛けられた。右側を見ると、亜麻色の髪のボーイッシュな少女が目を輝かせてこちらを見ている。―まずい、とラークは過去の経験から予感した。
「も、も、もしかして、あの有名な『光の貴公子』…」
次の言葉を発する前に、ラークは少女を睨んで口元に一本指を立て、「シーッ」っと息を強めに吐いた。
「…大きな声を出すな」
「…あっ」
少女は口元に手をやった。ラークの意図したことを理解してくれたらしい。
「えっと…。シャクーリアにお仕事ですか?」
「…そんなところだ」
ラークはそれだけ言った。必要以上のことは言う必要はないし、相手から何かを聞く必要もない。それ以上に、この少女に何か妙な違和感を覚えていた。
「…あの、これ」
ごそごそと、手持ちの鞄から手のひらサイズのぬいぐるみを取り出した。ラークはそれを見て怪訝な顔をする。
「ファンなんです。こんなものしかなくて…その」
照れているのか、顔を伏せながら両手でラークに差し出している。周りが何事かと視線を向けているのに気が付いて、ラークはしぶしぶ受け取った。
「…ありがとう」
そう言って、何かまた聞かれる前に退散しようと思い、ラークは一礼してその場を離れて船室へと向かった。その後姿を、少女はずっと嬉しそうな笑顔で見つめていた。
空気が張り詰めている。
広く、それでいて毎日綺麗に掃除されていた父の執務室。ヘディンは一人、その部屋の主と対面していた。互いに甲冑を脱ぎ、軽装でゆったりとソファに腰掛けている。格好だけは、久々に対面した親子水入らずな光景かもしれない。しかしヘディンは緊張でそんな心境ではなかった。
「…ま、そんなに固くなるな。ざっくばらんでいいぞ」
ファーナがいなくなったその日の内に、ヘディンはその旨と撤退要請を綴った書簡をこの父に送っていた。それを受けてか、例年よりも早くフィリア国境地帯から兵を引き上げて帰還してきた。
「…あの手紙には、ファーナが行方不明になった、としか書いてなかったが…。目覚めさせたんだな?アレを」
その言葉にヘディンははっとしてハサンを見た。
「父上…?!やはり、何かを知っていて『ファーナを護れ』と…!」
思わず立ち上がったヘディンをハサンは手で座るように促した。
「まあ落ち着け。…俺も知ってたわけじゃない。…何となく、予感があっただけなんだ。…それで、事の仔細は?」
「ああ…そうでした…。申し訳ありません」
へディンはストンとソファに腰を掛け、促されるままに全てを告げた。宝珠に触れたとたんに目の前から姿を消したこと、追いついたころにはもう『堕天使』が目覚めていたこと。
「今はラークも一緒です。…フォーレスへ向かっていると報告を受けています」
そこでヘディンは言葉を切った。ソファの背もたれに体重を預け、ふうーっと長い溜め息をハサンは吐いた。若干の沈黙の後、ヘディンが口を開いた。
「父上、教えてください。ファーナは何者なんです?この期に及んで何も知らないでは、ファーナの兄として失格です」
思いつめた表情を浮かべてそう言った息子を見て、ハサンはふっと安心したような笑顔を浮かべてから切り出した。
「…お前は、ファーナの母親を覚えているか?」
ヘディンは首を傾げた。ファーナの話なのにどうして母親の話が出てくるのだろう。
「もちろん。義母上は優しい人でした…。でも、身分だけで全てを図るこのカルディアでは、お辛そうでした」
何でも、ファーナの母ホワルは、一介の町娘であったのを、ハサンが一目ぼれして後宮に入れたとの噂があった。王族は貴族や分家筋の者と結婚するのが習わしだ。それは『天使』の血を守るだけではなく、『呪い子』を作らせないための配慮でもあった。しかしハサンは、その慣習を破ってまで結婚した。
「…お前の母サラを病で亡くして約2年…。ホワルは俺を支えてくれた。ずっと傍にと望んだが、彼女は一介の町娘だ。『呪い子』を宿せば、死んでしまうかもしれんと思っていた。…しかし彼女は俺にこう言ったんだ。『私は、絶対大丈夫。無事だから』と」
ヘディンはその言葉の不自然さにすぐに気がついた。
「まさか、気休めでしょう?絶対なんてことはありえない」
「だが無事だった…その言葉通りな。ファーナが生まれ持った魔力は、そんなに低いものでもない。普通の人間なら、死んでしまうところだったろう。…何故だと思う?」
「竜人だったのでは?一般人にだって居ない訳ではありません」
少し困惑気味にヘディンは答える。しかし父が考えているのはそうではないのだろう。それでなければ、わざわざこんな話はしない。
「…ならいいのだがな。俺にはそうは思えなかったんだ。世間では宮中で冷遇されて家出したなどと言われているが…。まるで置き土産のようにファーナを残して何も言わず忽然と居なくなった。それに何か意味があるとするなら…」
「それはただの考えすぎでしょう?それとも何か…根拠が?」
ヘディンも父の言葉を否定しつつ、一抹の不安を覚える。ハサンは少しヘディンの表情を値踏みするように見てから口を開いた。
「…ラークから、ファーナの精霊術の適正の話を聞いたことがあるか?」
「はい?」
突然、親友の名が出てきてつい間抜けな声を出した。
「知らんか。と言うより、お前を気遣って言わなかったんだろうな」
その言葉に、少しへディンは内心怒りを覚えた。何でも報告してきてくれていたものと思っていたのに。
「ファーナの適正…。一番は火系じゃない。…地系だった、そう言っていたんだよ」
「…なっ…」
その言葉に、胸に湧いた怒りは消えていく。その代わりに、天地がひっくり返ったような衝撃を受けた。
「そ、そんなバカな話がある訳がない!もしそれが本人の気質だったとしても…血を超えるなんてこと…」
ラークもそんなことをきっと自分に告げない。ヘディンはそう思い直す。魔術師の彼にとってそれは『非常識』なことだ。
「彼が嘘を吐いているとも思えなかった。だから疑ったんだ。『母親の血』を」
その言葉に悪寒が走った。ありえないが、可能性はゼロでもない。
「…まさか…」
顔を強張らせるヘディンに、ハサンはゆっくりと首を横に振った。
「…可能性の話だ。でも、これで全てが繋がる」
「で、でも、だからと言ってそれが『堕天使』を目覚めさせる条件になるとは…」
「それも可能性の話だ。…事実、ファーナはアレを目覚めさせてしまった。今はそう考えるのが一番筋が通る」
ヘディンは顎に手を当てて考え込む。もしそれが本当だったら、自分はファーナをどうすればいいのだろう。
「…父上は、どうされるおつもりなんですか、ファーナを…」
「どうって、このまま何もしないさ」
「えっ?」
厳しい言葉が返ってくるのかと思いきや、全くの正反対でヘディンは驚いた。
「父上なら、きっと斬って捨てると言うんだろう。あの人はそういうところで潔癖だ。でも俺にとっては、ファーナは何者であっても自分の娘だ。そんな事、出来るわけがない」
その言葉に、ヘディンははっとした。ファーナを逃がしたあの時、確かに祖父はファーナを殺そうとした。自分はそれに従わずに彼に託した。彼女の血筋に疑いがあるというだけで、何を自分は迷ってしまったのだろう。
「…少し…安心しました」
ほっとした表情をヘディンは浮かべた。
「だが、『堕天使』には、何らかの手を打たねばならないな。ファーナを無事に生かしてくれていることには感謝すべき…だが」
「それと関連があるのかもしれないのですが、彼の目覚めを機に、国内で魔獣の発生が相次いでいます。帰還した軍はそのまま各所に配備し、魔獣討伐に当たらせるのが最良かと。『堕天使』は…何か特別な対策を練らなければ、返り討ちにされるのが目に見えています」
ハサンの言葉に被せるように、ヘディンは持論を展開する。ここで承諾を得られれば、自分が描いた青地図に一歩近づく。固唾を呑んで父の言葉を待つ。
「お前のことだ、既に手は打ってあるんだろう?」
「まあ…前者は留守居の者を先行させていますが、後者は何とも…」
ヴィオルが言うように、伝説の類を探すしかない。そんな荒唐無稽なことを口にするのは事実であっても気が引けた。
「…そうだな。お前の言うとおり、数日の休息の後、軍を再編して各所に派遣しよう。最優先とすべきは国民の命だ。後者は…『堕天使』との関連も含めて調査検討を頼む」
その言葉にヘディンは胸を撫で下ろした。
「…何とか…。ラークが彼の傍にいますし、出来る限りのことはやってみます」
へディンは席を立ち、軽く礼をする。立ち去ろうとしたその時だった。
「待て、ヘディン」
ハサンがソファから立ち上がってヘディンを引き止めた。
「なんでしょう?」
「一つ聞いておきたい。『堕天使』は…どんな人物だ?」
その問いに、へディンは内心困惑した。
「…どんな人物かと言いましても…。私が遭遇したのは一瞬ですが」
「他の者の報告でも構わん。率直な感想を聞きたい」
唾をごくりと飲む。その印象を、王たる、いや、天教の元締めの父に告げてもいいものなのだろうか。若干躊躇いつつも、きっぱりと言い放った。
「悪い人物ではないと思いました。多少態度や言葉遣いは粗野ですが、遭遇した人物の話によると、ファーナに対しては優しかったと。それに、これと言って悪事を働いたとも聞きません」
「…そう、か…」
何か考えこむように、ハサンは口元に手をやった。
「…何か?」
「いや…何でもない。済まなかったな。戻っていいぞ」
「はい。…それでは」
一礼して、ヘディンは退室した。それを見送ってから、ハサンは窓際に行き、空を見上げた。
「ホワル…。お前は何をどこまで知っていて、ファーナを置いていったんだ…」
その呟きは、誰の耳にも届くことなく、宙に掻き消えた。
日が落ち、月明かりが海を照らしている。シャクーリアの警備隊に気付かれないように、船に明かりは付けないでひっそりと航海を続ける。
カティスが一人、甲板で月を眺めている。月の光が銀の髪を照らす。船の中ではささやかな宴会が開かれていた。決戦を前に、気分を高揚させようというのだ。
「あら?飲まないの?」
おっとりとした声が後ろからかかる。振り返ると、そこにはミランダが佇んでいた。
「…そういうアンタは」
「ちょっと酔っちゃって。風に当たりに来たの」
しずしずとカティスの隣へミランダは向かう。長い黒髪を右手で押さえて、気持ちよさそうに目を閉じる。
「…姫さん、酒飲んでたか?」
「ええ。一口飲んだだけで寝ちゃったわ。皆びっくり。お酒強い人たちばかりだから」
上品にミランダは笑う。そんなミランダを、カティスは不思議そうに見つめた。
「?どうしたの?」
「いや、海賊っぽくねぇよな、アンタ」
「それはもう…。元々私は神殿の巫女だもの。想像もしていなかったわ、この生活は」
ミランダが目を細める。
「大陸に売られるところだったの。そこをラズリが助けてくれたわ。巫女の力を使って、この集団を助けてきた。だから、副長、とまで言われちゃってね。そんなつもり無かったのだけど」
「昼ラズリが言っていた、水神さまがついてるってのは、アンタのことなのか?」
ミランダは軽く頭を振った。
「私の力だけじゃ不足だったわ。ラズリ自身に…水神さまのご加護があるのよ。だって…」
そこでミランダは口を噤んだ。
「だって?」
「秘密。…そうね、一言で言えば、それがラズリの運命なの」
口の前に一本、人差し指を立てて、寂しそうにミランダが微笑む。それを見て、カティスは眉間に皺を寄せた。
「運命…か。気に食わねぇ言葉だ」
「そうね。自分の与り知らないところで自分の人生を握られているなんて…残酷よね」
「…」
カティスは海面に目線を落とし、沈黙したまま、ミランダの言葉を聞いていた。弱い月明かりだけが真っ暗な海を心細く照らす。無意識のうちに、右手が胸元へと伸びていた。
「…?具合でも、悪い?」
それに気付いたミランダが声を掛ける。その言葉にカティスははっと我に返った。
「あ?いや…」
「ならいいけど…あら」
船内への出入り口から人が出てくる。ミランダは振り返って声を掛けた。
「どうしたの?」
「もうお開きにしますって!あ、カディさん、お姫様連れて行ってくれません?もういくら声掛けても起きないんで…」
その言葉に二人は顔を見合わせて苦笑した。
「…行きましょうか。眠り姫がお待ちよ」
「ったく…面倒なヤツだな…」
二人は船内へと向かう。灯火を照らさない船は、宵闇に掻き消えたまま、風を受けて目的地へと静かに向かって行った。