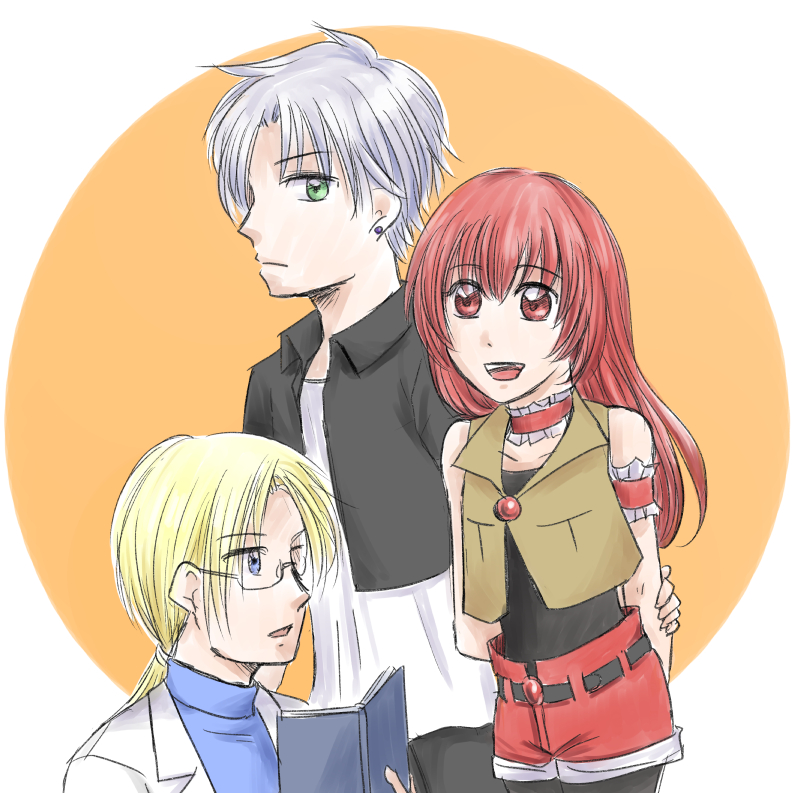城壁に囲まれた大都市・ハルザード。
その北側に、中島を有する湖がある。中島には、中央に高い塔がそびえたつ城が建っており、陸地とは100メートルほどの長さの石橋で繋がれている。中島の側面は切り立っており、城に出入りをするためには、この石橋を必ず渡らなければならない。
その石橋の往来が、今日この日に限っては非常に多い。馬車も人もだ。人々は一様に着飾っているし、馬車の馬の毛並も美しい。日が落ちてくるにつれ、その数は増えていく。
その様子を、城の南東の角の最上階、かつては物見として使われていた部屋から、一人の少女が見つめていた。窓枠に腕を預け、そこに顎を乗せてだらしなくしている。この、いつもと違う光景の理由を、彼女は一番理解していた。そしてそのことを考えるたびに憂鬱になる。空を飛ぶ鳥たちは気持ちよさそうで、自分もその中に混じれたらいいのに、と気持ちを馳せていた。
「いいなぁ…私も飛んでいきたい…」
「駄目です、ファーナ様。何を仰っているのですか、折角の晴れの日だというのに。早く着替えませんと遅れますよ?」
少し夢心地にすらなりかけていた少女の背後から、叱りつけるような女性の声が聞こえて振り向いた。自分より幾分か年上のその女性の顔を確認すると、また仏頂面になって窓の方を向く。声を掛けた女性は、大仰に溜め息をついて、ファーナの長い赤い髪を弄りだした。
「失礼いたします。そういうおつもりでしたら、先に髪を結わせていただきます」
「リン、いいから。解ってるから、先に着替えるわ」
リンの手を払い、クローゼットの方に向かう。払いのけられたリンの手は、近くのテーブルに置かれた。
「…ファーナ様。このリンも、お気持ちは解らなくはないのです。ですが、それ以前に貴女はこのカルディア神聖王国の第一王女であらせられることも、ご理解くださいませ」
「だから、『解ってるから』と言ったの」
ファーナはクローゼットにあらかじめ掛けてあった祭祀用の白い神官服を持ち出し、大きな鏡の前に持っていく。侍女のリンがそれを着付けはじめる。
――カルディア神聖王国。
約五百年前、カルディア平野を平定したヘディン・クルシードによって築かれた、天教という宗教を国教とした国家である。天教の祖――教主国でもあり、王家の者は全員神官の嗜みを身につけている。聖なる火を扱い、生者を恐怖より守り、死者の魂を天へと誘う。宗教と治世は同一視され、信仰厚い信徒はそれ故に従順な民となる。そして、この約五百年間、カルディアの地に限っては大きな戦禍がない。それが、王家を絶対的なものとしている大きな理由の一つである。
「父様は結局、フィリアの地から戻られなかったわね。居て欲しかったけれど…」
ファーナは寂しげな顔で父が居るはずの北の方角を向いた。
首都ハルザードから北へ六百キロほど行ったフィリア国境地帯での紛争は、未だ止むことがない。国王自らが陣頭指揮を執るために出立したのは、もう6週間も前になる。
「仕方ありませんわ。成人の儀は、その年十五の歳となる王族が、大満月の日に受けられるものと決められております。長たる王が居らずとも、それは執り行われなくてはなりません」
胸の赤いリボンを結びながら、リンは解りきったしきたりを口にする。ファーナはその言葉を聞いて、視線はそのままに、不満げな顔をする。
「せめて延期とか…」
「なりませんよ、ファーナ様。…大丈夫です。どうせ形式だけのもの。何も起こりはしませんから」
ポンとリボンを軽く叩き、リンはファーナから離れた。鏡の前には、白と赤で彩られた正装に身を包んだファーナの姿があった。鏡の中の自分を見つめて、しばらく目を閉じる。緊張しているのか、大きく深呼吸をした。流石に不安に思ったリンがファーナに問うた。
「…ファーナ様?」
「…不安なの。ここ数日、妙な胸騒ぎがして…。今もそう。只の緊張…なのかな…」
「大勢の前に出られるのですから、緊張されて当然ですわ。…それに、大満月ですから、誰しも不安になります。魔獣が凶暴になるとか、恐ろしい言い伝えばかりですから」
髪結いの道具を手元に引き寄せながら、何も特別なことはない、とリンは言外に匂わす。ファーナはその言葉を無理矢理飲み込んだ。
「…そうね。そうよね。うん、大丈夫…」
落ち着いたのを見計らって、リンはファーナの長い赤い髪を手に取った。
「さ、早く準備を済ませましょう。皆様お待ちですから」
ステンドグラスから差し込む橙の夕日が、室内をより厳かにしていた。
城の東側に設けられた教会の大聖堂には、数百人もの人でごった返している。前列には、他国からの使者や国内の貴族、後列は一般の見物客がベンチに腰かけていた。
「物凄い人出だな…」
その前列より数えて2列目に座る、正装した青年が、後ろを振り返って露骨に不快感を露わにした。後ろで束ねた長い金髪が、黒のコートに映えてきらりと光っているようにも見える。
「俺の時も同じことを言っていなかったか?ラーク」
その前に座る短い赤い髪の青年が、彼の方を向いて意地悪そうに聞く。それに気づいて、ラークと呼ばれた金髪の青年は前に向き直った。
「私は人混みが苦手でな。ヘディン、お前も知ってるだろう」
眼鏡に手をやり、青空のような色の瞳を閉じる。むっすりとした顔で憮然と答えた友に、ヘディンは吹き出しそうになった。この国の初代国王の名を付けられたヘディンは、正真正銘、このカルディア神聖王国の王子である。
「ははっ、知ってる。でもそろそろ慣れたらどうだ?今日のように、エルガードの長老達の名代であちこちに行かされることも多くなるだろう?『光の貴公子』さん」
ヘディンはラークとは対照的に、明るい表情をしている。
「…それでも、一介の研究者に頼むことではあるまい。今日は特別だ」
「そうだな。ファーナの兄として、長老達のお心遣いに感謝する、と伝えておいてくれ。…ファーナもな、お前にずっと会いたがってたんだ。全く、嫉妬してしまうよ」
くすくすと、声を潜めてヘディンは笑った。茶化してはいるが、嫉妬している、というのはヘディンの本心だろうとラークは思った。小さい頃から、互いに溺愛していたと言っても過言ではない兄妹だ。
「もう二十五になるのに、縁談の噂の一つも聞こえないお前が心底心配だ。もうファーナも成人だ。どこに嫁いで行くか解らんぞ」
ラークは半分本気で心配しながら言い返した。
「何、もう妹離れはするさ。…想う女もいる。俺の心配はしなくていい。だが…」
二の句を継ごうとしたとき、前方奥の扉が音を立てて開いた。大聖堂内がしんと静まりかえり、皆その音の方角を見やる。
赤い髪を結い上げ、飾り立て、赤と白の祭祀服を身に纏ったファーナが静かに現われた。色気のある化粧をし、ところどころに纏った金細工の飾りがより一層彼女を輝かせているようだった。普段のお転婆な彼女を知っている者は皆一様に深い溜め息をついた。
「…馬子にも衣装、とはこのことを言うんだな」
ラークの不謹慎なつぶやきに、ヘディンは黙ったまま、ラークの方を向いてギロリと睨んだ。
「…冗談だ。前向け」
ヘディンは仕方なく前に向き直る。丁度ファーナは、中央の祭壇の手前へと進んでいた。
「天より遣わされし、紅き聖火の守人の末裔よ、主の御前へ」
中央の祭壇にいる白髪の老人が、ファーナを呼ぶ。中央の祭壇には、老人の他に、二人の若い神官が付いていた。一人は茶色い髪の活発そうな少女、もう一人は、銀髪の、見るからに温和そうな少年だ。二人とも、青地の制服に白い上半身までのマントを羽織っている。
「…執行は先王…ヴィオル閣下か。ハサン様は親征から戻られなかったのか?」
ラークは小さな声で前列にいるヘディンに聞いた。ヘディンは振り返らずにこくりと頷く。ラークはその返事に渋い顔をした。
ヴィオルの言葉に従い、ファーナは中央に進む。途中、ちらりと観衆の方を向いた。多くの人がいる。心臓の鼓動が一段と早くなった気がした。
(大丈夫、何てことはない…)
リハーサルもしているのだ。何を取り乱す必要があるのだろうか。そうファーナは心の中で自分自身に言い聞かせた。
中央に辿り着き、観衆を背に巨大な神の像の方に向く。天を統べるという、天空神イーレム。その僕であり、使いであるのが『天使』と呼ばれる種族である。クルシード家は、その天使の一種、『赤天使』の末裔である。聖火を操り、生者を護り、死者の魂を天へと帰す。その役割を持たされて、約五百年前にこの地に降り立った。そう言われている。
ファーナは、大きく息を吸った。丁度ファーナの右隣になった銀髪の少年が、周りに聞こえないように囁く。
「大丈夫ですよ、ファーナ様。落ち着いて」
「サリ…うん、ありがとう」
サリと呼ばれた少年は、返事の替わりににっこりと微笑んだ。それを見届けたヴィオルが、再び大きな声で口上を述べた。
「今日この日を以て、汝、ファーナ・クルシードは、紅き聖火の守人とならん。人々を救い、導き、護ること。それが汝ら赤天使に課せられた使命である。その使命を全うすることを誓うか」
いつも以上に厳格な祖父の口調に、ファーナは身を固くした。元々ファーナはこの祖父が苦手である。端から見れば恐らく、カチコチに顔が引きつっているだろう。
「はい。この血に誓って」
「されば」
ファーナとイーレム像の間に、二人の若い神官が大きな燭台を持って高く掲げた。
「その誓いとして、聖なる篝火を」
ファーナは右手を燭台にかざした。二言三言、詠唱をする。
『我が血と盟約結びし火の精よ、世を照らす聖火となれ』
ボッと、燭台にたちまち火が灯る。日が落ちかけ、暗くなりかけていた大聖堂の中を、再び明るくした。観衆がおおっと歓声を上げる。
「ファーナは『世を照らす聖火』か…」
ヘディンがぼそっと呟いた。術の詠唱はその属性毎に旧い言葉で自由に紡ぎ、その属性の精霊達を行使することで効果を発揮させるため、その内容を解釈できる人間は限られている。ファーナの言葉を正確に理解出来た上で拍手を送った者は、ごく僅かだろう。
そんな観客のざわめきを静めるかのような、ヴィオルの声が響き渡る。
「これより、第一王女ファーナより口上申し上げる」
ファーナは観衆に向き直って、大聖堂の入り口の方まで見渡した。不思議と、ずっと感じていた不安な気持ちは無くなっていた。
「私の成人の儀に列席された皆様に感謝申し上げます。王家の末席を汚す身でありますが、皆様を護るという使命を胸に、精進してゆく所存です。…どうか、皆様の身に幸多からんことを」
そう言って、ファーナはまた手をかざした。壁際に掛けられている照明用の松明に、一斉に火が灯る。再び湧き上がる歓声に、ファーナは深く礼をし、大聖堂の奥へと戻っていった。
「これにて、成人の儀は終了となる。新たに天の御使いとなりし者に、今一度、祝福の言葉を」
ヴィオルがそう声を掛けると、来場していた人々が一斉に声を上げた。
「大いなるイーレムよ、新しき御使いに加護を!」
その大合唱が、奥へ下がったファーナにも聞こえた。身体の震えが、止まらなかった。
半ば放心状態で、ファーナは自室に戻った。既に日は落ち、部屋では丁度侍女のリンが、燈火に点灯しているところだった。
「お役目、お疲れ様でした、ファーナ様」
リンはいつもと変わらぬ笑顔でファーナを迎えた。その微笑みを見て、ファーナはほっと胸を撫で下ろした。
「ありがとう…あなた達は、もういいわ。後でちゃんと行くから、先に行っていて」
ファーナは部屋まで供をした護衛二人を下がらせて、部屋に入る。祭祀用の制服を脱ごうと、リボンに手を掛けたところで、リンが近寄ってきた。
「私が。ファーナ様はお疲れでございましょう」
リンは慣れた手つきでファーナの服を脱がしていく。
「…疲れたまま、これから披露会よ。各国の使者や貴族にとっては、こっちの方が重要…。体の良い外交の場なのよ」
自らが、その気もないのにその道具となるのは、ファーナにとっては気分の悪い話だった。
「そういうことはヘディン様にお任せすればよろしいのですよ。こういう事にかけては、ファーナ様と正反対ですわね」
「…兄様は、いつか王になるもの。私とは違う」
ファーナは悲しそうな微笑みを浮かべた。いつも一緒に居たいと願うほど、ファーナは兄ヘディンを思慕しているのに、社会的な状況がそれを段々許さなくなっている。ヘディンは次のカルディアの王として、多くの政務をこなすようになった。
いつまでも、子供のままではいられないのだ。
「…と、さあ、お召し物はどれにいたします?」
努めて明るく言って、リンはファーナにガウンを羽織らせて、クローゼットの扉を開けにいった。
「そこの、桃色の…。うん、それ」
薄桃色のドレスをファーナは差した。紅いバラのコサージュが胸に付いている、若干丈の短いスカートだった。リンは手にとって当惑した。
「ファーナ様、これ、短すぎ…」
「いいの。私らしいでしょ?兄様が、これが一番似合ってるって」
フワリと微笑んだファーナを見て、リンはそれ以上文句をつけることができなかった。
「ヘディン様のお許しがあれば、まあ結構でしょう。きっとお似合いですわ」
手際よくリンはファーナにドレスを着せた。髪も結い直し、戻ってきてから二〇分ほどが経過したところで、ドアがノックされた。
「誰?迎えならもうちょっと待って。もうすぐ済むから」
化粧直しも終りに差し掛かっていたころだった。鏡台に向かったまま、ファーナは外にいる人物に声をかけた。
「ファーナ様、僕です、サリエルです」
「サリ?いいわ、入って」
無遠慮にファーナはその人物の入室を許した。そこには、先程の儀式の際に声をかけた銀髪の少年が立っていた。ファーナと同じ位の年齢で、左目を前髪が覆っている、不思議な雰囲気を纏っている。
サリエルは部屋に入るやいなや、用意していた言葉を失い、立ちつくしてしまった。
「サリ?どうしたの?迎えじゃないの?」
ファーナは不思議そうにサリエルを見る。その言葉に、サリエルははっと我に返った。
「あ、はい、ヘディン様から、迎えに行くよう言われまして…。会場の大広間にはもう、皆さんお集まりになっております」
優しげな風貌から想像される通りの、穏やかな口振りでサリエルは話す。
「あの…それとファーナ様、僕、驚きました。さっきもそうですけど、とてもお綺麗です。いつもより、ずっとずっと、輝いています」
顔を赤らめて、精一杯サリエルは言い切った。相当な勇気を持って、サリエルはここでこうしてファーナに話をしているのだと、リンは直感した。
「サリ、本当?凄く嬉しい…」
ファーナが破顔一笑した。それをみて、サリエルの顔も明るくなった。
「…さて、準備はこれでいいですわ、ファーナ様。サリ、姫様をちゃんとエスコートするのよ。粗相のないようにね」
リンの意地の悪い言葉に、サリエルはまた体を固くした。
「は、はいっ!精一杯、努めさせていただきます!」
その様子があまりに面白くて、ファーナはくすくすと声を立てて笑った。
「それじゃあ、お願いね、サリ」
ファーナはサリエルの手を堅く握った。
大広間では、既に使者や有力貴族達が歓談を始めていた。
成人の儀など、カルディア王家の式典の類の際には常に、こうした社交の場が設けられている。場合によってはそれが数日に渡ることもある。カルディア神聖王国という大陸屈指の国家に擦り寄れば、何かと好都合である。小国の使者はこぞってカルディアの有力者に遜り、そうして目的を達して帰る。他国に攻められた時の後ろ盾、経済援助、その他もろもろの支援を約束する替わりに、カルディアに忠誠を誓う。
「ヘディン王子、ご機嫌麗しゅう…」
ヘディンも例外ではない。他国の使者から媚びへつらわれる立場にいる。ヘディンは、自分の父よりも年上の白髪の老人に頭を下げられていた。
「セザーヌ卿、お顔を上げてください。本日皆様方は大切な客人でございます。我々が頭を下げるべきところを、どうして貴方が下げましょうか」
「いえ、こうさせていただきたいのです。我が国シャクーリアは大陸最南方の島国故、日頃受けておりますご恩の礼を、こういう時にしか返すことが出来ませぬ。我らが身上、ご理解くだされ」
「いいえ。ご恩を受けているのはこちらの方です。南方貿易の拠点を置かせていただき、あらゆる物資がこの国に集まる…それは貴方がたシャクーリアのお陰なのですから」
そういう調子でヘディンは多くの使者と歓談している。大国ではあるが、決して偉ぶる真似はしない。それはある種、大国の余裕なのかもしれない。潰そうと思えば、何時だって潰せる。そうした冷たい自信を背後にして、表面は“いい人”を装う。それがヘディンのやり方だった。
ラークはそんな様子を見ながら、一人大広間の壁に寄りかかって冷たい茶を飲んでいた。元来こうした場が苦手である。むしろ積極的に話すべき場であるのに、一人でいる彼には、好奇の視線が注がれたが、本人は全く気にしていなかった。
話が終わったらしいヘディンが、ラークの所へ近づいてきた。
「もういいのか?」
「ああ。あとはお爺様が」
ヘディンは人だかりに目をやった。中心にいるのは、先程、儀式の際に壇上で執行をしていたヴィオルだった。
「相変わらず、院政なんだな」
「まあな。全く、いつになったら俺が権力握れるんだか」
ヘディンが苦笑しながらぼやく。王になってもう何年も経っている父ですら、まだ全権力を握っていない。
「…ああ、そうだ。後でちょっと付き合ってくれないか?頼みたいことがある」
「頼みたいこと…?何だ?」
「今この場では話せない。国家の機密事項だから」
その言葉にラークは怪訝な顔をした。こんな晴れの日に、この親友は一体何を言おうとしているのか。それが掴めず困惑する。
丁度その時だった。大広間の最も大きな扉が開き、ファーナが入ってきた。後ろにサリエルも控えて入ってきた。ゆっくりと広間の中央へと進んでいく。暖かい拍手が、出席者の中から湧いてくる。広間の中央に辿り着くと、ファーナは一礼して挨拶をする。
「皆様、本日は遠路よりご出席頂き、本当に感謝申し上げます。何分未熟者ですので、皆様方のお手を患わせてしまうこともありましょう。その時はどうか手助けしていただきとうございます」
そこまで言ったところで、ヴィオルがグラスを手に近づいてきた。
「…お爺様」
ファーナはぎょっとした。顔に出なかったか不安になる。
「さあ持て。乾杯の音頭を取って飲みなさい。もう大人なのだから、酒の一杯や二杯、軽く飲めなくてはならんぞ」
周囲からどっと笑いが沸き起こった。ファーナはグラスとヴィオルとを交互に見比べて、ゴクリと息を飲んでグラスを受け取った。
「あの馬鹿…!」
「ファーナ、お前酒弱いだろう!」
血相を変えて、ヘディンとラークが同時に人混みを縫って近寄ってきた。それに気付いて、ファーナがにこにこと二人に手を振る。
「あっ、ラーク先生!お久しぶりです。エルガードの皆は元気?」
「元気だ…って、そんなことはいいから、それは絶対飲むな!」
「お爺様、どうかお止めください。皆様に迷惑がかかります」
ヘディンは何とかグラスを渡したヴィオルに掛け合うが、首を横に振られてしまった。
「ならん。何故だ?酒を酌み交わすのが大人の嗜みだろう。」
つっけんどんにそう言われ、この人には何を言っても無駄か、とヘディンはがっくり肩を落とした。そんな止めに入った二人に、ファーナは心配しないでとばかりにひらひらと手を振る。
「大丈夫よ、先生、兄様。大人になったんだから、お酒も強くなってるはずよ」
そう言ってファーナはグラスを天に掲げた。
「皆様に神の祝福がありますように…乾杯っ!」
「乾杯!」
会場中から、乾杯の合唱とグラスを鳴らし合う音が聞こえてくる。
「あー…だから、大人になるとかそういう問題じゃあー…」
傍で呻く兄を余所に、ファーナはゴクゴクとグラスの中身を飲み干していく。飲み干したままの姿勢で、ファーナは止まってしまった。
「…ファーナ…?」
心配そうにヘディンはファーナの顔を覗き込む。目が、すうっと静かに閉じて、そのまま、後ろにぐらりと倒れていく。
「危ないっ!」
咄嗟に飛び出たヘディンが、間一髪でファーナの背中を支えることができた。周囲からは、おおっ、という歓声と拍手が沸き起こった。
「ファーナは…」
心配そうにラークが覗き込む。
「いつもの通り。気を失っただけだ。しばらくすれば起きるだろう」
ふう、と一息つき、むっすりとした顔でヴィオルを見上げる。
「…お爺様、ファーナが食事に入れた酒でも凄く酔うって、知っててこうさせたんですか?」
「…そうなのか?」
悪びれもなく言うヴィオルに顔を背けて、ヘディンはそのままファーナを抱え込んで立ち上がった。
「仕方ない。自室に連れて行きます。…皆さんはそのまま歓談をお続けになってください」
そのままヘディンとラークは、ファーナが今来た道を、そのまま戻って行ってしまった。大広間の入り口近辺に居たサリエルも、二人と一緒に部屋を出た。
ヘディンは部屋から出て、人気のないところまで来ると、ふうと一息ついた。
「ヘディン様、替わりましょうか?」
サリエルが心配そうに覗き込む。
「ははっ、ファーナに失礼だろ。そういうんじゃないんだ。あそこから出られて、ちょっと安心しただけだ」
ヘディンはちらっと後ろを見やって、言った。
「…お前も嫌だろ?ラーク」
「そうだな。あそこから抜け出す上手い口実を、ファーナが作ってくれたようなものだな」
そこまで言って、ラークはふと、自分の方にサリエルが興味深げな視線を送っていることに気が付いた。
「…ヘディン、そう言えばこの子は」
只の神官にしては、王子であるヘディンに馴れ馴れしすぎる。この少年もきっと同じような考えを、自分に対して抱いていると感じた。
「あれ?お前会ったこと無かったっけ。サリエルっていう。一年近く前に拾って、しばらく俺の近習にしてたんだけど、本人たっての希望で神官に」
「拾って、って…」
犬や猫でもあるまいし、と心の中でつぶやく。
「ふふ。実際そうなんです。命を、助けて貰いました」
フワリと優しい笑顔を浮かべたサリエルに、どこかラークはファーナに似ているなと感じた。
「で、サリ。こっちはラーク。俺の小さい頃からの親友で、ファーナが去年までエルガードに留学していた時に、家庭教師やって貰ってたんだ」
肝心な事は敢えて言わずに、へディンはそれだけ紹介した。
「あ、なるほど、それで…。」
それでもサリエルは何かが引っかかっているようだった。しばらく無言のまま、三人は月光が差し込む廊下を歩いていた。
「…あ、思い出した!エルガード当代きっての魔術師…『光の貴公子』、貴方が?」
ぽんと手を叩き、閃いたような顔をして、サリエルはラークの方を向いた。
「その通り。でもあまり騒ぐなよ。こいつそういうの嫌いだから」
答えたのは本人ではなくヘディンだった。ラーク自身は、否定とも肯定ともとれない態度のままであった。
「私のことを世間ではそう言っているようだが、そんな大層な人間ではない。噂など、真実とは遠くかけ離れたものなのだから」
ラークは優しい視線をサリエルに向けた。サリエルは感心したように、はぁ…と一息出した。そうこうしているうちに、何時しかファーナの部屋まで続く階段の前まで来ていた。
「さてと、サリ、今日はご苦労さん。後はもういいよ。朝から働き詰めで疲れたろう?」
ヘディンがねぎらいの言葉をかける。
「よろしいのですか?…お気遣い感謝いたします。では、僕はこれにて…」
サリエルは挨拶も早々に、立ち去ってしまった。本当に疲れていたのだろう。後にはファーナを抱いたヘディンとラークだけが残された。
「じゃあ、ちょっと待っててくれ。ファーナ置いてきたら、さっきの話の続きだ」
「解った」
ヘディンはラークをその場に残し、ファーナを抱えてその階段を上る。その先にある扉を叩くと、パタパタとこちらへ向かってくる足音が聞こえた。
「どちら様ですか?」
「俺だ」
その一言だけで扉は開けられた。扉の向こうのリンがヘディンの顔を見て不思議そうな表情を浮べた。
「あ、あれ?ヘディン様、これはどういう…」
「酒を飲んでしまって、この様だ。悪いがこのまま寝かせておいてくれないか」
「ああ成程…解りました」
リンは納得した表情を浮かべて、ヘディンを部屋の中に通した。ヘディンは真っ直ぐ部屋の奥に向かい、ベッドにファーナを降ろした。そしてしばらく、その寝顔を見つめていた。大事なものを、愛おしく思う、そんな表情だった。
しばらくそうしていたが、やがて目を閉じ、すっくと立ち上がった。目を開いたと同時に、厳しい顔つきになった。
「リン。日付が変わる頃にファーナを迎えに来る。動きやすい格好でいいから、準備だけはしておいてくれ。じゃあ、また後で」
「は、はい…」
扉を閉めて、また階下へと向かう。待っていたラークにヘディンは声を掛けた。
「ここじゃ何だし、俺の部屋に行くか」
ヘディンの自室にラークは招かれた。ヘディンは部屋に入ると、机の後ろにある窓際まで歩いていった。ラークもそれに続く。
既に夜である。曇ることなく、星空が広がっている。風も無く、静かな夜だ。ただ、いつもよりも大きい銀色の満月が、地上を照らし、この部屋の中にも光が差し込んでいる。
「毎年のことだが、薄気味悪いよな、大満月って」
ヘディンが窓の外の満月を眺めながら言う。
「…月は闇の力の象徴だ…。血が騒いで落ち着かん。…ところで、話というのは、ファーナのことか?」
ラークの問いかけに、ヘディンは身を翻した。
「…そうだ。父上が遠征に出る直前にな、俺に言ったんだ。『ファーナを護れ』ってな。そんなのいつもの事だ。でも、敢えて口にしたって事は何かあるような気がしてな…。今日のことしか考えられなかった」
「…今日のこと?」
「『成人の儀』さ。昼間のヤツは表向き。…実はもう一つあるんだよ」
ヘディンの表情が真剣味を帯びる。それを見て、ラークの顔が険しくなる。
「初耳だな」
「そりゃそうさ。この王家にしか伝わってないからな。きっと、お前のご先祖様も誰も知らないだろう」
その言葉に、ラークは顎に手を当てて考える。自分だけでなく、この王家とそれなりの付き合いのあった歴代当主までもが知らないという儀式は相当に重要なことに違いない。
「そんな機密事項を、私に漏らしてもいいのか?」
「…ああ。お前にも、その儀式に出てもらいたいからな。…その儀式で、何かよからぬことが起こった時に、俺と一緒にファーナを護ってほしいんだ」
機密とされている儀式で、いつもと違うことが起きる。それは十分に不安を掻きたてるものだった。
ラークは覚悟を決めて、ヘディンに返事をする。
「…承知した。その儀式の仔細を教えてくれ」