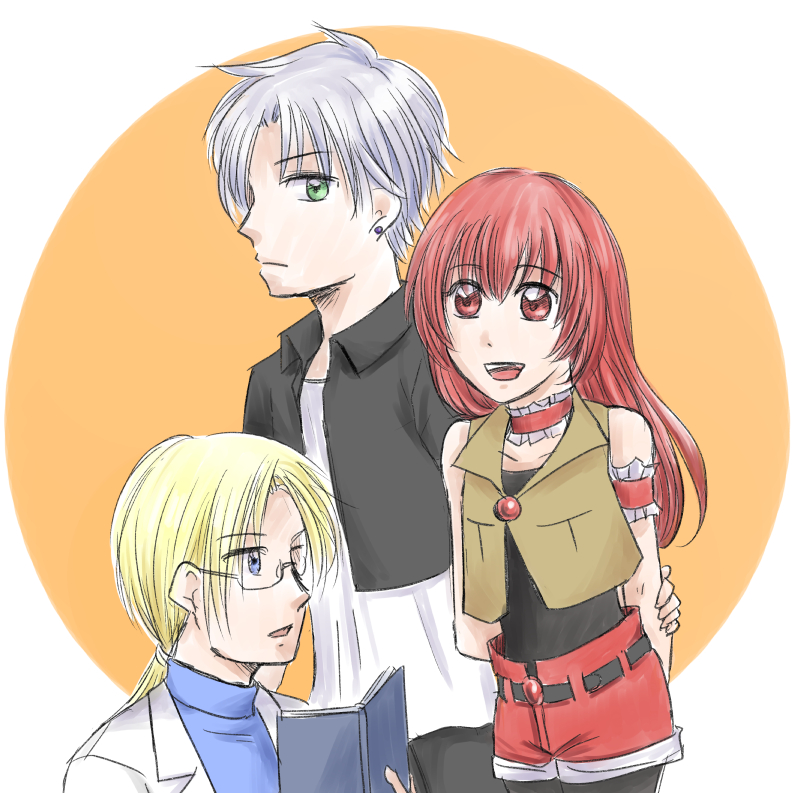銀色の、大きな月が、ずっとずっと、窓の外から覗いているような気がした。
怖くなった。夜なのに明るい。不気味で、そしてどこか冷たい。
「こわい…こわいよ」
私は誰かに泣きつく。高いベッドに、無理をして登ろうとして、落ちそうになったところを、その人に抱えられた。
「こわくないわ…。お母さんが、側にいてあげるから。」
その人は暖かかった。いつも自分を護ってくれる。泣きやむまでポンポンと優しく背中を叩いて、落ち着いたところで、ゆっくりと話し始めた。
「月はね…怖くなんてないのよ。夜に迷ったときは、優しく導いてくれる。真っ暗な夜を、照らしてくれる」
穏やかで、ゆっくりとした話し方。そのまま、うとうととしてしまう。
「…お母さんね、昔、月から来た天使様に助けて貰ったの。丁度こんな日に、森で迷子になってね…」
「月から天使なんてこないよ、お母さん。」
「ううん。あの人は本当に月から来てくれたのよ。だって、お月様と同じ色をしていたもの。とても優しくて、泣いてるお母さんをずうっと、見守っていてくれたの」
――あ、ダメだ、その先を言っちゃダメ!
「村まで送り届けてくれて、最後は、名前を告げてまたお月様に帰って行ったの」
「へぇ~?ホントにホント?何て天使さま?『白天使』さま?」
――ダメ!言っちゃだめ!行っちゃだめ!
「『白天使』さまじゃなかったけどね、…その天使さまの名前は――」
「ダメ!いっちゃダメ!」
勢い良くファーナは飛び起きた。側のテーブルで編み物をしていたリンが、驚いた顔でファーナの方を向いていた。
「ファーナ様、大丈夫ですか?」
編み物を置いて、ベッドに駆け寄る。ファーナの顔から、汗が噴き出していた。
「まあ、凄い汗…なにか悪い夢でも」
「うん…いい夢だけど…悪い夢…」
よろよろと、ファーナはベッドから降りた。いつの間にか寝巻きに着替えられていたのに気付き、寝る前まで自分が何をしていたのかを思い出そうとした。
「あー…お酒一気飲みして、それで…」
ズキズキと頭が痛む。ファーナは右手で額を押さえた。それを見て、リンが切り出す。
「お水、飲まれます?」
「うん。何かまだフラフラするし、頭も痛い…」
「二日酔いですね。もうお酒は止めた方がよさそうですね」
「…大人になったからって、飲めるようになるものではないのね」
そう言って、ファーナは深い溜息を吐いた。結局、その場にいた人に迷惑をかけてしまった。反面、余計な気を使う時間が無くなってよかったかもしれないと安堵した。
「まあ、こういうのは体質だと言いますね」
リンはそう言いながら、水を入れたコップをファーナに渡した。ふと時計を見やると、もうすぐ、日付が変わる時刻だった。
「ファーナ様。ヘディン様からお言付けがあるんです。動きやすい格好でいいから、ご用意なさってください。ヘディン様がファーナ様をお迎えに上がるそうです」
渡された水を飲みきって、ファーナは首を傾げた。
「何で?お迎えって?」
「さあ…私にもよく…」
よく解らないまま、いつも街にお忍びで遊びに行く服を着た。長袖にスパッツ、その上から赤く長いジャケットを羽織る。ブーツを履いたところで、ドアがノックされた。
「リン、ファーナの準備は」
ヘディンの声だった。
「丁度終わりました。今、そちらに」
ファーナが軽い足取りで扉を開ける。開けた先に兄の姿を確認すると、くるっと後ろを向いてリンに軽く手を振った。
「じゃあ、よく分からないけど行ってくる。リンはもう遅いから部屋に戻って休んでいいわ」
「はい、お気を付けて。お気遣いありがとうございます」
丁寧に礼をしたリンを残し、静かにドアを閉め、ヘディンと共に階段を下る。ヘディンが纏っている空気が、どこかしら重い。ヘディンも普段着だったが、腰に剣を差していることが気になった。
「お兄ちゃん、これから何かあるの?」
ファーナはヘディンの二人きりの時は「お兄ちゃん」と呼んでいる。実際に仲の良い二人なので、普段から畏まることを二人とも嫌がっていた。
「ああ。夕方のアレも成人の儀なんだけどな、もう一つ、真夜中にこっそりやる成人の儀もあるんだ」
「え?また何か人前に出たり、演説しなくちゃいけないの?」
ファーナが眉根をひそめる。
「いいや。そういうことは何もない。言うとおりにしてれば、何も問題はないさ」
それはヘディンにとっては願望だった。何も起こらないで欲しい。このままずっと、この生活が続けばいいと思っていた。
「なら、いいんだけど」
ファーナもどこか不安げだった。階段を下りきって、廊下に出ると、大満月が窓一杯に広がっていた。丁度先ほどまで見ていた夢と同じ風景。一層、胸のざわめきが大きくなる。
「…こんな夜だし、早く済ませたいね」
「ああ。見ていて気分のいいもんじゃないな」
そうしてヘディンは玉座の間へファーナを連れて行った。中にはヴィオルと、普段着に着替えたラークが待っていた。
「…あれ、先生?何で?関係無いんじゃないの?」
「ラークたっての希望だ。お前にとってはもう一人の兄みたいなもんだろ?見届けたいんだそうだ」
ヘディンがそう説明すると、ラークはどこかぎこちない笑みを浮かべた。
「そっかぁ~。何か安心する」
しかし、ファーナは少しほっとした様だった。そんなファーナを余所に、ヴィオルはいつもの厳格な声音で静かに告げた。
「…これより、真の成人の儀を行う。ファーナ、これからお前には、赤天使の末裔としての責任と義務を、身を以て知ってもらう」
ファーナは息を飲んだ。
「責任と義務を、身を以て…?」
ヴィオルはファーナに背を向け、玉座の後ろのタペストリーに手をかざし、徐ろに詠唱を始めた。
『我は神の目なり。封ぜられし番人の扉よ、開け』
すると、タペストリーの裏の壁が消えて無くなった。
「こ、これは…」
ファーナが驚く。玉座の裏に、こんな隠し部屋があったなんて。
「行くぞ」
ヴィオルが先頭を切って、手に炎を喚んで中に入る。三人が続いて中に入った。一つの広間並の広さの部屋の真ん中に、淡く虹色に光る玉が小さな祭壇のようなところに鎮座してあった。
「あの玉は…?」
「あの玉に触れること。それが成人の儀だ」
ファーナの問いに答えることなく、ヴィオルが冷たく言う。
「…それだけ?」
ファーナが不思議そうな顔をする。
「それだけだ。さあ、行け」
恐る恐る、ファーナは前に出る。玉の前まで進むと、後ろの三人を振り返った。ヘディンと目が合う。ヘディンはこくりと頷いた。
ファーナにとってはそれだけでよかった。再び玉に向き直り、触れようと手を伸ばした。
「――えっ」
玉が突然、まばゆい光を放つ。それと同時に、ファーナの意識に何かが流れ込んでくる。
「なっ、何これっ…!ああっ、嫌っ…」
「手を離すなよ、ファーナ!」
「は、離すなって言ったって…」
何故か手を離そうとしても離れない。自分の記憶でもない記憶が、脳裏をすさまじい速さで駆けていく。それもいい記憶ではない。戦争、貧困、様々な悲劇…。何故かそんな記憶ばかりだ。そして、わずかであるが、その記憶と一緒に、自分のものでは無い感情が流れてくることに気が付いた。
「――かなしい、哀しいの?」
誰に向かってでもなく、ファーナは呟いた。目を閉じる。閉じると一層、その記憶と感情の洪水が押し寄せてくる。それを掻き分けるように、その感情の主を捜そうとした。
(誰?あなたは誰?ねえ、どうして私にこんなものを見せるの?)
意識の中で語りかける。しかし、ファーナには、もはや流れ込む意識の濁流を抑えきれる気力が無くなっていた。涙が止まらない。誰かの哀しみなのか、自分が哀しいのか、それすら解らない。
そして、意識が段々薄れていく。
(あー…ダメ、もう…私は)
その刹那。記憶の濁流の最奥に、何かを見つけた。毅然と、深い緑の双眸を、こちらに向ける、土の色の髪をした女性。毅然としているのに、その瞳から大粒の涙がこぼれる。口を開いて、何かを語りかけているかのようだった。
(誰?この記憶は、あなたの?)
『――幾千の時が刻んだ、幾千の人の想い、歴史――。貴女は、その重みに耐えられますか?』
「えっ…」
そう聞こえた瞬間、ファーナは気を失った。
「うわっ!」
玉が突然、部屋全体を真っ白にするようなまばゆい光を放った。光が消えるまで数秒。恐る恐る目を開けた三人の前に、ファーナの姿は無かった。
「…ファーナ?ファーナ!どこだ!」
ファーナの立っていた小さな祭壇前までヘディンは駆けていったが、跡形もなく消えていた。そこには、先程と変わらず、淡く虹色に発光する玉が置いてあるだけだった。
「そんな…一体何が」
恐れていたことが起きた。自分の時はこんなことは無かった。その場で気絶しただけだったはずだ。
「…あの宝玉は『大地の涙』ですね。精霊の記憶が宿ると言う特殊なジェムと聞きますが…、ファーナが消えたのと何か関係が?そもそも何故こんなところに…」
至極冷静にラークがヴィオルに質問する。
「この城の中心にある塔の伝承は知っているな?」
「ええ。かつてこの塔は魔獣の巣窟だった。それを五百年前、『堕天使』もろとも封じたと…」
二人のいる場所にヘディンも戻り、ラークの言葉に続けた。
「あの玉には、この世界の記憶が詰まっている…。大国の王族たる者、その重さを知らねばならない。…それ故に成人の儀で使っている…父上はそう仰っていました」
「そうだ。…そしてもう一つ…、あの玉によって確かめるものがある」
「もう一つ?」
ヘディンが怪訝な顔をする。
「お前にはまだ言っていなかったな。あの玉は、天に仇をなすものを見極めるものなのだ。この塔に封じられた魔と波長が合うものは、その魔の面前に飛ばされ、神の裁きを受けることになるという。…いまだかつて、そんな者はいなかったと聞くがな」
ヴィオルの口の端が持ち上がるのを、ヘディンは見逃さなかった。
「お爺様…!まさか貴方はファーナを…!」
「待て、ヘディン」
いきり立つヘディンの肩に、ラークが手を置いて諫める。ヘディンも我に返って口を噤んだ。
「…転送され、神の裁きを受けるのと、封印との因果関係はあるのですか?まさか、封印が解けるなどということは…」
「『禁句』を言えば解かれる仕組みだと言われている。…天教徒たる者が言うはずはないと思うがな」
そう言うと、ヴィオルは部屋の奥まで歩を進めた。何も無い壁に手を置き、一言呟くと、目の前の壁が消えてなくなった。
「…この先は塔の最上階へ続いている。ファーナも恐らくはそこにいるだろう。万が一ということもある…急ぐぞ」
二人は頷き、駆け出した。
(…無事でいろよ、ファーナ…!)
…寒い。
…え、寒い?
そう思って、ファーナは目を開けた。頭がクラクラするのは、酒のせいなのか、それとも、さっきの玉のせいなのか。
「うっ…こ、ここは…」
体を起こして周りを見渡す。中央に何か置いてある他は、誰もいないし、何もなかった。時も空間も、凍り付いたかのような印象を受ける。ただ、大満月の青白い光だけが、冷たく室内を照らしている。
「な、何ここ…。お兄ちゃん!先生!お爺様!?」
むなしく、室内に自分の声だけこだまする。ファーナは途端に不安になった。
仕方なく、とりあえず目の前にある物体に近づいた。ガラス張りの、直径2メートルくらいの円形の物体。横から見る限りだと、白い何かのようだった。
恐る恐る上から覗きこみ、ファーナは息を飲んだ。
「なっ…これは、死体…?」
そこには一人の青年が横たわっていた。黒いジャケットに、黒いズボンを穿いた、銀髪の青年。髪が月の光を浴びて、きらきらと光輝いていた。彼の周りには、このカルディア原産の花々が、色鮮やかに敷き詰められている。
ファーナはすぐに疑問に感じた。この人は誰なのか。いつからこうなっているのか。どうして花々が色褪せぬまま敷き詰められているのか。
「まるで、埋葬したその瞬間が、そのまま止まっているよう…」
底知れない恐怖をファーナは感じた。どうしたらそんなことができる?どんな魔法だって、そんなことは不可能ではないか?神の業、としか言いようがない。
「それにしても、綺麗な銀の髪…。まるで月…」
ふっと口にした自らの言葉に、ドクンと心臓の鼓動が高鳴った。さっきまで見ていた夢――いや、あれは自分の記憶。母と一緒に寝た、最後の記憶を、鮮明に思い出した。
「ま、まさか、この人って…」
カルディアの地に封じられ、未来永劫、魂はこの世界を彷徨い続けているという。かつてこの世界を蹂躙しようとした『堕天使』。
…言ってはいけない。それは禁句。言ったから、母様は、ここからいなくなった。不幸が降りかかった。だからこそ、その名は余計胸に刻み込まれ、まるでカラクリのスイッチのように、思い起こされた。
「…『堕天使』カティス…?…その名を言ったから、母様は…」
その言葉を告げた瞬間だった。円形の棺桶が突然、まばゆい光を放った。
「きゃっ…!こ、今度は何?!」
パリンとドーム状のガラスが割れた。中から、ゴォォと音を立てて冷たい風が吹き荒れる。ファーナは咄嗟に顔を覆ったが、風に乗ったガラスの破片によって、服は所々破片によって切れてしまった。
やがて風が収まったことを感じ、ファーナは恐る恐る顔を上げた。色とりどりの花びらが優雅に宙に舞う。その中で、先程の青年が仰向けの姿勢で浮いていた。静かに、目が開く。透き通るような緑の瞳が、こちらを向く。ファーナは息を飲んだ。その瞳に引き込まれる気分を覚えた。
「う、うそ…」
姿勢を正し、その場に音もなく降り立った青年は、しばらくじっと自分の手を見つめた後、ふっと、ファーナの方を向いた。
「おい、お前」
「え、は、はいっ?!」
落ち着いた、凛とした声が空間にこだまする。ファーナは驚きと不安と緊張のあまり、声が裏返ってしまった。
「…俺の姿、しっかりと見えてるんだな?透けてもいないな?」
「…え…?そりゃもう、バッチリですけど…」
何を突然この人は言い出すんだとファーナは訝しんだ。しかし彼にはその答えで十分だったらしく、ふう、とまるで何かを諦めたかのよう溜息をついた。
「で、お前は?見たところ、赤竜の末裔…クルシード家の者のようだが」
ファーナはどきっとした。初対面の人物に、突然血筋まで当てられるなんて。
「…そうよ。私はファーナ。ファーナ・クルシード。カルディア王家の第一王女よ」
そう言うと、青年は目を丸くした。信じられない、と言った表情だ。
「…王女?王女のくせに、タブーを犯したのか。とんだ姫さんだな」
「えっ…タブーって、まさか」
ファーナは本格的に冷や汗をかきはじめた。
「貴方は…『堕天使』カティス…」
「そう。何だぁ?知らなかったわけじゃねぇだろ?…まさか、何も知らないのか?」
言葉の最後は、本当に唖然としたような声音だった。
「しっ…失礼ね!知らない訳無いわ!五百年も前、この世界を蹂躙しようと天から堕ちてきた天使…。最後は『白天使』さまに倒されて、罰として、ずっとずっと、魂だけはこの世界を彷徨わされてるって」
ファーナの答えに、カティスは、ふーんと唸り、少し面白くなさそうな表情を浮かべた。
「ま、常識的な回答、結構なことだ。…でも、アンタは、タブーを犯してはならないという『天教の常識』を破っちまったなぁ?」
「!そ、それはっ…」
たじろぐファーナに、風を切って近づき、ファーナの顎を右手で持ち上げた。
「っ!」
「『堕天使の名を口にすれば不幸が訪れる』って言うだろ?…そうだな、さしずめアンタは、手始めに今の生活が失われるだろうな」
吸い込まれるような緑の瞳がファーナを捉える。ファーナは視線をそらせない。
「…そんな…っ!どういう、ことよ…」
カティスは一度、ファーナの奥の壁に目をやると、ファーナを強引に反転させて首の辺りに手を回し抱き寄せた。
「えっ…」
「こういうことだ。よく見ておけよ…!」
丁度その時だった。目の前の壁が突然轟音と共に上昇し、埃が舞った。その埃の向こうに、三人の影が見えた。
「…ファーナ!」
「お兄ちゃん…くっ!」
現われたヘディン達の所へ駆けようとしたファーナは、強い力でカティスに抑えられた。見た目の華奢さとは正反対の腕力だ。
「貴様が…」
ラークが呆然とカティスを見つめて呟いた。
「…まさか、神罰が下る前に禁句を発したか…」
ヴィオルにとっても想定外のようだった。声が震えていた。
「ククッ…貴様らには感謝するぞ…。あの地獄から開放してくれたんだからな…!」
心底愉快そうにカティスは嗤う。ファーナは言葉を失った。ヘディンが一歩前に出て、ファーナを見つめる。
「ファーナ…何故、知っていた?口にした?!その男は天に、神に弓引きこの世界を支配しようとした『堕天使』だぞ!これでは…王家の者として、いや、天教徒失格だ!」
ヘディンが恐ろしい剣幕で怒る。ファーナはその時ようやく、事の重大さに気付かされた。
「お兄ちゃん…そんなっ、これは」
「言い訳か?お前は、そんなことを言える立場か?身の程をわきまえるんだな!」
ファーナは脳天に雷を落とされたようなショックを受けた。今にも泣き出しそうになる。
「泣いても無駄だ。もう何もかも遅い。…それが、お前の罪だ」
冷酷にヘディンは突き放す。腰に付けていた剣を、静かに引き抜き、ファーナとカティスに向かって剣先を向ける。
「…愚かだなぁ。なぁ、姫さん。これが、お前の責だ。全てがお前のせいで崩壊する。お前の日常も、この世界も、なにもかもな」
耳元で、静かに、冷たく、いやらしく囁く。悪魔の囁きだとファーナは感じた。その言葉によって、段々自分が追い込まれていく。解っていた、いや、解りすぎていた程なのに、どうして自分はその禁句を言ってしまったのか?いくら考えても、答えは出てこない。涙だけが、止めどなく流れ出していた。
「…さあどうする?ここにお前の味方は一人も居ないようだぜ?どっちに殺されたい?」
「うっ…ぐっ…あっ」
カティスは腕に力を入れ、ファーナの首まで持ち上げる。首を絞められた格好になったファーナは、涙を流しながらかぶりを振る。苦しい。息が出来ない身体的な苦痛も、もうどうすることも出来ないという絶望も、全てがファーナに襲いかかる。
「くっ!離せ下郎が!貴様を倒した後…せめてもの情けだ、ファーナ、この俺の手で終わらせてやるっ!」
「ヴィオル閣下は、後方へお控えください。ここは私たちが」
ヘディンが剣を水平に持ち、猛烈な速さで駆け間合いを詰めに行く。その後ろでは、ヴィオルを後ろに下がらせたラークが静かに魔法の詠唱を始めている。
「まるで猪だ。そんなにこの堕落した姫さんが大事か?」
太刀筋を早々に読み、ファーナを片手で腹の辺りで抱えなおし、カティスは身を翻した。その刹那、二人の目が合った。ヘディンの紅い瞳が、じっとカティスの緑の瞳を射るように見つめていた。
「――…ふん、そうか」
喉の自由が解放され、咳き込んでいたファーナは、カティスの呟きをかろうじて聞いた。が、目線を上げた先には、光球を作り上げたラークの姿があった。
「あっ…」
悲鳴が形にならない。
「ヘディン、避けていろ!『…矢となりて彼の者を捉えよ!』」
「くっ!」
姿勢を崩していたカティスに向かって、光の矢が放たれた。間一髪の所で避けてダメージは免れたが、頬に薄く切り傷が出来た。
矢は、丁度後ろにあったガラス窓を甲高い音を立て突き破り、室外に出て行った。カティスはふと、その方向を見やる。
「どこを見ている!」
左からヘディンが大剣を高速で叩きつける。それも間一髪で避けた。しかしカティスは壁際まで詰め寄られ、逃げ場が無くなった。
「…チェックメイトだ。二人揃ってこの世から去れ」
再びヘディンは剣先を二人に向ける。そこから数歩下がった所では、ラークが次の術の詠唱に入っている。どう見ても絶体絶命の状況だ。
ファーナは死を覚悟した。涙は止まらぬままであったが、覚悟を決めると何故か少し落ち着きを取り戻せた。してはいけないことを犯した罪。それが今すぐ償われるなら、そしてそれが皆の望みなら、自分はそれでいいと思った。しかし、それは死という逃げだ。自分で、自分の犯した罪の幾ばくかを償わなくては、それこそ名折れだ。
せめて、一矢報いなければ…そう思っていたその時だった。
突然、視界が変わる。宙に浮き、天井が見え、城の周囲にある湖が見えた。冷たい風が身を切るように吹き付ける。恐ろしいスピードで、湖の水面が近づいてくる。
「えっ…え、ええええええええ~!!???」
何がどうなっているのか、すぐに見当がつかなかったが、相変わらず腹の辺りを抱えられていることに気が付いた。
「あっ…貴方、実は死ぬつもり?!」
後ろのカティスに大声で訊く。風の音で声がかき消されたのではないかと思った。しかしカティスは冷静に、その言葉を聞き届けていた。
「…馬鹿言え。折角自由になれたんだ。まだ命はやれねぇな」
すると、大きく鳥が羽ばたくような音がしたと同時に、急降下が止まった。そのままの高度で、進路は南へと進んでいく。湖水には、大満月と同じ輝きをした銀の光が映し出されていた。
「翼っ!…天使の、翼…!初めて見た…」
まるでもう一つの月だ。ファーナは一時、全てを忘れ惚けてしまった。太古にこの世界に存在したと言われる『竜』によく似た翼が、カティスの背から伸びている。
「…貴様らは『竜人』の事を『天使』とか言うんだったな。自らを『天使』と称して偉くなった気分か?」
「なっ…」
ファーナはその一言で現実に戻された。今自分を抱えているのは、敵だ。『堕天使』だ。どんな甘言を使ってくるか解らない。
「偉いも何も、私たちは、神様からこの世界を守護するよう賜った『赤天使』よ。その事実に変わりはないわ。そうでなければ、このカルディアの地をこうして治めている理由がみつからない」
ファーナはきっぱり言い切った。後ろから、大仰な溜め息が聞こえた。
「ふぅ…。本当に何も知らないんだな…。まぁ、無理もないか」
呆れたような物言いだった。タブーと言われると、ファーナは途端に恥ずかしくなった。
「…私、そんなに悪いことをしたのね…」
「…ふん、今更だな。先にそう思っていれば、こんなことにはならなかった…だろ?」
「何で?!どうして、どうして私が、貴方を…」
名前を言ったから、それだけなんだろうか。ただそれだけで解ける封印なんて、どうして施すのだろう。封じるなら、もっと幾重にも防壁を巡らせて、二度と解けないようにすればよかったのに。
それに、あの玉は一体何だったのだろう。最後に見えた、あの女性は何者なのか。あの女性が、もしかすると何か知っているのかもしれない。
「…一つだけ教えてやるよ。あの封印を解くことが出来るのは、俺と同質の者だけ…なんだとよ」
「…!私が、貴方と、同じ…?」
愕然とした。自分が『堕天使』だとでも言うのか。
「何よそれ!信じないわ!私はっ…」
「信じるかどうかは任せるが、胸に手ぇ当ててよく考えてみるんだな」
「…」
ファーナは無言になり、下を向いた。先程まで眼下に粒のように見えていた城下町が、もう後方にあった。街道を歩く人はおらず、ただ大満月の光の元、息を殺したような静寂が満ちていた。
こんな風に、この国を出奔するなんて。こうして禁忌を犯して、惨めにも連れ去られる格好で、皆に憎まれて去るなんて。
充分、『堕天使』と言われても仕方がない。
「…貴方は、これからどうするつもりなの?」
静かにファーナが問う。
「南へ。…会いたいヤツがいる」
「会ってどうするの?」
「…食い下がるなぁ。どうだっていいだろう」
しれっとカティスは言葉をかわした。ファーナもそれ以上は追求しなかった。それは、今後きっと解ることだ。
「…決めたわ。私、貴方に付いていく。隙あれば貴方に止めを刺す。それが私の罪滅ぼしよ。兄様に認められなくても、それが私の、王家の者としての最後の努めよ」
他にどうすることも考えられなかった。このまま大人しく兄に捕まって処刑されるよりは、生きて罪滅ぼしがしたかった。
「…上等だ。ま、せいぜい頑張るんだな。…俺は逃げも隠れもしない。もっとも、アンタに俺が殺せるわけはないがな…ククッ」
高らかにカティスは笑う。宵闇に君臨する大満月のある方角へ、そのまま飛び進んでいった。
「…まんまと逃げおおせたか…」
冷気が籠もる部屋には、三人がそのまま取り残された格好になった。もちろん、誰も二人が死んでいるとは思っていない。
「あの男は純粋な『竜人』ですから。混血が進んだ“我々”とは違い、翼を持っている…憎たらしいことだ」
苦々しくラークが吐き捨てた。
「ウィンディアの『風読み』でもない限り、ヤツを今すぐ追うのは不可能…。ここは一度ヤツを秘密裏に始末する算段を考えた方がよさそうですね」
ヘディンが冷静にヴィオルに進言した。ヴィオルは黙って頷く。
「そうだな。明日、布告を出そう。『姫が行方不明になった。至急探し出しカルディアに送還せよ』とな。…ファーナを殺すのはそれからでいい」
苦渋の表情を浮かべてヘディンは頷き賛同した。
「…ヘディン、さぞ苦しかろう。お主はあの娘を特段可愛がっていたのだからな。しかし、あの娘はこの王家にあってはならぬ人物だったのだ。闇の眷属がここにいてはならぬ。無論、輩出したことすら、末代までの恥なのだ」
「心得ております。せめて、我が手で死を迎えさせてやりたい。今はそれしか思っておりません」
淀みない声でヘディンが言う。それに満足したのか、ヴィオルは先に出口へ向かった。
「儂は先に降りる。全ては明日、始めることとする」
振り返ることなく、後ろの二人にそう声をかけた。
「はっ…承知しました」
最敬礼をして、二人はヴィオルを見送った。居なくなったのを見計らって、囁くような声でラークが口を開いた。
「…これで満足か?」
ヘディンは無言で頷く。
「…よく耐えたな。『さぞ苦しかろう』。」
ラークはヴィオルと全く同じ台詞をヘディンに言った。しかし、口調は穏やかだった。
「これでいい。こうするしか、ファーナを救ってやることは出来なかった。後は…ヤツの手に掛かってる」
ラークはヘディンの肩に手を置いた。若干、震えているのが解る。
「…そう思うのなら、悲しむ事は無いだろう?」
ヘディンにとっても不本意だった。まさか最悪の事態がそのまま結果となるとは、考えが及ばなかった。妹が『堕天使』を呼び覚ましたと言う事実は、暗くヘディンの胸に突き刺さったままだった。
禁忌を犯した妹を、すぐに憎んだりするようなことなど出来なかった。今はただ、それでも愛おしい妹を遠ざけることが、最良だと思った。しかしそれは同時に、『堕天使』を野放しにするのと同義だ。結局、『堕天使』を討つことはすなわち、妹を討つことと同義なのだ。
「…俺も…『赤天使』失格だ」
涙が一筋、ヘディンの頬を伝っていった。