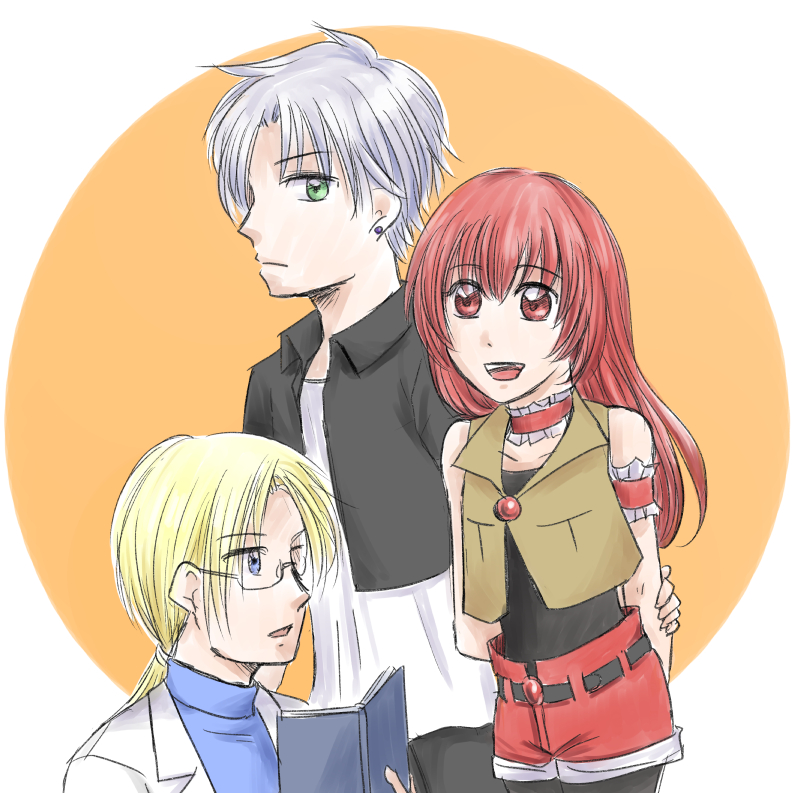もう日が傾きかけている時間。書道教室に向かう道すがら、名取裕也は忘れ物に気づき、慌てて生徒会室に戻った。
幸運なことに生徒会室には人がまだ残っていたらしく、窓から蛍光灯の光が見えた。
「名取、どうしたの。そんなに息を切らして」
残っていたのは生徒会長の高峰綺羅だった。翡翠のような色の瞳を丸くしてこちらを見ている。手元には、自分の「忘れ物」――文芸部の次回の部誌の校正用の原稿があった。
「それ!お前が持ってるそれを取りに来たんだ。家で校正しようと思ってたんだよ」
「あっ、ごめん。つい面白くて読んじゃってた」
はい、と高峰は原稿を差し出す。
「面白くて?」
鞄の中に原稿を入れながら、高峰に質問をする。普段、周囲にそれほど興味を示さない男なのに、食いついてきたのが名取にとって新鮮だった。
「うん。特に、相手の居ない交換日記の話のやつが。少し悲しいホラーだよね」
「ああ、それか。1年の小川のだな。実体験を元にしてるって言ってたな。小学生の頃に交換日記をしていて、一緒に小説家になろうって励まし合ってた友人が急に亡くなったんだけど、お墓がどこかも忘れちゃって、もし覚えてたら、こうやって日頃の事や自分の作品を、墓前に添えて報告したいんだ、って」
「ふーん……。そうなんだ、ありがとう。もの悲しさの理由が何となく分かったよ」
高峰はにこりと笑ってこちらを見た。
「興味あるなら、部誌、出来たらやろうか?一週間後には刊行する予定だけど」
「いいの?ありがとう。助かるよ」
助かるよ、という言葉に何だか引っかかりを覚えたが、余りがちの部誌を一冊でも多く頒布できる喜びには勝てなかった。また明日、という言葉を残して、名取は書道教室へと駆けていった。
*********
日はすっかりと落ち、宵闇が辺りを包んでいる。
白凰高校の灯りも今日はすべて消えている。そこまで多く設置されていない街路灯の薄ぼんやりとした光は、隣接している市営墓地の不気味さをより一層際立たせている。
その不気味さこそが居心地がいい、と青年は思いながら、一人で市営墓地の中を歩いていた。ある一つの墓の前で、足を止め、「お邪魔します」と一礼して敷地に上がる。
「これ、君の友達が書いた文が載ってるよ」
青年は墓石の前にしゃがみ、持っていた文芸部の部誌を、墓石に向かって開いて見せた。
「……君の事を忘れちゃったわけじゃないよ。君に会いたくても、どこに居るか分からない気持ちを、この文章にしたためてるんだ。よかったら、読んで聞かせようか。……えっ、読める?君、小学校3年生くらいだよね?難しい漢字、いっぱい知ってるんだ、すごいな」
ぺら、ぺらと、誰かが読んでいるのに合わせるように、青年はページをめくっていく。目当ての作品のページをすべてめくり終えると、心配そうな表情で、青年は墓石を見つめた。
「嬉しかったんだね、忘れられてなくて。……うん、君が落ち着くまで待ってるよ」
青年はそう告げて立ち上がり、ぼんやりと周囲を眺める。ふと、木枯らしが吹く。周りの木々がざわざわと音を立てていく。その音に耳を澄ませながら、青年は次の言葉を待っていた。――そう、ずっと待ち続けている言葉を。
三十分はそうしていただろうか、ふと墓石を見下ろして、青年は口を開いた。
「――もう、いいんだね、『次』に行っても」
ワイシャツの一番上のボタンを外し、制服のネクタイを緩め、首から提げている十字架を取り出す。そっと口元に持っていき、軽くキスをしてから、青年は、墓石に右手を掲げた。
「主よ、彷徨える彼の魂を、正しき道へ導き給え――」
墓石の前に、ふわっと、小さなつむじ風が発生し、天へと昇って消えていった。その様子をしばらく見届けて、青年は墓の敷地から通路へと出た。
「僕だって忘れないよ。大切だった人のことは、何年経とうが、ずっと」
墓石を振り返り、つぶやきを残して青年は立ち去った。
**********************
時期的には、綺羅くんが2年生の秋の話。
名取くんは生徒会の書記を務めながら文芸部にも入っています。名取くんにはもう一つ重要?な設定があるのですが……そのうち披露できるといいな。
9話10話なんなら11話以降のネタバラシですが、「彼」はこういうことをずっとしていました。
難しい漢字をいっぱい知っているんだ、という言葉に、国語が苦手という設定をにじませています(笑)