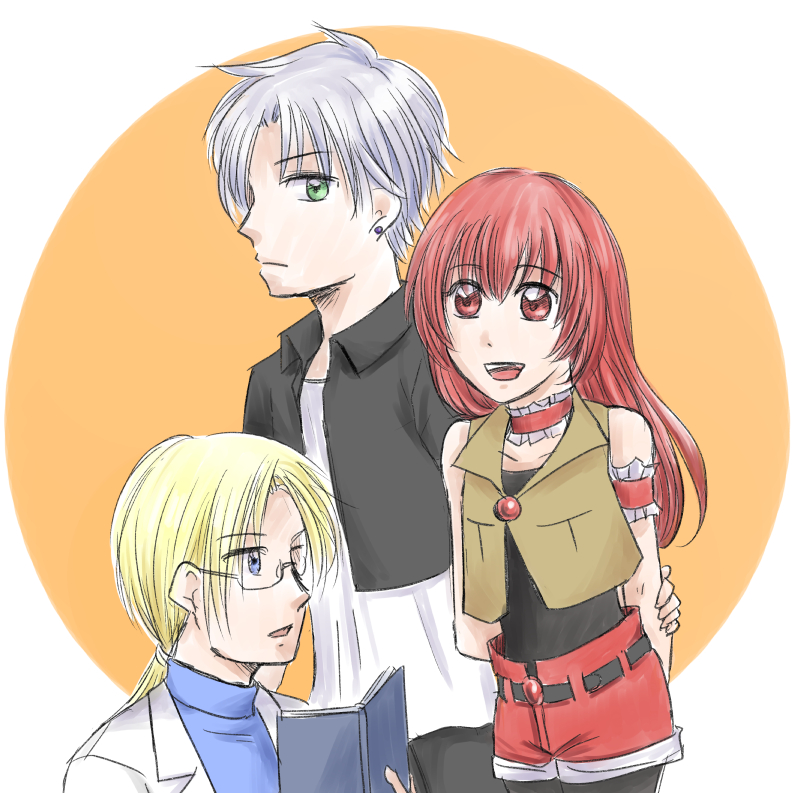意識が遠く、遠く遠ざかっていく。
外の音も、光も、だんだん感じられなくなってくる。
――なのに、何かが聞こえてくる。
不思議と優しくて、どこか懐かしい言葉。
…一体、どこで聞いたんだろう。
このまま飛んで街へ降りるのは目立つと判断し、カティスは街中に程近い山道で降りて歩くことにした。時刻は昼時。そもそも人一人担いでいる状態で街中を闊歩するのも躊躇われる。どうしたものか、と思案していた時だった。
「――っ!」
先の下り坂から、人が登って来る気配がした。しかし、行くも進むも一本道だ。警戒しながら、平静を装って普通に歩く。
やがて見えたのは、ファーナより幾分か年上の青年だった。日差しを避けるためか、頭には白い布を巻き、ところどころから短い茶色い髪が覗いて見える。籠を背負っており、山菜取りにでも来ているかのような風貌だ。
すれ違い様に会釈をしようと、青年が顔を上げた。カティスと目が合い、その後、背負っているファーナに気付いて目を丸くした。
「―え、あ、ちょっと待って下さい!ファーナ…!貴方の背負ってる女の子…ファーナじゃないですか?!」
しまった、と内心でカティスは呟いた。ファーナはかつてこのエルガードに留学していたと言っていた。知り合いがいてもおかしくはないのだ。呼吸を整えて、すれ違った青年に振り向き直った。
「どうして…、行方不明になったって前布告が…」
「…家出、だとよ。だが今はそれどころじゃねぇんだ。さっき魔獣に襲われちまって、毒を食らったみたいでこの様だ。今は俺の魔法で応急措置はしてあるが…」
以前にも彼女自身が使っていた言い訳と状況を、カティスはさらりと述べる。すると青年の顔が強張った。
「ちょ、ちょっと降ろしてもらえませんか?容態を看るので」
「?お前は…医者か何かなのか?」
訝しげな顔をしたカティスを見て、青年ははっとした。
「あ、申し遅れました。僕はティオって言います。ファーナとは同じ下宿の仲間だったんです。…一応、医者を目指している身なので」
「…そうか、それは渡りに船だな」
カティスはファーナを背から降ろした。地面に横たえるが、相変わらず青白い顔で息は細く、容態は変わっていない。
「…これは…」
ティオが厳しい表情で呟く。背負っていた籠を下ろし、数枚の薬草と小さなすり鉢を取り出した。
「どうなんだ?」
「…やっかいですね。もしかして、大きな蜂型じゃなかったですか?」
話しながらティオは慣れた手つきで薬を擂り始めた。
「ああ。有名なのか?」
「強毒性という意味では、そうですね。昔それで、尊敬していた方を失いました」
ティオの声が暗くなる。
「お前のその薬は…」
「一応、解毒剤を調合しているんですけど、気休めにしかならないですね。とにかく街に下りないと」
すり鉢に水を入れて、ファーナの口元に持っていく。
「飲んでくれるといいんですが…。あ、よかった」
ファーナの喉がごくりと上下する。ティオはほっと一息吐いて立ち上がった。
「行きましょう。ここからはそんなに時間はかかりません。急がないと…」
カティスはその言葉を聞きながら、再びファーナを背負う。
「なるべく、人に見つからないようにしたいんだが」
その言葉に、一瞬ティオは疑問を持ったが、すぐに意味を理解した。
「大丈夫です。ファーナのあの布告ですよね。ここでは出た後すぐに取り下げられましたから、連絡する人はいないと思いますよ」
「取り下げ…?どういうことだ?」
カティスは訝しんだ。
「いくら中立国だからって、利益にも毒にもならないようなものまで干渉しないもんなのか?…こいつが見つかって、エルガードに何か問題でもあるってのか?」
ティオはしばらく、うーんと唸ってから答えた。
「何もないと思いますけど…それは長老会の判断ですから。…まあ、慎重を期するほうが無難ですね。僕の下宿先まで、なるべく見つからない道を行きましょう」
下宿「アドネス」。
家庭的な雰囲気のある、初老の夫婦が営む、こぢんまりとした留学生用の下宿である。
もう陽が落ちかけていた頃、その下宿のドアが開いた。台所にいた女主人のメアリーは、ダイニングに出てきてそのドアを開けた人物を迎えようとした。
「メアリーさんっ!」
「いつもより早いねぇ、ティオ。…と、そちらは?」
メアリーはティオの後ろにいる銀髪の青年と、彼が背負う赤毛の少女に見て、目を見張った。
「…ファーナじゃないか!行方知れずって前…」
「話は後!ファーナの部屋、まだ空いてましたよね?すぐ使えますか?」
「え?ちょっと待ってね、オルバ!」
メアリーは上の階に上り、部屋にいる下宿生を呼んで、あれこれ準備をさせる。直ぐに階下に戻って来て、ファーナの顔を覗き込む。青白いその顔を見て、メアリーは眉を顰めた。
「…まさか、この顔色…」
「魔獣の毒にやられた。今はこの兄ちゃんの解毒剤で何とかごまかしているが、根本的には解決してない」
その言葉にメアリーの表情が険しくなる。
「いいよ、メアリーさん!」
上階から、女性の声が聞こえた。
「はいよ!じゃあこっちに来ておくれ」
焦るような足取りで、メアリーは階段へ向かう。カティスもそれに続き、二階の一室に通された。整えられたベッドにファーナを横たえると、カティスは一つ息を吐いた。ファーナの顔色は変わらず青白いまま、息は細い。
「これじゃあ、リアンさんの時と全く同じじゃないか…」
メアリーが震えた声で呟いた。
「そうなんです…。襲ってきたのも、多分」
「…リアン?そいつがさっき言ってたお前の尊敬してたって奴なのか?」
カティスが顔をしかめてティオに聞く。
「ええ。当時このエルガード一の魔術士だった方です。例の魔獣が大量発生して、討伐しに行ったんですが…。って、話してる場合じゃないですね。僕、学院に薬が無いか当たってきます」
小走りにティオは下宿を出て行く。それと入れ違いで、くせのある金髪の少女が部屋に入ってきた。
「お湯とタオル、持ってきたよ、メアリーさん」
彼女も不安そうな表情を浮かべていた。桶とタオルをベッド横のチェストの上に置くと、冷たいファーナの手を暖めるように握って目を閉じた。
「ファーナ…頑張ってよ。こんな再会、ないじゃない…」
今にも泣きそうなオルバの肩を、メアリーがポンと叩く。
「今ティオが学院に行ったわ。何か…きっとあるはずよ」
オルバはそれを聞いて少し落ち着いたらしい。ベッド際から離れて、ふとカティスの方を見る。
「…貴方が、ファーナを…攫ったの?」
「…だったら?」
カティスはこんな状況にも関わらず、傍目には動じてないように見えた。その態度が、オルバの怒りを買った。
「それなら、私は貴方を許さない!せっかく、せっかく大好きなお兄様と一緒に暮せるようになったのに!その幸せを壊して、挙句死なせてしまうのなら…!」
「その幸せを破ったのはコイツ自身だぜ?コイツは家出だよ。俺はたまたま居合わせただけだ」
え、とオルバは言葉を詰まらせた。
「そんなわけ無いわ!だってファーナは…」
「知るか。起きたら聞いてみろよ。多分理由は誰にも言わねぇだろうけどな」
そう言って、カティスは部屋の入口へと歩き出す。
「どこに行くのよ?!」
「…あの兄ちゃんがもし、解毒剤を手に入れられなかった時に備えて、もう一つの手段を用意しておかなきゃならねぇ。…メアリー、その魔獣にやられて死んだのはリアンって奴で…間違いないんだな?」
「あ、ああ、そうだけど…」
そこでメアリーとオルバははっとした。目の前の青年の向かう先は分かったが、何故そのことを知っているのだろう。
「んじゃ行って来る。なるべく早めに遣すから、ちょっと待っててくれよ」
下宿から早足で5分程のところにある、三階建ての古びた建物の前で、カティスは足を止めた。壁には蔦が這い、人によっては一瞬おぞましさを感じるような外観だ。表には小さく、「エルガード歴史博物館」と書いてある看板がかけられており、その上から更に『クローズ』の札が掛かっていた。
カティスはそれを一瞥してから、慎重に扉を開く。ギィイ、という重い音と共に、薄暗い室内に橙の夕日が射す。その光が照らす先に、一人の人影が見えた。
「――来た、か」
その人影の居る部分の燭台にだけ、ふっと明かりが灯される。金の髪が、その光を受けて闇に煌く。カルディアで仕掛けてきた魔術師――ファーナが『先生』と言っていた男が、そこには立っていた。
「…まるで俺を待っていたみたいじゃねぇか。クラーテ家の…いや、黄金竜の末裔…ラークって言ったか」
ラークの元へカティスは近づく。足音がいやに室内に響いてくる。ラークは無表情のまま、その場から動かなかった。
「南へ行くなら、この街を必ず通ると思っていた。それに…血が、騒ぐのでな。…ところで、わざわざここを無視せず現れた理由は何だ?」
「アンタと姫さんの兄貴の思惑通り、姫さんは生かしてやってる。…だが、さっきここに来る途中で魔獣に襲われてな。アンタも知ってるだろ?でかい蜂みたいなやつさ」
ラークの表情が強張る。
「…先代が死んだ原因。なら、アンタはそれを治せるスペルを組んであるはずだ。…いや、アンタじゃなくても、精霊共が知ってるはずだ。…そう思ってな」
ラークが値踏みするような目でカティスを見る。信用されてないのだろう。カティスには重々承知のことではあった。
「…成程、事情はよく分かった。確かに…スペルは組んである。だが…それをそのまま信じる訳にはいかんな」
「!アンタ…妹同然の教え子の命は後回しなのかよ!?」
「『そういう物言い』が信用ならん。…『堕天使』と言われた貴様が、他人を慮るだと…?」
ラークが右手を広げる。カティスはその動きにつられ、腕の先に架けられていた絵を見た。
「――っ!」
カティスは息を詰まらせた。大満月の逆光に照らされ、黒く描かれた『天使』の絵。驚きの表情を隠せないカティスを見て、ラークは眉間に皺を寄せた。
「たった一人、貴様は『何を成す為』この世界へと来た!貴様の『真実』…『裁かせて』もらうぞ!」
その言葉と同時に、空気が、景色が変わった。何も無い、広い空間が目の前に開けた。
「…たいした詠唱も無しに空間転移か…。随分と高位の魔術師様で」
茶化すようにそう言って、カティスは剣の柄に手を掛ける。
「この程度なら、『守人』でなくとも時空は操れる」
右手に光の刃を作り出し、ラークも構えた。
「へえ…。ちゃんと勉強してんだな。あの腑抜けの『監視者』の一族も、地に堕ちてから火が点いたか」
「戯れ言を…。その口、二度と利けないようにしてやろうか!」
ラークがカティス目がけて斬りつける。予想外の速さに、カティスは反応が遅れた。かわしたが、頬に切り傷が出来た。
その血を指で掬い取り、舐める。
「…上等だ。やってやろうじゃねーか」
カティスの口の端には、笑みが浮かんでいた。
気が付くと、見慣れた天井がそこにあった。身体がとても重くてだるい。一体何をしていたんだっけ。
「…?…あれ…、ここ…」
ファーナの言葉に、ベッド脇で看病していたオルバが気付いた。
「ファーナ!気が付いた?」
ファーナはオルバの姿を見て驚き、目を見開いた。ゆっくりと身体を起こそうとするが、具合が芳しくなく上手くいかない。
「うっ…」
「無理しないで、ファーナ。寝てないと」
オルバが慌てて立ち上がり、ファーナをベッドに戻るよう促す。言われるがまま、ファーナは再び布団に戻り、顔だけをオルバの方に向けて、疑問をぶつける。
「何でオルバが?それにここ…」
「アドネスのアンタの部屋だよ。魔獣にやられて、毒が全身に回って、ずっと意識を失ってたの」
「…魔獣…そうだ私、おっきな蜂の魔獣に刺されて、それで…」
ファーナは額に手をやって、思い出そうとする。それ以上、思い出せたことは、何か、安らぐような声が聞こえたことだけ。
「具合どう?大丈夫?」
「うん…なんか、すごく身体だるくて重い…。グラグラするし、吐き気するし、寒気もするし…」
そこでふと、今までずっと一緒だった人物の姿が無いことに気が付いた。
「…ねえ、カディ…あの、銀髪の男の人、一緒だったよね?どこにいるの?」
「ああ、あの銀髪の人?ラーク様のところに行ったけど…」
その言葉を聞いて、ファーナは途端に表情を曇らせた。
「えっ…」
「だ、大丈夫よ。呼びに行っただけだから、すぐ戻ってくるわよ」
ファーナの不安げな表情に、オルバも不安になった。いつもなら、嬉しそうな笑顔を浮かべてくれるのに、真逆の反応だ。いつの間にか仲違いでもしたのだろうか。
「だ、だめ…。先生は駄目…。きっと私のことも、カディのことも殺そうとする…」
「え??あんた今なんて…」
仲違いどころではない物騒な言葉にオルバは顔をしかめる。しかしそんなことはお構いなしに、ファーナはむっくりと起き上がった。
「…私、先生のところに行って来る!」
無論、オルバはそのファーナを止めようとする。
「ふぁ、ファーナ!そんな身体じゃ無理よ!っていうか、殺されるってどういうことよ!」
「身体は大丈夫!何とかなる!」
そう言うと、手近にあったサンダルを履き、ファーナは飛び出していった。
「ファーナっ!何ともなる訳ないじゃない!」
ファーナには制止の声など聞こえなかった。真っ直ぐ、博物館へと走る。体調の悪さは、微塵も感じなかった。
(昔言ってた…。先生は、『堕天使』のことが、元凶が憎いって…!)
光刃が容赦なく降り注ぐ。剣を抜いたまではいいが、カティスは間合いを詰められずにひたすら回避に徹底していた。
「ちぃっ!」
走り続けて流石に息が上がってくる。接近戦に持ち込めないという、分の悪い状況だけではない。どう考えても相手の能力が想像以上なのだ。詠唱から発動までの時間の短さ、威力、どれをとっても混血の進んだ竜人とは思えない。
「混血の癖に…。黄金竜の血統ってのはどうなってんだ…」
思わず洩れたカティスの呟きに、ラークが答えた。
「…先祖返りさ。お陰で、生まれながらの殺人者…『呪い子』だ」
「!」
その時、一瞬隙が出来た。柄を握りなおして一気に間合いを詰める。
『氷瀑!』
剣を振り下ろそうとしたその時、目の前に氷の盾が現れた。剣がはじき返された勢いで、カティスはバランスを崩して着地した。距離はまた幾分か離れてしまった。
「…成程、それなら納得だな。その力も、俺に対するその憎悪も」
衝撃で痺れた右手を振りながら、カティスは挑発するようにニヤリと笑みを浮かべて立ち上がる。
「こんな悲劇は…いや、あの戦争の惨劇も、この五百年間で生まれた悲劇も、貴様がこの世界への『門』を開いて堕ちたことが原因だ!多くの同胞を殺し、この世界に混沌をもたらした貴様は…、再び目覚めた今、更なる悲劇をこの世にもたらすつもりか!」
ラークの言葉に、カティスは苦笑いを浮かべた。
「だとしたら、どうする?」
「『裁く』までだ!」
ペンダントの水晶を握り、ラークは詠唱を始めた。カティスはそれを一瞥し、小さく舌打ちする。
(さっきまでのは無駄撃ちじゃなかったってことか。精霊数が圧倒的に不利だな…反属性の俺の術じゃあここから巻き返しできない…)
しかも、これほどの手練れが詠唱するということは、それだけ強力な術と言うことだ。どうにかしなければ、本当に命に関わる。
『我が血に依りて来たれ、裁きを下す光の賢者よ…』
(ちっ、ヤな感じのスペルだな…。…こっちならどうだ!)
カティスも剣を構えて詠唱を始める。
『時と空を統べし移ろいたる者達よ、我が名と血の元へ集え…』
(…この詠唱、まさか)
ラークはカティスの詠唱に疑問を持ちつつ、続ける。
『闇を裂き、闇を裁け。世に暁光をもたらし給え…我と共に下さん、光の鉄槌!』
ラークの術の発動が速かった。巨大な光線が、カティスめがけて飛んでいく。
(ちっ…間に合わねぇかっ!)
大きな爆発音が、室内に響き渡った。
足元が揺れた気がした。ファーナは丁度、博物館の前に着いたところだった。
(地震…?)
しかしそんなことに構ってはいられなかった。躊躇無く、ファーナは扉を開けた。既に客の姿は無く、今にも落ちそうな夕日の淡い光が、静寂に包まれた室内を細々と照らしている。
「先生―!カディ!いるなら返事してー…!」
そう大きな声で呼びかけながら奥へと進んでいくが、自分の声が反響するだけで返事は返ってこない。すると、奥からランプと雑巾を持った茶髪のツインテールの少女が現れた。白いフリル付きのエプロンをしており、どうやら博物館で手伝いをしている学生のようだった。
「あの…申し訳ないんですが、今日はもう閉館で…お連れの方とはぐれたんですか?」
ファーナより2歳ほど年下だろうか。背の低いその少女に目線を合わせるように、ファーナは屈んだ。
「ラーク先生、どこにいるか分ります?」
「先生?えーっ!ラーク様にご師事なさってたんですかぁ!」
何故か少女は目をキラキラと輝かせて、全く別のことに感激している。
「あー…えっと、それはいいですから!もしくは、銀髪の男の人…見かけてませんか?」
少女はうーんと唸り、思い出そうとする。
「いいえ、見ていませんね。あたし、ついさっきまで上の階にいたんで、その間に階下に行かれたのかも…」
下の階。ファーナはこの建物の下にもいくつかフロアがあることを思い出した。
「…さっきの揺れ…。分かったわ、ありがとう!」
少女を置いて、奥の執務室へと向かおうとしたが、呼び止められた。
「あ、そっちは関係者以外…」
ファーナは振り返って、告げる。
「…大切な人達が、ケンカしてるかも知れないの。だから、止めに行かなきゃ」
「それって、ラーク様も?」
「そう」
それを聞いて、少女は一念発起したかのように握り拳を作って前のめりに大声で言った。
「わ、私も行きます!」
「駄目よ、危ないかも知れない。ここでお手伝いか何かしてるのよね?なら知ってるでしょ?ラーク先生の強さ」
しかし少女は胸を張って、言う。
「あたしは一度死にかけてますから、へっちゃらです」
それは違うでしょとツッコミを入れようとしたが、多分引き留められないと思った。
「…分かったわ。でも無理はしないでね?私はファーナ。貴女は?」
「コリィです。ラーク様に命を救われて、それからこうしてお手伝いを無理矢理させて貰ってますっ」
胸を張って答えたコリィに、どおりで、と、心のどこかでファーナは独り言ちた。
視界が晴れてくる。しっかりと佇んでいる男の影を確認して、ラークは息を飲んだ。
「…正直、恐れ入った。今のが『守人』の本領、というところか…」
視線の先には、寸でのところで光線を留めるカティスの姿があった。勿論、無傷である。
「精霊の時を止めてしまうとはな…」
『汝らが在るべき場所へ移ろえ』
そうカティスが声を掛けると、たちまちその光線は消えて無くなった。剣を下ろし、腰に手を当てて、カティスは口を開いた。
「いい加減にしろよ。折角アンタらの意向を俺が飲んでやったってのによ、アイツが死んだら元も子も無いんじゃねぇのか?俺の始末なんて二の次だろうが」
「貴様を倒したら行ってやる」
ラークは手に氷の剣を召還し、カティスに向かって駆け出した。カティスは溜め息をついて構える。
「…ったく、強情なヤツだな…」
左からの一閃を受け流す。更に素早く切り返してきた一撃をかわし、こちらの剣を振り下ろす。しかしそれも受け止められてしまった。
(くそっ、このままだとまずいな…)
カティスは次第に焦りを感じ始めていた。
「…あたし、ラーク様に助けて貰った時から、感じてたことがあるんです」
古びた石製の螺旋階段を、ランプを照らしながら降りるコリィが、ぼそっと後ろのファーナに話しかけた。
「とても綺麗なのに、心の中にはとてつもない闇を持ってるって…」
「どうして?」
二人の声は暗い空間にこだまして響く。それが一層、二人の不安を掻き立てさせる。
「何か、すごく遠くを見てたの。虚ろな顔をして…。ほら、強い陽差しって、建物に当ったらその分濃い影を作るでしょう?…何か、そんな人だなって…」
言い得て妙だとファーナは思った。五百年前の歴史を語るときに見せた、恐ろしいと感じるまでの憎悪を見せた時の彼は、まさしくそうではなかったか。
暗い中を照らすランプの光。それはまた、壁に二人の影を色濃く作り出している。時に光は揺れ、その度影もまた揺れる。ファーナは、コリィの言葉を反芻しながら、その影を見つめて階段を降りた。
やがて目的の部屋の前まで辿り着くと、岩が壊れるような音が聞こえてきた。
「―…ここみたいね。危ないから、私が先に行くわ」
先を歩いていたコリィを後ろにやり、ファーナは鉄製の扉に手を掛けた。
キン、と金属音が鳴り、カティスの手から、剣が離れる。宙を舞い、とても手を伸ばしても届きそうに無い場所に落ちてしまった。
「今度こそ…チェックメイトだな」
気を取られている間に、カティスの眼前に氷の刃が向けられた。しかしカティスは表情を変えずにラークを真っ直ぐ見つめた。
「アンタは、何のために俺に刃を向ける?俺を殺せば、世界が平和になるとでも思ってんのか?」
「…そうだな。貴様が今後この世に何かをしでかすことは無くなるだろう」
その言葉にカティスはふっと笑った。
「…アンタも、何も知らないんだな…。いや、知らなくて当然か」
「何…?」
ラークの顔に、怒りの表情が浮かぶ。歴史研究なら、世界中の誰よりも第一人者であるという自負がある。それを真っ向から否定された気分になった。
「…やってみろよ。自らが『裁いた』その結果、後悔しない自信があるならな…!」
「何を訳のわからないことを…。ならば、望みどおりに…!」
ラークが刃を胸に突き刺そうとしたその時だった。突然、左手の壁が音を立てて開き、少女二人が駆け出してきた。
「だめっ…!」
その声の方向に二人は顔を向け、一様に驚いた。
「ファーナ…お前」
「コリィっ!何故お前が…」
二人が驚いている隙に、ファーナはカティスの目の前に両手を広げて立ちふさがった。カティスを庇うように。
「ファーナ、どういうつもりだ。まさかそいつに情が移ったか」
ラークは刃を下げなかった。ファーナの首元に、ひやりとした空気が流れる。そんなことは気にせずに、ファーナはラークを睨んで毅然とした態度を崩さなかった。
「…先生にはさせない。これは私の責任だもの。私が禁忌を犯したことは、私が何とかする。だからそれまで誰にも手出しなんかさせないわ」
ラークもカティスも目を見開いた。しかしすぐに、嘲るような冷たい笑みをラークは浮かべた。
「…お前にそいつが御せる訳がない。諦めろ」
「嫌よ。それなら私はどうすればいいの?汚名を着たままこれからずっと、生きることになるの?私には帰る場所はない。…そうでしょ?だから私は、無理でも私自身の手で決着を付けたい。無理ならそこでカディに殺されればいいわ!」
それを聞き、ラークは刃先を下げてファーナの方に近づいた。手を顔に差し出そうとしたのを見て、ファーナはきつく目を閉じた。
(殺される――)
しかし、ファーナの想像とは違い、こつんと軽く額を叩かれただけだった。
「えっ…」
ファーナは目を見開いた。そこには、この国に留学していたころに見ていた、優しいラークの顔があった。
「馬鹿か。死んでしまえば、その責任も果たせなくなるだろう?ヘディンが悲しむぞ」
「…え?…だってお兄ちゃんは」
自分を殺そうと、剣を向けていたじゃない。
そう告げようとしたが、ラークの優しい眼差しがその言葉を封じた。でも、それならどうしてあんなことをしたのだろう。
「…だから私がここにいる。闇の対極、光の力を持つものだけに与えられた特権。彼の者を『監視』し『裁く』力…。私だけが、この男の罪を裁くことができる」
ファーナの肩をそのまま自分の方にやり、奥にいるカティスに近づこうとする。
「!先生!」
ファーナが叫んで呼び止めようとする。しかし、彼の動きを止めたのは、右手を掴んだコリィだった。
「コリィ…何のつもりだ。部外者のお前に止められる筋合いはないぞ」
「そうかもしれません。でも、私、この人がぱっと見て悪い人には見えないんです。この人の罪ってなんですか?そしてどうしてラーク様だけが裁けるって言うんですか?」
ふうと一息、ラークは溜め息をついて、宥めるように言う。
「…昔、この世界を滅茶苦茶にした張本人だからだ。こいつは強大な力を持っていて、今またこの世界を滅茶苦茶にするかもしれない。…こいつを止められるのは、私の一族だけなんだ」
「反省してるかもしれないですよ?そして、今度はいいことをしようとしているかもしれません。それを見極めずに、ただ悪い奴って決めつけるのって、ただの言い掛かりじゃないですか!」
「言い掛かり…だと」
その言葉に、ラークは表情を強張らせた。それに気がついて、ファーナが慌てて意見する。
「あのっ!先生、私ね、それを見極めたいって思ったの。見極めて、本当に悪いことをするのなら、その時どうにかしようって。今まで、そんなに悪さはしてないよ。むしろ、優しいくらい…」
「それを情が移ったと言わずして何と言うんだ、ファーナ?」
ラークは呆れたような口調でファーナをたしなめる。しかしファーナはかぶりを振った。
「違うの。情が移ったんじゃない。私が見てきて感じたこと。そして考えてること。…先生、いつも言ってたじゃない。自分で見聞きしたことだけが『真実』だって!カディは、悪いことしようとしてるのかもしれないけど、悪い人じゃない。…それが、私が見た『真実』よ!」
ファーナは、自分の言葉に嘘偽りはないと信じて疑わなかった。ラークの青い瞳を捉えて決して目線をそらさず見つめ続けた。
「ファーナ、お前…」
ラークの胸に、ファーナの真剣な表情が突き刺さる。ファーナは本気だ。自らの信念を突き通そうと一途になるところは、兄ヘディンとよく似ている。
(ファーナの見た『真実』か…)
ファーナの言葉を心の中で反芻し、ラークは氷の刃を消した。それまで大した時間は経っていないはずなのに、随分長いように感じられた。
「先生…?」
「…分かった。お前が見た『真実』…それを信じよう。…命拾いしたな、カティス」
後ろでむっすりとした表情を浮かべているカティスに、ラークは声を掛けた。ファーナはその言葉に安心して、ガクリと膝から崩れ落ちた。
「おい、ファーナ!」
「だ、大丈夫…。緊張がほぐれた、だけだから…」
眉間に皺を寄せて、痛みや辛さを耐えているような表情をファーナは浮かべている。顔色は相変わらず青白い。屈んでファーナの様子を窺うラークに、ファーナはしがみついた。
「…丁度いい。ファーナ、これを握っていろ」
ペンダントの石を、ファーナの手に握らせる。
『来たれ、光の王よ。我らが無念、晴らすために』
ファーナが握っている水晶から、まばゆい光が発せられる。
『彼の者の裡の邪なる影を、汝が威光でかき消し給え。彼の者の裡に満ちて、癒しをもたらせ給え』
ふわりと、優しい光がファーナを包む。苦しそうだった表情はやがて穏やかになり、安らかな寝息を立てて全体重をラークに預ける格好になった。
「だ、大丈夫なんですか?」
コリィが心配そうにファーナの顔を覗く。
「ああ。…2、3日経てば、体調も元に戻るだろう。アドネスに…」
階上からかすかに聞こえてきた声に、次の言葉は遮られた。
「ラークさまーっ!どこですかぁー!ファーナ、ここに来てませんかー?!」
「…オルバさんですね。あたし、先に上に行ってます」
コリィが小走りに部屋を出て行く。残されたラークとカティスは、互いに顔を見合わせた。
「…ほら、連れて行け。あまり長居すると、今度はお前が光の影響で倒れるだろう。二人も担ぐ力は私には無い」
ラークはファーナを持ち上げて、カティスに託そうとする。
「もうクタクタなんだけどな、アンタのせいで」
渋い顔をして、暗に拒否する。ふ、とラークは笑みを浮かべた。
「お前が攫って行ったんだ。最後まで面倒見ろ」
「元はと言えば、アンタらが押し付けたんだろーが…」
ちぇっ、とカティスは舌打ちして、しぶしぶ受け取る。
「念のため、明日病状を見に行ってやる。疲労もたまっているだろう。しばらくこの街に逗留しているといい。カルディアには通報しないからな」
「…偉そうだなぁ、アンタ…。ま、お言葉には素直に甘えるとするか」
ファーナを抱えてカティスはゆっくりと出口へと向かって行った。部屋に一人きりになると、ラークは長い溜息を吐いた。落ち着いた、と思った瞬間、ペンダントの水晶が淡く光った。
『ロストールの心配は、杞憂に過ぎた…と判断すべきかな』
ラークにしか聞こえない声なき声。光の精霊術で用いる言葉で、それに応える。
『…いえ、私はやはり…己の感情に流されていましたから。ファーナやコリィの言葉で少し頭が冷えました。この数週間、傍に居続けた者の方が『真実』に近い』
寂しそうにラークは微笑んで、首から提げている水晶を見る。
『…まだまだ、ですね、私は。あんな子供達に諭されるなど』
『それでいい。それが解っただけでも、充分だ。…ようやく、我らを行使するに値する精神を持てるようになったな』
ラークはその言葉の意味を理解できずにいた。しばらくの沈黙の後、その意味に気が付き、ようやっと口を開いた。
『…貴方がたには、これまでは当主として認められていなかった…と?』
無理もない、と心の中で反省する。それだけ己の妄執に駆られていたのだ。そのような心構えで、精霊達を行使することなど、行使される精霊達が嫌がるに違いない。
『忘れるな。我ら光の精は、邪念なく誠実な心を持ち、総てを公平に裁き、正しき道を示し、育む者。行使者たる者もまた、そうあらねばならぬ』
右手で水晶を固く握る。目を閉じ、静かにその声に応える。
『ええ…。肝に銘じます』
再び目を開け、虚空を見つめる。その顔には、晴れやかな表情が浮かんでいた。