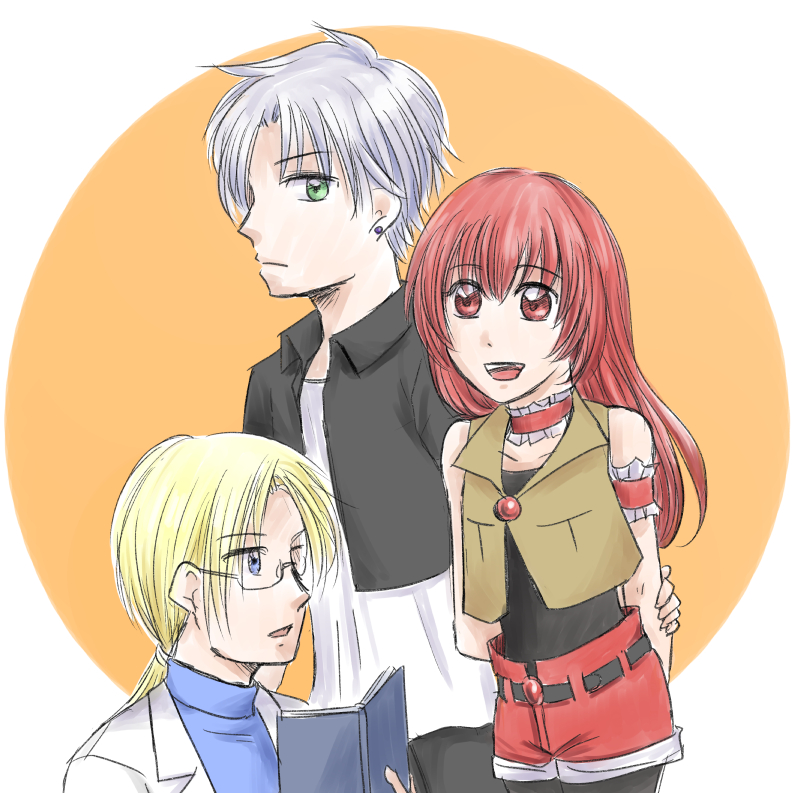ひらひらと、雪が舞う。
空には厚い灰色の雲が立ち込めていた。目の前に見えている北方の山脈の頂は、すでに白くなっており、平地の草木も枯れて、長い冬への身支度を終えている。
「うーん、頃合い、っていうのもあるけど、何か引っかかるのよね…」
一人の女性が、見張り塔ほどの高さで宙に浮きながらポツリと呟いた。身に纏う蒼いカルディア宮廷騎士団の制服は、色を失くしつつあるフィリアとの国境地帯に映える。長い癖のある緑の髪を押さえ、集中するように目を閉じた。
「――っ!」
妙な音を聴いて、はっと目を開けた。眼下に、巨大な猿のような魔獣が3頭走っているのが見えた。北の山から下りてきたのだろうか、南のほうへ向かっている。
「流石辺境、って感じ?…黙ってもいられない、か」
魔獣めがけて急降下する。数本のダガーを懐から取り出し、軽く詠唱する。
『風よ、刃に纏いて彼の者を切り裂け!』
勢いよくダガーをそれぞれの魔獣に向けて投げる。その一本ずつに、カマイタチのような衝撃波が乗る。空からの不意を突かれた攻撃に気付かぬまま、スッパリと魔獣の身体が裂けた。
「…ふう。今年は不作ってワケでもなかったのになぁ」
音を立てず、ゆっくりと大地に降りる。魔獣の亡骸をまじまじと眺めていたが、すぐに違和感を覚えた。
「…こいつ、見たこと無い…。図鑑にも載ってないんじゃ…」
「そーなんだよなー。最近そういうの多くてさぁ」
突然、後ろから男の声がした。彼女には聞き覚えのある声だった。
「…その声、ノエル?!」
はっとして振り返る。そこには、同じ緑の髪を持った青年が立っていた。少し厚手の服を着て、首にはマフラー代わりの黄色いスカーフを巻いていた。
「よ、カリーナ。奇遇だな」
相変わらず軽い調子の喋り方だ。驚くカリーナを他所に、ノエルは魔獣の遺骸の傍まで風を切って歩み寄った。
「何でアンタがここに…」
カリーナの疑問に、呆れ顔で振り返ってノエルは一つ溜息を吐いた。
「そりゃこっちの台詞だよ。お前、よりによってカルディアに派遣されてんのかぁ?」
「よりによってって…アンタはまさか、フィリアにいるの?!じゃあ、何度も私のジャミングしてたのは…」
悔しい思いで胸が一杯になる。ここに来てからというもの、幾度となく『風読み』を試みても上手くいかなかったのは、祖国ウィンディアの『風読み』の同年代の中で一、二を争っていた人物のせいだったなどと。
「んー、そういうことかな?」
ノエルはおどけた調子で首を横に傾げた。カリーナは、はあ…、と深い溜息を吐いた。
「ま、今はそんなことどうでもいいっしょ。無事いつもどおり停戦にもなったんだし。もう明日ぐらいには発つんだろ?」
「…いつもより、大分早いけどね」
むすっとしたままカリーナが答える。フィリアとカルディアの国境紛争は、いつも雪が降り積もり始めてから一時停戦をする。それが今年は雪も降る前に停戦の締結をしてしまった。いつもとは違う都合――姫の行方不明事件があって、実際その報がきっかけであったことも知っているが――、実際のところは、それは戦争とは別問題ではないかと、カリーナは考えていた。
「まあ、そちらさんの事情ってモノがあるんでしょ?…オレはそれだけとは思えないけどな」
そう言って、ノエルは目の前の魔獣を指差した。
「…やっぱり、アンタもそう思うんだ?」
「ああ。停戦締結の一週間くらい前からかな?確か大満月の頃さ。何か魔獣が増えたり、見たこと無い奴が出てきたりさ。こっちの陣営としては困ってたところで、停戦は渡りに船って奴だった。そっちにだって出てるんだろ?」
「まあ、報告は上がってるね。遭遇したのはこれが初めてだったけど」
カリーナはすぐ傍の魔獣を指差した。魔獣と遭遇した、という報告は日に日に多くなってきていた。人間同士で争っている場合ではない、と王は判断したのだろうか。その判断の根拠は下々の者には明かされていない。
「…何のせいだと思う?」
ノエルが、声を潜めた。周りには誰もいないのに、まるで誰かに聞き取られまいとするように。
「増えたのが?」
「そ。…尋常ならざることが起きてるって感じ、しないか?」
「…そうね…。何か…風が変わった気がする。まるで何かにおびえているような…」
不安げにカリーナは空を見上げた。冬に差し掛かろうとしている、いつもの晩秋の曇り空。変わりないはずなのに、何かがずっと引っかかっている。その正体を、掴めそうで掴めない。
「…ま、いいさ。そのうち、何か起きるなら起きるんだろ。その時なんとかすりゃいい。変なこと聞いて悪かったな」
ぽん、と軽くカリーナの肩を叩いて、ノエルはその場を立ち去ろうとした。
「ノエル!」
「次に戦場で会ったら、互いに命かけようぜ?…あ、そうだ。一つとっておきの情報、教えておくわ。お宅の姫さん…無事だぜ」
「え?何で…?」
何故そんなことが、敵側にいる人間に分かるのか。カリーナには見当がつかない。同じ『風読み』なのに、得られる情報が違うのだろうか。
「…オレの所に来るとっておきの風が告げてくれるんだよ。とにかく、信用してもらっていいぜ。…あ、オレから聞いたなんて言うなよ?お前だけの心の中に収めといてや」
ふわりと、ノエルが宙に浮く。その姿を、カリーナは下から眺めていた。
「じゃあな、また会う時まで達者でな!」
北へ、ノエルは去っていく。その姿が見えなくなるまで、カリーナはそのまま見つめていた。
「…私もそろそろ戻るかな」
最後の偵察任務を終えて、カリーナは逆に南へと進路を取った。…もしかしたら、ノエルは自分がこの辺に毎日出てきていたのを知っていたのかもしれない。そうふと思ったカリーナはまた、胸の奥底で悔しがった。
「カリーナ、戻りました!…って、またシオンだけ?」
幕舎へと戻ると、作戦会議に使う円卓には、同年代の軍師・シオンしかいなかった。最近冷え込んでいるからか、シオンは青い制服の上から白いマントを羽織っていた。
「ああ。ハサン様も団長も、各部隊のねぎらいに回っていらっしゃる。じきに戻られるはずだ」
聴く者によっては機械的だとも思われるほど冷静な口調でシオンは告げた。それが苦手だと言う者もいるが、カリーナはあまり気にしていなかった。
ふーん、とカリーナは唸って、シオンを見る。机の上に広がっている地図を見ながら、色々とメモを取っている。相当格好良い部類に入るのに、こんな性格では女性も寄り付かないだろうな、と不謹慎にも思ってしまった。女たらしのノエルに会った後のせいか、余計そう感じる。
「…俺の顔に何か?」
「い、いや?…さっき懐かしい奴にあってさ。ちょっと考え事してただけ」
「…懐かしい奴?偵察中にか?」
冷たく鋭い視線をシオンはカリーナに向ける。カリーナはどきっとしたものの、自然に答えてしまった。
「祖国の…ウィンディアの知り合い。ノエルって言うんだけどさ、どうりで私の『風読み』成功しないわけだよ。ジャミングかけられ…て…?」
話すうちに、シオンの目線が一層冷たくなっていく。その様子に、カリーナの言葉はだんだん小さくなっていった。
「ノエルだと?!あのふざけた『風読み』か…?アイツに負けてたのか、お前は!」
何時になく感情的に声を荒げたシオンに、カリーナは驚き戸惑った。
「え?やだ何、知り合いなの?ノエルと」
「アイツは俺のエルガード時代の旧い知り合いだ。くそ…思い出しただけで腹が立つ…」
肩まで震わせて怒るシオンの様子が、ついついおかしくなってしまい、カリーナはふっと噴き出して笑ってしまった。
「何がおかしい」
「だって、滅多にそうやって怒らないでしょ?それが何だかおかしくてさ」
「…怒る時もある。俺だって人間だ」
苛つきを残しながらも、またいつもの無表情に戻る。一しきり笑い終わった後、カリーナは息を整えて話を変えた。
「はー、それにしてもいいなぁ、エルガードかぁ。シオンも行ってたんだ。私はずっとウィンディアで勉強してたけどさ。あ…もしかして、年齢的に『光の貴公子』ともお知り合い?」
その言葉に、シオンの表情がまた怖くなる。また地雷を踏んでしまったと気づいたカリーナは息を詰まらせたが、シオンは存外落ち着いていた。
「…まあ、な。…人間がどう足掻いたところで、『人ならざる者』には勝てない…。それを思い知らされた、奴にはな」
その表情には、寂しさのような、憂いのような色が射していたように、カリーナには思えた。
窓からは半月が顔を覗かせていた。あれから約三週間。北方・フィリアとの停戦と、帰国の知らせが綴られた手紙を、ヘディンは眺めていた。
(…出発は今日。こちらへ着くのは二週間後か…)
物思いにふけっていると、ドアがノックされる音で現実に引き戻された。
「…誰だ?」
もう夜中だ。来客の予定は入っていない。訝しんでいると、
「王子。ライラです。入室してよろしいでしょうか?」
ドアの向こうの人物の声にヘディンは内心どきりとした。努めて冷静に、入室の許可を告げる。扉が開かれた先には、ライラのほかにもう一人いた。
「…レオン…」
ライラの声を聞いた時とはまた違う緊張感がヘディンの中に走る。二人とも、宮廷騎士の正装に身を包んでいた。
「…ライラ、君は今日は非番では?」
「父のたっての希望で、こうして参りました」
後ろに控えているレオンがにやりと笑う。
「…その服…宮廷騎士団にまた入れてくれ…、か?」
「いいえ。これはまあ、ここまで来るのに怪しまれないためのカムフラージュみたいなもんですよ。俺は話がしたかっただけです」
そう言うと、レオンは前にいるライラの肩をポンと叩いた。
「ありがとよ。あとはいいから、お前は帰れ」
「…はい分かりましたって言うと思います?父上。私はこれでも宮廷騎士の副団長を拝命している身。聞かねばならない話だと思います」
にっこりとライラは笑う。ヘディンは、はあーっと長い溜息を吐いて、二人に机の前の椅子を勧める。
「…なんとなく、用件の予測はついてるが…」
「そうですかい?なら前置き無しに言いましょう。王子の味方になりに来たんです」
「…は?」
ヘディンは拍子抜けした。言っている意味がさっぱり分からない。
「どういう…」
「王子の隠してるものを共有した上で、お味方したいってことです。姫のこと、あの兄さんのこと、それと…この国のこと」
ライラがはっとしてヘディンを見る。ヘディンはレオンを睨むように見つめている。…父は見当違いのことを言っているわけではない、ということだ。
「何が狙いだ?」
「狙い?見返りってことですかい?そんなものは何もないですよ。ただ、強いて言うなら…王子の望む未来が見てみたいってことですかね」
あっけらかんとしているレオンに対して、ヘディンは表情を崩さない。
「…信用ならないって顔ですな。まあ、そうだと思いましたけど」
レオンがぼりぼりと頭を掻いた。参ったな、といった表情を浮かべて一つ溜息を吐いた。
「…ここ一週間くらい、書庫に篭って色々調べてたんすけど…、あの兄さんは、天教で言うところの『堕天使』なんでしょう?この城の塔に封じられてたのを姫様がどういうわけか叩き起こしちまった…違いますか?」
「え?ち、父上…そんな突拍子もないことを…」
動揺してライラがヘディンとレオンを見比べる。ややあってから、ヘディンの方が、参ったという表情を浮かべた。
「…どうして貴方にはいつも見抜かれるかなぁ…」
「隠し事が苦手なんですよ、王子は」
二人は打ち解けあったような、安心した笑顔を浮かべていた。しかし、ライラはそうはいかない。
「王子、それに父上も…どういうことです?それに、我々宮廷騎士への下命は…」
「レオンの推測は真実だ、ライラ。それでファーナはお爺様に命を狙われてる。お前達への命令は…お爺様への牽制が大きい」
「つまり、我々は王子にいいように使われたということですか?」
ライラが怒るのも無理は無い、とヘディンは内心開き直っていた。
「お爺様の目を盗んでファーナを逃がすにはこうするしかなかったし、追わないと不自然だろう?…それにお前達は、命令とあらば、ファーナを罪人として殺すことはできるか?」
「そ、それは…」
ライラが口を噤む。
「俺には無理だった。殺せと言われたが、そんなことできるはずない。それがどんな理由であっても。…だから、信用に足るか足らないか分からないが、その男にファーナを託してみたのさ。…あとは、レオン、貴方が彼らと遭遇したとおりだ」
最後にレオンに振った。
「ま、俺は信用してもいいと思いますがね。…その奥に、何を秘めているかまでは分かりませんが」
「では、信用に足らない場合は…。伝承にあるとおりなら、人間が生粋の『天使』に勝てるはずがないのでは?」
ライラの至極当然の質問に対して、ヘディンは背もたれに体重を預けて溜息を吐いた。
「そうなんだよな…。とりあえず、手は一つ打ってあるが」
その言葉を聞いて、ライラの脳裏に、姫がいなくなった日に交わされた、城門でのやりとりが浮かんできた。
「まさか、あの時の、ラーク殿との会話…」
「そういうこと。アイツが何とかしてくれるはずだ。むしろ、アイツしか出来ないと思う。…それよりも、不安なことがある」
ヘディンはそう言うと、立ち上がって机の右端に畳んで置いてあった自国の地図を広げた。そこには、領事館の名前と、日付、数字が書かれてあった。
「…魔獣発生の報告数だ。三週間前から、辺境部で特に増えてきている」
指で地図の外側をなぞって示しながら、ヘディンが説明する。
「三週間前?…まさか、『堕天使』が喚んでいるとか…」
「それがそうとも言えない。味方として引き連れるのなら、もっと一点に、しかも線を描くようになるはずだ。…もっと深い意味が隠されている…そうとしか思えない」
「…五百年前、『天使』が来るまでは、世界中で魔獣が闊歩していたといいますがね…。これじゃまるで、その時代に戻ったみたいですな」
その言葉に、ヘディンは顔を上げて姿勢を正し、レオンを真っ直ぐに見つめた。
「…俺には、止まっていた時が…歴史が動き出したように感じられる。だから、俺達も動くべきなんだ。…レオン、味方になってくれるというその言葉、信用していいんだな?」
「ええ。無論」
「ライラ、君は」
「…ここまで聞いてしまえば、一蓮托生、というものですね。仕方ありません」
仕方ない、と言いつつも、ライラの顔はどこか嬉しそうだった。
「そうか、恩に着る。…いずれ動くべき時に、俺達は動く。いいな?」
二人は黙って頷いた。三人の密談は、ただ半分に欠けた月だけが見ていた。
――くらくらする。
それはこのキツい日差しのせいだと、ファーナは必死に思い込もうとした。山道をまた歩き始めて3日。見覚えのある植物が繁茂している。
「うわ…」
ぼーっと周囲を眺めながら歩いていたため、足元のバランスを崩して転びそうになった。その声に気付いたカティスが後ろを振り向いた。
「…おい、無事か?」
「へ、へーき…」
地面についた手を離して、ゆっくりと身体を起こす。ファーナの顔からは、汗が吹き出ていた。
「…そうは見えねぇけどな」
ぼそっとカティスが呟く。その呟きは、ファーナには聞こえなかった。
「…?今なんて?」
「何でもない。平気ならさっさと…」
ブン…という大きな羽音に、その続きの言葉は遮られた。その音の方向に二人は身体を向ける。歩いてきた方向の茂みから、黒い影が飛び出してきた。
「っ!」
ファーナに向かって、大きな蜂のような魔獣が飛びかかる。体調が優れないせいか、とっさの反応が出来ず、ファーナの右腕に大きな針が刺さる。
「ああああっ!」
激痛が、ファーナの身体を襲う。針を抜いて、今度はカティスの方へと向きを変えた。
「くっ、コイツは大物だな…っ」
剣を抜き、高く跳んでかわす。真っ直ぐに突き進んでいた巨大蜂は、突き刺す対象が忽然と姿を消えてしまい、勢いで針を地面に刺してしまった。
「…間抜けな奴」
剣をそのまま振り下ろし、身動きの取れなくなった魔獣の身体を真っ二つに切り裂いた。魔獣は断末魔を上げて息絶えた。
「おい、無事か?!姫さん」
魔獣にとどめを刺すと間髪置かず、カティスは倒れたままのファーナに駆け寄った。しかし、ファーナは青白い顔をしたまま気を失っていた。どうしようか思案していると、遠くから、先ほどと同じ羽音が、大音量で聞こえてきた。目を凝らしてもその姿は確認出来ないが、状況は瞬時に理解できた。
「しまった!コイツ…仲間呼びやがんのかよ!」
ファーナを左手で抱きかかえて、白銀の翼を出す。勢いよく空へと舞いあがったカティスが眼下に見たのは、黒い巨大蜂の群れだった。獲物の存在を知らせたのであろう先ほどの蜂の元に終結している。相当な高さまで飛んだのに、その羽音は聞こえてくる。
「こっちに来られると厄介だな…って、来やがった!」
黒い群れは、間違いなくこちらに向かってきている。距離はそう離れていない。接近戦で倒すにしては、左腕で抱えているファーナが邪魔で無理があった。
「…しゃーねぇ」
右手に握ったままの剣を、群れの方向へと向けて詠唱を始める。左耳のピアスの石が、淡く紫色に光る。
『――我が眼前の敵を、闇世へ誘え!』
詠唱が終わると同時に、黒い霧が現れ、群れを包んだ。程なくして巨大蜂たちは重力に逆らうことなく、ボトボトと地面へと落ちていく。少し時間をおいてから、近くまで降りて絶命していることを確認した。
(手間焼かせやがって…)
ほっと一息吐いて、次は左腕に抱えたファーナを見やった。玉のような汗が顔中にびっしりと噴き出し、息は細く、絶え絶えになっていた。
(くそっ…相当なんだな、この毒…。…親和性はあるようだし、こっちでやるしかないか)
少し先の開けたところへ降り、ファーナを横たえる。胸の辺りに手をかざして、カティスは静かに詠唱を始めた。
『――…彼の者に巣くう彼の者と異なるものを、捕らえ、縛れ。一切の自由を奪い、時を止めよ』
幾分か、ファーナの顔色が良くなる。後は、どれだけ術の効力が持つかが勝負だ。
そう思ったカティスは、ファーナを抱えて再び空へと上がり、休息できそうな場所を探す。すると南の方向に、白い石造りの建物が立ち並ぶ街が見えた。その光景を見て、カティスは小さく舌打ちをしてから呟いた。
「…エルガード、か…」