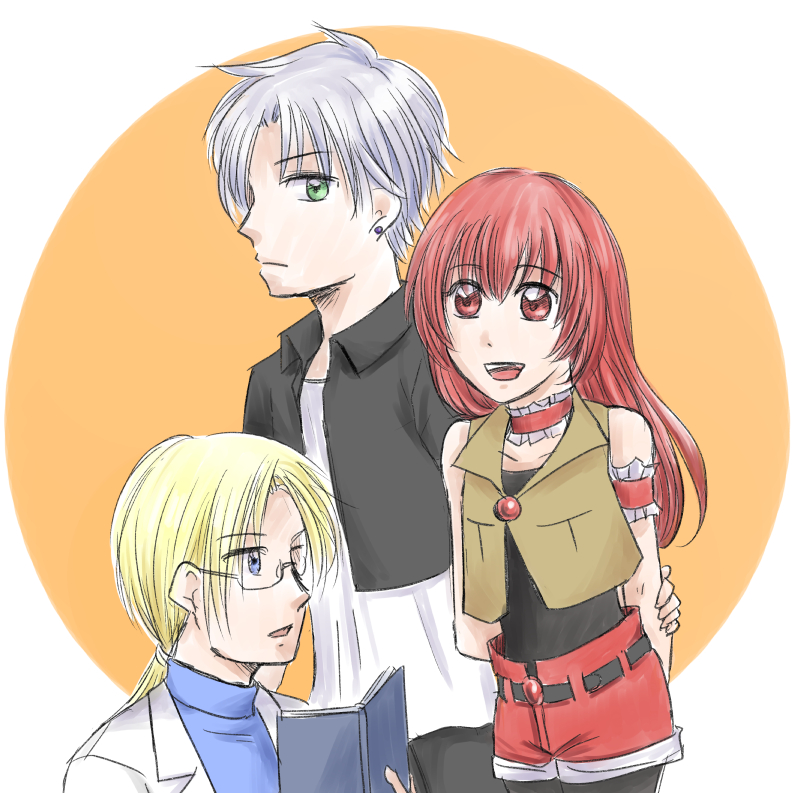サルアを出発して2日目。ナサラ山脈の尾根へと昇る山道を、ファーナとカティスは歩いていた。
ナサラ山脈は大陸の南側を南北に縦断しており、カルディアから先は東西に国を分かつ国境にもなっている。二人が入ったサルアの登山道はすぐに途切れてしまい、獣道をひたすら歩く状況が丸一日続いている。
「ふー、山頂到着―っ!」
視界が開ける。周り一面の緑に、ファーナは心なしか疲れが飛んだように思えた。空気がすがすがしい。雲が近く、木々が、森が小さく見える。
「まるで空にいるみたい…」
南の方へ視線を向ける。そこには、一段と高い山と、さらに、人工的な壁のようなものが山の斜面に沿って長々と連なっているのが遠目に見えた。
「って…あれは、国境の壁…?」
もうそんなところまで来てしまったのかと驚いたと同時に困惑した。普通なら、街道にある検問を通っていくのだが、追われている身の今回ばかりはそうはいかない。
「んだよ、先に上がるって走って行ったのにこんなところで突っ立って」
後ろからカティスが声を掛けてきた。ファーナは振り返って、迷惑そうな表情を浮かべたままのカティスに先を見るよう、南の方角を指さした。
「だって、あれ…」
「ん?何だ、国境がどうした」
「あれ凄く高さあるよ?どうやって超えれば…」
不安そうなファーナの顔を見て、呆れたようにカティスは溜息を吐いた。
「…お前、馬鹿だろ」
「な、何を突然失礼なことを!」
顔を真っ赤にしてファーナは怒る。それに対してカティスは至って冷静だった。
「こうするんだよ」
バサッと音が鳴ったかと思えば、カティスは宙に浮いた。背中には銀の翼がある。
「あ、なるほど…」
ファーナが下からカティスを見上げる。カティスは宙に浮いたまま、南の方角を見つめていた。そのまましばらく沈黙が続く。
「…で?」
カティスが上から見下すようにファーナを見つめる。
「へっ?」
「何か言うことあるんじゃねえのか?」
その言葉にファーナはハッとした。一緒に連れて行けと頼まなければ、普通に自分を置いていくつもりなのだ。それもそうだ、サルアで恋人の振りをしたところで、元々の関係は変わっていない。
――何故かすごく悔しい。
自分が勝手についてきているだけ。けれど、その見張るべき人物に頼らなければ、その勝手もできないのだ。
「…何もなければ、俺はこのまま飛んで行くぜ?」
にやりとカティスは笑みを浮かべた。
「わ、分かったわよ!…お願いします、私も…一緒に連れてってくださいっ!」
目をきつく閉じ、顔を真っ赤にしながら頭を下げて、ファーナはカティスに懇願した。
「…解ればいい」
耳元でそう囁かれて、ファーナはびくりとした。その刹那、膝と肩を抱えられ、足がふわりと宙に浮いた。
「うわっ…」
びっくりしてファーナは目を開ける。目の前には青空が広がっている。目線を左に移すと、緑色の山々が遠くに見えていた。
「す、すごい…」
カルディアを脱出した時は夜だったこともあり、ファーナは改めて空を飛んでいるという事実に驚愕した。地上よりも幾分か冷たく感じる強い風。遠ざかっていくミニチュアのような景色。それらがファーナの心を躍らせる。
「あまり動くと、落ちるぞ」
カティスのその何気ない一言で、ファーナの心は躍るのをやめた。それは本当に洒落にならない。
「…は、はい…」
ガチガチにファーナは身を凍らせた。あまり頭を動かさないように、目線だけあちこちに動かす。ふと、カティスの透き通った緑の瞳が視界に入った。真っ直ぐに、前だけを見据えている。
「…」
その瞳に、しばしファーナは見入っていた。こんなに綺麗な瞳が映してきたものは何だったのだろう。聞いたところで、答えてくれる訳もないのは重々承知だったが、そう思わずにはいられなかった。
「…んだよ、気味が悪ぃな」
その視線に気が付いたカティスがファーナの方を向く。ファーナは内心ドキッとした。
「…いや、綺麗な緑の瞳だなって…思って」
素直にファーナは思っていたことを口にした。カティスはつまらなさそうな顔をして、顔を背けた。
「…あんまり変な事言うと、落とすからな」
「えっ…!?」
折角褒めたのに、と続けたくなった言葉を、ファーナは飲み込んだ。
(…ホント、素直じゃないなー…)
背けたカティスの頬が、心なしか緩んでいたように、ファーナには見えた。苦笑を浮かべて、ファーナはまた視線を左に向ける。いよいよ、カルディアと隣国・ナサラを隔てる城壁を超えていくのだ。
(…さよなら、私の故郷…)
寂しい気持ちが込み上げてくる。けれど、もう後には戻れない。
この先、どんなことが待ち受けているだろう。そう考えるだけで、少しだけ前に向くことができているような気がした。
「一体どういう事ですか!」
カルディアの城の一室で、ライラの怒号が響く。シャルはその気迫に気圧され、目をきつく閉じた。部屋には、ライラとシャルの他、エレンと黒髪をオールバックにした男性、スキンヘッドの男性が居た。
「…いや、だから、駆け落ちで家出らしいんですよ…。王子のご命令どおりじゃないですか、追わないって」
困惑した表情でシャルはサルアであった事の次第を話す。一番年下のシャルにとっては、周りをきつい表情の先輩に囲まれるのは相当辛い。
「どこの馬の骨とも分からん男と一緒というのが、問題なのだ。王家全体に関わる問題なのだぞ?」
眉間に皺を寄せて、オールバックの男性がライラの後を継いでシャルを糾す。上背があるせいか、威圧感が半端無い。
「…オードの言うことももっともですが…。エレン、彼と一緒だった貴女はどうです?」
剃髪の男性が、ちらりとオールバックの男性を眼鏡の奥から見やった後、エレンに質問の矛先を変えた。落ち着いたものの言い方に、シャルは内心ほっとした。
「私も居たけれど…シャルの言うとおりよ。姫は知らない男と一緒になりたくて駆け落ちした。…誰にも追って欲しくない。そう仰せでしたわ」
「そーだ。俺も一緒に居たけどその通りだぜ」
突然部屋の扉が開けられ、壮年の男性が断りも無くずかずかと入ってくる。その男性を見て、ライラは目を丸くした。
「ちっ…父上?何故…!」
「ちっ…ちちうえー?!この方、ライラさんのお父さんなんですか?!」
シャルが絶叫して二人を見比べた。
「…馬鹿!レオン殿は10年くらい前まで、この騎士団の一員だ。それくらい覚えてないのかっ」
オードが囁き声でシャルを叱る。後頭部を力強く押して、礼をするように促した。シャルがちらりと横を見やると、慌ててエレンも礼をしているのが見えた。
「だって、父上、もう宮廷には関わらないと」
「んー…ま、気分だ。で、お前のご主人様は今どこだ?」
「い、今会議で…そろそろいらっしゃるかと…あっ」
そう告げたところで、再び部屋のドアが開いた。赤い髪の青年が入ってくると、彼もやはりまず驚いた顔をした。
「これはこれはヘディン王子、ご機嫌麗しゅう…」
レオンはおどけながらヘディンに挨拶をした。
「レオンじゃないか!三年前に『もう宮廷には関わらない』と言って故郷に帰ったはずでは…」
ヘディンがレオンに駆け寄り、当然の質問をする。
「…何、たまたまシャル坊の制服を見たら、妙にここが懐かしくなっちまっただけですよ。…積もる話もしたいんですけど、…ちょっとこちらにいいですかい?」
レオンはヘディンを手招きし、外に連れ出そうとする。その二人を、宮廷騎士の5人が止めようと声を上げた。
「ち、父上!何も私達まで内緒にするようなお話ではないのでしょう!」
「私達もサルアで姫と居合わせた身です。お話なら私達も加えさせてください」
「…それとも、我々が聞いてはならないようなお話ですか?」
最後に聞いたオードの質問に、レオンが答えた。
「…いやまあ…。お前達への悪口だらけの積もる話になりそうなんでな。…ささっ」
ヘディンはレオンに背中を押されつつ、後ろを振り返った。
「悪いな皆。ここは二人で話させてくれないか」
「王子…」
それ以上、追求する者はいなかった。二人が出て行った後、残された5人はしばらく無言のまま呆けていた。
「えっ…あの、いいんですか、副長!絶対もっと重要な話ですよ?!」
静寂を破るようにシャルが声を上げた。それにライラは溜息を吐いて答えた。
「分かっているわ、シャル。…私達は命を受けて動くのみ。無駄な詮索はかえってよくありません」
「でも…」
戸惑うシャルの肩をエレンが軽く叩く。
「レオン殿は、私たちよりも姫様たちと長く居たわ…。その間に、何かを掴んだのかもしれないわね。…それも、『家出』以上の情報を…」
シャルは先日のレオンの言葉を思い返していた。
「…王子の真意は、別のところに…?」
5人は、部屋に立ちつくしたまま、互いに顔を見合わせた。
山道を歩き、南下していく二人の目の前が開けてきた。どうやら人里に着いたようだった。丘の下に民家が見える。向かい側の斜面は掘削されており、鉱山町だと思われた。町の中には、日の光を受けてキラキラと輝く川が流れている。
「どうする?降りるの?今日もそろそろ日が傾いてくるし、出来れば降りたいなぁ…」
ファーナがへとへとな顔をして、疲れも何も感じていなさそうなカティスに尋ねる。カティスは大仰な溜め息をついて、返事をした。
「…仕方ねぇなぁ。コレだからか弱い姫さんは…」
「だーれがか弱いですってぇええっ!」
ファーナは握り拳を掲げて殴ろうとする。しかしカティスは難なくかわしてしまった。
――カルディアを出てから半月、サルアを出てから6日になる。ナサラに入った後は、時折小さな村に立ち寄りながらの山旅だった。共に過ごすうちに、ファーナとカティスの仲も、軽く冗談を言い合えるほどになっていた。
二人は丘を降り、町中へと入っていった。町の名はルードといった。活気があり、町の人々も小綺麗な感じで、片言の共通語を話している人が多い。
「観光地ってわけでもなさそうなんだけど…」
キョロキョロと辺りを見回しながらファーナが呟く。特によそ者向けの標識がある訳でもない。不思議そうにしていると、
「…あれか」
カティスが何かを見つけた。一つの看板を見つめている。ファーナもその視線の先を見てみた。
「…ジェム発掘所?」
魔法を大別すると二つあり、その内の一つ、この世界の自然を構成する精霊を使役する魔法・精霊魔法を使う際に、使役者と精霊を仲立ちする役目を負うのがジェムである。一般に宝石として出回るものであるが、その宝石の中に好んで精霊が集うと言われる。その石のある場所によって集う精が異なり、大きさや美しさではなく、その精霊の量によって価値が決まる。
「ああそっか。買い付けに来てる業者さんなんだ」
ジェムは汎用性が高い。高濃度の物は、魔術師が好んで身に付け、それほどでもない物は照明器具等として使われる。器具として使い始めたのは歴史的には最近で、主にカルディアの東の隣国・スレークで盛んである。
「…なるほどな、スレーク語が聞こえる訳だ」
「カディ、解るの?」
「大体はな。暇だから覚えた」
「…ナルホド…」
ファーナは時々、カティスの博識ぶりに頭が下がる。それもそうだとも思う。約五百年の間、この世界を彷徨い続けたと言うのだから。歴史がすなわち、彼の人生そのもの。それでも、昔から想いを変えず、この世界にとって悪いことをしようとしている。…それは、その歴史を否定することなのだろうか。
そんなことを考えながら、発掘所へと向かってみる。洞窟になっていて、天井に穴が空いている。そこから陽差しが差し込み、洞窟内の石英をキラキラと照らす。十数人の作業員達が、その石英を吟味し採掘している。
「うわぁ…綺麗…」
宝石箱のような光景に、ファーナは目を輝かせて奥へと入っていく。カティスは渋い顔をしてその後を付いていく。
「どうしたの?」
それに気付き、ファーナが声を掛けた。
「…光の精を集めているのか…。俺には辛いな」
一瞬、ファーナはそれが何故だか見当がつかなかった。
「…あー…。こないだもそんなこと言ってたよね。居づらいって」
夜が来ない村で、そう言っていたのを思い出した。
「俺には闇の精霊が居るからな」
その言葉にファーナははたと気付いた。この前は、単に闇の精霊術を扱うからだと思っていたが、どうもそれ以上のようだ。
「…闇の精霊が居るって…まさかカディって」
「…まさかも何も、竜人の貴族階級ってのは、その一族で精霊と血の盟約を結んでいる。…俺には…生死を司る闇の精が内にいる。…お前が赤竜、火の精を内に飼っているようにな」
「き、貴族?カディが?」
信じられない、と言った表情をファーナは浮かべる。
「お前も十分らしくねぇよ。…ま、その一族に生まれついた以上、逃れられない運命なんだ、これは。お前も十分に解ってるだろ」
「う、うん」
ファーナの一族は、カティスの言うとおり、赤竜の血を引き継いでいる。その一族は皆、赤い髪と瞳を持ち、ジェムが無くても、その血を仲立ちとして、その属性の精霊術を最大級まで使える力を潜在的に持つ。人と天使―竜人は違う。生まれた段階で既に圧倒的な力の差があるのだ。
故に、カルディア王家は他の何にも脅かされることなくその統治を守っている。物理的な力、そして宗教的な求心力。普通の人間ならば、それにひれ伏すことになる。
「…解ったらとっとと外に出せ。本気で…」
カティスの声を遮るかのように、奥から叫び声が聞こえた。
「…な、何?」
奥から大勢の人が走って出口へと向かう。何かから逃げているようだった。
「でっ…出たぁ!魔獣だっ!」
「あんたらも早くお逃げっ!」
「ちっ…」
ファーナ達も逃げようと、後を向いて走り出した。しかし、蔦のようなものが延びてきて、ファーナの足に絡む。
「きゃっ…!」
ファーナは前のめりに転び、そのままズルズルと後に引きずられてしまった。後ろを振り返ると、巨大なバラのような植物が、数人の人を蔦で絡めて捕らえていた。
『剛き炎よ、我が前の敵を焼き払えっ!』
ファーナが呪文を唱えると、胸に下げていたペンダントが発光し、炎が作られた。自分に絡んでいた蔦と、バラの花を焼いたが、本格的なダメージを与えられなかった。
「ええっ、植物のくせにーっ!」
「バカか!捕らえられている奴らも焼いてどうすんだ!」
出口の方からカティスが駆け寄る。
「え、じゃ、じゃあどうすれば…」
どう戦うか思案している内に、再びバラが咲いた。どうやら捕らえている人間から、生気を奪っているようだった。
「叩き斬るしかねぇだろ!」
剣を抜き、カティスが走り出す。延びて捕らえようとする蔦を切り払い、植物の胸元に飛び込み斬りかかるが、
「―!」
捕らえている人間を盾にして、身を守ろうとする。出しかけた剣を無理矢理地面に叩きつけて、カティスは悔しがる。
「こんの、無駄に知恵つけやがってっ…」
「カディっ!」
「っ!」
ファーナの叫び声が先か後か、カティスはそのまま両腕を縛られ、背丈の倍以上もある高さに咲く花の目の前まで吊り上げられた。
『クク…上物ノ臭イダ』
魔獣が口を利いた。知能レベルが高い、上級の魔獣のようだ。
「へぇ、人語を解するのか。これは驚きだな。俺はお前にとっちゃ毒だと思うがな」
カティスは捕らわれてはいたが、余裕綽々の態度だった。
『ソレハドウカナ。我ラも竜ヲ喰ッテ力ヲ付ケタ。闇ノ甘美ナ香リ…ドンナ花ヲ咲カスダロウナ…魅力的ダ』
「な…んだと?竜を喰う…?くぅっ!」
カティスはその言葉に愕然とした。深く考える間もなく、とたんに、がくりと力が抜ける。
ファーナは遠くで上手いこと倒せる方法を必死に考えていた。―そうだ、これなら。
『火の精よ、我が腕に集い纏え。我と共に、敵を焼き払えっ』
ファーナの両手に、炎が集う。猛ダッシュで魔獣の元に走る。
「いっけぇええっっ!」
人が捕まえられていない場所目がけて殴る。そこから少しずつ焼き落とす。魔獣も蔦をファーナ目がけて走らせるが、
『我が身を守れ、炎の衣よ』
呪文一つでファーナの周りに薄い炎の結界を作り、近づいた蔦を焼き払う。その炎の手で人々を捕らえている蔦を、服に火が燃え移らないように千切り、解放した。
「カディっ」
最後にカティスを解放した。場所のせいか、魔獣のせいか、カティスは憔悴していた。
「…ちっ、姫さんなんかに助けられるとはな」
「強がり言ってられるなら、何とかしなさいよ!私じゃ部分的に焼き払えるけど、止めはさせそうにないわ」
吸い取った力のストックがあるのか、また魔獣は元通りに復元されていく。確かに、どこかにある心臓に当る部分―核を何とかしなければ意味が無さそうだった。
カティスはゆっくりと立ち上がり、魔獣の方を向いた。
「…お礼にイイモン見せてやるよ、とっておきだ」
そう言うと、カティスは胸に手を当て静かに詠唱し始めた。
(こ、これは…)
以前夜が来ない村で使っていた魔法の言葉だった。学校で習うどの言葉にもないスペル。なのに不思議と心が落ち着く。
それほど時間はかからなかった。詠唱と共にやがて花が萎れ始めた。
『キ、貴様…何ヲッ…!オオ…力ガ…力ガ抜ケル…』
魔獣がうめき声を上げる。やがてその声も小さくなり、次第に萎れ、枯れていってしまった。
「えっ…ええ?枯れちゃった…。何で?」
カティスと魔獣とを見比べる。カティスは枯れてぼろぼろに散っていく魔獣をじっと見つめていたが、ファーナの視線に気が付いてにやりと笑った。
「…言ったろ、とっておきだってな。そう簡単にタネは明かさねぇよ」
やがて先に捕らえられていた人が正気に戻り、口々に何だったんだと話す。そんな人々に目もくれず、カティスは踵を返した。
「今日は流石に俺も疲れた。これ以上はいいだろ。出るぞ」
カティスが足早に出口へと向かう。ファーナも慌ててそれに付いていく。出口に差し掛かる前にふと後ろを振り返ると、枯れた花は跡形もなく飛散し消えていた。
カルディア城の外、教会の陰で、ヘディンはレオンの話を聞くことにした。時刻は昼下がり。二人が立っている日陰には、暖かな日差しは遮られている。
「ここなら誰も来ない。…それで、積もる話とは何だ?本当に下らない話をするために二人きりになったわけではないだろう」
ヘディンは平静を装っていたが、このレオンにだけは昔から何かと見抜かれていた。今も、秘密にしていること、騙していることを見抜かれるのが嫌だった。
「…単刀直入にいいましょう。俺が、姫様を逃がしました」
ヘディンは目を丸くする。驚きと、少しの安堵が入り交じる。
「…逃がした…?どういうことだ」
「姫様が、極端に帰城を拒んでいたからです。そんな姫様を無理矢理シャル達に手渡すのは不憫ってもんでしょう?だから、手助けしたんですよ」
「拒んだって…」
ヘディンはあくまで何も知らないという姿勢を見せながら話す。本当は違っていても、それを見抜かれるのは厄介だ。
「家出ですってよ。何か、身分違いの恋みたいで、若い兄ちゃんと二人でしたぜ」
「…連れが、いるのか?」
今度は本気で驚いた。あの男と、行動を共にしている。そしてあの男も、ファーナを殺すことも、どこかに放置することもしていないということに、胸の奥底で安堵した。
「ええ。銀髪の、緑の瞳。年の頃は二十くらいの悪ぶってる男で。まぁ、姫様もその男を頼ってる感じだったし、その男も姫様に優しくしてましたぜ?」
間違いはなかった。安心したと同時にヘディンの顔が苦々しくなる。レオンの言葉をそのまま想像すると嫉妬心が芽生えてきた。
「…かけおち…か…?」
嘘の言葉の筈なのに、少々怒気が含まれた。
「…うーん…そうなんでしょうかねぇ…。傍目にはそう見えましたし、本人たちもそう言ってましたけど…」
レオンがぼりぼりと頬を指で掻きながら、空を見上げる。
「でも、あの兄ちゃん、尋常じゃない。闇の…禁呪のジェムを持っていた。あんなのと姫様が一緒だなんて、ちょっとぞっとするな」
「闇のだと…?何者だ?」
本当はその正体を知りつつ、ヘディンは知らない素振りをする。
「さあて…。俺には皆目見当が付かなかったですが…王子なら何かご存知だと思ったんですがねぇ」
にっと笑ってレオンはヘディンに視線を送る。
「王子の名前を出したときにね、姫が、俺に泣きついてきたんですよ。普通好きな男と一緒になるのに、兄貴のこと思い出してワンワン泣きますかね?…これはただの家出じゃない…少なくとも、本意ではないな、って思ったんですがね」
茶色の瞳がヘディンを射抜く。背中に嫌な汗が流れる。
「そして貴方は、一国の姫の捜索に『家出なら放っておけ』という命を騎士たちに出している。…まるで『そのまま逃がせ』って言っているもんですよ。何かあるんなら、帰りたがる訳なんかないですからね。…捜索なんて形だけ。真意はどこにあるんです?」
ヘディンの喉が上下する。一つ息を吐いて気分を落ち着かせる。
「…家出と言うのなら、家出だろう。俺にはそれ以上のことなど解らない。アイツはまだ自由の身だ。身動きが取れなくなる前に世界を巡るのもまた、修行だ。俺の事なんて…ただのホームシックだろ?…だから他意も何もないよ。それだけのことさ」
ヘディンは寂しそうに微笑んで返した。しかし、心の中はずっと冷や汗を掻いていた。
彼の正体、ファーナがしでかしたこと、そして、自分の本懐。全て隠し通さねばならない。偽りの秩序を成り立たせ、今はそれを護っていく時期だ。自分も、その秩序の上で踊らねばならない。
しかしレオンは、その偽りの秩序の綻びを見つけてしまった。その下に隠されている真実を、求めている。
「…本当ですかぁ?俺でよければ、力になるのになぁ」
レオンは疑いの目を向け続ける。しばらくうーんと唸った後、大仰に溜め息をつき、元来た出口へと向かう。
「…ま、いいでしょう。ああ、姫から伝言がありましてね。『絶対、いつか帰るから』って。王子に嫌気は差してないみたいでしたよ」
レオンはそう告げた後、後ろを振り返った。ヘディンの顔には安堵の表情が浮かんでいた。
流石に堪えたらしく、この日はきちんと宿で寝泊まりすることになった。部屋に着くやいなや、さっさと寝ようとしたカティスに、ファーナは声を掛ける。
「ねぇ、今日…いや、こないだも使ったあのとっておきの魔法って何?聞いたことないよ?」
根掘り葉掘り聞こうとするファーナを、カティスは一瞥してから布団を被る。
「…貴方は何者なの?『堕天使』なら、人の命を救う真似なんかしないはずなのに…。貴方は、本当に『堕天使』なの?」
布団の中からは答えはない。ファーナは自分の知識をもう一度おさらいする。『堕天使』とは、天界からこの地界を支配せんと堕ちてきた悪い天使。摩訶不思議な術を使い、人々に死の恐怖を与え、そうして神様に封じられた――。
目の前の人物と見比べる。矛盾した気持ちがファーナの中を駆け巡る。夜が来ない村に夜を呼んで村人たちを助けた。ここでも、まず人々の命を最優先にして戦った。
「答えてよ。あなたは、一体何をしようとしているの?」
しばらくの沈黙のあと、かったるそうにカティスはようやく口を開いた。
「…何度も言わせるな。お前は、それを見届けるために付いてきているんだろう…。なら俺が何を言っても無駄だ」
それきり、カティスは口を開かず、寝てしまった。
「…んー…もうっ…」
ファーナは大きく溜め息をした。腰掛けていたベッドから立ち上がり、財布だけを持って、部屋を出た。既に陽は落ちかけていて、レストランがある階下からは、いい匂いがしてきていた。
「私もなんか食べてから寝よ…」
階下へ行き、レストランに入る。地元の人達も使う食堂らしく、様々な人でごったがえしていた。丁度空いていた二人席に付いて、自分の分の夕食を注文した。
料理を待っていたその時だった。
「あれ、お嬢ちゃん、さっきの…」
声を掛けられてファーナは顔を上げた。そこには、さっき洞窟で声を掛けたおばさんが、買い物袋を抱えて立っていた。ファーナは返事に困った。
「あ…どうも」
「ん?感謝をするのはこっちだよ。お嬢ちゃんたちがあの魔獣をやっつけてくれたんでしょ?ありがとうね」
おばさんは空いていた向かいの席に腰掛けた。
「…あ、いえ…私は特に」
「いいのいいの。最近はよく出るようになっちゃってね。こないだも丁度逗留していたエルガードの魔術師さんに退治してもらったのさ」
ファーナははっとした。南下していると言うことは、エルガードにも近づいているということだ。
「あなた達みたいに強い人が一人でもいれば、ここも随分安全になるんだろうけどね。そうはいかないね。娘を今修行に出してるけど、いつ帰ってくるかわからないしね」
「…そう、ですね…」
ファーナは答えに困る。何故か、彼女たちの苦労が自分のせいなのかもと、訳の分からない責任感に苛まれた。
「おーい、セドニーさん!パン出来たぞ!」
厨房の方から声が聞こえた。おばさんは、はーいと返事をして、パンが入った大きな袋を受け取り、またファーナのところへと戻ってきた。
「あいよ、このパンあげる。お礼だよ」
小さな袋の中にロールパンが五個ほど。受けた恩には全然足りないけれどね、と一言付け加えて、おばさんは帰っていった。
朝。陽も昇ったばかりの頃に、カティスは目を覚ました。サイドテーブルを見ると、袋が一つ、メモと一緒に置いてあった。
『町の人からお礼を貰いました。いつ起きるか分からないけど、食べてね』
カティスは袋の中身を取って、口に運ぶ。隣のベッドでは、まだファーナが眠っていた。その寝顔を眺めて、カティスは呟く。
「…まだ、何も知らなくていい。まだな…」
その言葉は、ファーナに届く由もなかった。
カルディアの湖上城からそれほど離れた場所にない、ハルザードの国立図書館に、およそ書物とは似つかわしくない風貌の人物が、魔術書のある一角で本棚を凝視していた。長い白髪交じりの灰色の髪を後ろで束ね、長袖を着ていてもその下には鍛えられた筋肉があることが解るような、体格のいい壮年の男性だ。
「…おや?レオンどのではないですか?」
その壮年に声が掛かった。小声だが、しっかりと聞き取れる、落ち着きのある澄んだ声だ。
「ん?ああ、アンタ確か宮廷騎士の…」
壮年は声を掛けた人物に目をやった。数日前、宮廷で出会ったばかりの青年だ。制服は着ていなかったが、剃髪に眼鏡という風貌には見覚えがあった。
「エルンストです。以後お見知りおきを」
書物を抱えたまま、ぺこりとエルンストは礼をした。
「非番かい?」
「ええ。レオンどのは…また随分と珍しい場所に」
王子の剣術指南までしていたほどの武術の腕を持っている人物が、書物、しかも魔術書とにらめっこをしている姿は、エルンストに違和感を抱かせた。
「ん?ああ…まあ、調べものをちょっとな」
そう言って、レオンは頭を掻いた。
「お手伝いしましょうか?私は魔法を扱っていますので、このあたりの本のことでしたらなんなりと」
「んー…」
エルンストの提案に、レオンはしかめっ面をして考え込む。
「…魔法以外で詳しい分野は?」
「戦には向きませんが、天教学を研究しています」
「…ふーん…。なあ、それなら、天教学者のアンタに一つ訊いていいか?」
「はい?」
「…闇の力、と聞いて思い当たるモンを挙げて欲しいんだが」
エルンストは、レオンの質問に首を傾げながらも答える。
「…?質問の意図がよく解りませんが、そうですね…。天教においては、闇の力は生死を司る、神に近い力とされています。天使戦争の時に現れた『白天使』『堕天使』は、その力を有していたと言われています」
まあ、伝説上のお話ですけどね、とエルンストは笑って付け加え、続ける。
「しかし、現代にそれを扱える者はいないはずです。禁呪とされていますし、精霊術の見地から言うと、精霊との親和性が高くないと扱えない魔法の一つですから。使用できる素養のある者がいない、そして、使用しようとしても言語が伝わっていない。だから、扱える者はいません」
レオンはエルンストの言葉にうんうんと頷いてから、再び切り出した。
「なら…これは仮定の話なんだが、もし、扱える者がいたとしたら、どんな可能性があると思う?」
物騒な話に、エルンストは顔を顰める。
「…そんなことはないと思いますが…。一つは、『白天使』『堕天使』に連なる者がいるという可能性、もしくはその当人がこの世界に再び現れたという可能性…ですね」
「…当人が?」
「ええ。『白天使』は天界に還り、我々を見守っていると言われています。そして『堕天使』は、カルディアの城の真ん中に立つ塔に封じられ、未来永劫、魂のみこの世を彷徨う罪を背負ったと言われています。その伝説が事実なら、可能性は0ではありません。ですが…」
そこでエルンストは軽く咳払いをした。
「そんな者が現れた時点で、この国はこの国でなくなってしまうんです。彼らはこの国を治める『赤天使』よりも天使の位が高いと言われています。これまでこの国が『赤天使』によって治められてきたことが、また、『天使戦争』のようなことが再び起こっていないことが、彼らの不在の証左なんです」
きっぱりとエルンストは言い切った。その言葉を聞いて、レオンは目を閉じ、口に笑みを作って溜息を吐いた。
「…わかったよ、ありがとうな。ちょっと…興味があって聞いてみただけだ、他意はない」
エルンストはほっとした表情を浮かべた。
「そうですか。また何か解らないことがありましたら、お答えしますので。それでは」
満足げな微笑みを浮かべて、エルンストは一礼してカウンターの方へ去って行った。自分の説明でレオンが納得してくれたと思ったようだった。
しかし、エルンストの言葉は、レオンに一つの仮説を閃かせた。サルアで姫と一緒に匿った、闇のジェムを持つ銀髪の青年、そして、兄を思い出し泣いた姫と、何か事情がありそうな王子の態度。
(…そうとなれば、次は歴史書、だな)
レオンは意気揚々と、歴史書のある書棚へと向かっていった。