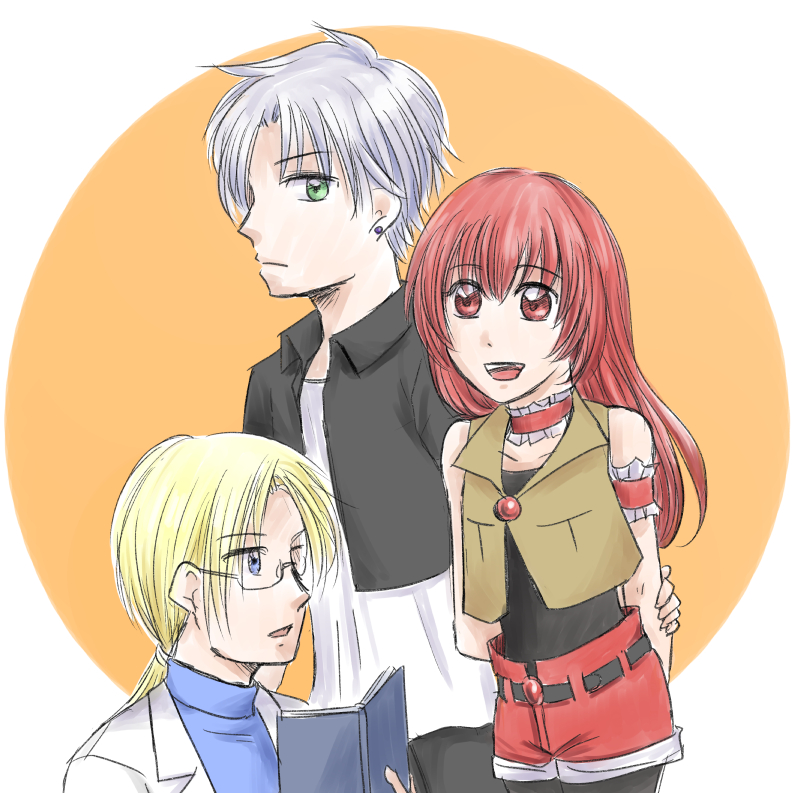後に、「シャクーリアの政変」と呼ばれることとなる事件から4日が過ぎた。一隻の船が穏やかな大海原を南へと進んでいた。
リクレア近くのラズリ達のアジトへ、シャクーリアからの難民を迎えに行き、シャクーリアに降ろすのに丸3日。一夜をシャクーリアで明かし、早朝に発ったばかりだった。
「んー、順風満帆っすね」
暖かな日差しに照らされた操舵室で、伸びをしながらシジェが言う。
「そりゃそうだ。おれの船なんだからな」
後ろの指令席でラズリが自慢げに答える。
「…欲を言えば、もう少しくらいこっちに付いてきて欲しかったっすけど…」
結局、ラズリの船に乗っていた多くのクルーが、故郷であるシャクーリアに残る選択をした。元々がシャクーリアの政治に不満を持っていたものが殆どだったから、目的を達した今、船に残る理由もなかった。残ったのは、リーテルが圧政を敷く前から海賊としてラズリと行動を共にしていた者や、今の生活が気に入った者達ばかりだった。
「シジェは良かったのか?降りなくて」
「僕は守るものないですからね、オーガスさん達とは違って。それに、ダタさんに色々教えてもらいたくて」
妻子持ちのオーガスもシャクーリアに残った者の一人だった。それに対してシジェはすぐさま船への居残りを表明していた。
「ダタ殿か。…姫のフォーレス行きは本当に納得いってるんだろうか」
「さあ…。どのみち、あのお姫様には何を言ってもムダだと思いますけどね。一度決めたら頑固ですから」
その言葉にラズリはふふっ、と笑った。
「そうだな。でもそれにおれ達は助けられた。偶然の出来事だったかもしれないが…こればかりは感謝しないとな」
「…くしゅん!」
甲板で海を眺めていたファーナが大きなくしゃみをする。
「…おい、また体調不良か?」
隣で肘をついてかったるそうにしていたカティスが、さも迷惑そうな顔でファーナを見る。
「いや…潮風が鼻に入っただけだと思うよ?」
ファーナはグシュっと鼻をぐずらせて言う。
「大事な御身ですから、ご自愛なされませ」
カティスとはファーナを挟んで反対側にいたダタが心配して声を掛けた。
「過保護だぜ、おっさん。コイツ、土砂降りの雨をシャワー代わりに使ってたぐらいなんだから」
「な、雨をシャワー代わりに…!?」
ダタが目を白黒させて絶句する。それを尻目にカティスがあっと小さく声を上げた。
「…そうだ、何か忘れてると思ったら…思い出した」
「?」
「シャクーリアで、『赤天使』って言ってた奴に遭遇したんだよ。カナンって名乗ってたな。アイツの手足と口縛ってきたけどどうしたかなと思って」
ダタとファーナがそれを聞いて口をぽかんと開けた。
「…カナン様を?!」
「ええー…」
ダタは鳩が豆鉄砲を食らったような顔になり、ファーナは苦笑いを浮かべた。
「やっぱ姫さんの親戚か?」
「う、うん…。うちの家系って、三百年くらい前に分家してるんだけど、カナンはもう片方の跡取り息子なの。…帰国してから一度も見てなかったけど、シャクーリアにいたんだ…。ダタは知ってた?」
ファーナに問われ、ダタは首を横に振った。
「いえ。布教の旅に出られているとは聞いておりましたが…。それにしても、大丈夫でしょうか」
「うん?何が?」
ファーナは小首を傾げた。
「姫様が、カナン様の『布教』を邪魔したと国に知られては…。姫様にあらぬ嫌疑がかけられてしまうやも…」
「会ってないもん、大丈夫よ」
ファーナはあっけらかんとして笑う。
「それに、ミランダ達がそのまま国外追放してるだろうさ。姫さんの顔が割れてるとしたらあのお妃さんぐらいだ、問題ないはずだ」
カティスもどうということはないといった風にファーナの言葉に続けた。
「…ん?あれ?…待って、カディはカナンに会ったんだよね?」
「ああ」
「…それって…もしかしたらそっちの方が…」
そこまで言って、ファーナははっとして口をつぐんだ。隣には何のことかと怪訝な表情を浮かべているダタの顔があった。
「そっちの方が…?何ですか?」
不審そうな目線をファーナとカティスの二人に向ける。ファーナはその視線に耐えかねて、顔を引きつらせ、カティスは苦い顔をした。
「あ、いや…何でもない…ヨ?あ、ああそうだ、先生に頼みたいことがあったの思い出した!私行くね!」
ファーナは猛ダッシュで船室の方へと走っていった。
「あっ…ちょっと待て、俺もアイツに聞きたいことが…!」
カティスも慌ててその後を追う。ダタは一人ぽつんと甲板の上に残されてしまった。
「…やはり…。ラーク殿には詮索するなと言われたが、気になる…」
ダタは顔をしかめて、二人が消えた船室への扉を見つめた。
「…で、二人揃って来た訳か」
ラークの部屋で、息を切らしながらカティスとファーナはベッドに突っ伏していた。ラークは机に向かって書き物をしていたところだった。
「いや~、ホント危なかった…。ダタには言えないもんね…」
「お前…少しは考えて喋れよ…」
はー、と二人そろって長い溜息を吐き、身体を起こしてベッドに腰掛けなおした。
「それにしても、カナン殿が、リーテルが言っていた『天使』か…。ヘディンには報告しておいた方がいいな」
ファーナが首を傾げる。
「何で?」
ラークはペンを置いて二人に向き直る。
「カナン殿はヴィオル殿に心酔してるからな。シャクーリアの一件と、コイツの存在が我々以外に知られることは、ヘディンにも、お前にも良い方には転ばないだろう。用心するに越したことはない」
「あ…なるほど…そうなんだ」
合点はいったようだが少し気落ちした様子になったファーナを、カティスは不思議そうに見やる。
「あ、そうだ、頼みたいことがあるんだけど…」
「ん?何だ?」
「それって、お兄ちゃん宛ての手紙だよね?」
「……」
ラークはバツの悪そうな表情を浮かべて、無邪気に訪ねてきたファーナから目線をそらした。
「隠さなくなって、昔からずっと二人で文通してたの知ってるんだからね!…ね、それお兄ちゃん宛ての手紙だよね?」
ファーナの念押しに、ラークは観念して音を上げた。
「ああそうだ。それがどうかしたか」
「あの…私の手紙も…その手紙の中に、入れて欲しいんだけど…」
打って変わって不安そうな表情でファーナはラークを見つめる。ラークは一瞬考えてから答えを告げた。
「ああ、構わない」
「ほ、…ホント?」
ラークの返答に、ファーナの表情が明るくなる。一方で、隣のカティスが首を傾げる。
「おい、検閲とかされねえのか?」
「ウィンディアの『風読み』特製の人工伝書鳩を使って飛ばすから、間違いなく本人に届く」
「…成程な。そりゃいい技術だな」
珍しく、カティスが興味深そうに唸る。
「じゃあ、私書いてくるね!」
ファーナは勢いよくベッドから立ち上がった。
「今日の夕方には飛ばすぞ?」
「分かった」
笑顔で頷き、ファーナは部屋から出て行く。足音が聞こえなくなると、カティスは腕を後ろにつき、天井を見上げて、はー、と長い溜息を吐いた。その態度を見て、ラークは眉を顰めた。
「…お前は出て行かないのか」
「俺はアンタに聞きたいことがあって来たんだよ」
そう言うと、カティスは身体を起こして向き直った。
「アンタの博物館に…『杖』の遺物なんか置いてないか?」
「杖?どういう…」
「でかい虹色の玉がフヨフヨ浮いてる杖。玉の周りには4つのリングが掛かってる…」
身振り手振りを交えてカティスはラークに説明する。しかしラークには見当がつかないようで、考え込んでしまっている。
「いや…、無いな。そんな特徴的なものがあったら憶えてるはずだ」
「…そうか…」
ラークの回答に、カティスはやや気落ちした。
「その杖がどうした?」
「昔盗られたモンなんだが、もしかしたら…と思っただけだ。幾度か探したこともあったが見つからなくてな」
「その杖は…余程大事なものなんだな」
「…まあな」
そう短く言って、カティスは立ち上がった。
「邪魔したな」
「いや…」
カティスが部屋から出て行く。ラークはまた静かな部屋に一人となった。
(虹色の玉…カルディアにあった『大地の涙』か…?だがあれは杖ではない…。一体何のことだ…?)
カルディアの王宮内教会に、多くの礼拝者が集まっていた。
今日は一週間に一度の魂送りの儀の日である。死者の魂を天へと返す儀式。毎回王族の誰かが聖火を焚くため、祭壇に登る。今日はヴィオルの番だった。
「ヴィオル様の時は、やはり人が多いですね…」
参列者の最前列で、ライラが隣のヘディンにこっそりと話す。
「年の功というやつだな。あとは声がいいのだとか」
「確かに…。綺麗な低い声ですね」
朗々と、それでいて威厳のある低い声が教会内に響き渡る。祭壇に掲げられた火が、なお一層激しく燃え上がる。
その脇で神官が数人、魂送りの舞を踊っている。その中にサリエルもいた。
「…最近はサリのファンもいるらしい」
「…ああ。何かこう…変な言い方ですが、美しいですよね」
銀の髪が、緋色の炎に照らされて橙に光る。蒼い瞳が心なしか潤んでいるように見える。ライラもその姿をうっとりと眺めていた。
その時だった。サリエルの身体が崩れた。教会内でどよめきが起こる。ヴィオルもそれに気がついて、詠唱を中断して駆け寄った。
「サリ…?!」
――白い、白い世界。
懐かしさを感じる世界。
そこには何もなく、全てがある世界。
「…ここは…?」
サリエルは、急に目の前に広がった世界を見渡した。夢の中にしては現実感がある。そして、来たことがあるような気もする。周りは白で囲まれており、自分がどこにいるのか、立っているのか浮いているのかも解らない。
「!」
視線の向こう、白い空間に半分溶けているような人影が見える。ぼやけて輪郭まではわからないが、その雰囲気には覚えがあった。
「『白天使』さま…?!」
近づこうとしてその人影に向かって思わず走り出す。しかし、一向に近づけない。
「ど、どうして…!」
流石に息が切れてくる。まるで何かに阻まれているかのように。彼の元に辿り着くためにはどうしたらいいのだろう。立ち止まり、息を肩でしながら考える。しかし、この右も左も解らない空間ではどうしようもない。
『…私の声を聞く者よ…』
「?!」
声が聞こえた。あの時、教会で祈っていた時に聞いた声。あの時よりも随分とはっきり聞こえる。
『…世界は今、再び混沌に…。私の力を、そなたに…』
その言葉に呼応して、ドクン、と心臓が高鳴った。
「あっ…」
何かから『解放された』ような感覚が、サリエルの全身を駆け巡る。そしてそれと同時に、様々な思い出が蘇る。
「僕は…ああ、そうだ…あの時…」
「っ?!」
バシン、と音にならない衝撃をヘディンは受けた。
「ま、まずい…」
「まずいって、何がですか?…あ、王子!」
ヘディンも祭壇に駆けて行く。サリエルの元に着き、頭を自身の膝に持ち上げると、サリエルは目を見開いた。
「えっ…あれ、僕…」
サリエルは茫然自失とした状態で目線を泳がせる。ヘディンと目が合った途端、顔に不安の色が射した。
「す、すみません…。大丈夫、ですから…」
ヘディンの腕に捕まってサリエルはよろよろと立ち上がった。
「…王子…僕、…『白天使』さまの声を聞きました…」
「!」
「『白天使』…だと?それは本当か?!」
ヘディンよりも先に、ヴィオルが声高にサリエルに尋ねた。その声は教会内に響き、その場にいた群集を騒然とさせた。
(くそっ、こんな大衆の前で…!)
ヘディンは心の中で舌打ちした。サリエルの方がかえって動揺して、ヘディンの顔を不安げに見つめる。
「取り敢えず、休める場所へ…」
ヘディンはまだ足元が覚束無いサリエルを抱えて去ろうとしたが、ヴィオルにその行く手を阻まれた。
「お爺様…」
「…サリエル。『白天使』殿はなんと?」
遠慮も無くヴィオルはサリエルに尋ねる。サリエルは一度逡巡し、大衆に聞こえるように大きな声で告げた。
「世界は再び混沌に陥るだろう…と。でも、きっと『白天使』さまが再びこの世界に降り立ち、その混沌を鎮めてくださいます」
教会内がざわめく。ヘディンは複雑な気持ちでサリエルを見つめる。サリエルは弱りながらもどこか確信めいた表情でその大衆を見つめていた。
「静まれい!皆の者!」
ヴィオルの一声で教会内がしんと静まった。皆が皆、ヴィオルとサリエルに視線を向け、次の言葉を待っている。
「『白天使』様からのお告げぞ!昨今の魔獣の出現、そこから生まれる混沌も、いずれは我等『天使』の力で平定されるであろう!皆心安らかにせよ!」
どこからともなく、声が上がる。たちまち大歓声となり、教会全体が一体となる。
「大いなるイーレムの加護あれ!」
「『白天使』の再来を!」
そんな歓声を背に受けながら、ヘディンは苦々しい気持ちでサリエルを伴って教会を立ち去った。
途中、教会を抜け出したライラも合流し、なるべく人通りの少ない道を通って、ヘディンの自室へとサリエルを連れて行った。未だ足元が覚束無い様子のサリエルを、自室のベッドに横たえる。サリエルはぼうっとした様子で、椅子に腰掛けたヘディンと、その横に立つライラを眺めた。
「王子…申し訳ありません…。その」
何からどう謝るべきか、サリエルは困り果てる。しかしヘディンは首を横に振った。
「お前が故意に何かをやったわけじゃない。何を謝る必要がある」
「でも…あの」
一体何から言えばいいのか、サリエルは二の句が継げないまま視線が泳いでいた。その様子を察して、ヘディンが先に口を開いた。
「…『思い出した』んだな?」
ヘディンが優しくサリエルに語りかける。弾けたようにサリエルは顔を上げた。
「え?な、どうして…」
「どうしてかは後で話す。…まずは『あの時』の…俺がお前を拾った時の話を聞かせてくれないか?」
不安そうな表情をサリエルは浮かべた。ライラがそれを察して、ヘディンを見やる。
「王子…。『あの時』というのが私には見当がつきませんが、しばらく時間をおいてからの方が…」
「…だ、大丈夫です、ライラさん。お気遣いありがとうございます」
ヘディンではなく、サリエルが答えた。その声は少しだけ震えていた。ライラはやはり心配そうに尋ねる。
「…いいの?」
「はい…。今、話さないといけないような気がするんです」
そう言って、サリエルは上半身をゆっくりと起こし、掛けていた毛布をぎゅっと強く握り締めた。
「僕の村は…カルディアとスレークの国境付近の山中にあって、『白天使』に連なる人物が隠れて暮していたという伝説がありました。僕のように銀の髪を持つ人が多くて、そして、『白天使』さまを崇拝していました。…それだけでなく、『神の言葉』と言われていた…『禁句』も伝えられてきました」
「えっ…」
ライラが驚いて小さく声を上げた。それが本当なら、スキャンダルどころではない。ふとヘディンを見やったが、それほど驚いてはいなかった。
(もしかして、このことを知っていた…?)
ライラは胸に浮かんだ疑念を飲みこみ、サリエルに再び目を向ける。サリエルは二人の表情を確認してから、続ける。
「だからこそ、外界との交流は殆ど持ちませんでした。僕達の存在は『あってはおかしい』存在だから。天教の権力構造が揺るぎかねない…当時はよく解らなかったけど、大人たちはそう言っていました。
でも、禁を破る者は少なからずいたんです。…そしてそれが元で、あの日、村はスレークの人間に襲われました…」
一層、サリエルは毛布を握る拳に力を入れる。身体が小刻みに震えているのが分かる。
「僕も襲われて、教会まで逃げ込んで…殺されそうになったところで『神の言葉』を発したら…目の前が真っ白になって…っ」
そこでサリエルは一度言葉を詰まらせる。
「その後のことは、覚えてないんです。…気がついたら、どこかの宿のベッドで、王子が目の前に…」
そこまで言い切って、はーっと、長い溜息をサリエルは吐いた。
「…辛かったわね」
ライラは堪らなくなってサリエルに近づき、その背を優しく撫でた。サリエルの身体の震えが徐々に収まっていく。
サリエルはライラに会釈して身体を離してから、その後ろで椅子に腰掛けて依然として表情を変えないヘディンに視線を向けた。
「一つ…教えていただきたいんです。王子は…どうして僕を助けてくださったんですか?そして、どこまで僕の事を…」
「…お前には辛い話になるかもしれないが、大丈夫か?」
「はい。ここまできたら…知らないといけないと思うんです」
真剣な表情をしたサリエルを見て、ヘディンは一息ついてから話し始めた。
「…あの日。スレークとの国境付近を探索していた時に、白い光の柱が遠くで見えた。何事かと思って近づいてみると、地図にない隠れ里があって、その光の元らしき場所…教会には…息も絶え絶えのお前と、多くの『外傷の無い』男の死体が転がっていた」
「…!」
サリエルとライラは顔を引きつらせた。
「教会の祭壇にはイーレム像と…『白天使』の像が並び立っていた。その時に推察したんだ。…お前が『白天使』…白銀竜の血を継ぐ者で、『禁呪』を…いや、闇の精霊術を行使して、賊の命を奪ったのだと」
そう言いながら、ヘディンは立ち上がり、サリエルに近づいた。ライラはヘディンの後ろに控えるように後退する。
「王子…」
ヘディンはサリエルの前に屈み、左頬を隠す彼の長い前髪を静かに掻き分けた。
「…それは…!」
ライラが息を飲んだ。そこには、妖艶な光を湛えた紫色の澄んだ瞳があった。
「…あの時、賊に潰されて…開かなかったはずの…瞳だな」
「は、はい」
「…怪我していたのは本当だったが、致命傷には到っていなかった。開かなくしていたのは…俺が封じていたからだ。そこから異様なまでの力を感じたからな」
「!?」
「その魔法が解けた。だから思い出したんじゃないかと思ったんだ。…ま、学生時代に遊びで覚えた程度の封印魔法じゃ…いつかこうなるとは思ってたけどな。いずれにせよ、そんな危険な魔法を扱える奴をそのまま野放しにしておくわけにはいかない。そう思ったからお前を手元に置いたんだ。魔力を封じた上でな」
そう言って、ヘディンはサリエルの髪から手を離した。サリエルは俯いて、何かを考えているようだった。
「…王子…。僕はこれからどうしたらいいんでしょうか…。『白天使』さまは僕に力を下さった…いえ、王子の施した封印を解いてしまった。それは…この力をもって、世界中で苦しんでいる人々を助けにいけという意味なのでは…?」
純粋に解釈すればそうなのだろう、とヘディンは思った。しかし、『白天使』は『堕天使』の事を知らない訳がない。そのための抑止力として力を与えたのであれば、彼こそが『堕天使』に対する唯一の対抗策となる。しかし、心のどこかでそれを望まない自分がいた。このまま全てを告げれば、彼はファーナを、『堕天使』を追って旅に出るだろう。だが、その有り余る力で誤ってファーナを傷つけてしまえば、サリエル自身も傷ついてしまう。
「…お前に、その力が御せるのか?」
サリエルははっと目を見開いた。
「俺は…お前を拾った時ほど恐ろしいと思ったことは無かった。あれだけの命を一瞬で奪った力…禁呪にされて当然だ。その力を御せることなく、闇の精霊に身も心も支配されれば…お前はただの殺人鬼と化す。俺はそんなお前を見たくない」
「王子…」
サリエルの両目から、涙が一筋流れた。
夕焼けが水平線をオレンジ色に染め上げる。
甲板に、ラークとダタ、シジェが立っていた。ラークの手元には、鳥の形をした木製の玩具みたいなものがあった。
「へぇ~、これが人工伝書鳩…。初めて見るっす」
緑色のジェムが空洞になった胴体部分に入れられており、夕日を受けてキラキラと光る。
「それにしても遅いな、ファーナ」
「呼んで来ましょうか」
そうダタが言って船内に向かおうとしたところに、ファーナが小走りで駆けて来た。
「お待たせ!…先生、これお願い」
便箋は一枚だけだった。それが綺麗に八つ折りにされている。
「…これだけでいいのか?」
「色々書こうかなって思ったけど、書いてるうちにとりとめがつかなくなったから、シンプルにしたの」
「そうか」
そう言って、ラークは自分の手紙と合わせて小さく折りたたみ、胴体の内側の空洞に貼り付けた。
「あ、これが、さっき言ってた伝書鳩…?」
「ああ。予めジェムには行き先を覚えさせておいてある。だから間違いなく本人の下に届くようになっている。心配しなくていい」
「そんなことができるのですか…。エルガードの技術は」
ダタが感心したような声をあげた。
「いえ、これはウィンデイアの技術です。私とヘディンに共通の悪友がいましてね」
ラークはにっこりと笑う。
「さあ、行って来い」
天に掲げると、滑空するかのように北の方角へと旅立っていった。
「あとは…無事に着いてくれればいいね」
手紙に託した想いが無事に兄の下へと届くように。ファーナは北の空を見つめながら、心の中で深く祈った。